
『天晴!な日本人』 第49回 神算鬼謀(しんさんきぼう)の奇才、天才参謀の秋山真之(さねゆき)(1)
ここから先は
3,910字
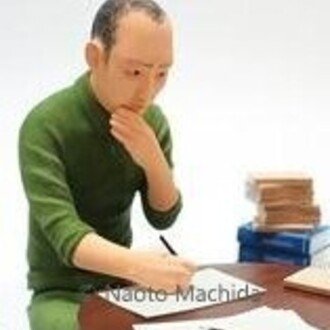
書評、偉人伝、小説、時事解説、コメント返信などを週に6本投稿します。面白く、タメになるものをお届けすべく、張り切って書いています。
無期懲役囚、美達大和のブックレビュー
¥1,200 / 月
初月無料
書評や、その時々のトピックス、政治、国際情勢、歴史、経済などの記事を他ブログ(http://blog.livedoor.jp/mitats…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
