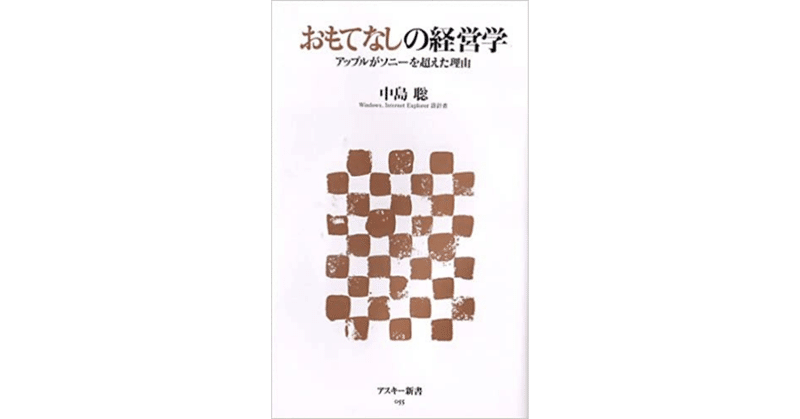
読書メモ|おもてなしの経営学
数年前「なぜ、あなたの仕事は終わらないのか」を読んで中島聡氏のファンになった(わりとすぐ熱狂する)。で、少し前にVoicyを聴いて(やっぱり素敵なひとだ)と思い出して、著書を読むことにした、その1冊目。Web3が話題の今「ウェブ2.0という言葉が広く使われるようになって2年ほどたつ」から始まる本を読むのは一興
受付嬢が1億5000万円
Googleによる買収で、YouTubeにいた受付嬢がミリオネラになった話。
(受付嬢も株を持ってたのもすごいし、それが19ヶ月で「億」になるのも夢がある)
マイクロソフトのプロダクトにはソウルがない
マイクロソフトのカルチャーは、ビルゲイツそのもので、「優れたものを作る」のは「市場で勝つ」ための手段。対してアップルの製品にはソウルがある。ピュアなモノづくりの姿勢が人々の心を打ち、熱烈なファンにしてしまう。その結果、ミュージックビジネスのリーダーになった。
「こだわり」には、作る方の自己満足のための「こだわり」と、使う人の満足度をとことん上げるための「こだわり」の2種類がある。
エンジニアの自己満足のためのコスト増はユーザーにとっての価値を一切増やさないので利益率を圧縮するが、逆に「ユーザーにとっての価値」をそのコスト以上に増やす「こだわり」は企業の利益を増やすことになる。
例えば「床屋の満足」いかにも床屋に行ってきましたという髪型が嫌だと事前に伝えても、床屋はどこも、いかにも床屋に行ってきましたとわかるようなさっぱりとした髪型に仕上げるという話。使う人をもてなすためではなく、作る人の自己満足は床屋もエンジニアも優秀な人ほど陥りやすい
アップルにできたことがソニーにできなかったのは、スーツ族とギーク族の軋轢が原因
ソニーの凋落については、出井氏を中心とするスーツ族が、久夛良木健氏(プレステの生みの親)を代表とするギーク族の心を掴むことができなかったことが原因だと(中島氏は)解釈している
アップルのスティーブジョブスはマーケティングの天才なのでスーツ側の人間だが、ギークの心をつかむのが天才的にうまい、そんなカリスマ性を持つリーダーがはっきり方向性を示したからこそ、あれだけのことを短期間に成し遂げた
ダブルメジャー
米国のマイクロソフト社で働くようになって最も強く感じたのは、日本にごく少数しかいない「ビジネスのことがわかる技術者」「ITのことがわかる経営者」がたくさんいることだ。IT企業で出世したり、ベンチャー企業を起こすためにはビジネスの知識も不可欠であることを米国のエリートは強く認識しているので、エンジニアの学位を取得後、一旦IT企業に就職して経験を積んでから、再び学校に戻ってMBAを取得するのが典型的である
英語という共通言語が必要なわけ
私がマイクロソフト本社で働いていた時も、周りにはイタリア人、イギリス人、カナダ人、インド人、中国人、イスラエル人、とさまざまな国からきた人たちがおり、米国生まれの人は明らかに少数派であった。その人たちとコミュニケーションをとる際に英語という共通言語は必要不可欠だった
アプリケーションのウェブアプリ化 アドビの英断
Adobeやマイクロソフトのようにパッケージソフトを販売している会社にとって同じような機能を提供するウェブアプリはとても厄介な存在だ。流通コストはゼロに等しく、ユーザーに試しにつかってもらうことも実に容易だ。未完成のものをベータ版として公開し、ユーザーからのフィードバックを受けながら徐々に改良してゆく開発手法も。最も厄介なのがビジネスモデルの違い。この新しい市場の流れを止めることができないなら、自らリーダシップを発揮することで自分のビジネスの将来について自ら定義してゆこうというのがAdobeの英断である。
再就職が難しい社会では生涯教育が成り立たない
46歳の時にワシントン大学のEMBAという働く人たちのためのコースに通った。1ヶ月に3日間ほどの集中講義を受ければ2年でMBAが取得できるというものである。このEMBAは最低でも15年の実務経験を積んだ社会人のためのコースだ。転職も解雇も比較的容易にできる米国では常に自分の価値を高め続ける必要がある。雇用の際に年齢制限を加えることが許されている日本では(日本でも2007年に改正)ある程度の年齢を超えてからの再就職は厳しく、学校に戻って勉強し直すことがキャリアップにつながるとは考えにくい。中国やインドへのアウトソーシングの流れがブルカラーからホワイトカラーにまできたときに、日本を先進国の地位に保つのは教育しかないと思うのだが・・・
トヨタとGMの違いはクラフトマンシップ
GMに代表される米国の製造業が産業革命以降突き進んできたのは、製造工程を細かなステップに分解し、さらに各ステップにおいて専用ツールを用いて単純作業にすることで、低賃金の労働者を使って大量にものを安く作る手法だった。これが効率を優先させたいホワイトカラーと、それに抵抗するブルーカラーの対立を生んで、生産効率の向上を妨げる結果となった
トヨタは、実際に製造ラインで働くブルーカラーの人々に主導権を与えたため、クラフトマンシップと呼ばれる自分の仕事に対する「誇り」や「愛着」を維持したまま大量生産技術の優れた部分だけを導入することができた
SEO業社とGoogleのいたちごっこ
「ユーザーにとって最も価値のある検索結果を返す」ことをモットーとするGoogleは、サーチ結果が、SEO業社が高値で仲介をしている「有料リンク」によって人為的に順位を引き上げられた商用サイトばかりでは役に立たないと、さまざまな措置をしているが、業者も対抗するのでいたちごっこである。一番迷惑をうけるのはSEO業社の顧客である
ひろゆき氏との対談とか、後半もめっちゃ面白い
ウインドウズを使い続けると遅くなる(なる!!!!!)のは私のせい?
とか・・・
本読む時間も足りないのに、丁寧に書いてもアレなので、このくらいでおしまい。要約じゃなくてあくまでメモだし。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
