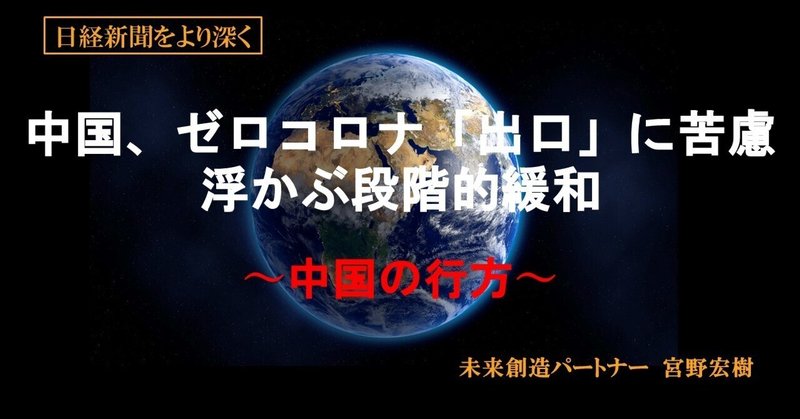
中国、ゼロコロナ「出口」に苦慮 浮かぶ段階的緩和~中国の行方~【日経新聞をより深く】
1.中国、ゼロコロナ「出口」に苦慮
中国政府が新型コロナウイルスを徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策の「出口」を模索している。習近平(シー・ジンピン)指導部の威信を傷つけぬよう、段階的な緩和に動くシナリオが浮かぶが、全面解除なら感染爆発で200万人以上が死亡するとの試算もあり、道のりは容易ではない。
「ようやく営業を再開できた」。広東省広州市で飲食店を営む女性は喜ぶ。大半の地域で11月後半から店内飲食が禁じられていたが、市政府が緩和を決め1日から中心部で多くの飲食店が営業を再開した。車の交通量も目立って増えた。
中心部では多くの建物でそれまで求めていたPCR検査の陰性証明も不要になり、大半の検査所が撤去された。北京市でも1日、大型商業施設が相次ぎ営業再開を表明した。重慶市でも2日、高リスク地区以外の住民の外出を認め陰性証明なしでスーパーで買い物ができるようになった。
コロナ対応を担う孫春蘭副首相は1日、衛生当局での座談会で「(変異型ウイルス)オミクロン型の病原性の弱まりなどから、予防・抑制措置のさらなる適正化の条件が整った」と述べた。ゼロコロナ政策には一切言及しなかった。
衛生当局は11月11日に「20条措置」と呼ばれる緩和策を発表したばかりだが、現場レベルでの実行が遅れていた。26日以降には都市封鎖(ロックダウン)などへの不満を示す抗議活動が全国に広がり、一部は習近平国家主席の退陣や政治的自由の拡大まで求めた。
中国がゼロコロナ政策を巡って揺れています。厳しいロックダウンは抗議を広げる可能性があり、解除は習近平国家主席の政策の誤りを認めることであり、感染をさらに拡大させる恐れがあります。ロックダウンを続けるも地獄、解除も地獄という状況です。
2.ホワイトペーパー革命
11月の最後の週末に、中国国内で抗議行動が席捲しました。大都市の上海から遠隔地までデモ隊は政権の厳しいゼロコロナ政策に反対し、自由を要求するスローガンを唱える抗議行動を行いました。
上海や他の中国の主要都市では警察が出動し、沈静化したかに見えますが、インターネット上で抗議を続けています。
検閲をくぐりぬけるために、皮肉で抗議している人もいるようです。
「良い良い良い確かに確かに確かに正しい正しい正しい権利はいはいはい」などと中国版TwitterのWeiboに投稿されているようです。
大規模な抗議運動は多くの若いデモ参加者が白紙のA4用紙を掲げているため、「ホワイトペーパー革命」と呼ばれています。
このホワイトペーパー革命が起こった原因は少なくとも10人が死亡した新疆ウイグル自治区の高層アパートの火災にあります。3カ月以上ロックダウンされていた地区での出来事でした。ロックダウン、移動制限によって住宅から出ることができない住民が火災が発生した高層ビルから脱出することができず、消火活動も遅れ、亡くなりました。
この出来事により、共産党政権の政策であるゼロコロナ政策に猛烈な反発が起きました。少なくとも10都市で抗議デモがおき、習近平退陣など、これまでは見たこともない抗議が起きたのでした。
中国政府はゼロコロナ政策の緩和に動き始めていますが、果たしてどこまで踏み込めるのか。また、抗議運動は収まるのか。まだ予断は許しません。
3.習近平のメンツ
2012年の内部演説で、習近平国家主席は党幹部に、ベルリンの壁が崩壊してから2年後に崩壊したソビエト連邦は、誰も立ち上がって体制を救うのに十分な「人物」が居なかったことで運命が決まったのだ、という内容を語っています。
このような発言から、毛沢東以来、中国で最も強力な支配者としての地位を確立し、先月の第20回党大会で、自分の子飼いの人物だけを取り込んだ習近平国家主席が、これまで成果を強調してきたゼロコロナ政策を放棄できるかについては、疑問が残ります。
過去の歴史を見ても、独裁者が挑戦的な行動を受けた時、本能的な反応は抑圧です。そのため、ホワイトペーパー革命がこれで鎮まれば良いのですが、これ以上の広がりを見せると、弾圧に動く可能性が高いと思われます。
習近平国家主席は2019年に香港で民主化を求める何百万人もの抗議者から「挑戦」された際には、厳しい国家安全維持法で対応し、数十人の活動家の逮捕につながり、最終的には力で鎮圧しました。この前例からしても、弱腰な対応はしない可能性は高いといえるでしょう。
そして、もう一つのメンツは、ワクチンです。西側諸国からは「海外製の有効性の高いワクチン」を使用しない限り、感染拡大は収まらないという指摘を受けています。
米英などの海外製ワクチンが本当に有効かどうかはわかりませんが、その批判が出ていることは事実です。
しかし、これまで頑なに国内製にこだわってきていますので、これも簡単には変更できません。この点も習近平国家主席にとっては、ストレスでしょう。
3.海外からの目
海外からの目は、1989年の天安門事件の再来があるのではないかというものです。米国上院議員団は書簡を送っています。
米国の超党派の上院議員グループは、北京の秦剛ワシントン大使に鋭い言葉の手紙を送り、共産党政権が1989年の天安門事件を思わせる弾圧を実行すれば「米中関係に重大な結果をもたらす」と警告しています。
海外からの厳しい目は、中国で再び悲惨な出来事が起きないようにするためには非常に重要です。
さらにIMFは経済的な厳しさを指摘しています。
シンガポールで開催された東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議で、IMF専務理事のクリスタリナ・ゲオルギエヴァは、見通しは「例外的に不確実」であり、世界的な金融引き締めなど「リスクに支配されている」と指摘しています。
また、中国のゼロCovid政策が自国経済に打撃を与え、ロシアのウクライナ侵攻によるインフレ圧力がアジア地域を襲う中、アジアの指導者や中央銀行に対し、「例外的」不確実性に備えるよう警告を発してもいます。
この「例外的」不確実性は、習近平国家主席が打ち出したコロナウイルス感染者をすべて排除するという政策から脱却できるかどうかを、北京が見極めようとするため、中国は、不動産セクターの深刻な減速と相まって極めて厳しい経済状況に置かれるためにやってくるということです。
中国政府には、ゼロコロナ政策の緩和への動きがみられます。しかし、習近平国家主席のメンツもあり、世界の他の国で進んでいる「通常」の社会を取り戻すにはまだまだ時間がかかるものと思われます。果たして、中国は経済が保てるのか、そして、政権が保てるのか、しばらく注目しておかなければなりません。
未来創造パートナー 宮野宏樹
【日経新聞から学ぶ】
自分が関心があることを多くの人にもシェアすることで、より広く世の中を動きを知っていただきたいと思い、執筆しております。もし、よろしければ、サポートお願いします!サポートしていただいたものは、より記事の質を上げるために使わせていただきますm(__)m
