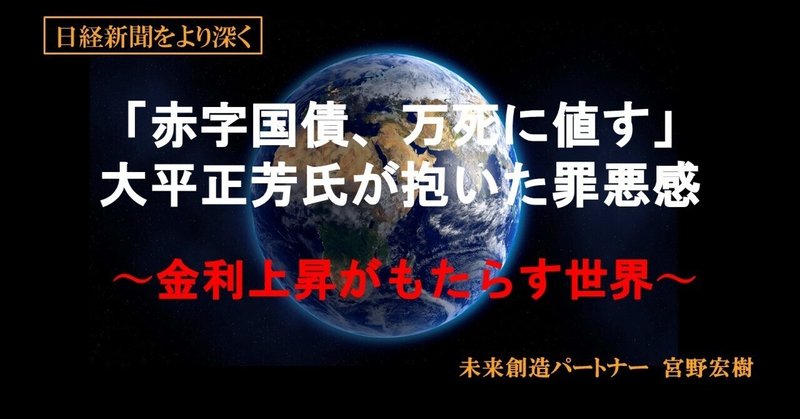
「赤字国債、万死に値す」 大平正芳氏が抱いた罪悪感~金利上昇がもたらす世界~【日経新聞をより深く】
1.「赤字国債、万死に値す」
借金漬けの国家に未来はない。そんな強い信念を持っていた元首相の大平正芳氏が、蔵相(現財務相)だった1975年に赤字国債の発行に追い込まれたのは歴史の皮肉だ。
第1次石油ショックのあおりで、日本経済は74年に戦後初めてのマイナス成長に陥った。税収の落ち込みで歳入不足が生じ、どうやりくりしても赤字国債の発行は避けられなくなっていた。
それでも大平氏は最後までなんとか借金をせずに済まないか悩み、苦しんだという。「赤字国債は万死に値する」。娘婿で蔵相秘書官だった森田一・元運輸相は、大平氏がそう口にするのを何度も聞いた。
「『万死に』はちょっと強すぎる表現で、大平らしくない」。こう話すのは森田氏の娘で「祖父 大平正芳」の著書があるメディアプロデューサーの渡辺満子さんだ。
政争の季節だった。大平氏にすれば政敵に弱みをみせられない。政治的に譲れなかったにしても、これほど悔やんだのはなぜか。
いちど借金に頼るようになればそれは雪だるま式に膨らみ、危機が起きたときのツケは将来の世代が払わなければならない。敬虔(けいけん)なクリスチャンだった大平氏はそう考え、強烈な「罪の意識」を抱いた。
なんとしてでも償いたかったのだろう。首相として臨んだ79年10月の総選挙では、一般消費税の導入を掲げた。しかし、増税への反発は予想以上に激しく、撤回を余儀なくされる。「財政再建」で票は稼げない。自民党は敗れた。
それから40年あまり。大平氏が恐れたことは現実になっている。財務省によると、国債に財投債や借入金などを加えたいわゆる「国の借金」は、9月末に1251兆円に達した。
国際通貨基金(IMF)は地方政府と社会保障基金も合わせた日本の債務残高が、21年に国内総生産(GDP)比で260%を超えたとみる。およそ200%だった太平洋戦争末期の水準をすでに大きく上回る。
英国の例を挙げるまでもなく、危機はいつ起きてもおかしくない。なのに、岸田文雄首相は借金のさらなる上積みになんのためらいもないようにみえる。
21日に国会へ提出した2022年度の第2次補正予算案は29兆円近い歳出のうち、実に8割の22.8兆円を国債の増発でまかなう。経済対策をまとめる直前には、財務省が提示した25兆円から一夜にして4兆円の増額を決めた。
「規模ありき」のそしりは免れない。いまは国債の発行をどれだけ増やしても、長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)を続ける日銀が買い取ってくれる。金利は上がらず、コストがかからないから、必要性の低い借金も重ねるモラルハザード(倫理の欠如)が起きる。
一般消費税で政権基盤が揺らいだ大平氏は、80年に自民党内の造反による内閣不信任案の可決で衆院解散に追い込まれた。選挙戦のさなかに倒れ、帰らぬ人となった。罪の意識を背負ったままだった。

日本だけではなく、世界の債務は大きく拡大しています。債務は金利が上昇した時に、問題が噴出します。
2.日銀資金循環表から見えること

資金循環表を以下のように簡略してみます。

日本の家計+企業+政府の負債合計は3,999兆円あり、これは、GDP546.8兆円(2022年7月-9月)の7.3倍に当たります。
日銀が1%の利上げをすれば、日本全体では39兆円の利払いが増えることになります。2%の利上げで70兆円にも上ります。
全体でみると「金融資産=金融負債」です。預金は預金者にとっては金融資産ですが、銀行にとっては同じ金額の負債となっています。
株は、返済順位が最も低い劣後債です。(解散するまでは清算の必要がない)しかし、株券を発行する企業にとっては、資本という負債であり、株主にとっては、同額の金融資産となります。資本は会社ではなく、株主が高い配当を求めて預託したものです。
こうした借りたり、貸したりの仲介役をしているのが、金融機関です。この金融機関は免許業種です。(民間銀行、生保、証券、政府系金融、ノンバンク)これらの業種が免許を必要とするのは、日銀が通貨を増発できる間は、政府が救済することで、金融危機を避けたいという黙約があるからでしょう。
日銀は、GDPを大きく上回る605兆円の証券(国債、株)を購入し、銀行には国債担保での貸し出しを134兆円行っています。
また、日本は対外に対しては超過資産を持っています。(円の累積流失)海外からは日本の国債、株式、円を885兆円購入が入り、日本から1,329兆円借りています。
逆に海外が円を購入した分が日本の対外債務885兆円です。そして、日本の対外資産は、対外資産1,329兆円-対外負債885兆円=444兆円です。
3.金利が上昇すると・・・
金利が上昇すると、日銀の資産が棄損します。日銀は合計605兆円の国債や株を保有しています。この資産が購入価格を下回って、含み損が発生する可能性があります。これは、日銀の信頼性に問題が出る可能性があります。
別の角度から見てみると、金利が上昇すると、金融機関の保有債券も下落します。しかし、金融機関の場合、問題はレバレッジです。
金融機関は、自己資本を信用の源にして、金利の低い短期マネーを調達し、金利の高い国債、社債、株などの債券を購入しています。
長期金利(運用益)-短期金利(調達コスト)=金融機関の業務純益
米国の短期金利は現在、4.6%付近と高い水準にあります。(1年以下の短期国債の金利:2022年12月)しかし、長期金利である10年債の利回りは3.6%付近と、短期金利より低い。
これは、逆イールドと呼ばれる現象であり、大きな不況の前に起こることが多いと言われています。
日本の金融機関も例外ではなく、金利が上昇すると、レバレッジをかけていた場合、逆回転し始めます。
銀行が短期金利でマネーを調達し(4.6%)、長期金利で運用すると(3.6%)で運用すると、銀行の業務純益は1%の赤字になります。赤字の運用はできません。このため、銀行は金利で運用している国債、社債、貸付金を減らさなければならなくなります。このため、経済は不況化する可能性が大となります。逆イールドになる稀な時期は、銀行は長期マネーの運用(長期債の購入、社債の購入、貸付、株の購入)を減らします。企業と政府に入ってくる資金が急減し、不況になっていくのです。
米国はすでにこの状況です。このように金利が上昇することで、大きな問題が起こりうるのです。そして、米国の世界最大級ヘッジファンドのエリオット・マネジメントは金融危機を警告しています。
米国が金融危機に見舞われた際は日本も例外ではなくなります。しかし、今度の金融危機は、世界の基軸通貨である米ドルへの信認の問題ともなってきます。
米ドルの基軸通貨を支えてきたべトロダラー(原油の決済はドルで行うという約束)は崩れる可能性が大きくなっています。サウジアラビアは中国との関係も深め、人民元で原油決済を行う可能性も出ています。さらに、世界はCBDC(中央銀行デジタル通貨)に向かっていきます。すると、貿易での決済もドルを必要としなくなってきます。
現在、ドルが強いと見えるのは、決済通貨としてドルが使われるため、常に世界がドルを外貨準備として保有しておく必要があるからです。しかし、CBDCとなり、直接の外貨交換となり、米ドルが基軸通貨であり続けた媒介通貨の役割が終わりに向かっていきます。
すると、経常赤字である米ドルは本質的には強くありません。米国を支えているのは、世界最大の米国債を保有している日本なのです。そして、米ドルが基軸通貨としての役割を終えていき、交換レートが下がり、円高となった場合に、日本の対外純資産は目減りすることになるのです。仮に1ドルが100円になったとすると、約30%の円高です。日本の金融資産1,329兆円は、30%目減りし約400兆円の損失を被ることになります。
政府も金融機関も世界中でバランスシートを膨らませました。それは負債を膨らませたということです。そして、それは金利が上昇した時に、その清算を迫られます。
来年は金融機関にその兆候がはっきりと出てくると思われます。
未来創造パートナー 宮野宏樹
【日経新聞から学ぶ】
自分が関心があることを多くの人にもシェアすることで、より広く世の中を動きを知っていただきたいと思い、執筆しております。もし、よろしければ、サポートお願いします!サポートしていただいたものは、より記事の質を上げるために使わせていただきますm(__)m
