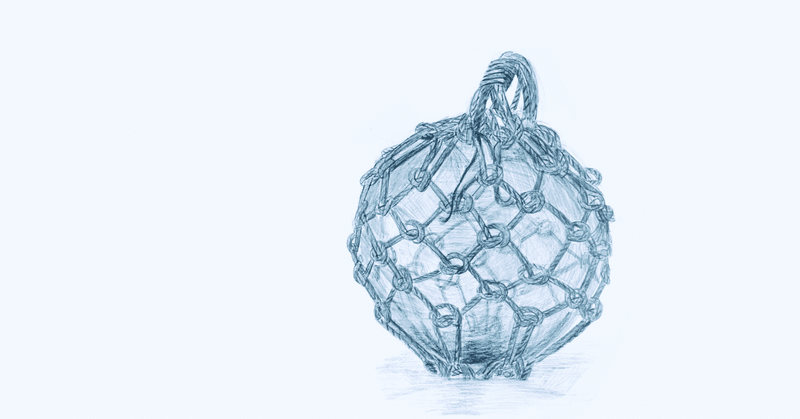
身を尽くしても
冬までいい子にして待っていると言ったはずだった。会えないのは、寂しかった。
***
いつもわたしから連絡してはあのひとが返事をくれて、あのひとは決して自分がボールを持ったままにしないからわたしがなんとなく引いてラリーを止めてしまうのが常だったのに、冬にまた仕事でミオちゃんの住む町に行くよと、珍しくあのひとのほうから連絡が来た。
わたしが願を掛けずとも、あのひとが己の思いの強さだけを縁にしてわたしとは無関係にまたこの町にやってくる日が来るだろうということは分かっていたものの、それでも会える目処が立つというのは嬉しいもので、わたしは「いい子にして待っています」と盛大に尻尾を振ってしまう。「会いに」来てくれるわけではないということは分かってはいるのだけれど、もうなんでもいい、と思う。記憶に縋るのには慣れているけれど、いま約束に縋れるのが嬉しい。どこにも辿りつけないのは分かっているけれど、どこにも行けないまま、ここで辛うじて重なる未来を見ていたい。
2月は来るのを教えてくれなかったのが寂しかったから、次来るときにはちゃんと知らせてほしいと駄々を捏ねておいたのはわたしなのだけれど、忘れずにいてくれていたのだな、と思う。わたしにとっては一生の心の支えになるような数日でも、あのひとの人生の中では次第に霞んで遠くなってゆくのだろうと、前触れもなく再会したあの日にわたしは気づいてしまったのだ。かつてわたしの呪いを解いたあのひとが次にわたしにかけた呪いは「もうわたしじゃないのかな」で、言語優位の脳の構造をしていてそれなりに記憶力もいいわたしには、とても呪いが効きやすい。あのひとが再会以来殊更に、なにかを確かめるように「好きだよ」と言いつづけてくれたのはおそらく、わたしが「もうわたしじゃないのかな」と一歩下がりかけたのに気づいたからだ。
わたしはそうやって先回りして諦めがちだけれど、あのひとは概してそんなに過去を振り返らないのだろうなとも思う。あのひとはちゃんと前を向いて今を大事にできるひとで、過去を解釈して納得しようとしていつまでも引きずっているわたしは、あのひとのそういうところが好きだ。あのひとは遠いところまで飛んでいくタイプで、わたしは狭く深く埋没していたいタイプだけれど、ちがっていても大丈夫だ、と思う。わたしと共有したい日々のよしなしごともわたしに吐露したい日々のささくれもあのひとがもたなくても、そういえば夜半に地震があった朝や勢力の強い台風が接近した夜にあのひとは心配して連絡をくれて、わたしのことを気にかけてくれてはいるのだと実感する。2月以来三日にあげずとりとめのないメッセージを送ってしまっているわたしを、むしろ忘れるほうが難しいかもしれないけれど。
名前を呼んで、こっちを向いて、できるだけ長く好きでいて。それだけでもう十分すぎるほど要求してしまっていると思う。求めていいことなどそう多くはないと思っているので、与えられるものに満足していたい。あのひとが「伝えたい」とか「触れたい」とか思ってわたしにくれるものに満足していたい。いつも一緒にいたいのにいつも一緒にいると壊してしまうわたしは恋愛下手だから、形も距離も問わず、ただ変わらずに長くつづくものを選んでいきたい。誰かに愛されなくなっていく日々を必死で繕うように笑って笑って、結局泣くしかなくなっていったことはまだ記憶のそう深くないところにあって、だから、薄くてもいいから変わらないものがほしい。離れていても変わらないものがほしい。わたしがいつまでも安心していられるような、変わらないものがほしい。そしたらわたしはたぶん、ちゃんと笑っていられる。
叶うならせめて、とても寂しがりで甘えん坊な女があのひとの愛した町に住んでいることを覚えていてほしい。わたしが名前を呼ばなくてもたまに思い出してほしい。わたしが会いたくて寂しいことをわかっていてほしい。会える日を楽しみに楽しみに待っているけれど、そのぶん会えない日々が寂しいことも、わかっていてほしい。わかったうえで応えてもらえないことも、わかってはいるけれど。
滅多にあのひとのほうから連絡が来ないのが、わたしがあのひとのことなど忘れていられている状態のほうがほんとうは健全なのだとあのひとが解釈しているからなのだとしたら嫌だ、と思う。連絡がすこしずつ間遠になれば、あのひとはわたしの回復を見るのだろうか。
連絡するのも寂しいし、寂しいから連絡しないのも余計に寂しいし、こうしてまた寂しさの自家中毒に陥っていく。会えないことも、あのひとの人生にべつにわたしが必要ないことも、それでも呼べば必ず応えがあることも、あのひとがもう寂しそうでないことも、なにもかもが寂しい。あのひとのせいで寂しい、と言ってしまうのはすこし違っていて、あのひとでしか満たされない自分のせいで寂しい。というのもほんとうは不正確で、あのひとでしか満たされないと思い込んでいる自分のせいで寂しい。解像度が高くなればなるほど救いようがない。
「わたしがやめたら途切れてしまう」、がまだ嫌だ、と思う。あのひとがいなくても生きていけるけれど、あのひとを必要としていたいわたしはどうすればいいのだろう。駄々を捏ねる以外にはもう俺通信しか送れないのに、まだあのひとにわたしのことを考えていてほしくて、そうでないと生きていけない気がするから、自動的に1日1回わたしのことを思い出すシステムがあのひとに搭載されてくれないだろうか。そうしたらあのひとにわたしのつまらない俺通信を見せずに済むのに。
会ったら「会えて嬉しいよ」と笑ってくれるだろうけれど、あのひとには会いたくて眠れない夜などないのだろう。寂しいと言ったらそれを否定も肯定もせずにただ「会いに行くよ」と返してくれるけれど、「わたしもだよ」ではないのだろう。当たり前のことだけれど。わたしの寂しさは良くも悪くもわたしだけのもので、受け止めてもらえない言葉は一周回ってわたしを余計寂しくさせるので、どんどん吐けなくなっていく。ケアされればされるほど、非対称性が浮き彫りになる。
同じ温度でない感情を強要したところで虚しくなるだけだから、今夜も名前を呼ぶことしかできない。「せんせい」はもう「寂しいからちょっとだけこっち向いてわたしのことを考えて」のおねだりでしかなくなっていて、あのひとはわたしのほしいことばを知りすぎているので、「ちゃんとそっち向いてるよ。安心してね」と返され、わたしはいったいなにに安心すればいいのだろう、と思う。そうやってわたしを安心させてあのひとはなにがしたいのだろう。「安心してね」は、わたしにはむずかしい。けれど、不安定になって呼びたくてメッセージ画面を開くたび、その「安心してね」が目に飛び込んできて、ああ、なら大丈夫だ、と思ってそっと閉じる。「好きだよ」より「安心してね」に救われる自分の思考回路がいまだよく分からないままに、お守りをくれてありがとう、と思いながら何回も何回も見返している。
***
あのひとと眺めた海で人が死に ふたりの海を世界が吞んだ
海水浴客の事故が連日のように報道された夏、4月にあのひとが「俺の好きな場所」と連れていってくれた海をGoogle mapのストリートビューから特定する作業は案外容易にできてしまって、わたしはやっぱりネトスト気質なのだろう。わたしたちふたりだけだった砂浜が誰も知らない海でなくても、世界に接続されてしまっても、わたしはあのひとの好きなものを知るのが好きで、あのひとの瞳を通して見る世界はわたしにすこし優しい。
あのひとがいなくても、海に抱かれていれば大丈夫だ、と自分に言い聞かせている。わたしにとって先生は海なんです、と酔った勢いで伝えてしまったら、「じゃあきみはそこで泳いでいるクジラなのかな」と返されて、思ったより近くにいてくれるのね、とすこし泣けてしまった。あのひとはいつもそうやって、軽率にわたしに優しい。海に身を浸すことをあのひとは「身体も意識も、外界との境界が薄れ、混ざり溶け合う感覚」といつか形容したけれど、あのひとにとってわたしが海に身を浸しているいきものなのだとしたら、あのひととわたしはあのひとのなかで混ざり溶け合っているということなのだろうか。そういうことでいいのだろうか。わたしの不安定すらもすべて受け止めて飲み込んでしまう、海。
引き換えわたしは底の浅い女で、あのひとに捏ねていい駄々などもう残っていない、と思う。会いたいだとか寂しいだとか生きるのが辛いだとかもう嫌だとかは、言えなくなってしまった。わたしの「死にたい」は甘えだったはずなのだけれど、あのひとに「死にたい」が言えないのは、近しい人の自死を経験したことがあるあのひとを痛めたくないせいか、それで気を惹きたくないという僅かに残ったプライドのせいか、その感情がいつの間にか手触りを持ちすぎたせいか分からない。あのひとがかなしいのはいや、などと先回りしているわたしはよくよく愚かだと思う。「わたしより先に死なないで」と脈絡のない我儘を言ったら、「そこは年功序列で」と似合わない台詞を返されて笑ってしまった。「ずっと好きでいられる、繋がっていられる」という安心感と、「もうそんなに時間が残されていないのではないか」という妙な焦りが交互にやってくる。べつにどちらにも根拠はない。
***
日中忙しい日々が続いたけれど、夜ふっと息をついたときに思い出す顔が、もうずっとあのひとだ。あのひとにはあのひとの居場所があることをちゃんとわかってはいるのだけれど、それでも、ここにあのひとがいればいいのに、と思う。会わなくてもあたたかいひとではあるし、こうしてレトリックだけでもつながっていられるけれど、それが寂しくないわけではないのだ。会える日を楽しみに楽しみに待っていたら、会えない日々が寂しくて仕方なくなってしまった。ことばで掬えるものはもうすべて掬いきってしまわれた気がしていて、会わないと、触れないと掬ってもらえないところが寂しさに悲鳴を上げる。間を隔てる数百キロの距離はあのひとが伝えてくれる感情を殺さないけれど、温もりを殺す。わたしとあのひととではたぶん、時間の流れる速さが違う。わたしは、5ヶ月先を「今度」と言えない。
夢でいいからそろそろハグされないと死んでしまう。言うに事欠いて「夢に出てきて」という弩級の駄々を捏ねたうえで泣き疲れて眠ってしまったわたしは、首尾よくあのひとの夢を見ることに成功して満足する。平安時代なら、わたしは毎日うるさいくらいにあのひとの夢に出ていると思うけれど、現代を生きるわたしはわたし自身の夢くらいしか操作できないことを知っている。
臆面もなく「夢で会えたので満足」を伝えてしまうわたしに、臆面もなく「しばらく夢で我慢して待っていて」と返すあのひとは、結構ロマンチストだと思う。「待っていて」と言われたらほんとうに待っていてしまうけれどいいのだろうか。あのひとは己の言葉を軽くしないひとだから、あのひとのくちから出た言葉は信じていいと思ってしまっているけれどいいのだろうか。わたしのことはいくら軽く扱ってもいいから、己の言葉を軽くしないで、は、いつか願ったことだったような気がする。
「楽しみにしててね」まで追い打たれて、わたしは再起不能になってしまう。わたしは「楽しみにしてる」は言えても「楽しみにしてて」は絶対に言えないから、ああ負けているなあ、と思うし、その胆力はどこから来るの、とも思うし、自信があるのね、とも思う。たぶんわたしが「楽しみにしてるわたし馬鹿みたい」と心のどこかで思ってしまっているのがバレていて、その愚かしさすらも肯定されている。夢の中の、笑い転げるわたしの声も、あのひとの細められた目尻の印象も、腰に添えられた手の温かさも、抱きしめられたときの力強さも、それなりにリアルだったのに、ほんものがほしい、と思う。ほんとうは、夢だけでは足りない。
***
あのひとは、期限を切らない漠然とした「また会いたいね」や「また一緒にお酒を呑みたいね」は言ってくれても、薄っぺらな「会いたい」や「寂しい」や、まして「来てほしい」とは絶対に言ってくれないひとだ。来るかもわからない「また」を信じて待ちつづけているわたしも結構可愛いとは思うし、会いに行く理由を探してしまいそうになっている自分を俯瞰したときに重いなと思ってしまったから、9月は会いに行かないつもりだった。なのに馴染みのバーカウンターの中の男が、あそこのレストランに付き合ってよと誘うので、ああ、寄れてしまう、と思った瞬間思わず首を縦に振っていた。
昔のわたしは「会いたい」すら素直に言えなかったけれど、今のわたしは「会いたい。でも迷惑はかけたくない。それでも、『おいで』と言われたい」という自分の感情くらいは的確に把握できるようになっている。あのひとはわたしを随分素直にしてしまった。怖くてしばらく聞けなかったけれど勇気を振り絞って、用事で近くに行くのだけれどこの日かこの日奇跡的に空いてたりしないでしょうかとメッセージを送ったら、あのひとは嬉しいお誘いをありがとうと笑うので、わたしは泣きそうになる。会いたいのはわたしだけだと思っていた。
「会いたい」と言ったときに、昔は「ありがとう」といなされていたけれど、それより先に「嬉しいよ」が出てくるようになった今のあのひとのことが好きだ。言わせたみたいな「嬉しいよ」に、「ほんとにうれしい?」とは思ってしまうけれども、言わせているわけではないと思っていてもいいのだろうか。あのひとは口先だけの嘘をつかないひとだから、それくらいなら流すか黙るかしてしまうから、だから信じていてもいいのだろうか。あのひとがわたしに会えて嬉しい理由などひとつも思いつかず、正面切って聞いたところでどうせ「好きだからだよ」と笑われるだけなのが目に見えている。それはしあわせで、同時にとても不確かなことだ。
「楽しみにしてるね!」は、ちゃんと語尾がエクスクラメーションで、ずるい、と思う。「好き」に忠実なわたしを好きだと言ってくれたあのひとだから、この衝動に従うわたしすらも受け止めてくれるのだろうか。理性で感情を殺すわたしと、感情のまま一目散に駆けてゆけるわたしと、あのひとにとってどちらが可愛いのだろうか。その感情の矛先があのひとに向かうとき。
***
わたしはあのひとにタイミングを合わせる努力をしているし、あのひとは会おうとする努力をしてくれているので、これだけ距離が開いてもそれなりに会えている。会ってくれるというだけでまだ大丈夫だなと思えるのは、距離が開いたことで会えなくなっていったひとがいたからだ。触れていないと意味がないパターンをうまく維持できなかったぶん、触れていなくても繋がっていられる相手を大事にしているといえば、まあそれはそうなのだろう。けれど気まぐれや暇つぶしだけでは説明がつかない程度に、あのひとは揺るぎなくそこにいてくれていて、そのことがわたしを安定させる。冬まで待たなくてよくなったわたしの情緒は4月の凪いだ海に似て、連絡の頻度が如実に落ちた己を自覚し、翻っていつものわたしのメッセージは、どれだけ言葉を並べようともすべて、寂しい寂しいこっちを向いてわたしのことを考えて、と言っているだけなのだなと思う。
「会いたい」も「寂しい」も詮無いと気づいてからずっと言えなくて、やっと言える「はやく会いたいです」を、わたしはどうやらとても言いたかったらしい。けれどようやく吐いたそれに「はやくおいで」が返されて、ひどい、と思う。こんなの知らなくて、ぜんぜん知らなくて、だれか助けてほしい。いつも知らない角度からのあのひとの優しさに殴り倒されている。会えて嬉しいのはわたしだけではないと思っていいのだろうか。迷惑でしかないだろうなと思っていたし、迷惑でしかないだろうなと思っている。けれど、感情を受け止めてもらえるということの幸せをこんなふうに与えられてしまって、わたしはいったいどうすればいいのだろう。
わたしをよく知る人に、「その男の返信が早いのは、時間に余裕があるからではなくて、『あなたと連絡を取り合っていたい』と思っているからだよ」、と言われて、改めて言語化されるとなんだか沁みてしまった。ことばもたくさんくれているけれど、態度すべてで示してくれていると思う。
数日後、贅沢になったわたしが酔った勢いに任せて、待ってるよって言ってください、と駄々を捏ねたら、「うん、首をながーくして待ってるよ」に駄目押しのような「早くおいで」が追い打たれて、身体の奥のどこか深いところから、堪えようもなく「うれしい」が満ちてくる。ときどき喉の奥で膨らむ塊の熱さがどれだけ痛くても、ただこのうれしさのためだけに耐えられると思った。ことばをほしがるわたしは我儘で、「そういうふうに愛されたかった」を至極的確に抉られていると思う。「それがほしかった」をそのかたちのまま穿たれて、もうすべてを投げ出してしまいたくなる。
あのひとの追い打ちがうれしいのは、いつもなんとなく、わたしがもらえているのはわたしからのメッセージに返信する一瞬だけなのだろう、と思ってしまっているからかもしれない。一度返信はしたけれどなにかが頭の片隅に引っかかっていて、もう一言を追い打ちしようと思ってくれたのなら、わたしはそれがうれしい。たぶん、「この返信だけではこの子は寂しがるけれど、べつにそれ以上要求することもなく飲み込んでしまうのだろうな」をフォローするための追い打ちなのだろうと薄々察しはじめてはいるけれど、わたしはもうだめになってしまったので、「わたしはそれがうれしい」とあのひとに伝えてしまう。べつにわたしを嬉しがらせるためにやってくれているとまでは思わないのだけれど、仮にそうだとしてもわたしは思惑通りに嬉しがるだろう。あのひとは、ちいさな失望や不信をひとつも残さないでいてくれるひとだ。
注がれても注がれてもまだ自己肯定感がゆらゆらと揺れて、拗ねたふりをして、けれど駄々の捏ねかた一言一句すら気にしながら零した「会いたいのはわたしだけなんだろうなと思っています」は「そんなことないよ」がほしいだけの我儘でしかなく、絶対に「そんなことないよ」と言ってくれるのが分かっている相手にしか言えない、と思う。やっと言える。我ながら面倒くさい女だなあと思うけれど、止められない。
わたしは勝ち負けのある人間関係しか想定できないタイプなので、「負けてもいい」と思える相手に添うてゆくしかない。昔からあのひとには負けてもいい、と思っているし、甘えたがりを甘えん坊にさせてくれてありがとう、と思っている。甘えたがりを見抜かれたあの瞬間、どうしようもなく嬉しかったことを覚えている。あのひとは、甘えたくて仕方ないくせに甘え下手なわたしに、「甘えていいんだよ」と言いつづけ、けれど決して無理に引き寄せることはなく、ただひらいていつづけてくれた。
あのひとが好きだ、と思う。認めるのが怖くてずっと逃げてきたけれど、もう認めてしまおう。あのひとが好きだ。好きだと言ったところで穏やかな「好きだよ」しか返ってこない、ただそれだけの関係でも。会いたいと言ったところで叶わないことのほうが多い、ただそれだけの関係でも。ただ、また触れたくて、それだけのために生きている。わたしはただの澪標なので、ときたま船乗りの道しるべになる以外はただ海に抱かれていることしかできないけれど、どこまでもただそれだけのために、あのひとの海を泳ぎつづけたいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
