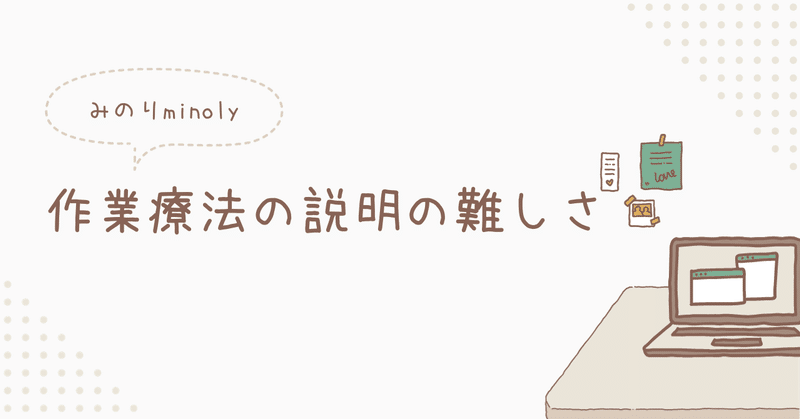
#8 作業療法の説明の難しさ
こんにちは。みのりminolyです。
私は、1年生の最初の授業で、以下のような質問をしています。
現時点(1年次最初)で、あなたは作業療法を知らない友達に作業療法をどのように説明しますか?
この反応を含め、作業療法を説明するということに着目して、考えてみました。
「作業療法理論」での質問
私の担当する「作業療法理論」という科目では、1回目の授業でトップに挙げた質問をし、答えを書いてもらい、最後の授業でその答えを再び書いてレポート課題としています。
1回目の授業では、
・リハビリテーションをする医療専門職
という意見が、大半を占めます。
では、理学療法士との違いは?というと、困ってしまう学生がほとんどです。
1年生の最初の授業では、この質問に答えられないことは当然と考えて質問しています。
意地悪な質問かもしれませんが、科目の最後には、理学療法士との違いだけでなく、作業療法士が持つべき見方・考え方を説明できるようになってもらっています。
それが担当する科目の目標です。
《できていない学生も中にはいるかもしれませんが…》
理論とは専門職の見方・考え方を伝えるもの
私が担当する「作業療法理論」は、名前からして難しそうという印象を持たれます。
そこで、理論を学ぶことがいかに大切か、そして、どのように役立つのかを実感してもらうために、トップに挙げた質問をするのです。
専門職は、それぞれの見方・考え方を持っています。
同じ患者さんでも、医者からの見方、看護師からの見方、介護士からの見方、理学療法士からの見方、ソーシャルワーカーからの見方、ケアマネジャーからの見方、そして、作業療法士からの見方は異なるものです。
専門職独自の見方・考え方は、患者さんやその家族、他の職種、そして、後輩に伝えることができなければ、専門職として存続することができません。
専門職独自の見方・考え方を他者に伝えるために、先人たちによってまとめられたものが「理論」なんだと授業では伝えています。
一度説明できるようになっても再びわからなくなる
作業療法理論の授業で、理論として、作業療法を説明できるようになってもらえます。
そして、歴史や成り立ち、領域などを学習する「作業療法概論」や、作業療法の「作業」について考える「作業科学」「作業分析」、日本の作業療法士協会が作った理論(理論ではなくモデルだと位置づけていますが細かいことは置いておいて)「生活行為向上マネジメント」などの関連するものを学習する1年生は、比較的作業療法について理解してもらっているように感じています。
一方で、2年・3年と学年が進むにつれて、総論から各論に進むので、検査・測定や治療について学べば学ぶほど、
理論と作業療法が乖離しているような気がしてしまうようです。
本来は、考え方「理論」とそれを実行するための「手段」を学んでいるのですが、「手段」であるはずのものが作業療法そのものだと思えて来てしまうようです。
《教育の問題点でもありますが…》
そして、実習で現場を見てくると、「手段」のできなささに追われることや、「手段」は目につきやすく多くの指導を受けることで、
「手段」が作業療法そのものだとなってしまうようです。
さらに、就職すると、「手段」を使って、患者さんが、身体的・精神的指標において改善すれば、診療報酬上、業務上、評価されてしまうこともあり、
さらに作業療法を見失っていくように思います。
何のために、その「手段」を使っているのか、そこはどこにも評価されないのです。
でも、患者さんや家族、他の職種には説明しなくてはいけません。
そして、後輩にも。
「作業療法は説明しても分かりにくいんですよ。」
「なかなか理解してもらえないかもしれないけど…」
「日常生活を支援する…」
「理学療法は足で、作業療法は手のリハビリ」
「作業療法は手工芸などをするんです。」
うまく説明できないことの枕詞を使ったり、
ごく一部の「手段」を、作業療法で行うことと説明したりします。
作業療法士として病院や施設で働く作業療法士も、作業療法をうまく説明できていないように思います。
この汚点は、業界全体の問題といえそうです。
まとめ
・理論とは、専門職の見方・考え方を説明するもの
・作業療法は、一度説明できるようになっても、各論を学んだり、実習、現場で働くようになることで、その説明があいまいなものになりがちである。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今後の励みになりますので、「スキ」を押していただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
