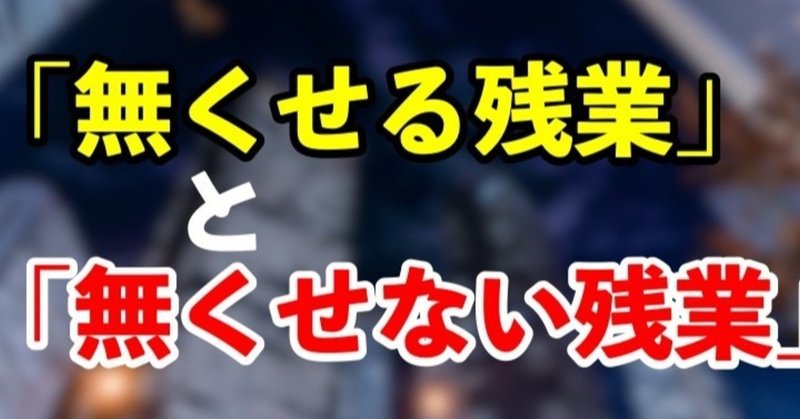
「無くせる残業」と「無くせない残業」
残業研究家の私も残業ゼロではない
私は普段、YouTubeで「残業しない方が良い」という話をしています。
そう言いながらも全部の残業をなくすというのは完全には不可能と考えています。
実際、私自身の状態としては、新規事業を扱う職員としてはかなり残業が少ない方ではありながらも、今年度はおそらく年間20〜30時間は残業しました。
残業をゼロにした方が絶対に自分の時間を確保できますし、体力も温存できるので、絶対に残業は無くした方が良いに違いありません!
しかしながら、皆さんもご存知の通り、現実はそう甘くはありません。
「無くせる残業もあれば無くせない残業もある」と言うことです。
「無くせる残業」と「無くせない残業」がある
残業には種類がたくさんあります。
習慣的な残業、業務が重なった時の残業、不安だから帰れない残業、定時の前にやる気スイッチが入る残業、空気的に帰りづらい残業、無意識に自分で仕事を増やしてしまう一生懸命過ぎ残業、お金が目当て残業、やったことのない仕事での残業。
その中でも無くすのが難しいのは次の2つです。
一つは、やったことのない仕事をする時。
もう一つは、どうしても仕事が重なってしまった時。
逆に言うとそれ以外の残業は、自分次第である程度コントロールできます。
無くせない残業①「やったことのない仕事」
やったことがないというのは、
新入社員だからやったことがない、人事異動で畑違いのところに来たなど、
そもそもその仕事が初めてというパターンと、
人事異動をしていなくても、新しい事業を任された時や、他の人が今まで担当していた仕事を任されると言うパターンがあります。
あるいは、今までと同じ仕事をしているにもかかわらず、制度が変わったために今までのやり方とは違うやり方で進めないといけないと言うパターンもあります。
私は以前に、職員の人数を管理する仕事を担当した経験があります。
その時に、職員の業務日報をもとに職員一人ひとりの10年分の残業時間の推移を見ていったのですが、どんなに優秀な人であっても、あるいは仕事に対して「割り切っている」ような人であっても、人事異動のタイミングや分担の変更が行われた時、新規事業の担当になった時には、半分以上の確率で残業が増えていました。
なぜ、やったことのない仕事は残業が増えるのか?
それは説明するまでも無いかもしれませんが、具体例を挙げると
例えばA4一枚の文書を作る時、その文書を作るのが初めてでなければ1分くらいで作れたりするものです。
それが、初めて作る文書となると
「日付はこれでいいんだろうか?何かルールがあるのか、それとも適当な日付で良いのか?」
「〆切の設定はどうすれば良いんだろう?去年と同じくらいにしておけば良いのかな?」
など、一つひとつの作業に悩まなくてはなりません。
そうすると、1分で終わることが10分かかってしまいます。
1分で終わることが10分かかるということは、
それを積み重ねていくと、3時間で終わるものが6時間かかったり、8時間で終わるものが10時間かかっても終わらなかったりして、残業が増えるわけです。
無くせない残業②「仕事が重なってしまう時」
どんな人でも、仕事が重なる時期ってあるはずです。
普段効率的に仕事をしている人も、定時まで目一杯使って1日の仕事を終わらせ、帰る頃にはくたくたになる、そういうことって、一見余裕のあるように見える人にもあるのです。
そういう時間目一杯で仕事をしている時期にも突発的な業務が急に課長から頼まれたりとか、面倒なお客さんに当たったりとか、他の課や県庁から電話かかってきて「この数字合わないんですけど」と言われて調べなければならなくなったり・・・。
いろいろ予期しないことが発生するものです。
普段から要領よく仕事をしている人でも、必ず繁忙期というのはあり、さらにそこに余計な、いや、突発的な仕事が重なると、残業ゼロを維持するのは難しくなります。
出来ることは何か?
「やったことのない仕事」と「仕事が重なる時」は残業になりやすいという話をしました。
「それでも残業ゼロの人はいる」と言う人もいるかもしれませんが、いきなりそこを目指すのは難しいはずです。
では、どうしたらいいか?
結論から言うと、この2つ以外なら残業が減らせるということです。
「帰りづらい」という言葉、主語は「私」
例えば、帰りづらいから残業してしまう。
これって実は、帰りづらいと思っているのは自分の問題だったりします。
帰りづらいという言葉は、そう思う人が主語です。
つまり「私が帰りづらい」のであり、「周りの人が帰りづらい」のではありません。
言い換えると、勇気がないことが問題なのです。
勇気を出して「すいません今日は…」って言ってみると意外に周りの人は何も言わないものです。「いやいや、それが言える雰囲気じゃない」と思うかもしれませんが、言ってみないと分かりません。例えば10人中7〜8人が残業しているくらいの職場なら全然言えるはずです。
私は霞ヶ関での勤務を経験したことがあります。私の課では50人中50人が早くても夜10時までは残っていました。研修員の立場だったので常に業務がたくさんあるわけれはありません。夜7時にもなればやることが無くなるのですが、上司に絶対服従の文化の中で、「すいません、今日は…」なんて、とても言える雰囲気ではありませんでした。本当に忙しいのは1割〜2割の職員でしたが、みんな、やることが無くても11時くらいまでは残る。そんな環境で誰も帰ろうとしないのです。
でも、そんな職場ってはっきり言ってオワコンです。
私は1年という期間が決まっていたので我慢しましたが、もしこれを読んでいる方の職場がブラックならば、すぐに退職して別の職場を探すべきです。
話を戻しますが、無駄な残業には、勇気がなくて帰れない以外にもあります。
褒めてくれない時は必要以上に仕事をしてしまうもの
「必要以上に丁寧に作業している」というのが残業の原因となっている場合も多いです。
これは、「なんで自分ばかり」と被害意識が強いときや、「こんなに頑張ってるのに」と褒めてもらえない時に起きやすい症状です。
では、なぜ「自分ばっかり」とか「こんなに頑張っているのに」と思っている時に残業が増えるのか。
一つは、怒りが残業の原動力になるということ、もう一つは、努力を認めて欲しい気持ちが原動力になることです。
一杯いっぱいの時ほど無駄な残業をしてしまうメカニズム
こんなに仕事が忙しくてツラい。一杯いっぱいだ。
こういう時って、怒りや嫉妬などのネガティブな気持ちも同時に強くなっていきます。
「あの人は仕事が少なくてずるい」とか、
「あの人いい加減でずるい」。
こういう時に怒りや嫉妬の裏返しで出てくる感情が「正義感」です。
「あの人は要領よくやっているけど私はちゃんと正確に丁寧にやる!」
「私はきちんと、こういうところまでやっているんです!」
一見すると、真面目な姿勢で仕事に取り組んでいるので、
自分でも気づきにくいのですが、
その原動力は「怒り」であり、承認欲求、究極的には「褒めて欲しい」と言う感情なのです。
「なんで自分はこんなに忙しいんだろう」
→「あの人は仕事が少なくてずるい」
→「自分は仕事が多い」
→「自分がこんなに仕事をしていることを周りの人に知って欲しい」
「なんで自分の仕事はこんなに大変なんだろう」
→「あの人はいい加減に仕事をしていてでずるい」
→「自分は正確に丁寧に仕事をしている」
→「自分の仕事のやり方が正しいことを周りに見せつけてやりたい」
さらに抽象化するとこうなります。
「苦しみ」(ツラい)
→「怒り」(あいつがムカつく)
→「自己憐憫」(自分が可哀想)
→「承認欲求」(認めて欲しい)
そう、最初は単純な苦しみだったものが、
他人への怒りとなり、結局は承認欲求、つまり褒めて欲しい気持ちが原動力で仕事をしているのです。
歪んだ気持ちから仕事をしているので、無駄なことに時間をかけてしまうことも多々あります。
例えば、必要以上に細かくチェックしたり、必要以上に資料を揃えようとしてしまったり、必要以上に前倒ししたり…。
こういう時は冷静さが欠けているので
上司から「そんなにやらなくて良い」と言われても反発心しか湧いてきません。
自分では必要と思ってることでも、実は必要ではないことをしている。
この状態で冷静に自分の残業の内容を見極めるのは無理です。
一杯いっぱいの時ほど、効率的に仕事を行うのは難しく、余計な仕事をしてしまうものです。
ですから、
普段から一杯いっぱいになる前に効率的に仕事を終わらせておくことが大事なのです。
他にも残業にはいろんなパターンがありますが
「やったことのない仕事」とか
「仕事がどうしようもなく重なった時」はある程度仕方ない。
それ以外はある程度コントロールできる!
そこさえ抑えておけば、「残業なんて大したことない」と思えるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
