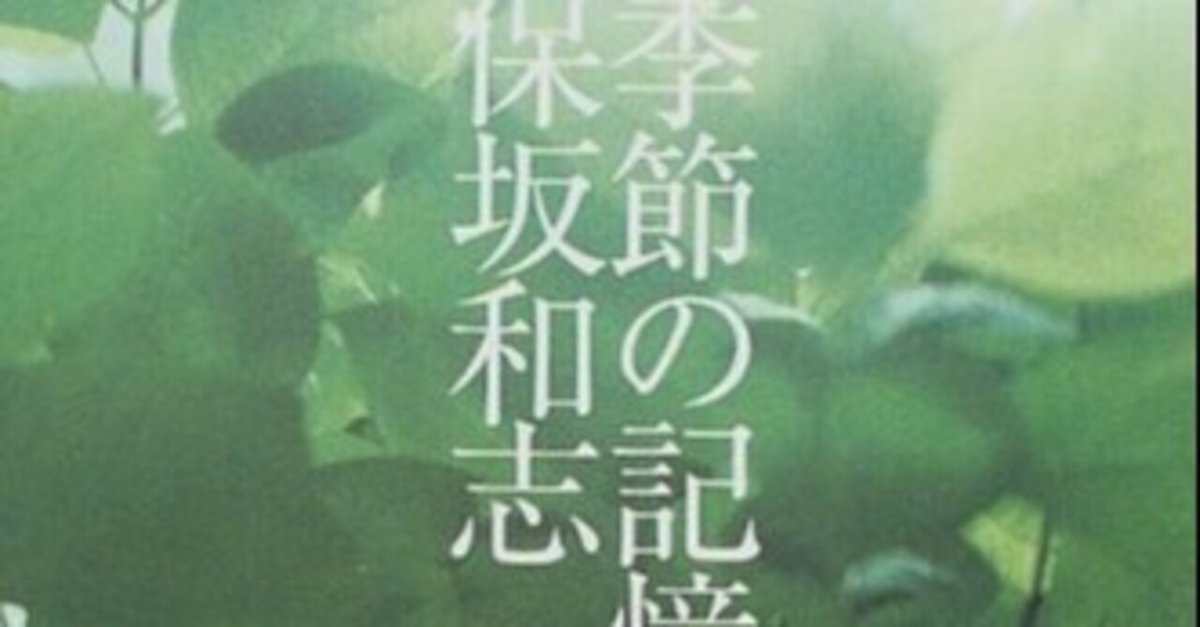
保坂和志『季節の記憶』中公文庫
この小説の魅力は、人々のゆるいつながり。この「ゆるさ」がポイントだ。どこにも「きつい」ところがない小説だ。
主人公は妻に去られた中年男性で、5歳の息子を育てながら自宅で仕事をしている。彼はお金より暇がほしくて会社をやめたぐらいで、マイペースの人。この親子と、数軒先の近所に住む便利屋の男とその妹の4人が中心となり、そこに主人公の昔の同僚やら、いったいどういう関係だか読んだけど忘れるような遠方の知人やらが訪ねてきたり、電話してきたりする。便利屋の妹の友人が離婚して戻ってきたりもする。
それらの人たちが「ゆるく」つながっている。鎌倉を舞台に、そのゆるいつながりが丁寧に描かれていて、大きな出来事は何も起きず、かといって単調で退屈というのではない。のんびりしながらも、どこか哲学的な会話もあって、主人公たちと一緒に「そういえば、そうだよなぁ」と考えてしまう。
この人の小説によくあるように、今回も気のいい、おっとりした人たちが集まって、のんびりした会話を展開するわけだが、今回は珍しく少々問題がある人も出るのである。離婚して実家に戻ってきたその女性は、人を見ると血液型を尋ねて勝手に性格を決めつけたり、まったく職歴もないのに「ネットワーク」で何かを始められると思い込んでいる。主人公も彼女と話すときはいらいらするのだが、単にネガティブな登場人物として描かれるのではなく、彼女さえもゆるい網のようなつながりに自然と入り込んでいる。
それは「有機的」と形容したいような人間関係で、仕事を始めるための機能的な「ネットワーク」などとは対極のつながり方だ。そこに「個」がないわけではないのだが、「個」と「個」は完全に切り離されることがない。まるで部屋から部屋へ、欄間や襖から音が伝わり合う日本家屋のようだ。
このつながりの中心にいる5歳の息子はまだ字を習っておらず、ただ近所の人たちに可愛がられ、見守ってもらえている。いわばこれは「楽園時代」の話なんだな。このあと、息子は小学校に上がるし、字も覚えることになるだろう。近所のやさしいお姉さんは結婚して離れていくかもしれない。人々の事情が変わってしまったら、それは「失楽園」というほど大げさなものではないけれど、このゆるいつながりもまた確実に変化していくのだろう。それまでの、奇跡のような楽園時代だ。
最後に読み終わって気がついたのだが、保坂和志の小説なのになんと猫が出ない。驚いてしまったが、小さな息子がどこか猫的な立場にいるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
