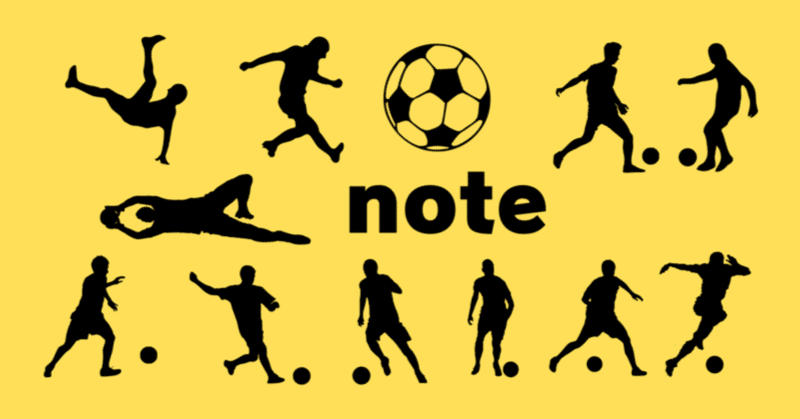
久々にWEリーグを観て、サッカーの要素を考えた。
早朝3時くらい、久しぶりに、DAZNでWEリーグの試合を観る。首位を走る三菱重工浦和レッズレディースと、上位3クラブと大きく勝ち点差がついての4位ノジマステラ神奈川相模原の対戦。しっかり見て、「女子サッカーに耳をすまして」noteサイトで久々にレビューでも書こうかな、と思っていたけど、前半だけ観て、とりあえず、これまでのような形式の耳すまレビュー(全選手レビュー)を書くのはやめとこう、となっている。WEリーグ初年度、浦和駒場スタジアム現地で私は、同じ対戦カードの試合を観に行っている。その時は、栗島・柴田のダブルボランチの見事なコンビネーションが圧巻で、なすすべなくノジマステラが負けてしまったという印象の試合だった。浦和がめちゃくちゃ強かった。今回の試合も、結果としては、浦和が完封勝利した。しかし、前半しか観ていないが、ノジマステラも決して完敗という内容ではなかった。浦和の先制点の猶本光のカウンターからのゴールの直前は、実はノジマステラの決定的なチャンスのシーンだった。ピンチはチャンスという言葉があるけど、チャンスがピンチになることもある。そんなことを象徴する前半4分の現象だった。
この試合を観ながら、サッカーで重要な要素は何だろうという根本的なところを考えてみた。
まず、ボールコントロール。特に狭い局面でも簡単に奪われないボールコントロール技術があると、試合で大きな武器となる。
次に、ポジション。ボールを持っていない時に、良い距離感でポジショニングをとって、良いタイミングで、良い状態でボールをもらえる準備をする。サッカーはボールに触っている時間より、ボールを持っていない時間の方が圧倒的に長く、だから、準備する想像力・創造力がとても大切な要素のように感じる。味方や相手の個性を理解しておくことも重要だろう。個性を理解しておくことで、プレーの予測ができ、どういう距離感・関係性でボールを受けるとよいかという判断がしやすくなる。もちろん、個性なんて固定的なものではないので、予測はあくまで予測で、外れることはあるのだけれど。
そして、プレーの正確性。冒頭に述べたボールコントロールもそうだし、トラップ、パス、ドリブル、シュート、ひとつひとつのプレーが研ぎ澄まされていて正確な選手は、当然ながら良い選手だなと思う。
それから、判断。私にとって、サッカーの醍醐味ってここにあるのではないかな?と思うほど、とても大切な要素だと思っている。教科書に書かれたことを実行する、というイメージではなく、自分自身で状況から判断してプレーを選ぶ。そして、失敗したり、成功したり、を積み重ねていく。このことが、きっとサッカーの楽しさ・面白さの大きな要素なのではないかと思っている。いくら勝利しても、いくら優勝しても、指導者の操り人形のように、自分自身で考えたり判断しないで、常に顔色を伺ってプレーしているようなサッカーは、果たしてサッカーといえるのか?という問いは常に私の中にある。
それから、ボールの奪い方。当然ながら、相手と距離がありすぎれば、相手は自由にプレッシャーを感じずにプレーできるし、ボールを奪うことなど到底できない。ゲームの展開を読み、まず一番決定的に流れを変えることのできる「インターセプト」を狙う。それが難しければ相手が前を向けないように、振り向かせないように後ろを向いてプレーさせるように追い込むことを狙う。それも難しければ、前を向いた瞬間のファーストタッチを狙う。それも難しければ、隙ができた瞬間にボールを奪えるような「間合い」(距離感)を保ち、いつでもボールを奪えるような準備・体制を整え、しっかりとボール保持者についていき、ステップを踏みながら、軽くかわされないように即座の対応ができる体勢でのぞむ。また、後ろにセカンドディフェンダーがいることが確認出来たら、ある方向だけ確実にシャットアウトして、セカンドディフェンダーがボールの展開を読みやすいような方向づけをして、連携で奪うという方法もある。
いろんなサッカーのプレーが技術としてあるけれど、そこに「闘争心」が加わり、アグレッシブに連続してプレーし続けることができると、よりサッカーの強度が増す。浦和なら柴田選手、ノジマなら石田千尋選手や笹井選手は、そういったメンタリティが感じられる選手だと思った。やはり、360度のプレッシャーがある中でプレーしないといけないため、ボランチの選手はそういうメンタルの強さが感じられる選手が多いような気がする。昔はJリーグジュビロ磐田にドゥンガという闘将がいたし、清水エスパルスの戸田和幸とか、ボランチをやることも結構あった中田英寿とか、シンプルに「勝ちたい」という気持ちが強く感じられる選手は、やっぱり実際強い。
サッカーは「タイミング」も重要。パスを出すタイミング、パスを受けるタイミング、仕掛けるタイミング、ボールを奪いに行くタイミング、シュートを打つタイミング・・・挙げだしたら切りがない。サッカーにミスはつきもので、相手に一瞬隙が生まれることがある。その一瞬の隙に、決定的なプレーができると、ゴールが決まったりする。その力の差が、浦和とノジマの差なのかな、と思う。
サッカーというスポーツは、格闘技のような要素があり、ボディコンタクト・接触は避けられない。それに対しても積極的にアグレッシブに、しかしファウルを犯さずにプレーできることもとても大切な要素だ。もちろん、自分自身が怪我をしないことも重要。
フィールドという「空間」をしっかりと見渡せる、視野の広さも重要だし、広さだけでなく、細かい場面情報を認識する能力も重要で、最適な判断を下す材料になっていく。こうした能力が非常に優れているなと感じさせるのは浦和の塩越選手。直前までしっかりと場面情報を細やかに認識していると感じられるプレーが非常に多く、プレーがスマート。
空間の話をした後には、時間軸の話もしておこう。最終的にはゴールと失点の数で勝敗が結果として決まってしまうわけだから、点差は何点で、残り時間はどれくらいあって、といった時間軸の要素も頭に入れておくことは必要だ。永遠に試合が続くわけではないのだから。90分なら90分、その中で最大限に力を発揮していくことを考えなくてはいけないし、90分ずっと高い集中力でマックスの力を発揮していくことは難しいわけだから、強弱をつけることも意識しないと、どこかで息切れしてしまう。もちろん、基礎体力を日ごろからつけるという前提があってのことだが、どうしたって多少のプレーの質の高低が時間帯によって出てきてしまうのはいたしかたないし、そのことも考慮に入れて、ゲームプランを練る力も必要だ。そういう時間軸でチームとしてしっかりゲームプランを臨機応変に変更する力を遺憾なく発揮したチームは、昨年度のINAC神戸レオネッサだったのではないかと思う。ポゼッション率は低い試合もあったりしても、なんだかんだで、最終的に勝利を収めていたり、引き分けという結果でなんとか逃げ切ったり、とにかく負けることが非常に少なかったし、ゲームプランが巧かった。おそらく、ゲーム展開に応じて、チームの意思統一というのが常にしっかりできている唯一のチームだったのではないだろうか。
4月29日(土)の浦和対ノジマの試合の前半を観終えて、重要だなと思ったことはそれくらいかな。スタッツをみたら、シュート数とコーナーキックの数は圧倒的に浦和が多かったので、後半は観ていないけど、前半以上に後半は浦和の完勝という内容だったのかなと思う。浦和のゲームプランは理想的だったということなんだろう。
後半を実際に見たら、また感想は変わるかな・・・。
#ジョガボーラきららさいたま のある記事に関しては、「ジョガボーラきららさいたま」の活動費として寄付し、大切に使わせていただきます。その他の記事に関しましては、「耳すま」の取材活動経費として、深化・発展のために大切に使わせて頂きます。
