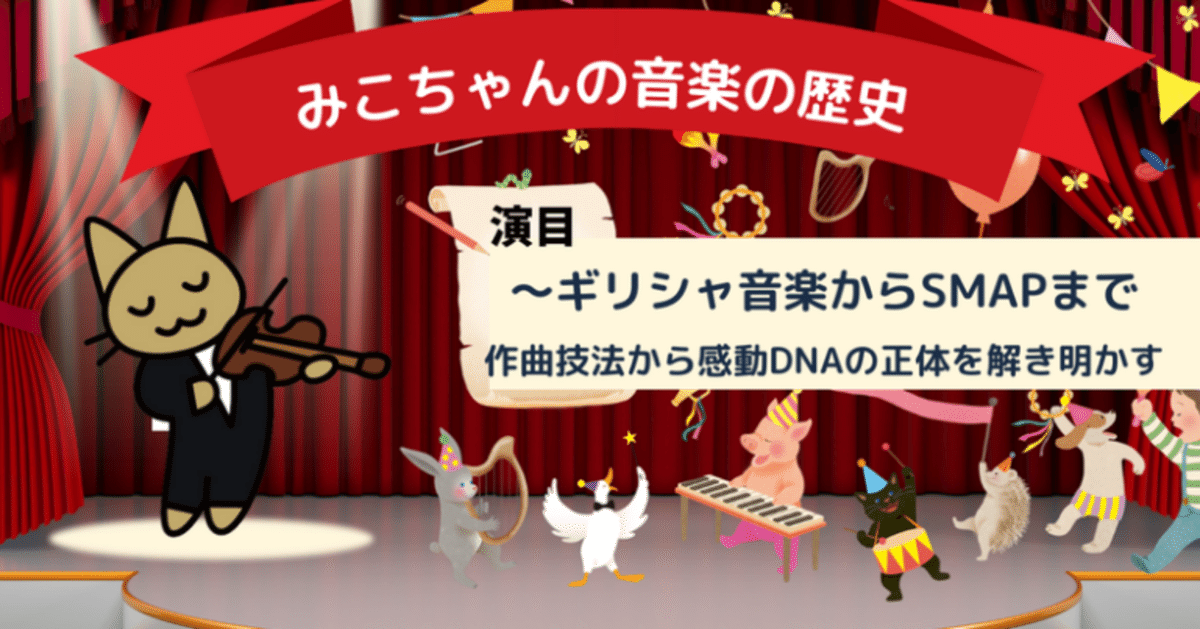
ベートーヴェンはやっぱり(とてつもなく)エッチです
では、みんな大好きベートーヴェン!
じゃじゃじゃじゃーん!
この有名な出だしは、ベートーヴェンの作曲技法をよく表しているので、このシリーズの掟を破って、ちょっとだけ楽譜を見てみましょう。といっても、第2回で楽譜引用したときと同じように、おたまじゃくしは読まなくていいです。図形として、「なるほど、そう見えるな」でまったくかまいません。
印象はどうですか?まるで、ハンマーを持ってじゃじゃじゃじゃーんと、五寸釘で藁人形打ち込んでいるように聞こえませんか?そして、楽譜もそう見えませんか?
そうですよね、印象として垂直方向にぶった切っている。そんな感じがしたら、これを読んでくれているあなたは、すでにベートーヴェンの本質に触れています。
これが、和声というものなのです。例えばドレミファソラシドというを主要な部分を取り出して、ドミソ。これを縦方向に弾くと、Cというコードができあがります。
ソ
ミ
ド
ベートーヴェンはこの縦方向に積み重ねる音の作り方を生涯追求しました。というか、これに魅せられて囚われの身になりながら、脱出を試みた生涯だったと言ってよいでしょう。
では、流れるような、モーツアルトのような旋律はベートーヴェンにはないの?たくさん知ってるよ!という方もいらっしゃるはずです。もちろんそうです。和声の達人ではありますが、ほとんどモーツアルトに匹敵するようなメロディアスな作曲ももちろんベートーヴェンはできました。
でもですね。
違うんです、モーツアルトとは違う。
モーツアルトは旋律に和声を同時に付けました。だから付けたというのはおかしいかな。間違いなく旋律と和声を同時に形にしているんですが、モーツアルトの脳みそをかち割ってみると、ほんのわずか、0コンマ0000000000000000.X秒くらい、彼は旋律を先に作曲しています。
ところが、ベートーヴェンは旋律でさえも、縦方向(和声学的)に作曲しているのです。
その例をお見せしましょう。
これも有名な曲なので、好きな方もいらっしゃると思います。あれ!?いつも聴いているのと違う!と思ったでしょう。そうです。高松あいちゃんがヴァイオリンで弾いていますが、これはもともと、ピアノ曲ですね。
これがピアノ譜なんですが、えーいと右手広げて主に薬指と小指で頑張って弾いているのが、赤い部分で、これを高松あいちゃんはバイオリンで抽出して弾いているというわけなのです。

モーツアルトと違って明らかに和音を先に作って、それに旋律を載せていることが分かりますよね。
鍵盤で視覚化するともっと分かりやすいです。こうなる。
一番右側の色がついているやつが、高松あいちゃんのバイオリンの旋律です。☆いわゆるショパンみたいに右手の旋律パートと、左手の伴奏パートって感じで分割されていませんよね。右手だって真ん中から左3本、中指、人差し指、親指は、ショパンで言えば左手で弾くべき伴奏の役割を弾かせています。
耳で聴いている分にはいいんですが、中身は、まあ、異様です。
曲は文句のつけようのないほど美しく極上に洗練されているけど、作曲しているベートーヴェンのことを思い浮かべつつ楽譜を見ると、まるで六本木の交差点を下記の格好で歩いているようなもんだよね。彼なら歩きかねない。アマンドの前で待ち合わせして、こいつが向こうから来たらどうします?目があって、「みこちゃーん、待ったあ?」とか言われる前に、他人のふりして帰りますよね(笑)。これが作曲家ベートーヴェンです。

でも、おなじくベートーヴェンでも、旋律優先で作曲しているものももちろんいっぱいあります。例えばヴァイオリンの有名どころだとこれです。
ピアノに一体化した楽譜にすると比較できます。
最初の運命の動画と比べてみてください。これも、おたまじゃくし読まなくていいです。図形としてみてください。運命は縦方向に輪切りにされてますよね。でも、このスプリング・ソナタはなめらかに明らかに横に書かれています。これが旋律優先の作曲のやり方で、ベートーヴェンはもちろんこれもできる。
でも、旋律優先しているな、という曲であっても驚くほど凝りに凝った和声進行の裏付けがあるので、軽やかに聞こえる曲でも、とても重厚な奥行きがある。これがベートーヴェンの魅力だと思います。
だから、ベートーヴェンをもっと楽しみたい方は、この縦方向の音の響きに気をつけてみると、もっともっと、ベートーヴェンさんの肉声が聞こえてきますよ!
最後にそんな旋律的でありながらそのすべての旋律に和声学的裏付けのある異様に美しい、とんでもない曲をご紹介して、縦方向の重厚な建築物が、横方向に溶かされていく、得も言われぬ背徳的な倫理的堕落をお聴きください。
トルストイの『クロイツェル・ソナタ』はご存知ですか。
性的な魅力にひかれてめとった妻。そして妻のバイオリン教師との不貞を知り、懊悩の果に妻を殺した夫がそのどろどろの精神の彷徨を語る小説ですね。一皮むけば博愛主義者のトルストイもこういう欲望があったのかもしれませんね。とはいえ、そこはトルストイなので、人間の理想と性愛との問題ってことでおさめてはいるんですけど、そんな取ってつけたような子供だましの嘘で当局の目はごまかせず(爆)、おもいっきり発禁扱いになってしまいました。
この曲聴いたら、自分の中に封印していたあんな小説……。書いてみたくなるのもしょうがないかもしれませんね。
和声という堅牢な倫理から、放恣で美しい女性の肉体のような旋律がとろけだす様子を、ぜひトルストイが「やべー」とつぶやいている姿を想像しながら聴いてみてください。
すぐに股を開く娼婦に金払うより、親友の貴婦人を、あるいはトルストイのように自分の貞淑な妻をベッドの上でじっくり娼婦にした方が、男性は愉しいですよね。ベートーヴェンの音楽とは、ひとことでまとめるとそんな音楽です(爆)。その秘密は堅牢な和声から蕩け出す旋律。それを可能にするのがベートーヴェンの和声学です。
それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
