
【短編小説】また冷蔵庫を開けるまで
小学校三年生の時にパパとママが離婚をした。離婚という言葉はまだ分からなかった。ある日の週末に、引越し業者の人がママの持ち物を全部トラックに乗せて持っていった。
出かける前に使っていた玄関の出入り口の姿見の大きな鏡や、学校から帰るとランドセルを放り投げて「なんかないかな」とまっさきに開けていた大きな冷蔵庫などが、見覚えのあった風景からすっかりお年寄りの前歯が抜けたように消えた。
これが離婚ということなのだなと、わたしは離婚という言葉を覚えるよりより前に、現実から生々しく学んだ。
食器もママがこの家に持ってきたものばかりだったらしく、ほとんどなくなっていた。作っても、入れる器がない。我が家ではその日からセブンイレブンが冷蔵庫になった。
プラスティックのセブンプレミアムの容器と、無造作に開封されたレトルト食品が、パッケージのまま毎日、三年間食卓に朝も夜も、そして休日は昼も並べられた。味は美味しかったと思う。
六年生の時にパパが再婚した。
真っ先にパパが買ったのは冷蔵庫だった。まるで入れ歯のように、三年間欠けていた場所に、また冷蔵庫が備え付けられた。戸惑うわたしをさそって、パパがスーパーに手を引いた。カートの二つのカゴの中には食べ切れないような食材が並んだ。懐かしい光景だった。
家に帰って、パパがこころなしか上機嫌で野菜、お肉、調味料、いろんなものを冷蔵庫に入れていった。
疑問を差し挟むということは、わたしにはなかった。大人の世界のことは分からない。これが三年前からわたしの決定的な人生観になったから。
新しいお母さんはどんな人だろう。
夕方チャイムが鳴った。
まるで昔のママのように、急かしているかのように三回連続で鳴った。こんな時にママのことを思い出してはいけない。首を振って、ママの面影を追い払った。
「はあい」
パパが無邪気な声を上げて玄関の扉を開けた。
わたしはリビングの椅子に座ったままで、目を固くつむって下を向いていた。
「ただいま。みこ」
懐かしい声が聴こえた。
目を開けるとママがいた。
「もう一度ママと結婚したんだ」パパが言った。
「そんなことできるの」
「離婚しても、婚姻届を出せばまた結婚できるんだ」
「おかえりなさい」ママの目を見た。
三年ぶりで、乾いていた涙が暖かく自分の頬を伝った。
三年間何がパパとママの間にあったのかは分からない。でもまたこうして、ママと冷蔵庫がここにある。それを受け止めようと思った。
「もう夕飯の時間だし、何か作りましょうか」
ママが、他人行儀のような丁寧語でパパに言った。
「そうだね、お願いしようか」
そんな他人行儀なやり取りはやだ。こう思ったわたしは言った。
「今日からは、ごはんは、みこが作るよ」
そういって、ママを遮って冷蔵庫を開けた。
パパが無造作にかごに入れて買ってきた食材が、料理ができ上がったときのような感じで、まるで調理されるのを待ちわびて楽しく踊っているかのようだった。
何を作ったのかは覚えていない。適当になにかを選んで、適当に火を通しただけだったと思う。
しんなりと新品の冷蔵庫で冷えた食材は、暖かく調理されてそれを三人で笑いながら食べた。わたしは、ぎこちなく笑っていたと思う。でもそのぎこちない笑いはいつしか溶け、楽しい笑いがまた日常になっていった。
料理が趣味になった。
そしてそれから、ひんやりした冷蔵庫を勢いよく開けると、いつも暖かい気持ちになった。
やっぱみこちゃんは、この企画に参加するなら本格小説だろーってことで書いてみました。主催者の皆様(^▽^)よろしくお願い致します。
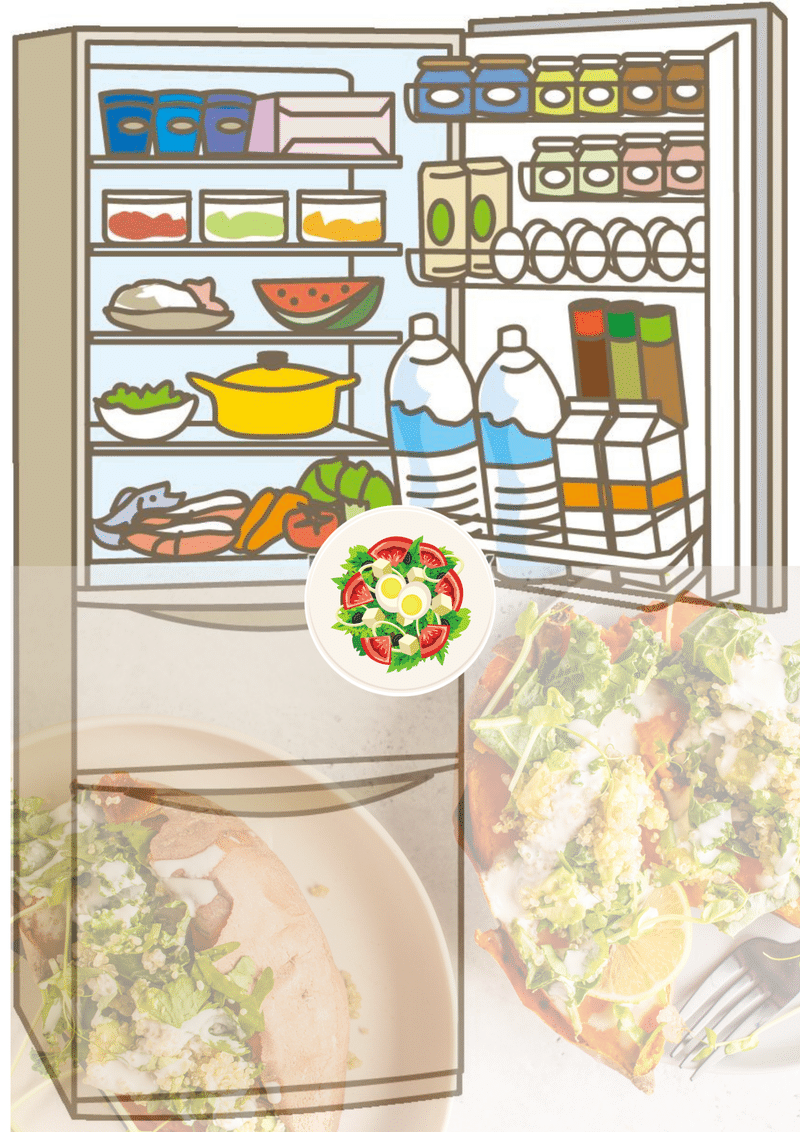
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
