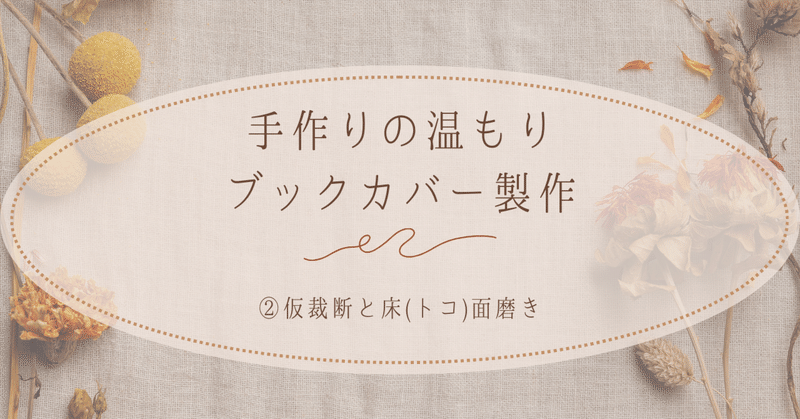
手作りの温もり ブックカバー製作②仮裁断と床(トコ)面磨き
こんにちは!
「手作りの温もり ブックカバー製作」シリーズ、第二回です。
前回は革素材を仕入れ、型紙を起こすところまで製作しました。
↑前回の記事はこちら
今回の副題は「仮裁断と床(トコ)面磨き」。
この順序で執筆しようと思ったのですが、先に床面磨きをしてから、仮裁断をするところまでをまとめようと思います。
言い訳…じゃなくて、理由はちゃんとあります!後ほどお伝えしますね。
銀面と床面
革には銀面(表)と、床面(裏)があります。
動物(今回では牛)の皮の表面を銀面と呼び、裏面を床面と呼びます。
「ギンメン」「トコメン」と読みます。
完成した革製品をイメージした時に、一般的に想起される「革」の質感というのは、銀面のことを指すかと思います。

「銀面」というワードの由来は諸説ありますが「銀のような輝きがあるから」という説や、革製品の技術が来日した明治時代に革を意味する英単語「grain(グレイン)」が訛って呼ばれるようになった説などがあるようです。
銀面は肌触りが良く見た目も綺麗なため、製品の表面になることが多いです。
一方で床面は銀面とは異なり、製造過程で漉き加工された状態のため、仕入れた状態では表面が毛羽立っています。

今回使うようなタンロー素材の床面は手触りがいまひとつなため、まずこのざらざらした床面を綺麗に整えてあげる必要があります。
その作業が、これから説明する「床面磨き」です。
床面磨き
「床面を磨く」とは、一体どんな作業なのでしょうか?
実は、「床面磨き剤」という専用の製品があるのです。
それがこちら……。

その名も「トコフィニッシュ」!
そのままなネーミングですね。中には、粘性のある透明な液体が入っています。成分表示を見ると、どれどれ……?
「水溶性樹脂、有機アルカリ、水」
誤解を恐れずに言ってしまうと、のりを水で薄めたような液体です(失礼)。
これを指ですくって、床面にムラの無いように塗っていきます。
が、その前に!
今回はここでひとつ新しい知識を得たのでそれを活かしていきます。
それが最初に言い訳をした内容です。
床面の毛羽立ちには、「向き」があります。
実際に撫でると分かるのですが、サラサラと手触りの良い方向と、そうでない方向があります。動物由来の素材という感じがしますね。
今回は、そんな床面の「向き」に逆らわないように床面磨きをしていこうと思い、仮裁断を後回しにしました。
その知識を念頭に置いて、先ほどのトコフィニッシュを塗り伸ばしていきます。
ぺたぺたぺた……。

トコフィニッシュを指で大体均等に塗り伸ばしたら、そこからさらにツールを使って、毛羽立ちを整えていきます。
ウッドスリッカーと呼ばれる木製の棒あるいは板状の道具や、ガラス板を使う方法が推奨されることが多いですが、今回使ったのはこちら。

「クラフト社製『ヘラ付ヘリ磨き』~!」
こちらはプラスチック製で、頭の部分でヘリ磨き…つまり断面を整えることができます。その機能はまた後の記事で登場予定なので、今回は右側の板状になっているヘラ部分だけを使用します。
というわけで頭のパーツは一旦お役御免。

これでひたすら一方向に、床面を磨きます。
圧を加えながら、革の組織にトコフィニッシュを浸透させるように磨いていきます。
私の場合、一度均等に磨いて表面の水気が無くなったら、もう一度トコフィニッシュを塗り伸ばして再度磨きます。
~それから30分後~

右が床面磨きを終えた状態
こんなにも床面の状態が変わります!
写真では上手く伝わらないかと思いますが、手触りがまったく違います。
上手に床面を磨くことができました。
トコフィニッシュの水分が完全に飛ぶまで、風通しの良い室内で乾燥させます。乾燥すると革が曲がるので、乾いた後に適当な重しを乗せて癖を除いておきます。
仮裁断
最後に、床磨きをした革を大雑把に完成品のパーツごとに切り分けておきます。

次回は「染色と色止め」の作業を進め、執筆しようと思います。
……が、染色の作業中にちょっと失敗をしてしまいまして。
次の記事は少し遅れるかもしれません。すみません……。
今回も最後までご覧頂き、ありがとうございました!
アドバイスやコメント等頂けると、大変励みになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
