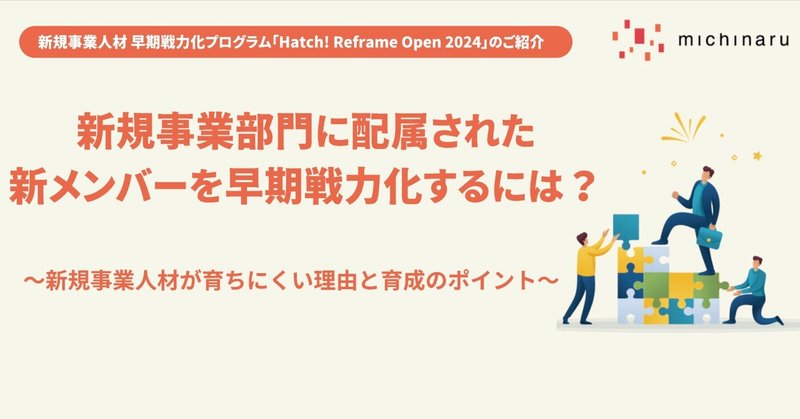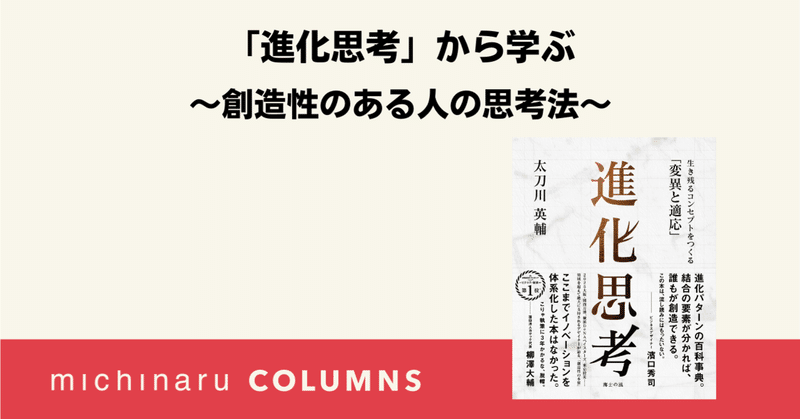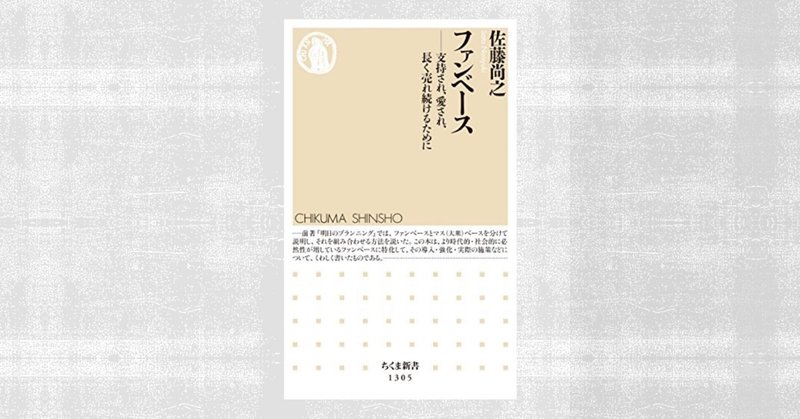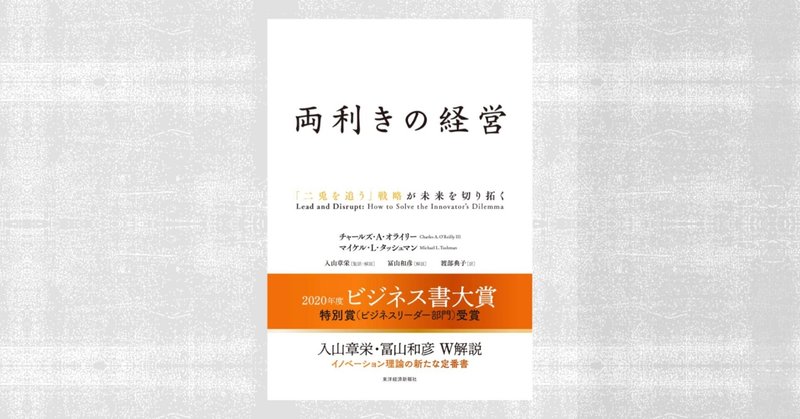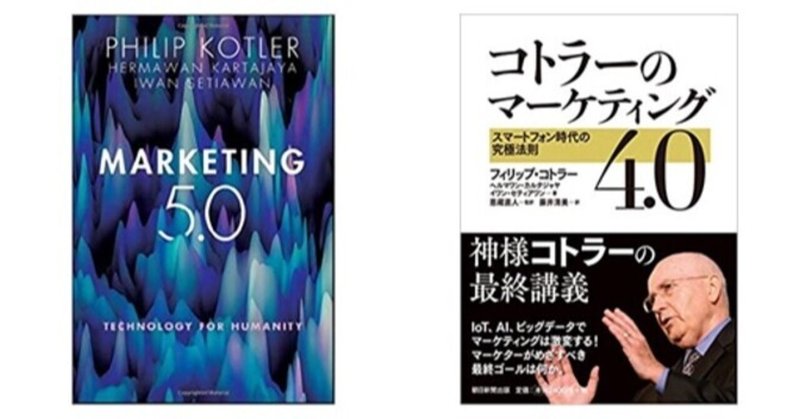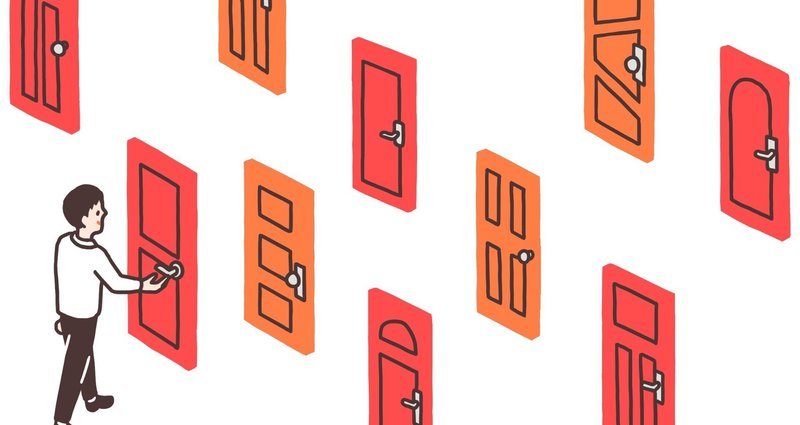
- 運営しているクリエイター
#新規事業

vol.12 「世界の知見をつなぎ」イノベーションを誘発するファーストペンギン 〜ビザスク端羽英子氏さんのはじめの一歩〜
ミチナル新規事業研究所、特派員の若林です。 組織に潜む「ファーストペンギン」が一人でも多く動き出して欲しい!という想いで知恵と勇気を与える記事を定期的にお届けしていきます。 第12号の記事では株式会社ビザスクを立ち上げ、「世界中の知見をつなぎ」イノベーションを誘発し続けているの端羽英子さんのはじめの一歩を紹介します。 学生結婚をきっかけに将来のビジョンが変化する熊本県出身で父親が地方銀行勤務、母親は専業主婦だったという端羽英子氏は3姉妹の末っ子で一番上の姉とは10歳違いだと

vol.8 「世の中を面白くする」スペースシェアサービスを生み出したファーストペンギン〜スペースマーケット:重松大輔さんのはじめの一歩〜
ミチナル新規事業研究所、特派員の若林です。 組織に潜む「ファーストペンギン」が一人でも多く動き出して欲しい!という想いで知恵と勇気を与える記事を定期的にお届けしていきます。 第8号の記事では当時日本ではあまり行われていなかったスペースシェアリングサービス「スペースマーケット」を立ち上げた、重松大輔さんの始めの一歩を紹介します。 社外に刺激を求めていたサラリーマン時代の出会い STRATUP DB インタビュー記事より 新卒からの5年間、大手通信会社に勤めていた重松氏は社