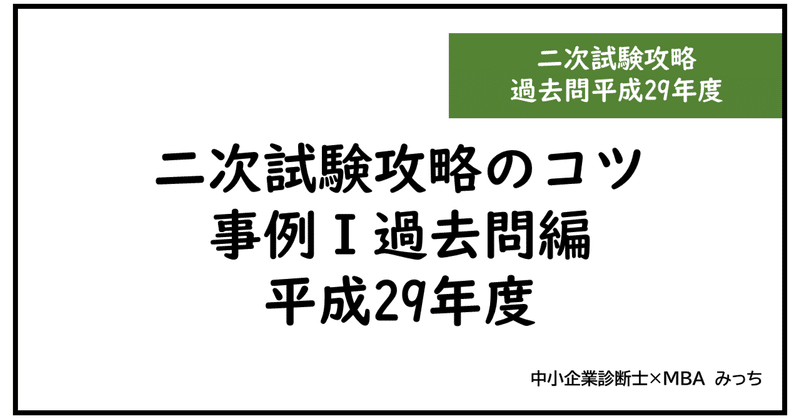
過去問チャレンジ事例Ⅰ(平成29年度)
概要編でお伝えしたコツとフレームワークを元に、過去問にチャレンジしていきます。二次試験は回答が公開されていませんが、正しい考え方で解くことが回答に結びつきますので、しっかりと思考の癖をつけていきましょう。
問題
<設問>
第1問(配点 20 点)
景気低迷の中で、一度市場から消えた主力商品を A 社が再び人気商品にさせた最大の要因は、どのような点にあると考えられるか。100 字以内で答えよ。
第2問(配点 20 点)
A 社の正規社員数は、事業規模が同じ同業他社と比して少人数である。少人数の正規社員での運営を可能にしている A 社の経営体制には、どのような特徴があるのか。100 字以内で答えよ。
第3問(配点 20 点)
A 社が工業団地に移転し操業したことによって、どのような戦略的メリットを生み出したと考えられるか。100 字以内で答えよ。
第4問(配点 20 点)
A 社は、全国市場に拡大することでビジョンの達成を模索しているが、それを進めていく上で障害となるリスクの可能性について、中小企業診断士の立場で助言せよ。100 字以内で答えよ。
第5問(配点 20 点)
「第三の創業期」ともいうべき段階を目前にして、A 社の存続にとって懸念すべき組織的課題を、中小企業診断士として、どのように分析するか。150 字以内で答えよ
事例1のコツ
1.組織の問題である
2.時制を意識する
3.キーワードを適切に抑える
4.因果関係を書く
5.SWOTを意識する
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
フレームワーク
こちらのオリジナルフレームワークを元に考えていきましょう。

解き方
基本的な解き方は、下記の6つのステップです。
まず設問文を読みイメージを固めながら、問題文を読みましょう。
問題文を整理すること、設問文と適切に対応させることが重要ですので、
上記のオリジナルフレームワークを活用しながら、論点ズレがないように
解答を作成していきましょう。
①設問文を軽く読む
②問題文を読む
③再度問題文を読み、キーワードにマークをつける(特に強みは重要)
④設問文を読み込み、解答の制約条件や出題者の意図をくみ取る
⑤キーワードをフレームワーク(時制・事業環境・組織・GAP)で整理する
⑥設問文の時制とキーワードを対応させ回答を作成する(強みを意識しながら)
※補足)④は、設問文に組織上の課題をあげてくださいなど、解答する際に制約があったりします。また、設問文に、どういう方向性で解答してほしいかなどの意図が含まれている場合もありますので、読み取りましょう。
▼フレームワーク作成方法
・強みを記載
・過去・現在・未来×事業環境・組織・GAPを問題文からキーワードを
抽出して記載
・設問で問われている時制と回答の記載を間違えないように対応させましょう
■強み
・主力商品の知名度の高さ
・取引先の支援
(主要取引先から販売支援の継続を条件に商品の存続を強く求められた)
・商標権
①過去×事業環境
・A社が事業を引き継ぐ以前のX社時代から高い認知度の主力商品
・前身のX社は100品目以上の菓子を扱い、10億以上の売上のある有力企業だった
・バブル崩壊後の景気低迷で販路拡大・生産力増強の過剰投資により
巨額負債を抱え、事業継続を断念
・県を代表する銘菓として人気だった商品が消えてしまうことを惜しみ、
菓子工業組合にひいき筋がその復活を嘆願
・商標権をA社社長が取得
②過去×組織
・A社社長と仲間7名で事業再建を開始
・県の支援で低利融資をうけ、かつての品質・食感を出すための機器を多額の資金を使って購入
・昔ながらの味の復活のために数年の年月をかける
・製造設備面に課題があったものの、商品アイテムを主力商品だけに限定してスタート
③過去×環境と組織のGAP
・厳しい市場環境の中、少ないリソースで戦う必要がある
④現在×事業環境
・X社から引き継いだ主力商品に依存
・全国市場への進出、首都圏出店の夢も未達成
・売上30億円の達成目標未達
⑤現在×組織
・製造、営業、総務部門からなる機能別組織
・部門長と9名の正規社員が所属する製造部門
・創業以来営業を担当してきた専務をトップに6名からなる営業部門
(県内外の取引先との折衝や販売ルートの開拓、出荷地域別の配送管理、在庫管理)
・自社店舗による直接販売は行っていない
・正社員18名、非正規社員70名
・人事経理業務は3名の正規社員で、社長の下で担当
・人手による作業である製造工程を大幅に変更し、自動化によって効率性を高められるようにした
・製造設備面に課題があったものの、商品アイテムを主力商品だけに限定してスタート
・2000年半ばに増資して、工業団地に移転
・HACCPに準拠
・3種類のラインアップ野焼き山車を日産50000個体制に整備
⑥現在×環境と組織のGAP
・主力商品依存からの脱却のための新商品開発の体制構築
・全国進出に向けた体制構築、地元以外の営業体制の構築
・さらなる売上増加に向けた社内体制の構築
⑦未来×事業環境
・首都圏への出店、全国市場へ進出
・全国の市場で戦うことのできる新商品開発
・実現のための人材確保・育成
・創業メンバーの定年退職、第三の創業期
⑧未来×組織
・実現のための人材確保・育成
・創業メンバーの定年退職、第三の創業期
⑨未来×環境と組織のGAP
・新商品開発する体制構築
・全国展開実現のための人材確保・育成
・退職する役員の後任
■おおまかな事例の内容と方向性
・地元で有名な銘菓を前身のX社から引継ぎ事業を開始。主力商品に絞り事業再建を行い、売上拡大。主力商品の依存度が高いこと、全国進出のための新商品開発が今後の課題。
第 1 問(配点 20 点)
景気低迷の中で、一度市場から消えた主力商品を A 社が再び人気商品にさせた最大の要因は、どのような点にあると考えられるか。100 字以内で答えよ。
時制:過去
■強み
・主力商品の知名度の高さ
・取引先の支援
(主要取引先から販売支援の継続を条件に商品の存続を強く求められた)
・商標権
①過去×事業環境
・A社が事業を引き継ぐ以前のX社時代から高い認知度の主力商品
・前身のX社は100品目以上の菓子を扱い、10億以上の売上のある有力企業だった
・バブル崩壊後の景気低迷で販路拡大・生産力増強の過剰投資により
巨額負債を抱え、事業継続を断念
・県を代表する銘菓として人気だった商品が消えてしまうことを惜しみ、
菓子工業組合にひいき筋がその復活を嘆願
・商標権をA社社長が取得
②過去×組織
・A社社長と仲間7名で事業再建を開始
・県の支援で低利融資をうけ、かつての品質・食感を出すための機器を多額の資金を使って購入
・昔ながらの味の復活のために数年の年月をかける
・製造設備面に課題があったものの、商品アイテムを主力商品だけに限定してスタート
<ポイント>
再び人気商品にできた理由は、強みと事業環境がマッチしたため。商品の品質確保、絞り込み、認知度、取引先の支援と販路確保など、少ないリソースで強みを発揮した点を織り込んで解答しましょう。
<解答例>
地元で認知度の高かった商品の商標権を保有、贔屓筋や主要取引先の支援もあり販路を確保できており、主力商品に絞りかつての商品に劣らない品質や触感を確保することができたため。
【補足】
設問文も読み込み、出題者の意図(解答のヒント)を見つけられるようになりましょう。
(設問文)
景気低迷の中で、一度市場から消えた主力商品を A 社が再び人気商品にさせた最大の要因は、どのような点にあると考えられるか。100 字以内で答えよ。
例:一度消えた商品が再び人気
以前は人気だった⇒なぜ人気だったのか?⇒人気だった要因を再現できたので、再び人気になった⇒当時の味を再現できたから人気になった
例:景気低迷の中
景気低迷の中⇒大量消費の時代ではない⇒絞り込まれた商品が勝ち筋⇒商品を絞り込んで味の再現ができたのが成功要因
第2問(配点 20 点)
A 社の正規社員数は、事業規模が同じ同業他社と比して少人数である。少人数の正規社員での運営を可能にしている A 社の経営体制には、どのような特徴があるのか。100 字以内で答えよ。
時制:現在
■強み
・主力商品の知名度の高さ
・取引先の支援
(主要取引先から販売支援の継続を条件に商品の存続を強く求められた)
・商標権
⑤現在×組織
・製造、営業、総務部門からなる機能別組織
・部門長と9名の正規社員が所属する製造部門
・創業以来営業を担当してきた専務をトップに6名からなる営業部門
(県内外の取引先との折衝や販売ルートの開拓、出荷地域別の配送管理、在庫管理)
・自社店舗による直接販売は行っていない
・正社員18名、非正規社員70名
・人事経理業務は3名の正規社員で、社長の下で担当
・人手による作業である製造工程を大幅に変更し、自動化によって効率性を高められるようにした
・製造設備面に課題があったものの、商品アイテムを主力商品だけに限定してスタート
・2000年半ばに増資して、工業団地に移転
・HACCPに準拠
・3種類のラインアップ野焼き山車を日産50000個体制に整備
<ポイント>
少ないリソースで強みをどうやって活かしているか?という観点で考えてみましょう。設問文の”正規社員数は、事業規模が同じ同業他社と比して少人数である”から、正規社員と非正規社員のスキルの違いなども考慮しながら考えてみましょう。
<解答例>
・特徴は、①直接販売は行わず主力商品だけに絞って販売、②自動化によって効率性を高めたこと、③正規社員を重要業務に適切に配置し、非正規社員を有効活用したこと。
第3問(配点 20 点)
A 社が工業団地に移転し操業したことによって、どのような戦略的メリットを生み出したと考えられるか。100 字以内で答えよ。
時制:未来
■強み
・主力商品の知名度の高さ
・取引先の支援
(主要取引先から販売支援の継続を条件に商品の存続を強く求められた)
・商標権
⑨未来×環境と組織のGAP
・新商品開発する体制構築
・全国展開実現のための人材確保・育成
・退職する役員の後任
<ポイント>
なぜ移転したか=工業団地のメリット×強みを活かして、将来の目標を達成させるため(課題(GAP)を解消させるため)という観点で考えてみましょう。難しそうな問いに対しても、常に強みと時制を意識して考えてみましょう。
工業団地のメリット=技術が集積している、地元企業の横のつながりなど
<解答例>
メリットは、全国市場進出に向け地元企業のネットワークを生かしながら新商品開発すること、HACCPによる品質管理体制の強化及び売上30億に向けた生産能力増強、自動化による効率性向上のため
第 4 問(配点 20 点)
A 社は、全国市場に拡大することでビジョンの達成を模索しているが、それを進めていく上で障害となるリスクの可能性について、中小企業診断士の立場で助言せよ。100 字以内で答えよ。
時制:未来
■強み
・主力商品の知名度の高さ
・取引先の支援
(主要取引先から販売支援の継続を条件に商品の存続を強く求められた)
・商標権
⑨未来×環境と組織のGAP
・新商品開発する体制構築
・全国展開実現のための人材確保・育成
・退職する役員の後任
<ポイント>
リスクの可能性=今までの強みが活かせない・喪失する、組織がマッチしていない恐れととらえて考えてみましょう。設問文の”全国市場に拡大することで”という部分から、全国市場関連のキーワードで回答する制約を意識して解答しましょう。
<解答例>
リスクは①全国市場では主力商品認知度が低く苦戦する可能性、②市場にマッチする新製品が開発できないリスク、③販路拡大・生産力増強のための投資リスク、④営業体制を人材確保難、⑤商品数が少ないなど
第5問(配点 20 点)
「第三の創業期」ともいうべき段階を目前にして、A 社の存続にとって懸念すべき組織的課題を、中小企業診断士として、どのように分析するか。150 字以内で答えよ
時制:未来
■強み
・主力商品の知名度の高さ
・取引先の支援
(主要取引先から販売支援の継続を条件に商品の存続を強く求められた)
・商標権
⑨未来×環境と組織のGAP
・新商品開発する体制構築
・全国展開実現のための人材確保・育成
・退職する役員の後任
<ポイント>
組織的な課題という制約のもと、今までの強みやうまくいっていたことの喪失、文中に記載されている今後の課題に目を向けて回答を作成してきましょう。設問文の”「第三の創業期」ともいうべき段階”というキーワードから、問題文の設立メンバー(戦友)の定年退職の部分を中心に考え、そのメンバーの担っていた役割や対策を意識しましょう。
<解答例>
課題は、①創業時からの従業員退職に伴う経営層の役割を引き継ぐ人材の育成・確保、②全国進出のための営業部門の強化、③新商品開発の人材強化、対策は、①次世代リーダーの育成、②正社員への権限移譲、③企業文化継承、④非正規社員の業務拡大など
時制(過去・現在・未来)を整理し、強みを意識した解答を行うことにより、大幅な方向性のズレをなくし、事故を起こさない解答ができるように学習をすすめていきましょう。また、改めて事例Ⅰの攻略法の記事をご覧いただき、どうやって解くかをイメージしていただければと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
