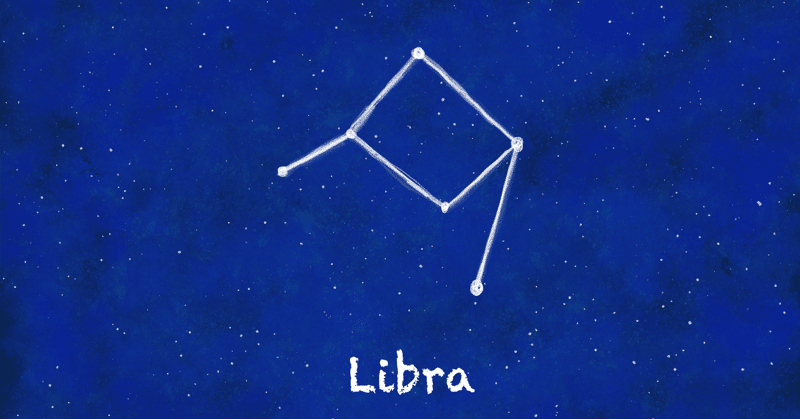
55/100 夜を入れる容器
文字書きさんに100のお題 044:バレンタイン
夜を入れる容器
フランク・シナトラが盲目の少女に「風の色は何色?」と聞かれたとき、かれはどう答えたのだろう。
そう考えたのは、信乃(しの)に「夜が消えてしまった」と泣かれたからだ。夜が消えたのは、夜を閉じ込めたつもりのタッパーのなかからで、ぼくはああこいつアホだと思った。ぼくはいつも信乃を馬鹿にしていたけれど、ほんとうは信乃は馬鹿じゃない。世界の見え方が違うだけだ。
那智黒の大きな目が溶けている。クリーム色のセーターに白い肌、目以外はひかえめな顔立ちの、茶髪をショートボブに仕立てた信乃は、耳が垂れた小型犬のように見える。ぼくが小鼻のふちをすべる涙を舐めると、信乃はおびえたように飛び上がった。二月の外気に触れていたせいか、信乃の肌はわずかに冷えている。
信乃はとつぜん触られるのが苦手らしい。ぼくが「触るよ」といえば、信乃は身を委ねてくる。信乃をセックス好きにしたのはぼくだ。だからみんなから責められている。アホのヒモなんか最低だって。
タッパーの中身はぽっかりと昼になっていた。ぼくがタッパーをクローゼットの奥に放り込んでおけというと、信乃は、そうしたら見えないよ、どうして夜が消えてしまったの? という。ガキは最初は答えられないようなことを聞くが、やがて大人が答えられる質問しかしないようになっていく。ぼくは信乃をヒトとして飼い馴らす気はない。深々と甘やかし、愉しいことだけを教え込み、飼い殺しにする。
窓の隙間がヒュウと鳴いた。信乃がごめんね、とつぶやいて窓を閉める。風は鳴きながら外へ逃げていく。
一度も世界を見たことがない少女にとって、風は質量をもった流体だったのだろう。「風は透明で目に見えないものなんだよ」、盲目の少女に透明という言葉をどう説明するのだろう。「夜は水のように閉じ込められるものではないんだよ」、信乃の目にうかぶ落胆の色。見たくない。
昼になったら、夜は逃げちまうんだよ。ぼくの言葉に、信乃はどこへ? と困った犬の顔で首をかしげた。クローゼットの奥、水道の蛇口の奥、信乃のかわいい鼻、耳の迷路の深い深いところへ。信乃が暗闇へタッパーを置けば、逃げ出した夜が帰ってくる。ぼくがそういうと、信乃は不満そうに、じゃあ結局夜は見えないんだね、といった。見える夜は、たいした夜じゃないのさ、とぼくがいうと、信乃は、そんなものかなあという顔をしてうなずいた。
roaring 40s・furious 50s・screaming 60s、馬の緯度を越えて、吠える狂う叫ぶ海を越えて、シーツを蹴散らして楽園の果てへ。ダブルベッドでぐるぐるまわすと、信乃はジェットコースターに乗ったガキみたいに喜ぶ。
ベタ凪ぎの馬の緯度まで戻ってくると、信乃は裸の胸にシーツを引き上げながら、シロクマさん来るかなあ、と聞いた。南極にシロクマはいない。北極熊の分際で楽園の果てまで来られるわけがない。
シロクマは熊代という。真冬に白熊アイスをたずさえてやってきた若白髪の灰色熊だ。シロクマの激しいプレイに信乃はぶっ壊されそうになったが、実際にシロクマが壊したのは先代のパイプベッドだ。やつが来るまえにベッドの支柱へ切れ目を入れたことは内緒にしてある。ベッドを弁償するさいの胡乱な目はいまでも覚えている。知恵遅れのガキの上前をはねるひとでなし。シロクマに説教される筋合いはない。
信乃の評判は上々だ。だれにでもビリビリ感じる淫乱で。客は蔑むように淫乱というが、淫乱とは相手に対して誠実だということだ。シロクマの目にうかぶ『カワイソウ』を見ると虫酸が走る。信乃は人が好きなのだ。そんな素直な子に育てたぼくの功績を客はだれも称えない。
シロクマは頻繁に信乃を買いにくる。ぼくが気に食わないから料金は二割増しだ。それでもシロクマは白熊アイスやらカステラやら甘いものをもって信乃のもとへ通ってくる。
信乃もシロクマを意識しているようだった。セックスのあとは二割増し、とろんと蕩けた目をしている。バレンタインのチョコレートを見にデパートの地下街へ行くと、信乃はチョコレートをふたつ買っていた。ひとつはぼく、ひとつはシロクマに。
ひさしぶりに街へ出た。明日の国の住人が足早にぼくらを追い抜いていく。信乃は歩道の花壇のパンジーや大根に浮気しながら歩いているので、ぼくの前後を行ったり来たりしている。
ぼくは買い物があまり好きではなくて、甘いもの好きの信乃のためでなければ、こんなところへは来ない。デパートにはこれでもかと明日のしあわせが並べてあって、ぼくはそれを見ただけで疲れてしまう。
好きの色ってこういう色? 信乃はチョコレートの深い赤色の包装紙をなでながら聞いた。包装紙も色々あるから、色々だろうよ、ぼくがそう答えると、信乃は、ひとによってちがうのかな、といった。
好きとか風とか、存在しないものの色は、勝手に決めてしまえばいい。星の位置も自分で決めればいいのだ。
ぼくは家電売り場で西瓜ほどの大きさの球のライトを買った。アパートに帰ってから、エアパッキンで梱包されたライトに黒いビニール袋をかぶせると、ぼくは信乃につまようじを渡して好きな星座を書いてみろといった。
信乃は黒いビニール袋に穴を開けた。エビフライ座、温泉座、五つの角のほし座。ぼくがライトをつけると、間延びしたうすい色の星が天井へひろがった。信乃は長い星だねとつぶやきながらライトを点滅させた。天井がななめになっているのが敗因らしい。
間延びした星のもとでチョコレートを食べた。そのとき信乃がべつのだれかのことを考えていたなんて、ぼくはまったく気づいていなかった。
ぼくが楽園へ行く船に乗っていたころ、赤道祭というイベントがあった。はじめての航海で赤道を越えると、一人前の船乗りとして認められるのだ。ぼくが経験したのは『しらせでポン!』というクイズ大会で、ぼくは賞品でポルシェのサングラスを当てた。華奢な鼈甲の縁のサングラスはぼくの尻で破壊され、ぼくは仕事仲間にボコボコにされた。
信乃はいつ赤道を越えてしまったのだろう。赤道を越えてしまわなければ、苦しいことも悲しいことも知らずにすんだのに。
バレンタインデイのあとの日曜日、信乃はシロクマといっしょにアパートから消え失せていた。
旅行鞄と、少ししかない衣服と、間延びした星のライトとともに。
食卓のうえに書き置きがあった。愛の告白と別れの言葉がひらがなで書かれている。裏返すとそれは極彩色のパチンコ屋の開店チラシで、沖縄式はぼられるからな、とぼくは頭を掻く。
頭の芯が熱い。冷凍庫を開ける。白熊アイスが残っている。冷蔵庫に凭れかかって、アイスを食べる。サクサクした白い地に宝石のようなフルーツたちが光っている。
信乃にチョコレートなんか買わせるんじゃなかった。チョコレート売り場でひっそりと、好きの色を探していた信乃の顔を思い出す。だれのことも好きな信乃がだれかを好きになるなんて。みかんと黄桃のどちらが好きかという問いにすら、まともに答えられなかった信乃が。
ぼくは信乃の面影を求めてさまよいあるいた。深夜の公園、川べりの露店市。大根が植えられた歩道も、デパートの地下街もさがしまわった。
迷子になった信乃を思った。信乃はいつも、ぼくを見つけると弾丸みたいに走ってくる。でも迷子になっていたのはぼくのほうだった。楽園へ行く船を下りてから、この街で信乃を見つけるまで。あるいは、信乃を見つけてからも、ずっと。
デパートの家電売り場で、信乃に似たお店のお姉さんがインターネットの説明をしていた。色々なことが調べられるし、おうちでお買い物もできるんですよ。老夫婦が、あいまいな微笑をうかべながら立ち去っていく。
信乃の行方も検索できない無能な機械を指さして、ぼくは変なことを聞いていいかな? といった。
お姉さんはどうぞ、とルーティンな笑みを見せる。
フランク・シナトラの風の話なんだけど、とぼくが説明すると、お姉さんはいくつか言葉を打って、文章の羅列を覗き込んだ。そして、このページですね、と画面を示す。
――風はあまりにも速く動くから、だれも風の色を見たことがないんだよ。
シナトラは、盲目の少女の問いに真実で答えることも嘘で誤魔化すこともしなかった。
素敵な話ですね、とお姉さんは素の笑みをうかべてから、びっくりしたように目をみひらいた。ぼくが泣いていたからだ。
ぼくが作り出したものは、がらくたの夜にすぎなかった。たぶんあるのだろう、夜を入れる広大な容器が。願いごとはかならず叶うのだろう、それが現世で叶うとは限らないけれど。ぼくたちが死んだあとで、ぼくの知らないだれかが、どこかで夜の壁につきあたる。その瞬間が来ることを、ぼくは信乃のために祈ろう。もう二度と信乃に会うことができなくても。
シナトラが盲目の少女に与えた夢は、信乃がいつもぼくにくれたものだった。
ぼくは信乃の目を通して見る世界が大好きだった。
きょう失恋したんです、と目を拳でこすりながらぼくがいうと、お姉さんは、そうですか、と痛みをこらえるような笑顔を見せた。
現在サポートは受け付けておりませんが、プロフィール欄のリンクから小説や雑文の同人誌(KDP)がお買い求めいただけます。よろしくお願いいたします。
