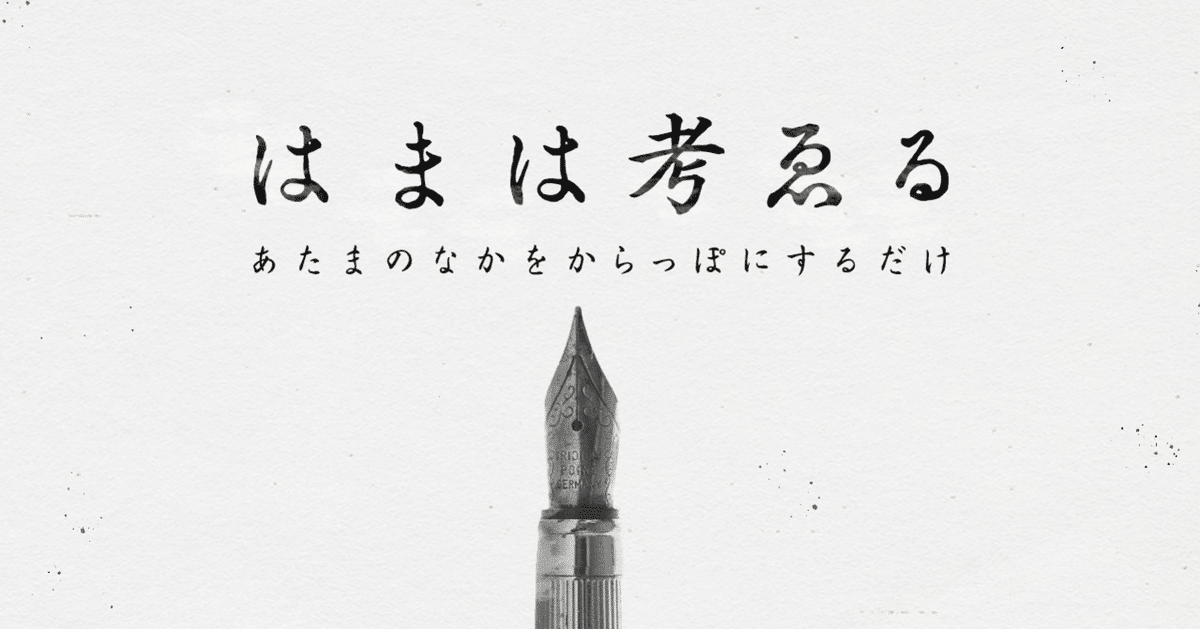
#はまは考える #2 あたまのなかをからっぽにするだけ
・意識
意識(いしき、Consciousness)は、一般に、「起きている状態にあること(覚醒)」または「自分の今ある状態や、周囲の状況などを認識できている状態のこと」を指す。 ただし、歴史的、文化的に、この言葉は様々な形で用いられており、その意味は多様である。
・ちゅうい‐りょく【注意力】
ある一つの事柄に気持ちを集中させる能力。
私は常日頃、頭に何かが浮かんでいます。
デザインのことやお仕事のこと、趣味のことや考え方のこと、好きなもののこと。これ、いつか何かに活かせないかなというアイディアや、突拍子のない空想や想像。勿論、このnoteのことも。
とにかく、大体頭に何かが浮かんでいます。
だが、その一方で、考える力はまだ足りないと感じています。
注意力が散漫だったり、重要視するポイントが人と異なったり、空想や想像はするのに、いざ必要な時にその力がうまく働かなかったり。
自分は、物事をちゃんと考えられているだろうか。
そもそも、考えるってなんだろう。
そう思い、今回調べることにしました。
01.そもそも人間は何かしら考えている。
そもそもヒトの脳みそは、大体常に何か考えているそうです。
https://toyokeizai.net/articles/-/135195?page=3
必要なことから要らないことまで、大体何かが浮かんでおり、それらがざーっとバーっと並んでいる状態だそうです。
私はというと、その通り、大体常に「頭がいっぱい」の状態。
ここに容量の大きい「漠然とした不安」「焦り」「心配ごと」「忘れられない失敗」などなどがぼんぼんぼんと入ってくると、たちまち容量がいっぱいになってしまって、「ここまでどうやって帰ってきたんだろう、覚えてない」というような事例が起こったりします。
まずは、このごちゃごちゃカオスな頭の中身をちょっとずつ整理して、頭の中に余白を作り、そこに「本当に必要なことに注力できているか」の意識づけ、が必要になると思います。
これが、今の自分にはとても重要な気がします。
02.ごちゃごちゃカオスな脳内を片付ける
さて、このごっちゃごちゃカオスを片付けるために、頭に溜まっているものを、できる限りで積み下ろしてみます。ここからは、私の実践したやり方を紹介します。
・「記憶」に頼るのをやめる
人間の記憶は薄れやすく、感情で消され、後から都合よく改竄される不安定なものです。
・大事な予定はカレンダーに書く。リマインダーやアラームをつけて通知。
・明日やるTodoを付箋に書いて机に貼ってから帰る。
・議事録を書くときは口頭のニュアンスを残す。
・作業を教えられたら自分自身で説明書を作ってまとめてみる。
一見当たり前のように感じる作業ですが、こういう記録が後になって
「嗚呼助かった!」と役に立つことが多々あります。
こういった作業は「自分が忘れないように設定する」と捉えがちですが、
最近は「自分が安心して忘れられるように」設定するものだと感じています。
・環境を整える
頭が定まっていない時は、大体環境も雑多になっていることが
私は多いです・・・。頭の中がまとまらない場合は、まずは外側から
整理した方が良いと思います。
私の場合は、下記のことを行ったりしています。
・デザインソフトをいっぱい開けすぎない(一仕事終えたら一旦閉じる)
・Finder(ライブラリ)を整理(失敗の原因も潰していく)
・ファイルを整理
・いらないものは消す
・飲み物、音楽(雑音消す)、温度管理など
・紙に書き出す
環境がちょっと整ったところで、今度は感情面をできる限り整理していきます。私の場合は、まず紙に書き出してみたりすることが多いです。
「理由はわからないけどなんか不安、もやもやする」という時は、「あーー」とか「わー」とかでも良いです。
自分の中でもやもや溜め込んでおくより、一旦外に出してしまうと、それは事実になります。それ以上でも以下でもなくなる。それに、自分が書いた「あーーー」を見ると、なんだか、「嗚呼テンパっているなァこの人は」と、自分のことなのに鼻で笑えてきたりもします。
不安なことも、書き出してみる場合が多いです。
不安なことは、大体頭を占めてしまうからです。
「今日失敗しないかな」「こう思われるのが怖い」「大事な時なのになんで頭痛いんだろう」「さて困った」など、とにかくなんでも良いので書き出してみています。「不安」はそう簡単には消えませんし、すぐに解決できるものでもなかったりします。そういうものこそ、頭の中でボワボワと容量を食っているので、書き出して少しでも圧縮していきます。
03.少しでも頭が空いたところで、考える視点を定める。
こうして、頭にちょっとだけ空きスペースが出来たところで、注力することは何か、そこに詰めるものを選んでいきます。
・
「失敗を恐れる」のではなく、「失敗はするもの」と捉える。
初めてやることは、大体失敗します。
そして何度もやっていることでも、失敗します。失敗した時は、頭の中にモヤモヤが貯まります。
それに対する「切り替えよう」という意思や「やってしまった」という後悔、単純に恥ずかしいと思う気持ち、それにつられた新たな失敗など、
他のものがどんどん生まれます。
・自分の失敗を分析する。
先ほど「失敗はするもの」と述べましたが、開き直るわけではありません。
先のことはわからないことが多いですが、過去から学べることは数多くあります。私は最近、今日1日の失敗を分析することにしています。誰にでも失敗はありますが、失敗の傾向はそれぞれ異なります。そして共通する原因も存在します。
「いつも失敗ばっかりなんだよね」という自虐が、「あ、こういう時、私はよく失敗するんだよな」「これ、確か前私こうやって失敗したやんな」という自覚に変われば、自虐よりきっと強いと思います。
「何をやってもダメだ」と漠然としたダメさで自分を責めるより、自分のことを知ることが出来るし、少し気が楽になると思います。
・考える視点を定める。
自分が失敗する条件がちょっと分かったところで、これから考えることについて視点を定めていきます。
・広く考える・狭く考える。
・目の前のこと(今何をすれば良いか)を考える。先のことを考える。
・自分の気持ちを考える。相手の気持ちを考える(もし自分が、相手の立場だったら?)
・場面を想像(イメージ)する。事実を並べる。
・視点に合わせ、方法を選ぶ。
例えば、バナーを作っていて、進捗を人に見せる時は。
一旦ここにこれが入って、こういう色合いで、という風に全体像をバーっと作って見せたりします。
しかし、これが下層ページのWFを作る場合だったら?
パーツは他ページを流用する場合が多く、その場合は最初に要素をバーっと持ってくるより、デザインルールを先に調べ、メモなどしてから、1個1個置いていった方が早く終わる場合が多いです。(私の場合です)
こうやって方法を選んでいくと、共通して考えることが見えてきます。
・文章を書くときのルール
・デザインを考えるときのルール
(PCで簡単に編集できてしまうからこその良心。本物を見る力)
(操作、管理におけるルール)
(他の方と協力して制作するときのルール、などなど・・・)
・やったほうが良いこと、やらなくて良いこと
などなどなど・・・
04.自分の考えの癖を知る。
物事を肯定的に捉えることも、否定的に捉えることも、適材適所でそれぞれ必要だと思います。
ただ、その中で「私はいつも、こう考えがちだよね」という考え方の癖を知ることが大切だと、最近は考えます。
例えば、物事をどう捉えることが多いか。
・ネガティブ?ポジティブ?
・物事をざっくり捉える?細かい部分が気になる?
・意図や話の流れも詳しく聞いた方が理解できる?結局どうなのかなって簡潔に聞いた方が理解できる?
また、どういった説明が得意で、わかりやすいと感じるか。
・バーっとイメージで思い浮かべるのが得意?図式で覚えるのが得意?
・文章で書くのが得意?絵で理解するのが得意?
・口語を交えて説明しがち?データを重要視しがち?
など、自分の傾向や、考える癖を知ることが必要だと考えます。
この癖を知っておくと、人との考え方の違いや、自分の得意分野・苦手分野を見つけるヒントになります。
終わりに
何かを考えること。
常日頃していることではありますが、実は自分の癖や視点が深く影響しており、無意識に働いている部分も多々見られます。
私も日々、「うわあ自分の考えクセが凄いな」と思いながら、日々周りの方に多くを教わり、「こういう考え方があるんだ」「そう考えたらいいんだ」と、異なる考えに触れ、勉強しています。
「自分は、どうやって物事を考えているかな?」という部分に立ち返ることは、自身が生まれ変わる行為に近いと思います。
頭のごちゃごちゃが片付いたところで、今度は
どうやったらオモシロイアイディアが浮かぶようになるのか、
どうやったら考えがシンプルになって、いつも冴え渡るようになるのか、
どうやったらクリエイターの頭の中身に近付くのか・・・を
考えていきたいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。
帰り道に聞くのは「歌うたいのバラッド」です。はまでした。
