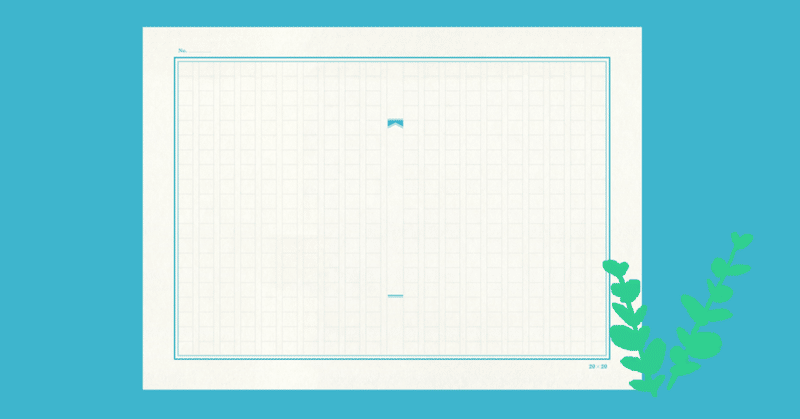
文章の添削をした話
自分の実力はさておき、なぜか昔から、添削を頼まれることが多い。
客観的に目を通し、評価することが必要な場面で依頼される。
お人好しだから添削を断らないのも災いしているのかもしれない。依頼があった以上はできるだけ良いものに、と考えて作業すると、最終的に元の文章は一体どこに行ってしまったのか、自分の文章にして返したことも一度ではない。
そう言っても、自分が書いた文章は同じように真っ赤にチェックされて返された経験しか思い出せない。元の文章がどこかに行ったことも同様だ。
今思い返せば、元の文章が稚拙だったのだろう。その割には憤慨したような記憶もある。
「文章を書く」という原体験はどこにあるのか、と考えると、学校の作文を思い出す。一つは小学生の頃。小学校二年生だったと記憶しているが、校外学習に行った時の話だ。
自然観察だったと思うのだが、団体行動で施設を管理をする「レンジャーさん」と呼ばれる人の指示で、行動をする。しかし団体から遅れたことによって、この指示に従わなかった人がいて、怒られている現場を目撃した。
ここからがまた複雑な話であるが、私の学校は所謂特別支援学級を含むため、通常の学習は支援学級で、それ以外は所属するクラスで、という具合になるわけだが、この指示に従わなかった(というより、従えなかったため怒られた)人(仮にAと置く)が、とある障害[特定を防ぐためにあえて伏せる]を持っていたのである。
当然Aはパニックになる。この場をどうやって乗り切ったかはいまいち記憶にないのだが、この目撃後も、一緒に行動をともにした記憶はある。(これに限らず、支援学級にも所属する同級生の担当を結果的に"押し付けられる"ことはその後も続き、挙句の果てには席替えは必ず支援学級所属の同級生が固定ということもあった。)
そんな現場を目撃し、一つも楽しいという思い出ができるはずもなく。全体行動はつつがなく終わったと記憶しているが、その後どういうイベントが起きたか記憶は一切残っていない。
学校に返ってくると、お礼のお手紙という名の作文が待つ。
私はバカ正直にレンジャーさんに怒られている姿を見て、楽しかったという気持ちも湧かず、むしろ二度と行きたくないと思った。ということを当初書いた。
しかし、周囲を見れば「とても楽しかった」「レンジャーさんにまた会いたい」。正反対の文章があふれていた。
そこで、私はまだ最低限の社会性を有していたからだろうか、それともその後の担任による詰問を避けるためか、これらの文章に同調するように文言を修正し、提出した。
最終的に「レンジャーさん」のもとに届いたかどうかは不明だが、何れにせよ尊敬できない人間もこの世の中にはいるものだ、ということを作文を通して気づいた記憶がある。
二つ目も同じく小学生の頃。
読者の皆様に置かれてはどう書いていたかはわからないのだが、「私は◯◯と思った」とか「~行った」とか「~した」という書き出しの作文を量産していた頃の話だ。恐らく小学五年生か六年生か。
理由は忘れたが、友人の文章を読んだとき「自分の心の声」を文頭に置いて、文章を書き出すという技法に触れた。
なんと素晴らしい表現だろうか、と思った記憶がある。
恐らく中学受験対策で、普段からそういった書き方の練習をしていたのだろう。今思い返せば全く稚拙な表現で、達意の文章(例えば、与謝野晶子「君死にたまふことなかれ」のように感情と巧みな表現力を組み合わせた作品)とは(当たり前だが)程遠いと感じるが、小学生ながらそのような書き方もあるのだと感心したのだった。
なお余談も余談だが、今指導している人たちに「自分の心の声」で始まる作文を提出されたら、私は怒ると思う。手法に拘泥し、本来伝えたいことにブレが生じるからである。
そんな紆余曲折を経て、今このように散文駄文を書いている。
これも添削されたらどう評価されるかと思えば、大学の頃に散々指摘された「文章が正対していない」だろうか。主述の一致はできるようになったと感じているが、指導して下さった鈴木先生には、まだ甘いと怒られるかもしれない。
そんな過去のことを思い出しながら、作文を採点しつつ講評をそれぞれに書いていたところ、とんでもなく時間がかかってしまった。しかし書いているときに感じていた、この気持ちの一部でも、そのエッセンスの1mmでも伝われば、より良い達意の文章がかけるのではないだろうか、と思ってならないのである。
そんな気持ちは裏切られる(というより厳しく指導しすぎた)こともあるが、それも含めて私の至らぬところである。日々精進だ。
継続的に記事を書くために、ぜひご支援よろしくお願いいたします。 より良質な記事を書くためおよび、世界の恵まれない子どもたちのために使わせて下さい。
