
意識とは何かを考える【267/300】
早くも10月が終わろうとしていますね。はこの亀谷です。
今年はAI関連が一般的に大きく普及したので、自分の意識というものに関して、とても深く理解出来た1年になりました。
ということで、「本日は脳と意識とを考えて、人として生きるってこういうことなんだろうなぁ」という自分の考えをまとめておこうと思います。
まだ自分の中で綺麗に整理出来ていない部分も多いので、文章は取っ散らかると思いますが、割と方向性として芯は食ってきていると思っていますので、お時間あればご覧ください。
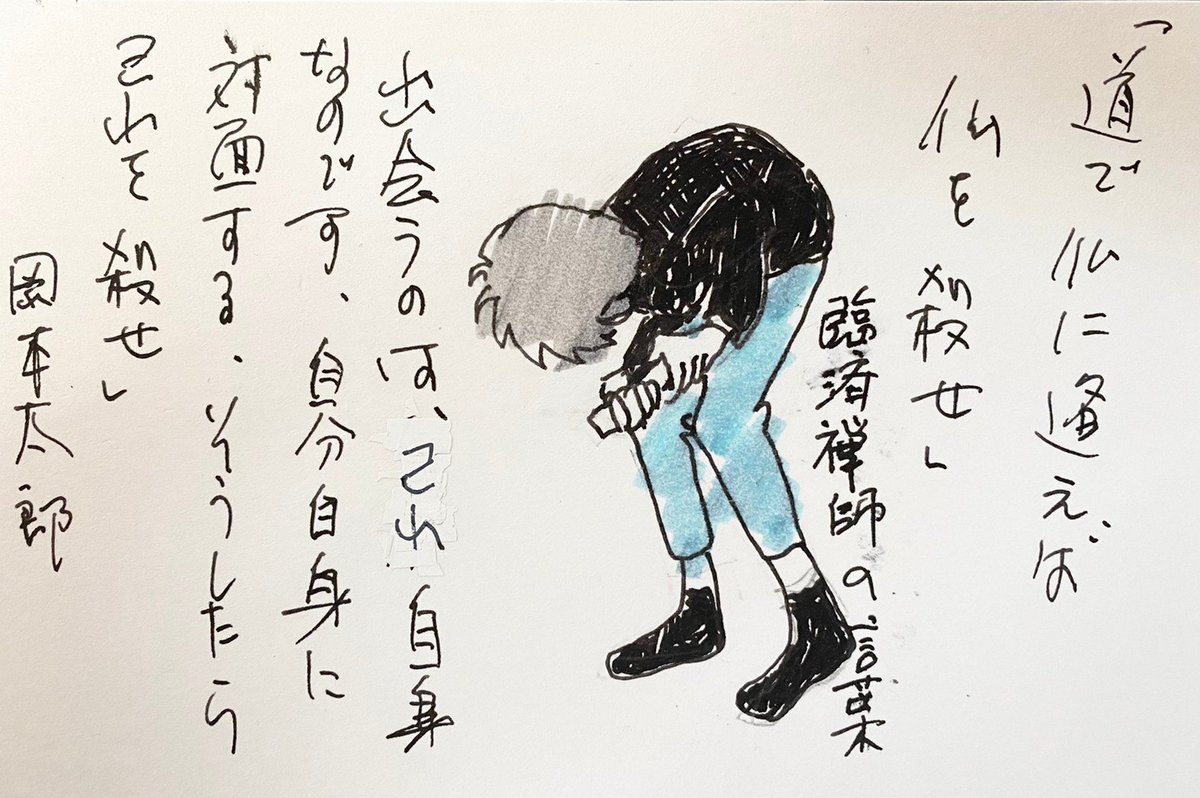
自己とは何かを考えていく過程とコンピュータ
昔から人は哲学者や宗教家を中心に、自己とは何か、意識とは何かに向き合ってきました。
昔はコンピュータがなかったので、あくまで人を観察することで、人とはこういうものだということを多くの哲学者がそれぞれの視点で語ってきています。
ただ、ここ最近はハードの発達により全く違うアプローチで、人とは何かが見えてきました。
それが脳の機能を科学的に再現しようというAI関連の技術です。
ピタゴラスが「必要性とは、可能性の隣人である」と言っていたり、アリストテレスが「人は物事を繰り返す存在である。従って、優秀さとは行動によって得られるものではない。習慣になっていなければならないのだ」と言っていたり、キルケゴールが「祈りは神を変えず、祈るものを変える」と言っていたりすることは、今のAIの動きを見ていると確かにそうだよなぁと思う部分が多くあります。
人は客観的に自分のことは見れませんし、他人は他人だと思ってしまいます。
人間を人間としてみるためには、人間の機能を模したコンピュータを観察するくらいの距離感がちょうど良いんだなぁと最近は思い始めました。
人の脳の仕組みを考えていった結果として出来あがった今の大量言語モデルは、客観的に人を理解するにはちょうど良い素材です。
特に、結局は人は大量の情報から予測して生きて反応しているのね。ということに気付けるのはとても大きなことだと思います。
それでは意識とは何か?
それでは、次に意識とは何かを考えます。
意識とは何かに関しては、この後に載せた2つの動画が私は好きです。
一つ目が私の好きな養老先生のYoutubeです。
養老先生は解剖学者の見地から、本や講演を通じて、人とは何かについて教えてくれています。
この動画を見ていると、意識が何故あるかは解明されていないことを前提として、養老先生は無意識の先に意識があることを教えてくれます。
しかも無意識を止めるために意識がある。という風に解釈されています。
2つ目はホリエワンの堀江さんと川上さんとの対談です。これもめちゃくちゃ面白い。
この動画では、川上さんが、川上さんが考える脳のプログラムと意識の発生について話しています。
その中で、川上さんが考えている結論も、昔は意識がなかった。ただ、進化の過程で意識は無意識のバグをとるために後から発生した。と思うと言われています。※このホリエワンの川上さんのシリーズ2回あるんですけど、面白いので、是非News Picksで見てみてください。
無意識があって、意識で制御している。
ノーベル経済学賞を取った心理学者のダニエルカールマンが、早い脳と遅い脳、システム1とシステム2みたいな話をしています。
ざっくり書くと人間ってついシステム1で反応しちゃうから間違えるんだよねぇ。
ってことを言っています。
システム1というのが、本能や感情によって動いている脳で、前頭葉を中心とした論理的に考えるシステム2が動き出すのには時間がかかる。ここを理解しておかないと間違えるよ。という話です。
この話も養老先生や川上さんの話と通じています。
結局、人は無意識に動かされていることを意識して生きるしかない。
今週の会社の昼練で、この本の解説やっていたのですが、
※この本はタイトルの邦訳がイマイチです。Atomic Habits An Easy & Proven way to Build Good Habit & Break Bad Oneの方が内容には沿っています。
まぁ、結局は習慣化の本って全部、この無意識と意識のコントロールの話に落ち着くんだよなぁと一人で思っていました。
習慣化っていうのが、ある意味、無意識の調整なんだなぁと。
まずは、生存本能をベースに作られた無意識というプログラムで人間がどう動くのかを理解する。
次に、変えたい部分を考えて、意識で制御することを決め、無意識が書き換わるまで実行する。
これが習慣化のプロセスです。
ただ、環境の変化は刻一刻と起きるので、その環境の変化によって起こる予測の修正に必要な情報は、都度自分の中にインストールしておく必要があります。
この流れをコントロールして生存していくことが生きるってことなんだなぁと。
逆にこの仕組みが分からなくても、とりあえずは生きていけるように出来ている無意識のプログラムは凄いなぁと関心すらしてしまいます。
自分とは何か?
その流れで、何で自分なんてものを認識してしまうのかもまとめておきます。
上の川上さんの動画で、堀江さんが言っているセンサー部分を身体が担っているから、自分という存在があると考える。というのも、あぁ、なるほどなぁと思うのです。
脳というプログラムを動かすために、外部からの情報を集めてくる視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚というものが存在していて、あくまで自分の身体は自分の身体に搭載された脳というデータのインプットデバイスにしか過ぎない。
それらからインプットされるデータを元に、脳が予測を行い、生存するように人は生きていると。
一つの脳に一つのインプットデバイスという構造になっていて、その環境により脳へのインプットは違って当たり前だから、他人が生まれ、他人と比較して自分を見ている自分が出来てしまう。
これからの時代を考えると
記憶容量や演算など、外部で機能を代替できるものは代替できる時代になってきているから、脳のエネルギーを考えると、余計なものは外部に置き換えてしまって、容量の都合上、必要なものだけ頭の中には残せば良いよねと。
プロ棋士の藤井聡太さんがAIから将棋を学んだという話もありますし、本能という変なシステムに制御されている不完全な人間に学ぶよりも、正しい判断をするだけであればAIに学んだ方が正しい可能性があるよね。
というのも、まぁ、確かになぁと。
その時に、所詮はセンサーに過ぎない身体に縛られて、自分というものに固執をし過ぎると、自分の脳の限界を超えた先にはいけないんだろうなぁと。
こんなことを考えていると、なんで人間なんて誰一人いなくても、世界的には困らないのに生きていかないといけないんだろうなぁ?と思ってしまいますが、これもこの理論だと生存本能という強いプログラムに縛られているからなんですよねぇ。
だから、結論、そんなことを考えても意味がないから、せっかく自分の身体をもった個体として生まれたのだし、自分の個体を使って新しい経験をし、未来の人類の礎か良いサンプルになりなさい。という話なんでしょう。
しかし、そう思い始めるとやはり生物が存在する裏には大きな意志が存在していて、この大きな流れを仕込んで何かを検証している気がしますが、答えはないので今日はここで終わります。
それでは、皆様、良い週末を!

いいなと思ったら応援しよう!

