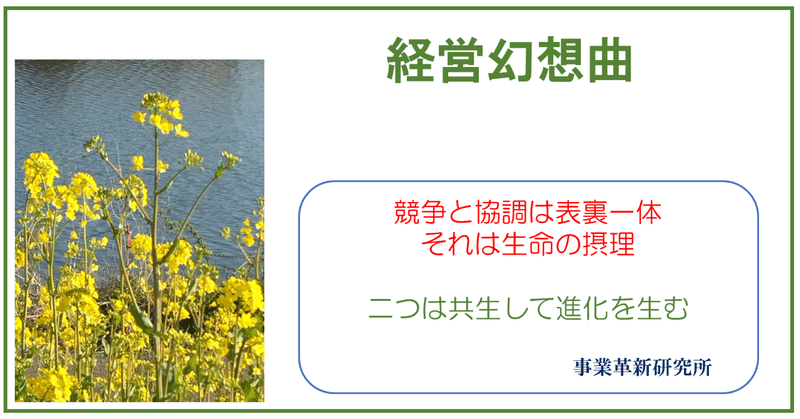
経営幻想曲 解説その2)
競争と協調は共生して進化を生む
⑴ 営業利益と人件費
経済の好循環へのみちを、ソフトで広い生産技術分野の観点から俯瞰する。本書はそれによって構想を綴る密書である。
ゴールは「好売上と好賃金」。
実体経済を盛り上げるアルゴリズムとしては、本書の提唱する本来的な「付加価値(added value)and 産業の論理(industrial logic)=AVAIL」を貫く。
それをクリアした暁には、目前に産業革命の景色が広がって見えるだろう。
原料や粗製品を加工して使用価値を創造し付加価値を産み出す経済行為は、むろんのこと、その方法はさまざまである。ただし労働者のこころ、納得基準は一つ。働いて豊かな生活ができることのみ。それが産業の論理、企業の存在価値をきめる。
平均賃金・最低賃金が労働者の求める水準に引き上げられることで、GDP(国内総生産)は押し上げられ万々歳、だれもがそんな空気を望んでいる。
とはいえ、それについては「経営の質」のかかわるところである。そして、キャパがなくてははじまらない。
フォーカスとなる根本課題は「営業利益と人件費の復原力」であり、そのエンジンを整備し、好循環の創生に努めることで、私たちの生活力にゆとりが生まれる。
そういったこころ・イデアなしで「成長だ」「分配だ」と唱え合っても、実体経済は空回りばかり。これ以上それが長引けば、もはや大切な社会までが取り返しのつかない、未曽有の土砂崩れを招く。
⑵ 労働を大切にする二つの社会
好循環にベクトルを向けた企業行動を、ここではマクロ行動とよぶが、それは、つぎの観念を前提としたものである。
――生産の活動過程において、企業は他企業とのリンケージが欠かせない。その「効果と効率」があって、互いの付加価値は生み出される。ここでは、各々の系の集合で形成される総和の枠組を企業社会とよび、そこでの労働の対価を糧に生活する総和の枠組を生活社会とよぶ。
付加価値と対価の健全な関係で〝豊かな均衡〟をたもっている状態が、マクロ行動の基本要件である。豊かな均衡とは、すなわち理論的・客観的な基準によって〝妥当な分配が履行できている状態〟をいう。
公正な人件費の算定基準を介してこそ、従業員や協力業者は当該企業の徳行に安心でき、元気に働くことができる。それらの精神面をも充たして適えられる連鎖的な活力を、ここでは「ライフダイナミクス(life dynamics:生活の原動力)」とよぶが、それを産み出すマクロ行動は、労働を大切にできる双方の社会によって成り得る――
⑶ 無い袖は振れない企業
未来の生産や流通の現場を脚色するなら、そこには高い労働生産性の文明がある。
生産手段はもちろんのこと、労働環境もスマート。権利と義務の釣合からも、張り合いある仕事現場と暮らしに恵まれた従業員――そういった健全なる企業イメージがある。
それなしでは、この国の明日が、元気を失ってしまう。
少子高齢化が進むなか、いよいよ人手不足も大きな課題となっているいっぽう、肌感覚で知る賃金格差状況や最低賃金に照らした実質的購買力、消費性向などを垣間見るとき、現状は、ライフダイナミクスにゆとりがあるとは言い難い。それどころか到底安らげる状況にはない。
とはいえ、企業側からしても「無い袖」は振れない。内部留保の大きさを咎める声はあるものの、それを危機管理の枠内と見做せば、他人がどうこう干渉しづらいこと。
⑷ 企業社会と生活社会の関係性
一体全体企業社会のどこを見れば、ライフダイナミクスの光明が射し込んでくるのか。表向きに掲げる企業の「ビジョン」の用語も、まったく白けた幽霊用語にしか聞こえてこない。
忘れてならないのは、実体経済は一企業でなるものではない。
実感できる盛り上がりは、企業たちが、「有る袖=マクロ行動」に仕立て直してこそ、企業社会と生活社会の豊かな関係性が確立する。それを持続可能にする論理を取り入れ、是非とも実像化しなくてはならない。
そこに辿り着けるのは、企業たちを下支えする「産業の論理」と「エリートたち」であり、リンケージからなる大きな輪(全員野球)のプロジェクト推進室とともにパラダイムシフトに向き合い、いますぐ立ち上がることである。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
