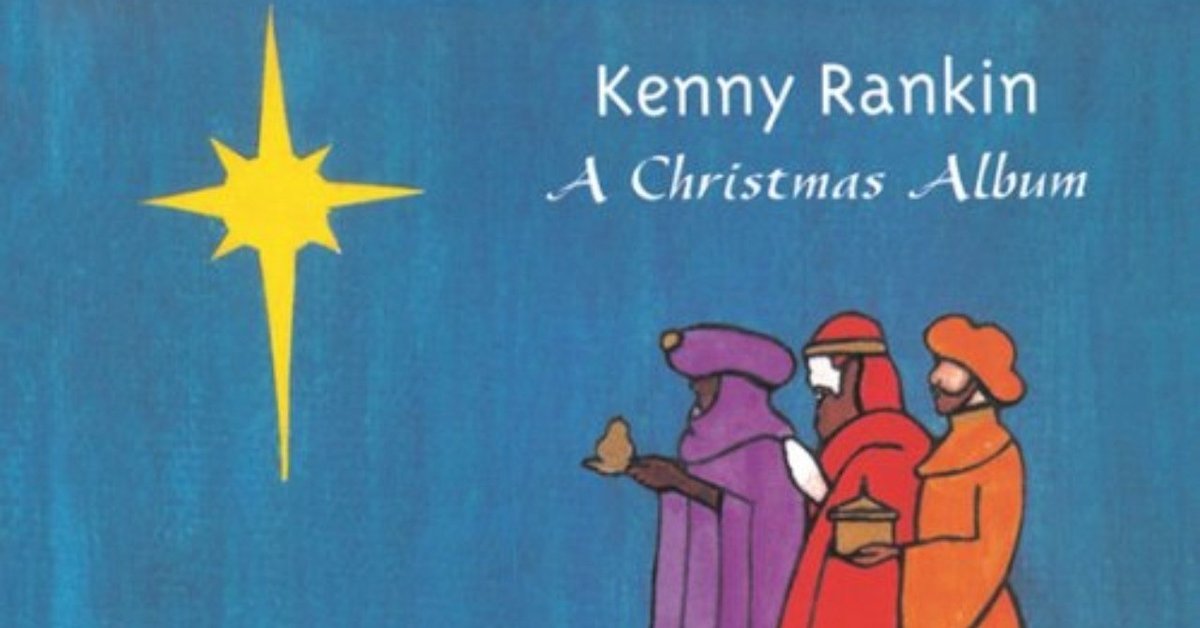
自分がこんな声で歌えたらいいのに Kenny Rankin『Christmas Album』
寝て起きたら菅田将暉になってないかな
「寝て起きたら、問題がすべて解決していないだろうか?」「寝て起きたら、自分があの有名人になっていないだろうか?」と夢想するときがある。ほんとうに意味がない話だけれど、考えたことがない、という人もめずらしいのではないか。たぶん。
自分も、毎日の中で疲れ果てたときに、「寝て起きたら菅田将暉になってないかな〜」と考えることがある。馬鹿、という2文字では、ちょっと表しきれない愚かさ。起床して、眠たい目をこすりながら洗面台の前にたち、鏡に映った30歳を過ぎた男の間抜け面に、ため息をつく。もう傷つけない、もう傷つかない……。
では、自分の嫌いなところはどこだろうか。そんな後ろ向きなことは、クリスマス・イヴに振り返るべきではありませんが。
ただ、その中から、一つ。声を挙げてみたい。自分は、たまにギターの弾き語りをするけれど、その際に悲しくなるのは、ギターの腕前よりも、歌声のほうだ。モゴモゴして、低くて、音域が狭くて、なにもよいところがない。すぐにひっくり返るし、曲の後半になると息切れもする。
そうなると、美声になればよかったのにな、と、心から思う。寝て起きたら、みごとに歌えるようになっていないかしら。
「寝て起きたら」というところが肝心で、「生まれたかった」とまでなると、さすがに、生みの親に悪い気がする。寝て起きたら、今のままで、よくなっていた、というのが、控えめでよいのではないか。よくよく考えれば、なにも、控えめではないけれど……。
しかし、中には、「こういうふうに生まれたかった」と、ただ、感嘆するしかない才能、技術の持ち主もいる。両親にはいささか申し訳ないけれど、この表現は、惜しみない賛辞だとも思う。
その人の音楽を初めて知ったとき、こんな声に生まれたかった、と心から思った人がいる。Kenny Rankinだ。
キャリアに裏打ちされた技術
彼のキャリアを考えると、やはりボサノヴァやジャズへの憧憬をのぞかせ、来たるべきAORの時代ともリンクした、『SIlver Morning』『The Kenny Rankin Album』あたりが、ピークとみなされているのだろうか。フリー・ソウル方面からの人気も絶大で、「Haven't We Met?」「Peaceful」などは、その界隈におけるスタンダードといってもよい。
しかし、Kenny Rankinのデビューは、なんと1957年。Paul Ankaと同年というのだから恐れ入る。そのあと、João Gilbertoなどに影響を受けてギターの弾き語りをメインにしていくが、そのスタイルでコロンビア・レーベルと契約したのも1963年。これも相当に早い。ちなみに、この時代のシングルは『COLUMBIA COMPLETE SINGLES 1963-1966』としてまとまっている。
Bob Dylanの『Bringing It All Back Home』(1965年)にリズムギターとして参加していることも、ご存知の人はいるかもしれない。だから、AORの名盤として数えられることも多い『The Kenny Rankin Album』(1977年)の頃などは、もう、かなりのベテランなのである。
この人の魅力は、とにかく、その歌声に尽きる。もちろんギターも相当な腕前なのだけれど、ジェントルで優しいテナーボイスは、何物にも代えがたい。一聴して彼だとわかる節回しも図抜けていた(とくに、スキャットはハチャメチャにうまい)。のちにジャズ・シンガー的な活動にシフトしていくのもうなずける。
とはいえ、過度に泣きを入れるような、ひけらかす歌唱はしない。聴き手におもねらず、端正で硬派な一面もある。技術を鼻にかけず、どこか凛々しいイメージを持っているのは、彼のキャリアがなせる技なのか。プロフェッショナルが持つ、力みのなさ、というか。
小西康陽は彼の歌声をこう評している。「こんな声に生まれたかった。あるいはこんな風に歌うことが出来たら幸せだっただろう、と聴く度に思う」。この表現に付け足すことは、なにもないだろう。
そこまでの歌声を持つ人だから、カバーも多い。ほかの人の曲を歌っても、十分に、自分のものにできる武器を持っている。「Penny Lane」や「Blackbird」のカバーは、Paul McCartneyも絶賛したという。どちらも『SIlver Morning』に収録されている。名盤!
クリスマスの最良の語り手
このアルバムは、本人のサイトだけで販売されていた、キャリア唯一のクリスマス・アルバム。収録曲も、とくに解説することもないぐらい、有名なものばかり。だいたい、アルバムのタイトルだって直球なのだし。メロウでジャジーなクリスマス・ソング集といえば、1行で説明できてしまう。
ただ、そんなアルバムは星の数ほどあるけれど、とにかく、ここでは、彼の歌声が別格。それが、すべて。テクニカルなひけらかしはないのに、「歌がうまい」ということを、これほどわからせてくれるアルバムもないだろう。
たとえば「The Little Drummer Boy」の、太鼓を叩く音を模した”Pa rum pum pum pum”を、ここまで詩情豊かに歌える人は他にいるだろうか?
クリスマスというイベントは、気の早いことに、12月が始まった頃から準備が始まり、賑々しく盛り上がっていく。そして当日になると、はなやかな祝祭はあっという間に終わってしまい、妙にさびしくなってしまう。
いざ、その時が来ると、あっという間に終わってしまって、楽しい記憶が、ぼんやりと残る。クリスマスの音楽も、そういう類のものなのかもしれない。その中には、どのような願いであれ、真摯な祈りも、きっと含まれている。
サンタクロースも、クリスマスツリーも、生まれてから、何度も目にしている。それでも、町中にきれいに飾り付けられていると、見るだけで、うれしくなってしまう。そんな「楽しい記憶を呼び起こすもの」としての現象がクリスマスだとして、その感情を表現するのが世に数多あるクリスマス・ソングなのだとしたら、このアルバムは、まさに、それらの最良の語り手だと思う。
(Kenny Rankinの、とくに1970年代の作品は、どれもすばらしい。Don Costaがアレンジを手掛けたあまりにも甘美な『The Kenny Rankin Album』、ブラジル音楽とフォークとAORのよいところだけを集めたような『Silver Morning』は、もしあなたが好きになれなかったとしても、どうか、そのことをぼくに言わないでほしい)
付録1:好きなクリスマス・アルバム5枚
Cor Vivaldi & Ignasi Terraza Trio『El 25 de Desembre Swing, Swing, Swing』
バルセロナのジャズ・ピアニストが、少年少女の合唱団を率いて録音したアルバム。カタルーニャのクリスマス・シーズンの伝統曲が演奏されている。軽快なピアノ・トリオ(+ときどきホーン)に、子供たちのコーラス。悪かろうはずがない。
一般的には知られていない曲ばかりだけれど、とにかくアルバム・タイトルのごとく、スウィングするジャジーな雰囲気が魅力。合唱のアレンジもうまい。クリスマスの高揚感をしっかりと味わせてくれる隠れた好盤。ジャケットのデザインも素敵だ。
Shawn Colvin『Holiday Songs And Lullabies』
デビュー作は、グラミー賞の最優秀コンテンポラリー・フォーク録音賞を受賞した実力者。『かいじゅうたちのいるところ』でおなじみ、Maurice Sendakの『子守唄と夜の歌』にインスパイアされたというアルバムで、1998年に生まれた彼女自身の娘に捧げている。
「ホリデー・ソングと子守唄」というタイトルの通り、クリスマスソングと子守唄をバランスよく収録。1970年代のSSW作品を愛好しているような人なら必聴だ。とくに、ひかえめに重ねられるストリングスやホーンは絶妙。自分がいつか子供を育てることになったら、こんなアルバムを聴かせてあげたいと思う。
Tracey Thorn『Tinsel & Lights』
オリジナルは2曲のみで、残りのカバーも、Joni Mitchell、Randy Newman、Sufjan Stevensなど、シンガー・ソングライターのオリジナル曲をメインに取り上げているところがおもしろい。
降り積もる雪のように、しみじみと弾かれるギター(Ben Wattが参加しているのだけれど、実にツボを押さえている)。素朴ですこし翳りのある歌声、ボーカルを前面に出した編曲。クリスマスが特別なものであり、同時に、誰にでも訪れる普遍なもの(この表現が、「西欧」からの視点に寄りすぎたものであることは、理解しているのだけれど……)だというすばらしさを伝えてくれる。
J.S. Bach『Christmas Cabtatas』
Kevin Mallon指揮、Aradia Ensemble。クリスマスにちなんだバッハのカンタータを収録したアルバム。待降節第一日曜日のための「喜びて舞い上がれ」(BWV 36)、待降節第四日曜日のための「道を備えよ」(BWV 132)、これまた待降節第一日曜日のための「来れ、異邦人の救い主」(BWV 61)。
小編成の古楽団体で、小気味よく澄んだアンサンブル、透明度のある合唱が魅力だ(各パートにつき2人のようだ)。ソロ歌手も歌い方が清廉でよい。なによりも、各カンタータの終曲の合唱をしんみりと静かにやるあたりが心憎い。バッハのカンタータ入門にも適しているだろう。
Phil Spector『A Christmas Gift For You』
実家にいるとき、両親は、このアルバムをクリスマスのときにずっと流していた。その事実だけでも、「育ててくれた恩」を感じている。
付録2:好きなクリスマス・ソング5曲
「Have Yourself A Merry Little Christmas」
誰でも知っているようなナンバーだけれど、やはり、これほど、自分の中の「クリスマス」のイメージを決定づけた楽曲はない。この曲が入っていれば、どんなクリスマス・アルバムでも買ってしまう。
「The Bell That Couldn't Jingle」
名曲揃いのクリスマス・ソングの中では、少し地味かもしれないけれど、Burt Bacharachの手によるこれを忘れることは、自分には考えられない。歌詞の夢見るような雰囲気も含めて、もっともっとカバーしてほしい曲だ。
「Wonderful Christmastime」
誰もが知るような有名曲だけれど、アレンジは聴けば聴くほど不思議なもの。シンセサイザーに触れ、音を出しながら、「このサウンドを使いたい」というモチベーションが先に来て、作られたのではないかしら。とはいえ、鈴の音の使い方や、リズム感などは、むしろ20世紀前半の楽曲のようでもある。Paul McCartneyの趣味性と(当時の)テクノロジーが融合したユニークさは、未だに聴き飽きることがない。
「Christmas」
自分がもっとも愛するバンド、The Blue Nileもクリスマス・ソングを残している。ひたすらに美しい夜のサウンド。どんなに悲しいことがあっても、こういう音楽が世の中にあって、それと出会えることがあるかもしれないから、生きることを諦めずにいられる。自分にとっては、そのような存在。
「On Christmas Morning」
この曲をクリスマスの朝に聴くときほどの幸せを、音楽を聴く行為の中で見つけることはむずかしいかもしれない。
