
住宅ローンの金利が上がってきているって本当?これからどうなるの?変動金利or固定金利どっちがいいの?を、FPが7,500字で解説!
「家を買おうか迷っているけど、住宅ローンの金利ってどうなん?」
この前、友人に聞かれました。
住宅ローンの金利。
30代である私の周りでは、今かなりホットな話題です。住宅ローンの金利と言えば、歴史的な低水準が続いてきていましたが、少し変化の兆しが見えてきました。
ので、今日はそのことについて書いてみようと思います。長いですが、かなりかみ砕いて書いたので、ぜひ最後まで読んでみて下さい。お茶でも飲みながら。足を崩して。
っていうのもですね、ここ数年、本当にこの住宅ローン関連の質問が多いんですよ。友人からの多い相談のトップ3の中に、「住宅ローン、変動金利と固定金利、どっちがいい?住宅ローンの金利、これからどうなるん?」があるんです。
ちなみに、よくある相談トップ3の、他の2つもご紹介。
◆「資産運用に興味あるんやけど、何から始めればいい?」
「オススメの投資信託や株を教えて!」
→まずは、何のために資産運用したいんか、考えてみよっか。投資信託は手段やから。その前にどういう運用したいんか考えてみよっか。ほんでワタクシ、融資業務も行っている銀行員ですので、オススメの個別株は一切教えられへんで。インサイダー取引になったらアカンから。どの株がいいかは自分で考えて。そのための考える仕組みはアドバイスするからさ。簡潔に言うと、経済にアンテナ貼ることが大事やと思うで。
◆「このままフルタイムでバリバリ働くか、ゆとりを持って働くか迷ってるんやけど、こういう家族構成やったらどっちの方がいい?っていうか、これから何にどのぐらいお金がかかるか分からへんから教えて!」
→女性からが多い、っていうか、この質問してくるの、95%が女性。私の友人に女性が多い(中高6年間女子校)バイアスかかってるかもしれへんけど、ジェンダーギャップを感じるなぁ。
何にどのぐらいお金かかるか、どのへんまで詳細知りたいか次第やけど、平均的な数字や統計データならいくらでも教えるで。
って感じです。
話が飛んだ。
布団がぶっ飛んだ(言いたかっただけ)。
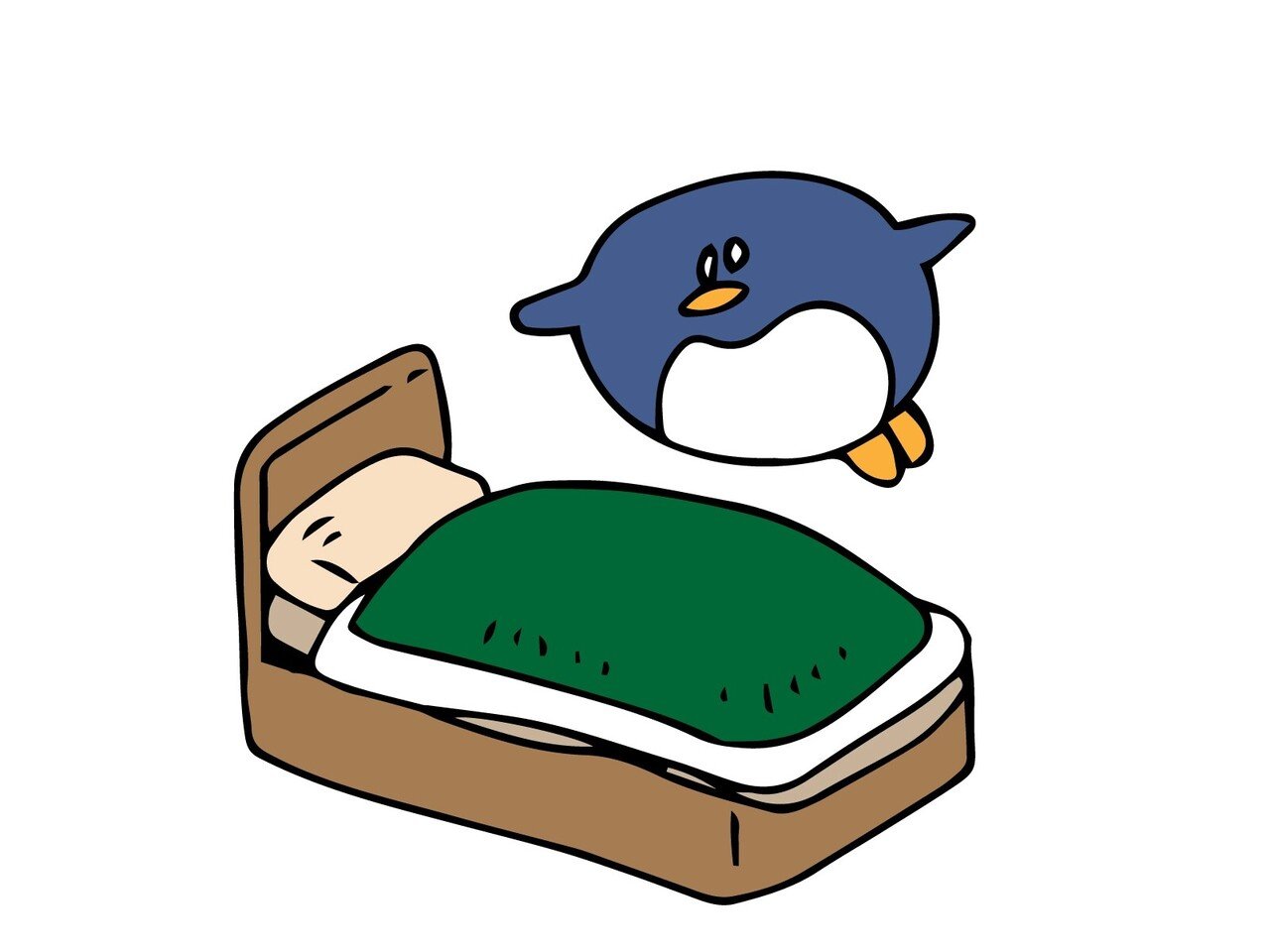
で、住宅ローン、変動金利と固定金利どっちがいいか、これから住宅ローンの金利はどうなるのかって話ですよね。
◆今、住宅ローンの金利はどのぐらいなのか
まずは、もし今、住宅ローンを借りたら、金利どのぐらいなん?ってとこから。各銀行の、金利を見てみましょう。金利が安い順にトップ3です。
<変動金利>
1.0.375%~ みずほ銀行
2.0.38%~ PayPay銀行
3.0.390%~ 住信SBIネット銀行
<10年固定金利>
1.0.67%~ イオン銀行
2.0.69%~ PayPay銀行
3.0.695%~ auじぶん銀行
<全期間固定金利>
1.0.995%~ りそな銀行
2.1.170%~ みずほ銀行
3.1.350%~ 新生銀行
(すべて2022年3月21日現在)
※ 住宅ローンを選ぶ基準は金利だけではありません。諸費用、特約、保障など、いくつか選ぶ基準があるのですが、今回のテーマは「変動金利か固定金利か」「これから金利はどうなるのか」なので、金利のみに着目してお話します。
上記は金利が安い順トップ3なので、平均的には、
変動金利・・・0.5%前後
10年固定金利…0.8%前後
全期間固定金利…1.5%前後
ってところでしょう。
ちなみに、特約つけずにこの金利なので、特約をつけると+αの金利になります。
ふーん。
で?
なんとなくこの金利が低いってことは分かったけど、どっちがいいのよ、これからどうなんのよ!
って思ったそこのあなた。
ちょっと待って待って。
早く結論を知りたい気持ちは分かるけど、1つずつ話していきます。
以下、FPむーと、Aさんの会話方式でいきます。

(フリー素材で見つけてきた写真なのですが、プールに浮かびながらこんな会話してたら、思わず振り返ってしまうよね。)
FPむー:住宅ローンの金利のもととなるものって何だと思う?何に影響するんだと思う?
Aさん:え、そんなの景気に影響するんでしょ?
FPむー:うん、景気に影響するんだけど、「景気」って抽象的やん。どの指標に影響するのか知ってる?
Aさん:そんな、住宅ローンの金利が決まっている指標があるん?
FPむー:実は、あるの!
Aさん:なになに、教えて!それを見ておけば、これから住宅ローンがどうなるか分かるやん!
FPむー:変動金利のもととなる指標と、固定金利のもととなる指標は別やねん。変動金利のもととなる指標は、短期プライムレートの金利、通称、短プラ。正確に言うと、この短プラに1%を上乗せして基準金利として、ここから各銀行が一定の利率を引き下げて決めている。固定金利のもととなる指標は、長期金利、主に10年国債金利。正確に言うと、それを参考に、各銀行が決めている。
Aさん:えっと…?変動金利と固定金利で、もととなる指標が違うことは分かったけど、それ以上は意味不明です。
FPむー:ごめんごめん、分かりやすく説明します。
ということで、会話形式から戻します(戻すんかい)。
◆変動金利のもととなるもの→短期プライムレートの金利。通称、短プラ。
短期プライムレートって何かって?
銀行が、業績や財務状況の良い会社に貸し出す時の、最優遇貸出金利をプライムレートと言います。そのうち、1年以内の短期貸出の金利を「短期プライムレート」(通称「短プラ」)と言います。
まぁ細かい話は覚えなくていいです。
覚えて欲しいのは、住宅ローンの変動金利は、この短プラに連動して決められているということ。
そしてその短プラ、ここんとこずーっと1.475%、13年間。
この推移を見てみて。
2001.2.9 1.5%
2001.3.28 1.375%
2006.6.24 1.625%
2007.3.20 1.875%
2008.11.17 1.675%
2009.1.13 1.475%
ここから、直近データの2022.2.10まで、ずーっと変わらず。
日本銀行からのデータです。一次情報やで。一次情報にさかのぼるの大事やで!
※上記の日本銀行のリンク、PCからだと見やすいのですが、スマホからだとかなり見づらいので、PCから見ることをオススメします!
そして、住宅ローンの変動金利は、このずーっと変わっていない短プラ1.475%+1%=2.475%が基準金利。
なので、ほとんどの銀行の変動金利の基準金利は2.475%のまま、ずーーっと変わっていない。
そうやねん、変動金利は変わってないねん。2009年1月13日からずっと。その前も、そんなに変わってない。もう一度見てみましょう。
2001.2.9 1.5%
2001.3.28 1.375%
2006.6.24 1.625%
2007.3.20 1.875%
2008.11.17 1.675%
2009.1.13 1.475%
ここから、2022.2.10まで、ずーっと変わらず。
1.375%~1.875%の間。0.5%しか変わってない。
ここでもう一度、今の変動金利と固定金利を見てましょう。
変動金利・・・0.5%前後
10年固定金利…0.8%前後
全期間固定金利…1.5%前後
変動金利と全期間固定金利なら、1%ほど差があります。変動金利と10年固定金利でも0.3%ほど差があります。
ということで、2009年から今日まで、変動金利のもととなる金利は変わってないんです。なんと13年間も!わぉ!
ほんでね、短プラが1.475%になった2009年1月って、どういう時か知っています?金融機関に勤めている人にとっては、「あー、あの時か」ってなるんですけど。
リーマンショックの後で、株価がめっちゃ下がった時なんです。
リーマンショックが起こったのが、2008年9月。
そして、その影響で、日経平均株価が一番安くなったのは、2009年3月10日、7054円98銭です。ちなみに、この記事を書いている今の日経平均株価は、26,827円43銭(2022年3月21日)。
2009年3月10日に日経平均株価を100万円買っていれば、今は380万円になっていますね、フフフ。1000万円買っていれば、3800万円になっていますよ、フフフ。
話が逸れますが、2009年と言えば、証券会社出身の先輩の言葉が忘れられません。
「今、日経平均株買っとき!だって7000円台やで!ほんの1年半前は、倍以上あったんや。仮に3500円になっても半分や。しれてるわ。」
って言ってました。
当時は新入社員だった私。「え、半分になるなんて嫌やわ!せいぜい2~3割ぐらいまでしか損したくないわ。」と思ったので、めっちゃ小口で買いました。日経平均株価に連動する投資信託を確か2万円ぐらい。小口すぎるやろ。ちなみに、一番最初に買った投資信託は、2009年、杏の実とグロソブでした。今でこそ悪名高い感じになってるけど、当時はメジャーだったんです。今でも、最初に買った当時の初心者用投信としては、悪くないと思っています。グロソブは、12年運用している私が、唯一損切りした投資信託だけど。
あかん、また話が逸れてもた。戻そう。
運用の話となると、色んな思い出がよみがえってきてしまってね。

さて、2009年1月からずっと変わっていない短プラ。
じゃぁ住宅ローンの変動金利が2.475%かと言うとそうではなくて、実際は各銀行がここから優遇して、今だと0.5%前後ぐらい。上記銀行だと.0375%~ありますが、あれ、最優遇金利ですので。色んな属性の人がいて、最優遇金利出せないことも多々ありますし、そのへんをまるっとまるめて、だいたい0.5%前後って感じ。銀行員としては、特定の銀行をオススメすることも出来ず(本当は自分が勤めている銀行をオススメしたいけど、全員にとってそれが正解ってわけでもないしね!)、あくまでもデータを載せました。
だから、各銀行の優遇度合いは変われど、住宅ローンの変動金利の基準となる金利は全く変わってないんですよ。
じゃぁ気になるよね。この短プラがどうやって決まるか。「無担保コール翌日物」などの市場金利に影響を受けて各銀行が決まります。無担保コール翌日物の金利とは、金融機関が1年以内の資金をやり取りするコール市場において、担保なしで資金を借りて翌日に返済する際の短期金利のことです。じゃぁ、「無担保コール翌日物」の金利はどうやって決まるのか。日銀の金融政策によって決まります。
はい、ここで画面閉じないで。
分かりやすく説明するから、もうちょっと読んで。

(↑画面を開くイメージ図)
◆住宅ローンの変動金利が今後どうなるか、何を見れば分かるの?
ってことが気になりますよね。
こういうことです。
住宅ローンの変動金利は何によって決まるの?
→短期プライムレートだよ。
→じゃぁ、短期プライムレートは何によって決まるの?
→無担保コール翌日物などの市場金利だよ。
→じゃぁ、無担保コール翌日物などの市場金利は何によって決まるの?
→日銀の金融政策だよ。
ってことです。
つまり、住宅ローンの変動金利は、日銀の金融政策によって決まるのです!
風が吹けば桶屋が儲かる的なニュアンスで話を飛ばしたけどね!
じゃぁ、住宅ローンの変動金利がこれからどうなるかは、日本銀行がどんな金融政策をするかってところがポイントとなる。その答えが、これ。日銀のHPだよ。
え、分からんって?
そうだよねぇ。日銀のHPって、金融機関関係者から見れば分かりやすいんだけど、そうでない人からだと分かりにくいだろうなぁって思う。ちなみに日経新聞も。
めっちゃ簡潔にまとめてみましょう。
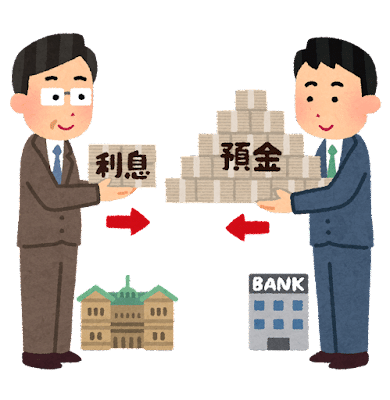
2013年4月 日銀が金融緩和を始めたで。「量的・質的金融緩和」を導入って言うんやで。お金ばらまくで、金利コントロールするで。
↓
いつまで続けるかって?物価が安定するまでやで。
日本銀行法では、日本銀行の金融政策の理念を「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」としています。物価の安定が大切なのは、それがあらゆる経済活動や国民経済の基盤となるからです。
ー日本銀行HPよりー
↓
物価が安定するってのは、昨年比で物価が2%上昇することやで。
って話です。
じゃぁ気になるよね。
今の日本の物価上昇率は、どのぐらいなんやろ?
2022年2月の日本の物価上昇率は0.6%です。
去年の夏まではマイナスだったのを考えると、じわりじわりと上がってきています。コロナ禍以前2020年2月以来の伸び幅。ちなみに、携帯値下げの影響(1.5ポイント)を除くと2%を超える数字。そう、ポイントは、目標の2%を超える数字ってこと。
今度、日本も物価はどんどん上がってくるでしょう。原油などの資源価格が上がってきていますし、さらに円安の影響もあります。1年前は107円やったのに、今や119円やで。(私は従来から円安に向かうでしょう派なので、問題視していませんが。)
各社が、色んな商品を値上げしてるニュースをよく聞きますよね。安い代名詞のような「うまい棒」でさえ、値上げすることとなりました。42年間ずっと10円を続けていたうまい棒が、2022年4月から12円へ。物価は上がってきています。
ということで、再度話をまとめます。
住宅ローンの変動金利は、短期プライムレートによって決まる
→短期プライムレートは何によって決まるの?
→無担保コール翌日物などの市場金利だよ
→無担保コール翌日物などの市場金利は何によって決まるの?
→日銀の金融政策だよ
→日銀の金融政策は、物価がポイント
→物価は上がってきているよ
ということなのです。
あとはね、もう1つ注目ポイントとしては、日銀のトップが2023年4月8日で任期なことですね。トップが変われば方針が変わる可能性もあって、もしトップが交代すると、金融政策を見直す可能性は5割以上ある(By大和証券の岩下真理チーフマーケットエコノミスト)との話もあります。
黒田総裁が就任したのは2013年3月、異例の2期10年ですからね。黒ちゃんの政策には賛否両論ありますが、日銀内からは高い評価を得ているそうです。
ということで、住宅ローンの変動金利について今後どう考えればいいか、少しつかめてきたでしょうか?
では次に、固定金利はどうなのでしょうか。
◆固定金利のもととなるもの→長期金利、つまり10年国債の金利など。これは市場によって左右される。
住宅ローンの固定金利は、10年国債の金利など。これは市場によって左右されます。
日銀の政策に影響される変動金利はここ10年以上全く動いていませんが、長期金利に影響される固定金利はめっちゃ動いています。長期金利の推移はこんな感じ。

ー楽天証券より、長期金利ここ10年の推移ー
2016年夏秋あたりが底でしたね。住宅ローンでも、確か10年固定で0.35%みたいな神金利がありました。あの時に10年固定の住宅ローン組んだ人、たぶん史上最低金利で組めてますよ!今だと10年固定で0.8%ぐらい。全期間固定で1.5%ぐらい。
で、この長期金利がどうやって決まるかが気になりますよね。
短期金利は日本銀行の金融政策などによって決まりますが、長期金利は、主に長期資金の需給関係によって決まるもので、物価の変動、短期金利の推移(金融政策)などの長期的な予想で変動します。そうした特徴から、「長期金利は経済の基礎体温」ともいわれていて、景気が悪くなれば低くなり、景気が良くなれば高くなるという傾向にあります。
ーSMBC日興証券のHPよりー
簡単に言うと、今後の景気予測に左右されます。そしてこの長期金利、最近ちょっとずつ上がってきています。

ー楽天証券より、長期金利ここ1年の推移ー
上がってきているのが分かりますよね。
つまり。
長期金利が上昇していきている
→長期金利を基準としている住宅ローンの固定金利が上がってきている
という流れなんです。
だから、各銀行が住宅ローンの固定金利を上げだしています。
何回も言って申し訳ないけど、変動金利はまだ今のところ上がっていません。固定金利が上がり出しています。
さて、じゃぁそんな中、変動金利と固定金利どっちがいいのか。
◆変動金利と固定金利の、メリットとデメリット
まずは、それぞれのメリットとデメリットをおさらいしてみましょう。
<変動金利のメリット>
・金利が低いので、毎月の返済額が抑えられる
・金利が低いので、元本部分をどんどん返済できる
・金利が上がったら、繰上返済や固定金利の切替などで対応可能
<変動金利のデメリット>
・金利が上がるかもしれないので、長期的な返済計画が立てづらい
・金利上昇局面に耐えられるのか
<固定金利のメリット>
・金利が変わらない安心感があるので、長期的な返済計画を立てやすい
<固定金利のデメリット>
・金利が高いので、毎月の返済額が増える
・金利が高いので、最初は利子部分の返済が大きく、元本部分がなかなか減らない
・固定金利の期間の途中で、繰上返済や変動金利に変更することは難しい(手数料がめっちゃかかる等)
◆以上を踏まえた上で、どっちがいいのかはこちら!
★変動金利がオススメな人
→今後すぐには金利が上がらないと思っている人
→とにかく毎月の返済額を抑えたい人
→このnoteに書いてある金利の動きをしっかり理解して、随時動きをチェックできる人
→途中で繰上返済を考えている人
→もし変動金利が上がっても、ちゃんと返済能力がある人(繰上返済できる余力があるとか、家計に余裕があるから金利が上がっても大丈夫とか)
★全期間固定金利がオススメな人
→金利のことがよく分からない人
→今後すぐに金利が上がると思っている人
→金利が上がるかもしれないことにドキドキしちゃう人
→長期の返済計画をしっかりたてたい人
→途中での繰上返済をあまり考えていない人
★10年固定金利がオススメな人
→固定の安心感と、返済額の安さの、両方のいいとこどりしたい人
→変動金利か固定金利か、考えすぎて選べない人
って感じです。
ふぅ、長くなってもた。なんと7,500字以上あります!
ここまで読んでくださった方々、ありがとうございます。住宅ローンの金利がこれからどうなるかは何を見ればいいのか、そして自身にとってどちらの金利がいいのか、見えてきたのではないでしょうか。
このへんを踏まえて、では、銀行員×FP1級CFPホルダーである私は、住宅ローンで何を選択したのか。長くなってきたので、続きは次回に続きます、たぶん。
こんなに長いのを読んでくださった方々、本当にありがとうございます!是非「読んだよ」でもいいので、コメントいただけると嬉しいです!
(7,528字)
ありがとうございます!サポートとても嬉しいです。いただいたサポートで、娘に絵本を買っています。
