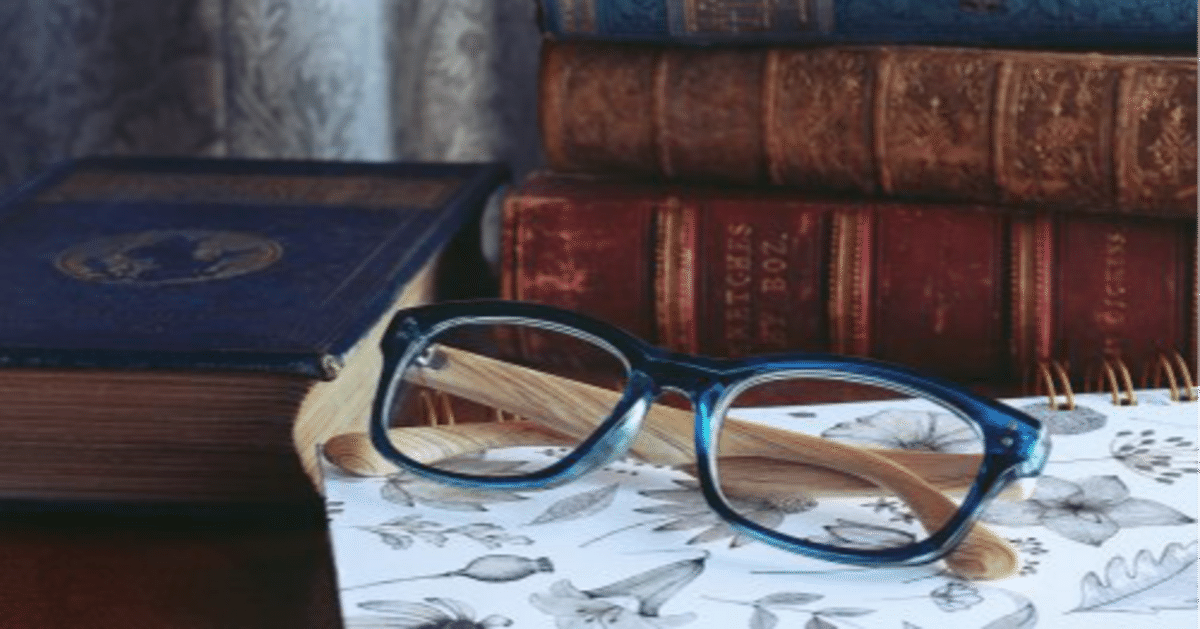
小児近視の薬物治療 (低濃度アトロピン点眼)の現状
作用機序
アトロピンは非選択的ムスカリン受容体拮抗作用による散瞳・調節麻痺薬であるが、近視の進行抑制する根本的なメカニズムは不明である。
現在提唱されている仮説として
調節機能への影響ではなく、網脈絡膜や胸膜に直接作用している可能性
後部強膜における細胞外マトリックス成分の産生を減少させる強膜リモデリング抑制機序
網膜アマクリン細胞のムスカリン受容体を介したドパミン産生機序
散瞳による眼内光量の増加作用
脈絡膜血流の増加作用
近年、脈絡膜血流との関係も多く報告されている。
動物実験ではモルモットの近視眼にアトロピン(AT)を注射することにより、脈絡膜肥厚、脈絡膜血流増加が認められ、眼軸進行が抑制された、
その機序として
強膜の低酸素標識であるビモニタゾールが減っており、脈絡膜血流の増加による肥厚が強膜低酸素抑制を促し、眼軸進行が抑制されるという、仮説。
また低濃度アトロピン点眼治療において、濃度依存性に脈絡膜肥厚が証明されている。(香港Low-concentration Atropine for Myopia Progression)
本邦、オルソケラトロジーとAT0.01%併用療法、AT0.01%単独療法での1年間の経時変化では、AT単独療法では最初の3ヶ月では脈絡膜厚の増加を認めるが、以降脈絡膜厚は減少していた。
比べて併用療法では肥厚した脈絡膜厚を保持していた。
また、脈絡膜厚変化は眼軸変化量と有意に相関していた。(AT単独0.14mm,併用0.42mm)
脈絡膜厚の変化は低濃度ATのみでなく、オルソケラトロジー、レッドライト療法、多焦点コンタクトレンズにおいても有意な増加が認められている。 →機序は不明
低濃度アトロピン点眼の有効性
2006年、シンガポールのAtropine for the Treatment of Childhood Myopia 1(ATOM1)
2012年、ATOM2
2年間のRCTにおいて、0.5%,0.1%,0.01%アトロピン点眼を評価、
0.01%AT点眼が治療と副作用のバランスが取れていて最適と示された
その後、香港のLAMP研究で、ATの濃度依存的に近視抑制効果があること、治療抵抗性は低年齢と相関するため、低年齢であるほど高濃度の0.05%アトロピン点眼が必要であると結論付けられた。
3年間の研究の最後の1年間はAT点眼中止し、リバウンド評価期間を設けた
それぞれの濃度のリバウンド率は0.05%が他の濃度と比べて大きく、低年齢であるほど有意に大きなリバウンドを示した。
0.05%AT使用の際は、テーパリング後の離脱、進行度が低くなる高学年での治療中止を検討する。
本邦のATOM-J研究では2年間のRCTで0.01%AT点眼の近視進行抑制率は15%と海外の研究に比べて低い結果であった。
リバウンド評価では0.01%ATのリバウンドは無かった。
オーストラリアでの同様の研究では、プラセボ群との比較で、屈折値0.14D,眼軸長0.04mmと統計学的有意差なし。
米国の報告では、プラセボ群との比較で屈折値0.02D,眼軸長0.002mmと有意差なし。
アトロピン点眼の反応における人種差の可能性がある。
副作用
ATOM2では、しゅう明と金券障害で調節レンズ、累進レンズが処方されたのは7%であった。
0.1%と0.5%ATでは瞳孔径が3mm増大したが、0.01%ではmm程度であった。
治療抵抗性と危険因子
LAMP研究においてAT点眼後も2.0D異常の近視進行が認められた0.05%,0.025%,0.01%群でそれぞれ9.1%,7.0%,19.2%であった。
対策としてはオルソケラトロジー、多焦点SCLへの変更、併用療法が考えられる。
併用療法の有効性
0.01%AT&オルソK併用群とオルソK単独群の比較で、併用群は単独群よりも28%抑制効果が高かった。
特に-3.0D以下の弱度近視で良好な結果、-3.0D〜-6.0Dの中等度近視では相乗効果が見られなかった。
オルソKは中央角膜上皮の平坦化で、周辺角膜が肥厚することで近視性デフォーカスや高次収差が増大、瞳孔径が拡大することで、周辺の高次収差の影響をうけやすくなる。
前近視の段階における低濃度アトロピン点眼の近視発症予防効果
国際近視機構(IMI)はSEが-0.50D〜+0.75Dの間を「前近視」と定義。
台湾の研究では5〜6歳の前近視有病率は25.0%と言われている。
調節麻痺下屈折値+1.00D〜0Dの非近視性児の研究では0.05%群はプラセボ群と比較して近視発生率を53.0%から28.4%に有意に減少させた
0.01%群では45.1%と有意な効果は認められなかった。
近視発症前からの薬剤介入により近視進行予防が期待されるが、長期に渡る治療の影響、低年齢児のリバウンド効果など課題点も挙げられる。
結語
低濃度AT点眼はアジア人においてはある程度の近視抑制効果がある。
前近視の近視進行予防効果も認められた。
低年齢には0.01%より高濃度のアトロピン点眼を検討する必要がある。
課題として、治療開始時期、終了時期、投与頻度や時間、斬減スケジュールの最適化が挙げられる。
眼科vol.66 No.1 2024
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
