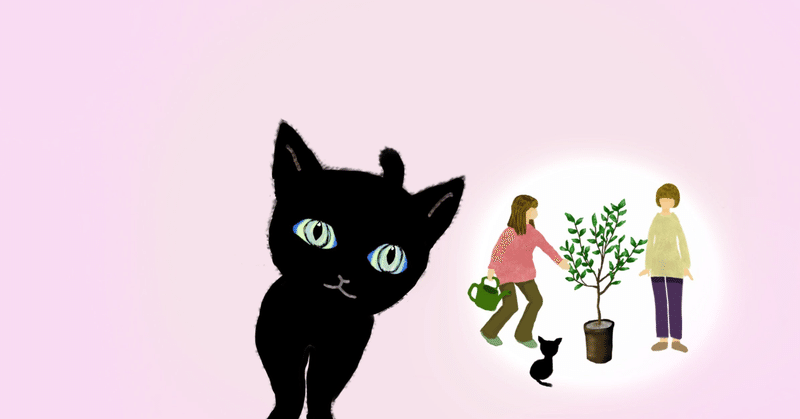
文芸批評断章19
北村透谷は『内部生命論』で次のように言う、「諸君よ、吾人が五十年の人生に重きを置かずして、人生の根本の生命を尋ぬるを責める勿れ、諸君よ、吾人が眼に見うる的の事業に心を注がずして、人間の根本の生命を暗索するを責むる勿れ」と。「人生の根本の生命」とは何か。「生命といふは、この五十年の人生を指して言ふにあらざるなり。」と言う。生命とは物質的生命でなくして霊的生命であり、死後も続くのである。人生の本質であり、文明の根底にあるものであって、「外部の文明は内部の文明の反影なり」となるのである。
イエスは「人はパンのみに生くるに非ず」と訴えた。その言わんとするところは、なるほど私たち人間にとってパン(この「パン」は衣食住の謂いであり、透谷のいうところの「五十年の人生」を支える物質的糧であろうと思われるが)は大切であるが、それ以上に神の言葉のほうが私たちの精神にとっては糧になる、ということであろう。ここではパンは否定されてはいないことに注目されたし。パンだけでなく神の言葉もまた重要なのであって、だからといってパンは必要といえば必要なのである。ところが透谷といえば、「五十年の人生に重きを置かずして、人生の根本の声明を尋ぬる」とするのであって、ここでは(少なくとも言葉の上では)物質的人生は否定されており、ただ霊的人生のみが探求の対象となっている。透谷の言葉をイエスのそれに翻案すれば、「人はパンに生きるに非ず」となる。ここで両者の言葉を比較してみると、「人はパンのみに生くるに非ず」は、パンを否定しておらず、物質も精神もともに人間が生きるには欠かせないとする。これに対して、「人はパンに生くるに非ず」と言えば、物質を全面否定しており、人間が人間らしく生きるにはむしろパンは不要なのである。イエスは穏健であり中庸を守っているのに対して、透谷は極端であり中庸を逸脱しているのである。私はここにロマン主義の病弊を見出すのである。かくしてこの過剰なる理想主義の病に陥った透谷、パンを捨てて神の言葉のみにすがったこの若きロマン主義者は、神に愛され若くして天に召されることとなったのである。
このような極論は、ロマン主義者であった若き日の高山樗牛が、愛こそが人生最大の幸福の源泉であって情死を讃えたことに通じるようにも思われる。「『今戸心中』と情死」である(「太陽」明治29年)。
人々の人らしきは其情にあり、吾れは情に殉ずるの人を見る毎に、感究まり意切なるの余り、其の最後の尤もらしきを想はずんばあらず。
天にありては星、地にありては花、人にありては情、是れ世に美しきものの最ならずや。あらゆる死は美しきなり、されども吾れは、愛に忍び恋に憧れて自ら天命を裁する所謂情死なるものの甚だ美はしきものなるを想ふ。
道徳家をして其の言はむと欲する所を言はしめよ、哲学者をして其の説かむと欲する所を説かしめよ。而も吾れは遂に人生の脆弱を認め、尽躯の汚染を救はむとすなる宗教家が現在の中に其の身を容るる所無き是の憐なる犠牲の為に其の最後の居住すら拒まむとするの意を解する能はず。吾れは脆弱有漏の人間として情死に向って満幅の同情を寄すものなり。
つまり、透谷は内部生命を重んじるあまりに外部生命を蔑ろにするのであり、樗牛は生きながらえて恋を成就することよりも恋に死ぬことをより美しいと感じて、同情を寄せるのである。いずれも現実味を欠く極端であり、これを私は病めるロマン主義と捉えるのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
