
こども家庭庁をみまもりたい
毎年4月はいろいろな制度がかわる月ですが、今年2023年は特筆すべき年です。
政府にあたらしい「庁」、「こども家庭庁」が誕生したからです。
1府12省庁、省は内閣府のこどもで、庁は孫のような関係といいます。
省庁を横断するデジタル庁・復興庁をのぞき、庁は各省にひもづく機関となっていますが、「こども家庭庁」は、内閣府にひもづく機関。
宮内庁、警察庁、金融庁、消費者庁と同じような立場です。
一覧にするとこんなかたちです。
小学校の社会科を思い出しますね。

これは、とても大きな出来事だと思いますが、あまり大きく報道されていない印象があります。
今日は「こども家庭庁」の総本山といってもいい、Webサイトからのぞいてみましょう。
1.こども家庭庁のサイトはどんな感じ?
各省庁のWebサイトを見たことがありますか?
たとえば、金融庁のトップページはこんな感じです。

そして、デジタル庁はこんな感じ。

わかりやすくシンプルなイメージですよね。
一方、こども家庭庁のサイトトップはこんな感じです。
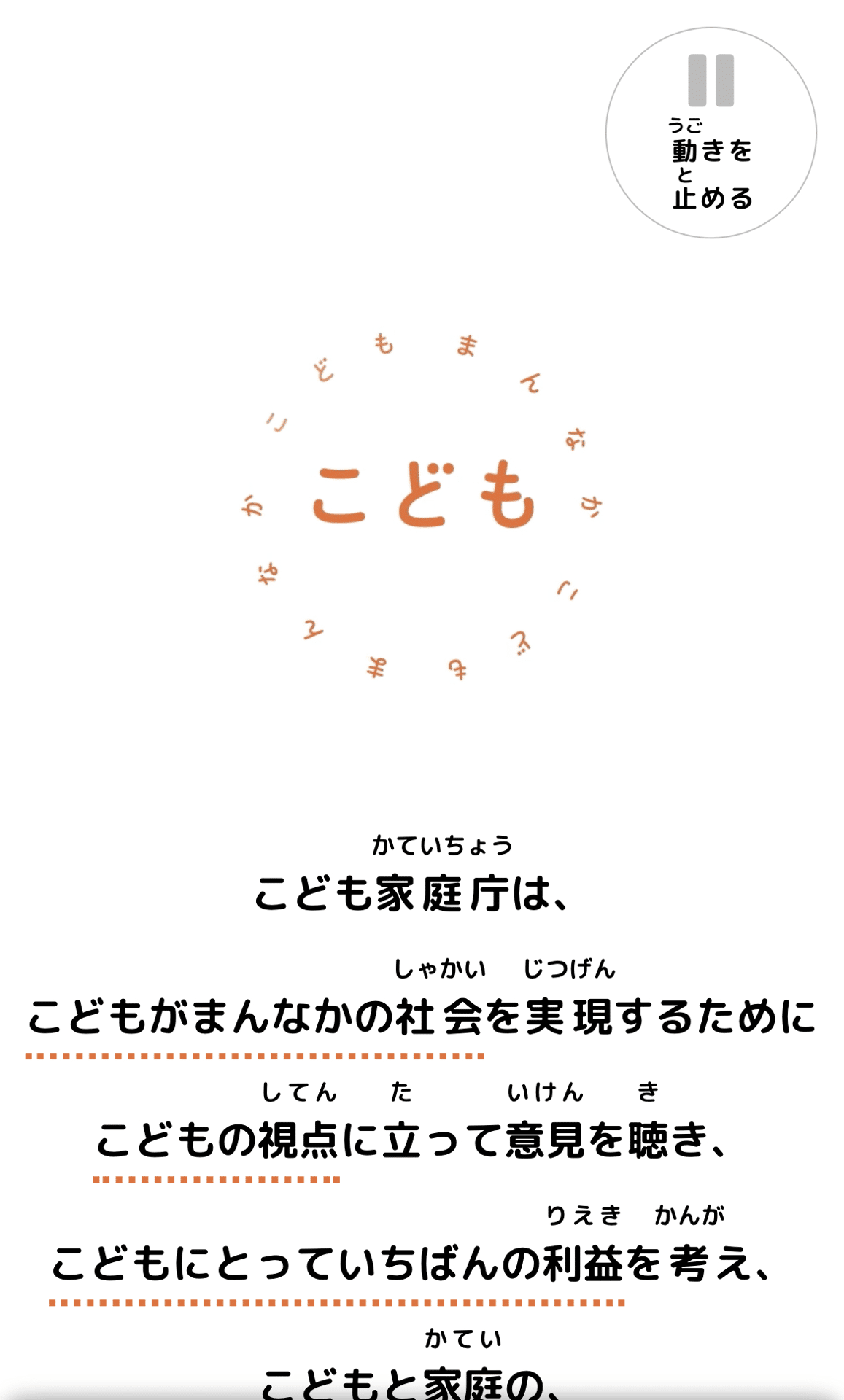
ふりがながある、ひらがな多い!!が最初のインパクトでした。
文字も大きく、画面に動きもある仕様になっています。
こども家庭庁はこれも同じく2023年4月から施行された「こども基本法」に基づいて運用されますが、「こども基本法」第11条には、(こども施策に対するこども等の意見の反映)として、以下のようにさだめられています。
つまり、なにかこどもに関する施策をおこなうときには、こどもや養育者、当事者の意見を聴くと決められているのです。
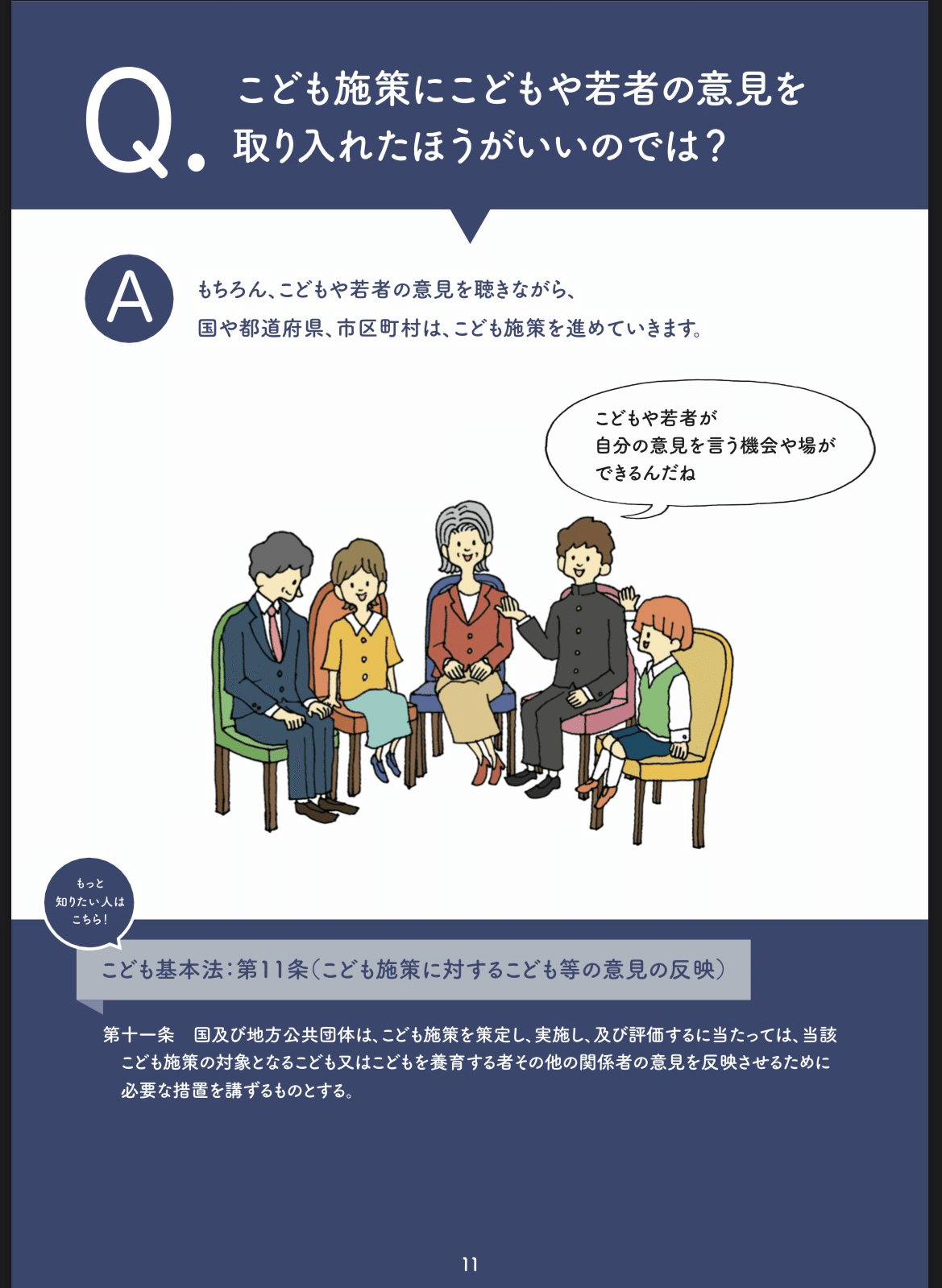
このサイトもその意見を聴くひとつの場、だからトップページから親しみのあるわかりやすいデザインになっているのかもしれません。
とはいえ、おとなが知りたい情報はそれはそれで必要です。
Webサイトトップページの下のほうにいくと、ちゃんと、おとなとこどもの別があります。
こども向けのサイトはこの秋オープンとのこと。
「更新」ではなく「うまれかわる」とあるところにも、配慮が感じられます。
ここをうまく活用することが重要になってくると思いますので、どんなアクションができるのか、この秋が楽しみです。

2.「こども」って、何歳まで?
ところで、こうして「こども家庭庁」が声を聞こうとしている「こども」って、何歳までのこどもなのでしょうか?
未成年は18歳未満、お酒を飲んではいけないのは20歳未満、そのどちらかかな?と思ってしまいがちです。
ですが、「こども基本法」すごい!と私が思ったのは、年齢で一律にさだめるのではなく、「心と体の発達の過程にあるひと」=「こども」、としているのです。
「こども」の抱える問題に、とても真摯に向き合っている気がします。

3.個人的に期待していること
私が個人的に期待していることは、「こども家庭庁」ができたことにより、あちこちにわかれていたこども関係の情報が集約されること。
まさに「こども家庭庁」ができた理由のひとつも、これです。
これまで「白書」(政府が、政治の各分野の現状と課題をひとまとめにして国民に報告する公文書)や「大綱」(各分野の根本となる骨組みで、目標や施策の根本となる方針を定めるもの)といった、こども関係の資料は、いくつかの種類に分かれていました。
たとえば、白書関係は、「少子化社会対策白書」「子供・若者白書」「子ども の貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況」。
大綱は、「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関する大綱」とわかれていました。
それが、それぞれ束ねられて、「こども白書」「こども大綱」となります。
従来別個にあったこども関係の情報がひとつになることから、統一性のある大綱の下で、これまでより総合的かつ一体的にこども施策を進めていくことが可能になりますし、行政の事務負担の軽減にもつながります。
特に「白書」はわたしたち国民向けの資料なのですから、「こども家庭庁」はできたばかりの機関なだけに、どんなことをしてきたのかを、しっかり見守ってフィードバックしていきたいものです。
組織をうごかしているのは人間、フィードバックがあればやはり嬉しいもの。
そうやって見守ることで、私も応援していきたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
