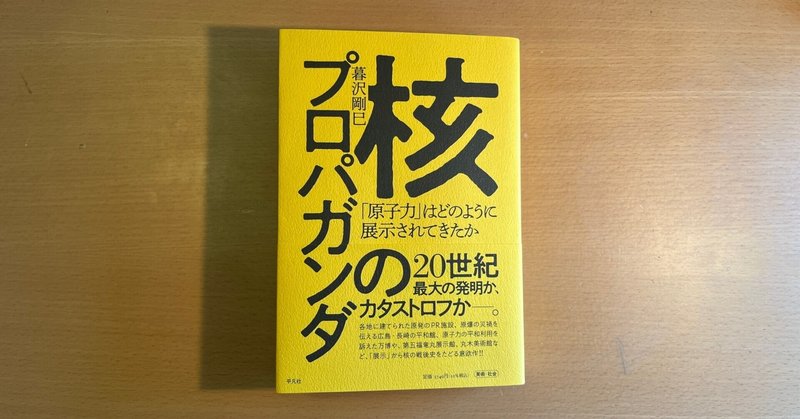
【読んだ】暮沢剛巳『核のプロパガンダ 「原子力」はどのように展示されてきたのか』
広島の平和記念資料館や長崎原爆資料館、東日本大震災・原子力災害伝承館、各地の原発PR施設等々、原爆投下や原子力災害、原子力利用を巡る展示やキャンペーンについて論じた本。印象に残ったのは、こうした展示がいかに政治的思惑や駆引や偶発的要因によって規定されているのか、という事だった。
本書の序盤、東日本大震災での原子力災害展示を巡って、「事故」と能動的に向き合うという発想の転換が示される。「事故」は定義上偶有的に生じるものであり、受動的に向き合う他ないように思えるけれども、ヴィリリオは「原事故」という概念を用いる事でそこに能動的発想を見出した。新しい技術革新が必ず生み出す新しい事故を「原罪」ならぬ「原事故」とし、新しい知の生産の契機として捉えるのだと。それは、われわれが受動的に事故に晒されるのではなく、われわれが能動的に事故を晒すという逆転である。この能動的発想によって作られるのが「事故の博物館」であり、暮沢はそれを事故から拡張し、アウシュビッツやヒロシマを巡る記憶装置にも敷衍する(P43-44)。
「事故の博物館」の意義は、事故を正確に記憶・記録し、今後同様の事態が生じた時の被害を軽減させる事だと著者は言う(多分だけど、ヴィリリオの意図は少し違う所にあるような気がした)。しかし本書で描かれる現実は、そうした健全な動機とは掛け離れたものだった。例えば311の原発事故を巡る展示では、復興ばかりが(現実離れした内容で)強調される一方、政府や東電や自治体の責任は意図的に語られない。被曝後間もない1950年代に日本全国で行われた「原子力平和利用博覧会」では原子力の平和利用がアピールされたけど、それは原子力技術輸出で覇権を狙うアメリカが、日本に原発を導入させるためだった。正力松太郎が「原子力平和利用博覧会」を取り仕切った動機は政治的野心だった。「原子力平和利用博覧会」では、原子力のポジティヴな側面ばかりが強調されていたけれども、その手法は今も、全国の原発PR施設に継承されている。風間サチコはそこに「胡散臭さ」を感じ取って作品制作をしていたというけれども、その胡散臭さは311の後に露骨に明らかになった。
こうした政治的な思惑は、国家による原子力推進の言説だけではなく、反核運動や市民運動の中にもあったという。日本の反核運動は共産党と社会党の政治対立に規定されていたのであり、両者の支持基盤である電力総連との関係故に上手くいかなかった。岡本太郎は確かに原爆投下の惨禍を描いた「反核」の人物だったが、同時に原子力の平和利用にはむしろ肯定的であり、「反原子力」「反原発」の人物ではなかった。著者は、近年、岡本太郎と反原発を結びつけようとする思潮を「俗説に過ぎない」と強く批判する(P317)。
「事故の博物館」は能動的な営為だというけれども、結局この本で描かれていたのはむしろ能動性の限界ではなかったか。最初に破局的なカタストロフがあったとしても、原子力を巡る言説は政治的な思惑や駆引に規定される。それは原爆を落とされた日本だけではなくアメリカでもそうだったのだという事を描いたのが、ノーランの「オッペンハイマー 」だったように思う。当時の最新の物理理論を使って兵器を開発するというのはいかにも能動的な営みに思えるけれども、実際に描かれていたのは、理論では対処できない予測不可能性や、政治的駆け引き、嫉妬心から生じた裁判沙汰、あるいは色恋沙汰等々、偶然性や不合理な人間の情念に翻弄され続けた科学者の姿であり、むしろ能動的に状況を統御する事が超下手な人物としてのオッペンハイマーだった。あの映画では冒頭、うやうやしくプロメテウスが引用されているし、「理性の限界」みたいな普遍的な話がテーマなんだとも思うけども、描かれていたのは形而上学的な深遠な話というよりは、普通にダメな奴の俗っぽいダメさが破局的なカタストロフを生み出してしまうという残酷な真理だった様に思う。
個人的には、「事故の博物館」は記憶装置としての側面が大きいんじゃないかと思う。白井晟一はそれを「メモリイを強いる造形」「悲劇のメモリィを定着する譬喩」として批判したという(P151-152)。しかし例えば星野太が指摘するように(※)、われわれは多かれ少なかれカタストロフに魅せられてしまう事を免れない。その仄暗い感情の存在を抑圧する限り、人は「美しい」言葉がもたらす偽の紐帯に屈する。
本書では、被曝遺構が偶発的要因に規定されている事も示されていた。広島と長崎の決定的な違いは、「長崎には、広島における原爆ドームに相当する施設が存在しない」事なのだけど(P91)、それは残存した建物が公共施設であったのか、宗教施設であったのかの違いによるという。第五福竜丸は事故後10年以上使われ、廃棄されていた所を発見されて保存が決まったという。自分は昨年初めて平和記念公園を訪れたのだけど、その空間が如何にも丹下らしい戦後の建築のモードに規定されていたのが印象的だったし、それが作られる過程での強烈なジェントリフィケーションの歴史にも驚いた。しかしそれがどれだけ恣意的で偶発的要因に規定されていても、そこで喚起された身体感覚は驚く程強烈だった。
※「カタストロフと崇高」(星野太『美学のプラクティス』(2021年、水声社)所収)
