
[008]経済のお勉強〜其の四〜インフレ
じっちゃまの解釈を正しく理解出来ているかわかりませんが、インフレについて勉強してみました。
インフレとは

じっちゃま曰く、《FRBの二つの使命(デュアル・マンドレート)とは①失業率の最小限化、②インフレ率2%に安定させること。新しい政策では期待インフレ率が3%、3.5%になってもすぐには利上げしない。もし好景気になってもFRBはなるべく粘って利上げしない可能性がある。》
インフレ率の安定化はFRBのもう一つの大きなテーマです。インフレとは物価が全体的に上がる事です。反対はデフレです。金余り状態で、商品やサービスが不足している状況で発生します。特定の商品の値段が上がるだけではインフレが進むとは言いません。様々な商品やサービスの平均的な変化を調査するため、バスケット(様々な商品、サービスの一般的な購入量をセットとする考え)の値段がどう推移するかを調査します。
インフレは悪か?
じっちゃま曰く、《経済成長とインフレは二人三脚で行った方がいいよね。》
一般的には物の値段が上がるので、給料が変わらなければ買える物は減ってしまうため、これはいかんとなるのが普通です。しかし適正なインフレ率(2%程度)は必要とされます。
ただし10%のインフレでは物の価値が適正に上昇しているのではなく、通貨の価値がぶち壊されている事になるためよろしくありません。また-1%や0%のインフレ率も問題を引き起こします。企業にとっては少しの間違い(値段設定や売る時期)が赤字につながるためです。そのため《微熱程度のインフレ》が丁度よいと言う事になります。この歴史的に丁度良いと言う事がわかってきた《2%》程度のインフレが企業の成長マインドを刺激し適度な競争を生み経済成長につながります。
インフレ率と株式投資
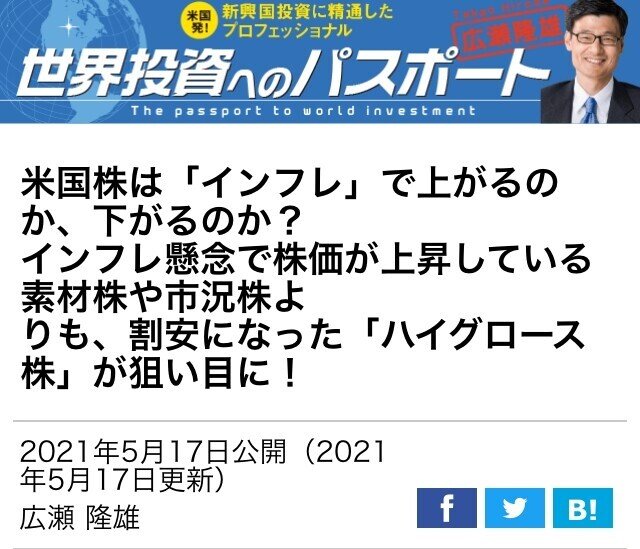
※インフレに関しては上記の記事に《じっちゃま》がまとめられています。
インフレ率の抑制に関しては金融政策と財政政策が重要になります。今回長くなったので別途これらについては書いてみようとおもいますが、ざっと言うと下記の要領です。インフレの原因は色々ありますが起こることは「金が余り物がない」という事に変わりはありません。これを抑えるには需要を抑える、すなわちお金を減らしお金が商品やサービスの購入に向かわない様にします。そのため政府は、増税、財政支出減、《金利アップ》等を行います。やはり最後は金利が関係してきます。
関連指標
◼️消費者物価指数(CPI=Consumer Price Index)
米労働省労働統計局が、毎月15日前後に発表している標準的なインフレ指標。 米国都市部の消費者が、商品やサービスに対して支払った価格の変化を算出したもので、基準となる年を100として、その基準年の価格と比較しどの程度物価が変化したかを表す。
◼️個人消費支出(PCE=Personal Consumption Expenditures)
米商務省が公表する、米国の家計が消費した財やサービスを集計した経済指標でGDPの約7割を占めるため米国の個人消費支出はGDPの先行指標と位置付けられる。FRBは比較的重要視する。
◼️生産者物価指数(PPI=Producer Price Index)
米国の労働省が米国内の製造業者の販売価格を約1万品目について調査し発表する。 製造段階別(最終財・中間財・原材料)、品目別、産業別の数値が毎月11日頃発表される。
一般的に消費者物価指数よりも景気を反映させるのが早いといわれ、先行指標として注目されています。一方、変動しやすい要素(エネルギー・食料)の影響を受ける事や
全ての産業が網羅されていない(サービス産業)事等がデメリット。
◼️GDPデフレーター
GDPの価格に関する指数で、GDPを時価で表示した名目GDPから物価水準の変化分を調整する際に用いられる。GDPデフレーターで調整することで、物価変動の影響を受けない財やサービスの数量つまり実質GDPがわかります。
◼️雇用統計平均時給 ※2021/06/11追記
じっちゃま曰く、《物価に関してはCPI(消費者物価指数)だけでなく雇用統計の平均時給を見ている。なぜなら賃金は上がりはじめたらズンズンと上がっていくから。FRBは賃金インフレにもっともピリピリと神経を尖らしている》という事でこれも重要。
メモ
インフレは55年周期でピークをつける。

(図=じっちゃまツイート引用)
最後に
日本にいると、インフレやデフレなんて意識する事ありませんでしたが、危機的な状況であると感じられ、日本の市場にだけ投資していてはいけないとより強く感じますね。
最後まで読んでいただきありがとうございます(≧∀≦)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
