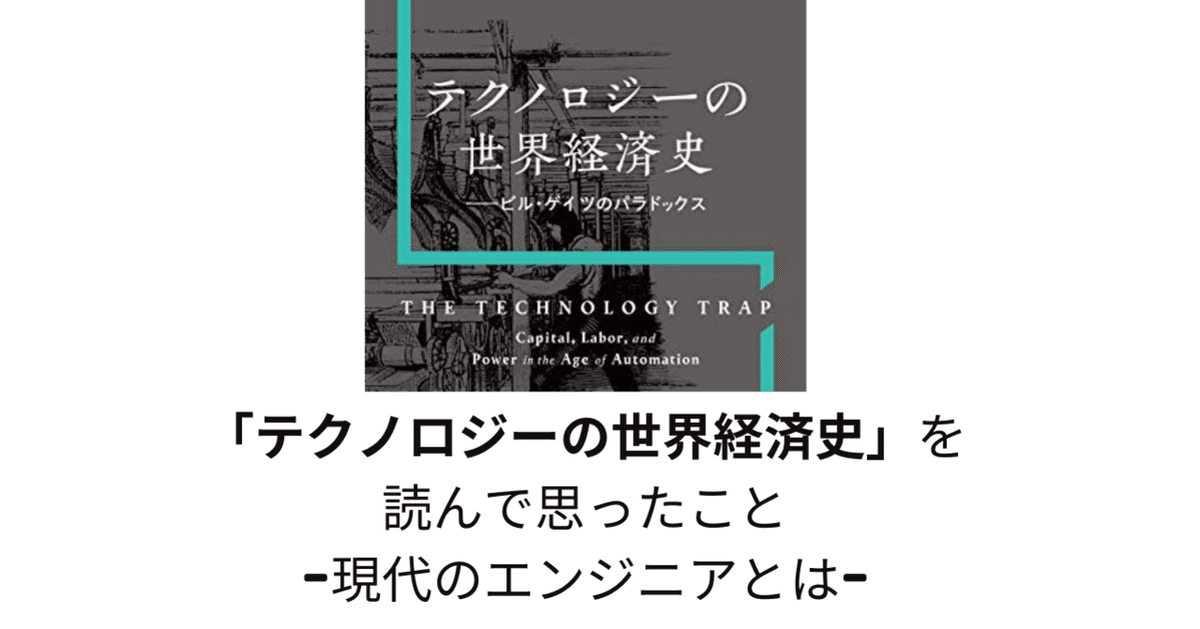
「テクノロジーの世界経済史」を読んでみた-現代のエンジニアとは
◯いつからエンジニアは生まれたのか
しばしばエンジニアは「魔法使い」と称される。シリコンバレーではソフトウェアエンジニアは高尚な職業という位置づけで、優秀なプログラマーであれば年収は日本の比ではないとともに、保険にも入りやすいと聞く。日本においても、昨今では中高生の将来なりたい職業ランキングでもITエンジニア・プログラマが上位にランクインすることがさも当然のようになってきた。
今では”エンジニア”はイコール”ITエンジニア”のことを指す文脈で使われることが多いが、工場機械や農業器具、伝統工芸などものづくりに携わる人はみんなエンジニアだ。私の父も、銀行のキャッシュディスペンサーやATMを開発していて、自分のことをエンジニアと名乗っていた。それも誇らしげに。
父は昔から地元のお仕事博物館や科学博物館に連れて行ってくれては、ロボットのコーナーで存分に知識をひけらかしてくれた。私も目も輝かせて「エンジニアってかっこいいなあ、、、」と教えられて育った。(その時点では魔法を使おうとは思っていなかったが)
◯複雑化、高度化していったエンジニアのお仕事
ではなぜ現代のITエンジニアは”魔法使い”と化しているのだろう?それは、「よくわからないから」に尽きる。私もSEになった後、地元の久々にあった友人「プログラミングができる」というと「すごいね!」みたいなことを言われたりすることもあったが、余り技術力に優れていないという自負があった私は、「いやまじで全然だよ」となった。それでもやっぱり世間のイメージからは、かっこいいアプリやサイトを作れる人といった印象があるのだろう。
歴史を振り返ると、活版印刷、自動綿織機、蒸気機関、電気、そしてコンピューター。。。どんどん人に求められるスキルは複雑で高度なものになっていった。テクノロジーの世界経済史によると、市場が求められるスキルが高くなるほど、その技術を有しているかで、教育による格差が広がっていくそうだ。
現代の人工知能も中のアルゴリズムはブラックボックスと化しているが、普及は進んでいっている。電気や蒸気機関と同じような汎用的な技術となりつつある。そういった意味で、機械学習に携わる人は人々にとってよくわからないが「すごい」となっていくのだろう。
◯大衆化する魔法使い
一方で、今では誰でも魔法使いになれる土壌は整ってきている。話題の乱立するプログラミングスクールは果たしてどうなのか?という議題はおいておいて、どこでもいつでもプログラミングは学ぶことができる。ただここで注意したいのは、仕組みや構造がわかれば魔法ではなくなってしまうという点だ。そこから先は、自分が作れないものやアイデアを具現化する力であったり、いかに高速でつくれるようになるか、というスキルの高め合いとなる。ハリーポッターの世界でもヴォルデモート卿とネビルじゃ同じ立ち位置にいるとはいえないだろう。(たまにハリ―のようなギフトをもった子が生まれてくることもあるが)
つまるところ、高等教育が発展しプログラミング教育が義務化されれば、魔法使いはより高度なスキルを持つ人材のみを指すようになるということだ。

◯魔法が当たり前になったらどうなるのか
今ではCMSやNoCode技術の進化により、Webサイトやインフラの構築ですら、初心者でもできるように簡略化が進んでいる。Webサイトは様々なビルダーがでてきてプログラミング知識は不要だ。先日、フリーランスの妻のためにWordpressでホームページを作ったが、「これで作り直す」と言われ、Strikinglyを教えられた。デザインも良く、なるほどこれで全然素人目にはよくできたサイトだ、といわれるだろう。
また、AWSなどのパブリッククラウドの普及、そしてFirebaseやAWS Amplifyのように環境構築が容易となるようにこれまで初学者にはハードルが高かったインフラ周りもどんどん手が入っている。中身を意識しなくても済む範囲が広がっているのだ。
誰もが魔法を魔法と意識しなくなったら――魔法を高度に使う人、魔法を作る人を除くと、残るは”人”に対しての能力を開発していくことが求められていくのではないか。Googleが提唱した心理的安全性や流行したマインドフルネス、コーチング、カウンセリングといったサービスが流行しているのもその要素はあるだろう。
ITエンジニアにとっても、最近ではエンジニアマネージャやVPoEなどの役職をおいて、ピープルマネジメントができる人材を求める企業は多くなってきている。ただ、マネジメント自体は誰もがなれる訳でもないし好みもある。軽はずみに「みんな、マネージャーになろうぜ!」なんてことは決して言えないし言う気もないが、コミュニケーションやチームビルディング、育成のような”人”に向き合うといった経験は一層大事にはなってくるだろう。
◯まとめ
上記のような流れは新しい技術が生まれる度に起こることだ。これは良いことだと思う。エンジニアも人であるし、ものを作らない側も技術に対する理解、そして作っている人に対する理解が深められ、相互理解が深められれば組織内でも円滑に物事が進むようになるはず。※できるのなら一流の魔法使いになりたかったが、、、笑
そんなことを夢見て、本日も私はたくさんの魔法使いの方々と向き合うためにお仕事に邁進していきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?


