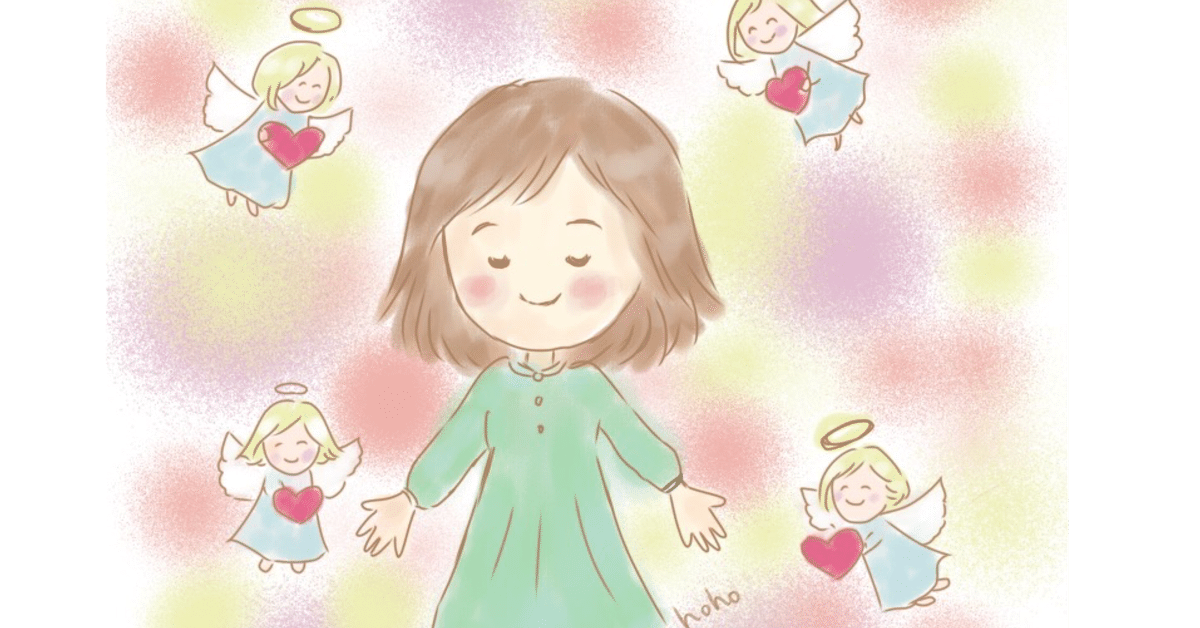
『愛子の日常』 物語をまとめて見たい方はこちら↓↓↓
第一話 〜愛子の誕生〜
序章 Ⅰ.
ハピバースデートゥーユー
ハピバースデートゥーユー
ハピバースデー ディア セントー
ハピバースデートゥーユー
彼の名はルーカス・セント・トーマス
緑豊かなロンドンの郊外に堂々とたたずむトーマス邸の主となったジョージが、スコットランドから嫁に来た一つ年下の妻オリヴィアとの間に授かった元気な男の子だ。
トーマスという苗字は、新約聖書からきている。つまりは、イエス・キリストの十二使徒の一人であるトマスに由来する苗字だとされている。
名前から分かるとおり、トーマス一家は由緒正しいクリスチャンの家系だ。
トーマス一家の長男として産まれたルーカスは、父と母から溺愛されていた。
ルーカスは、産まれて3ヶ月と半分の時に洗礼を受けたが、セントというミドルネームはその時にもらったものだった。
その際行われた洗礼式というのも、とても厳粛なもので、
(イギリスでの洗礼式といえば、通常赤ちゃんのおでこに水をかける類の事なのだが)この教会では、牧師が子供の鼻をふさぎ、水が溜まった桶の中に子供を潜らせるというものだった。
その儀式の後、洗礼を受けた子供に牧師が名前を授けるのだが、ルーカスの時は一般的な名前のつけ方とは違った。
洗礼名は、ペテロやマリヤといった聖人や天使の名をとるのが一般的であるが、「トーマス一家には、トーマスという立派な聖人の名が入っている」と牧師がふと思ったことがきっかけである。
ルーカスに与えられたセントという洗礼名は、
(カトリックの歴史上、稀に見る異端とも思える名前だが)牧師のかってなひらめきから来たものだった。
しかし、ルーカスの母はこのセントという名をやけに気に入っていた。
なんでも、ルーカスが洗礼を受ける日の朝、夢で不思議な啓示を受けたという。
この子は神の働き手に違いないと、その日から牧師がつけたミドルネームでルーカスのことを呼ぶのであった。
さらに、母の興奮はそれだけではおさまらず、「この子は神が遣うことは間違いない」と言って、その日から年号まで数えはじめた。
(つまり、ルーカスが洗礼を受けた年をルーカスの洗礼名からとって、セント1年と呼び、その次の年をセント2年、、、と数えていった。)
その日とは、AD2018年10月1日。ルーカス・トーマスが洗礼を受け、牧師のかってなひらめきから、セントというミドルネームを与えられた日だ。
これがルーカス・セント・トーマスの誕生秘話である。
セント6年(AD2023年)10月1日、この日も母はセントの誕生日・・・いや、洗礼された日を誕生日として祝って、ハピバースデーを歌ったのだった。
ハピバースデートゥーユー
ハピバースデートゥーユー
ハピバースデーディア セント
ハピバースデートゥーユー
序章 Ⅱ.
誕生日会の翌日、セントは公園で一人で遊んでいた。
広い芝生が広がる公園には、いくつかの丘がつらなっていた。
セントは、その丘の一つに這い上がり、持っていたボールを大空にむかってポーンと蹴り上げた。
そのボールは、大きな空の中に雲と一緒にフワッと浮かんだかと思うと、急にセントめがけて空から落ちてきた。
ビックリしたセントは、一瞬目が閉じ、その場で棒立ちになったが、すぐに目を開けた。
先ほどまで目の前にあったボールはどこかへ消えてしまったようだった。
目をキョロキョロさせると丘の下へと転がるボールが見えた。
さて、その公園には、セントよりも2才年上の女の子がいたのだが、
その女の子は芝生のすき間に、ニョキッとはえるカウバセリという花を見つけては摘んでいた。
(花といってもこの地域では、手入れをしていない庭などにどんどん生えてくるので、人々は雑草のように思っている花だ。)
女の子が花を摘んでしゃがんでいると、丘の上からボールが転がってきたのだった。
セントはというと、ボールを探して丘の下へとかけていった。
セントが丘の下へとかけていくと、女の子が両手にボールを抱えて立っていた。
左手には白い花を握りしめたままだった。
セントがその女の子の目を見ると、その瞳は黒く光がなかった。
髪の毛も黒く、肌は黄色かった。どう見てもアジア系の女の子なのだが、幼いセントはどうして真っ黒な目をしているのだろうと不思議に思うだけだった。
はじめに口を開いたのは、女の子の方だった。
「星の王子さま」
「星の王子さま」
「あなたは星の王子さまね」「きっと私と結婚するのだわ」
セントはポカンとしながら、その女の子の方へ近づいていった。
セントは再びその女の子の目を見たが、どんなに近づこうとも、その真っ黒な瞳にセントの顔が映ることはなかった。
ポカンとしているセントを横目に、女の子は持っていた花を一つ一つ編みはじめた。
細長く編んだかた思うと、両端をくっつけてリングを作った。
それをセントの頭の上にのせると、その黒い瞳からは想像もできないほどの感情豊かな表現で話しはじめた。
「やっぱりあなたは星の王子さまなのね」
「真っ白なお花の王冠」
「真っ青な瞳に、金色の髪の毛」「どれを見ても星の王子さまそっくりだわ」
「あなたは"わたし"と結婚するの。このお花の王冠が約束の証よ」
そう言うと女の子はセントにボールを手渡した。
「ハイこれ。あなたのでしょ。じゃあ、私お父様が待っているから帰るね。」
「またね。バイバイ」
セントの幼い頃の記憶はこれで終わりだ。
その女の子とはそれ以来会っていない。というのも、その女の子はロンドンの日本人学校に通う純粋な日本人で、父の転勤の関係でロンドンに移り住んだ外国人だったのだ。
セントは一般の公立校に通い、女の子が住むロンドンの中心部とは離れた地域に住んでいたものだから、その子とはもちろん会うことすらなかった。
30才になって結婚した相手が、まさかあの時の女の子だったとは、セント自身も考えもしなかったことだろう。
セントの記憶 Ⅰ.
何はともあれ、セントとその女の子は再び出会う事になるのだが、その時の記憶はあまり覚えていないのがセントである。というのも、あまりにも自然な出会いすぎてセントにとっては日常生活の一部としか思っておらず、一つの思い出として頭の片隅に記憶する事すらなかったからだ。
今となっては、どうしてこの女の子と付き合っているのか分からないほど、告白した記憶もなければ、付き合った経緯も覚えていない。
セントにとっては、その女の子と付き合っているという事実は二の次の話で、日常生活の方が優先され、その子を自らの意識の中に入れようとすらしなかった。
しかし、その女の子に対するセントの振る舞いとは真逆に、その女の子はセントの頭の中をかき乱し、セントの人生観や世界観を翻させ、セントに大きな影響を与えていくのだった。
「大西さやか」その名前が、セントの頭に鮮明に刻まれた出来事があった。
ロンドンからバスに乗ってグリニッジ天文台へと旅をした帰りの出来事である。
世間から見れば、それは女の子とデートをしたということになるのだが、セントにとってはそれは旅だった。
そう、セントはこれまで女の子とデートをした事などない。
今回も、これがデートというものだとは気付くこともなかった。
しかしその旅は、人間付き合いで冷え切ってしまったセントの心に、あなたの心は冷え切っているのだとはじめて気づかせるのには、十分な時間を与えていた。
その帰り道は、まるでセントの冷え切った心が自然万物にまで乗り移ってしまっているかのように、冷たい雨がしんしんと降っていた。
雨は二人の傘を打ち、やむ気配はなかった。
グリニッジ天文台からは、二つの傘の後ろ姿だけが見えていたのだが、二つの傘はぶつかり合うこともなく、なにか不自然な距離感を保ちながらバス停の方へと消えていった。
それから少し遅れて、バス停の方へとバスがやって来た。
二人にとっては冷え切った身体が待ちに待っていたバスだったはずなのだが、セントはホッとするどころか、どのようにしてバスに乗り込もうかと思い悩んでいた。
よりにもよって、そのバスには誰も人が乗っていなかった。
一緒にいた相手が女性だからというわけではないが、相手が先にバスの座席に腰を掛けてしまったら、自分は何処に座っていいのか分からなくなるに決まっていることをセントは知っていた。
もし二人掛けの席の窓際に彼女が座ったら、自分は何処に座ったらいいのか??
こんなに座席が空いているのに、わざわざ彼女の横の席に座る必要があるのか???彼女は迷惑がらないか????
そうは言っても遠くの席に座る必要があるのか?と何度も何度も思い悩んだ。
結局セントは、バスの扉が開いた瞬間、我先にと二人掛けの席の窓際を陣取って座った。
こういう状況に陥った時に、セントがよくやる秘策でもあった。
その後に彼女は続いた。
なんの躊躇いもなく、セントに導かれるように、セントの隣の席にポツンと座った。
セントは、雨で濡れたのか、冷や汗で濡れたのか分からない洋服の湿り具合に、気持ち悪さを感じ、背もたれに寄りかかることもできずにいた。
さて、二人が座席に座り終わると、バスは扉を閉め動き出した。
座席の下に取り付けられているヒーターからは温かい空気が流れ、二人の濡れた服を乾かし、冷え切った身体までも温めていた。
バスは無言のまま、何駅かバス停を通り過ぎ、彼女が降りるバス停へと何の問題もなく向かっていた。
問題ばかり抱えるセントに、これ以上考える隙を与えないほどバスはスムーズだった。
セントはというと、ここでも問題を抱えていた。無言の気まずさと、彼女がバスを降りる時どのように振る舞っていいのか気をもむ心がそうさせたのだ。
しまいにバスのスピードはゆっくりになり、すぐにバスは止まった。
ついにその時がやって来たのだ。彼女は立ち上がった。
セントは唾を呑み、恐る恐る彼女を視界に入れた。
彼女は明るくセントに手を振り、今にも踊り出しそうな軽いステップでバスから降りていった。
あまりにも気さくな振る舞いに、いつもなら会釈でもしてこの場を乗り越えようかと考えてしまうセントも、拍子を抜かれ不器用そうに手を振りかえしていた。
彼女はバスから降りると、セントに向かって再び手を振った。
セントは軽く会釈をし、いつバスが走り出すのかと気を揉んだ。幸いにも、この気まずい空間から助け出してくれと言うセントの祈りは通じ、バスはすぐに動き出した。
「ふ〜〜」という吐息が人のいないバスの中を流れ、時が止まったかのようにセントの視界には動く物は何も入らなかった。
少し大袈裟だが、この後は何かの祝福が訪れるとすら思えた。
しかし次の瞬間、セントにとってみれば最悪の事態が起きてしまった。
赤信号でバスが止まったのだ。
さっきお別れしたばかりの彼女とまた出くわしてしまうのではないかという不安が一瞬セントの脳裏をよぎった。
嫌な予感は的中した。
彼女は赤信号で止まっているバスに追いつき、セントと視線が合うとこまでやって来てしまったのだ。
何度同じような場面を迎えたことだろう。彼女には手も振ったし、会釈もした。つまり、セントができる振る舞いは全てやり尽くしてしまっていたのだ。
その手前、再び会釈をするわけにもいかず、困り果てた末にセントの思考は完全に止まってしまった。
いつもなら思考を回し続けて何気ない振る舞いでその場をやり過ごすセントだが、この時ばかりはどう振る舞っていいのか分からず時が止まった。
セントは覚悟を決めるしかなかった。
先程までうっすらと横の方に感じていた彼女の視線は、セントの斜め前にまでやってきた。
セントはなす術がないまま、彼女の方を見ざるを得なかった。
しかし、この状況下で、彼女は再びセントに手を振ったのだった。
セントにとっては、信じられない出来事であり、受け入れ難い出来事でもあった。
高度に洗練され考え抜かれた自らの振る舞いの上をいくものを見たのだから、それも無理はない。
次第にバスは彼女の歩くペースに合わせて動き出し、徐々に加速し本来のスピードを取り戻していった。
彼女はその間、一歩歩くごとにセントに向かって手を振り、何度も何度も手を振り続けた。
バスの窓越しに見る彼女は、あまりにも自然で、まるでミュージカル女優のように壮大で美しく見えた。
彼女を見送った後、セントはしばらくの間、彼女の振る舞いに思いを馳せた。
そこには、セントの理論など通じる余地もない、コミュニケーションの枠を超えた、セントが理解することができない感情が見え隠れしていた。
時を忘れ、自らを失ってしまう程、セントの意識は自らの思考から離れた所をさまよっていた。
「ブーッブーッ」聞き慣れたその音に、セントは我に返った。
いつものごとく、音が鳴ったスマートフォンをポケットから取り出すと、明るくなったホーム画面を見た。
「今日はありがとう!」
ホーム画面に出てきたそのメッセージを開いてみると、差出人には sayaka oonishi と書いてあった。
セントの記憶 Ⅱ.
実は、さやかとセントは同じ会社の同じ部署で働いていたのだが、セントがそれに気づくまでには長い長い時間がかかった。
時を知らせるハト時計までもが黙りきるほどの長い長い時間だった。
きっとこの話を聞いた人々は、セントは馬鹿なのだと思うことだろう。
まさか自分の席の右隣りに座っていた女性が大西さやかだとは、セント自身も気づいた時にはものすごい驚きようだったのだから。
これは、グリニッジ天文台に行った週末が過ぎ、新しい週をむかえた月曜日の話だ。
「ぴーぴー、キリキリ、ピョピョョ〜」小鳥たちが音痴に合唱をはじめた。太陽はもうとっくに出ているのだが、カーテンを閉め切って寝静まった人々は、まだ起きてこない。いつもと変わらないロンドンの中心街の静かな朝だった。
さやかはいつものように6時に目が覚めた。
とくに目覚ましをつけているわけではないが、いつもこの時間になると起きてくる。
カーテンを開け日光を浴びるために窓際に姿を現したが、顔を洗うために再び部屋の奥へと姿を消した。
さやかは、父と母と3人でこのロンドンの中心街で暮らしていた。
「カタカタカタカタ」「ゴトゴトゴト」静かな街に忙しそうな人々の生活音が聞こえてきた。
これから大西家の1日がはじまるのである。
朝ごはんはいつも母親が作ってくれる。イギリスでは朝食をしっかり食べる人は少ないが、日本人の両親だけあってそこは徹底している。
さやかはその横で自分のお弁当を作りはじめた。これが大西家のいつもの光景だ。
さやかはお弁当を作り終わると、母親がこしらえた朝食を食べるために席についた。
「いただきます」日本語で挨拶すると、器用に箸を使い、はしから摘んで口に入れた。
今日の朝ごはんはというと、白米に鮭の塩焼き、ポテトサラダに、ワカメの味噌汁だった。
さやかは全てたいらげると時計を見た。まだ会社に行くには早そうな時間だった。
そう思うとすぐ歯を磨き、リビングの片隅に置いてあったトランペットを取り出した。
「ブーッブーッ」吹く姿だけはいっちょまえだった。しかし、さやかは曲を演奏できない。
「ブーッブーッ、ドレミファソラシド〜、ブーッ、ドシラソファミレド〜」
これがさやかの日課だった。
さて、家から歩いて30分ほどのところにさやかの職場はあった。
いつものごとく、さやかは仕事がはじまる40分も前にもかかわらず会社に着くと、平気で自分の席についた。
仕事の準備でもするのかと思いきや、そうでもなく誰か人が来るのを待っている様子だった。
彼女は人が来るやいなや「おはよー」と声をかけ、その人の方へ近寄ると何やら話しはじめた。
また違う人がやってくると、今まで話していた人との会話は切り上げ、「おはよー」と声をかけては近寄って会話をはじめた。
そんなこんなで、40分も前に会社に来ていながら、何もやらずに仕事の時間になってしまうのだった。
そして、いつも10分前にセントがやってくるのだが、この日もそのルーティーンは変わらなかった。
「おはよー」セントの時も変わらず、さやかはそう言って近寄っていった。
ぼーっとしていたセントだが、彼女が昨日グリニッジ天文台に一緒に行った大西さやかだと分かると、目をまん丸にし「あっ、、、昨日の、、、」と言葉が出てこない様子だった。
さやかは、セントが驚いていることを知ってか知らずかただただニコニコしていた。
この日はセントとさやかはお昼が一緒だった。
というのも、いつもは当番制でお昼を取るのだが、この日はさやかが希望を出しセントと同じ時間にお昼休憩を入れていたのだ。
セントは会社の休憩室ではごはんは食べない。知っている人にごはんを食べる姿を見られるのが好きじゃなかった。
セントとさやかはセントのルーティーンに合わせて、道端のベンチでランチを食べた。
セントはいつものように近くのカフェでテイクアウトしたバゲットサンドとコーヒーがランチだった。バゲットサンドの中身は気分によって変わるものの、いつもランチはバゲットサンドを食べていた。
その隣でさやかは持ってきたお弁当を食べた。
とくに会話はなかった。
食べ終わると道ゆく人々を眺めながらセントはぼーっとしていた。
彼にはこういう時間が必要なのだ。
いつも何かのことを気にしてしまうセントも、この場所では何も考えずにいられた。
セントは、多くの人が行き交う街の中心街の片隅に、誰にも認識されずにポツンとたたずむその感覚が好きだった。
そうしてしばらくして、セントとさやかは一緒に職場に戻っていった。
さやかは職場の扉を開けると「ただいまー」と言って部屋に入っていった。周りは「おかえりー」と言って彼女を迎えた。
後に続いてセントも一緒に部屋に入ってきたのだが、気まずそうに肩をすぼめ何やら言葉を選んでいる様子だった。
セントの事だから、さやかのように「ただいま」と言うのは馴れ馴れしすぎるとでも思ったのだろう。
そうしてセントは「戻りました」とボソッと一言言うと自分の席へとぱっぱと行ってしまった。
この時からだろうか、セントがさやかの言動をいちいち気にかけはじめたのは。
セント達が席に着くと、とある女性が差し入れにケーキを持って来てくれたのだが、さやかは相手がその意思を伝えるより先に手を出した。
両手を前に出し、手のひらを広げて「ちょうだい」のポーズをしたのだ。
セントはそれを見て、なんてマナーのない奴なんだ!図々しいにもほどがある!と思った。
それからというもの、セントはさやかのちょっとした仕草でイライラしはじめたのだった。
運命.
グリニッジ天文台に行った次の週の金曜日。
この日もセントはイライラしていた。
なんでも、さやかがアメを配ったことが原因だったらしい。
さやかは袋いっぱいにアメを持ってきていた。そのアメを職場のみんなに配って歩いていた。
セントはそれを見て、アメなんかいらないと思った。どうせ配るなら、チョコレートやお菓子を配ればいいのに。アメなんかもらって喜ぶのは子供だけだと、さげすんだ。
さやかは皆んなにアメを配りながら一言二言交わして席に戻ってきた。
セントはそれを横目で見ていた。
セントも赤の他人がやっている事なんだから、気にしなければそれで済むのに、さやかがやっている事を自分の事のように恥ずかしいと思ってしまっていた。
さて、この日もセントとさやかは一緒にお昼を食べたのだが、何故かさやかと二人きりの時は、あんなに神経質になっていたセントも、さやかの言動にイライラする事は無かった。
ましてや、さやかとこうして二人でランチができることが幸せにすら思えた。
こんな時間が永遠に続けばいいのにと、セントは思いを巡らせていた。
「ねぇ、運命って知ってる?」
ふと、さやかが投げ掛けた。
最近はやさかのことを馬鹿にする傾向にあったセントだが、この問い掛けには冷静だった。
「知ってるよ」とセントが答えると「じゃあ、運命って何だ?!」と続けてやさかは投げ掛けた。
「予め定められている物事の結末」
セントは自分が言った答えが的を得ていることを確信していた。
しかし、「何それー」とさやかは笑い出した。「そんな難しいこと言われても、さやかには分からないー」
セントは内心、失礼な奴めと思いながらも、さやかの言う運命とは何を指して言っているのか気になった。
「じゃあ、さやかが教えてあげる!」と言うと、さやかは得意げに語りはじめた。
「例えば、神様が運命を決めて二本の木を選び、この木が大人になったら結婚させようと、同じ場所にその木を植えたとします。」
「しかし、神様が決めた事でも全て上手くいくとは限りません。その二本の木は、雨・風・吹雪に吹かれて、お互い違う方向を向いて成長してしまいました。」
「さて、問題です。」
「この二本の木は、もう大人になって結婚しないといけないのですが、神様はどうしたでしょうか?!」
「そんなの簡単だよー!」セントは答えた。「どんなに違う方向を向いていようとも、その二本の木を結婚させる。それが運命ってやつだろ?!」
「ブッブー!!違います!」さやかはセントが間違えて答えてくれたことに嬉しそうな微笑みを浮かべ(けど馬鹿にする事はなく)、得意げになって再び語りはじめた。
「この話は、さやかのお婆ちゃんから聞いた話なんだけど・・・」
「この話は、人を木に喩えているの」
「世の雨・風・吹雪に吹かれながらも頑張って生きてきた二人。その生き様はあまりにも美しく、誰が見ても成熟した品性を持っていました。」
「しかし、その生き様がゆえに、性格や品性(いわゆる個性)は、二人とも真逆に成長してしまいました。」
「こういう人たちを無理やり結婚させたとしても、(時間の問題で)直に離婚してしまうと思いませんか?セントさん如何ですかー?!」さやかは、大学の教授か何かになったかのようにセントに論じて見せた。
「それは一理ある」セントはここでも冷静だった。
「ではどうするか。」「神様はその成長した性格・品性通りに、個性の合う人を世界中から探してきて、その人と結婚できるような運命に変えてしまうの」
「つまり、運命は神様が決めるけれども、その人の生き方次第で、再び神様が介入して運命を変えてしまう事もあるってこと」
「つまり、、、あなたと私が結婚するのは運命だってこと!」
いやいや、それとこれとは話が違うだろ!と思いながらも「運命ね〜」とセントはつぶやいた。
「どう?運命の話。面白かったでしょ!」さやかは、またしても得意げに投げ掛けた。
セントは初めてさやかの内面を見た気がした。気さくにひょうひょうと自由に生きている彼女の姿からは想像もできなかったが、さやかは自らの意思を持って、人生について深く考えていた事をセントは知った。
セント自身も人生について考えに考え抜かれた人生観を持っていたが、そんなセントから見てもさやかの話は否定できなかった。
それどころか、世の雨・風・吹雪に吹かれてきた人生を木に喩えたことは、もののことなりを理解する上で絶妙な表現だったとセントは感嘆していた。
セントにとっては、「この人なら自分の人生観を深く理解してくれるかもしれない」と思える瞬間でもあった。
「ねぇ、今度家でお茶しない?」セントは思い切って誘ってみた。
セントから言い出すなんてあまりにも珍しい出来事だったことと、思ってもみなかったお誘いで考えてもいなかったことだったがゆえに、さやかはすぐに口を開けなかった。
「いいよ!」さやかはなんとか口を開いたが、セントの誘いにさやかが答えるまでには今目の前で起こっている事を理解する時間が必要で、さやかにとっては地球が一周回るほどの時間が過ぎたかとすら思えた。
しかし、さやかはすごく嬉しかった。
「じゃあ、来週の火曜はどう?」
「いいよ」
「じゃあ、来週の火曜ね!」
「約束!」
「約束」
陶器のコップ.
時間というものはすぐに過ぎ去ってしまうもので、来週の火曜日はすぐにやってきた。
2人は15時に仕事を終えるとセントの家へと向かった。セントの家はロンドンの中心街からは離れていてバスに乗って行かなければならない。
2人がセントの家に着いた頃には16時をまわっていた。ただ、アフタヌーンティーには丁度いい時間にも思えた。
セントはさやかを自分の部屋に案内した。
さやかが部屋に入ると、部屋の真ん中にはソファーが2つミニテーブルを挟んで置かれていた。ミニテーブルは膝よりも低く、高さは20cmほどだろうか?さやかはソファーに腰を掛けたが、そのミニテーブルに置かれた物を取るには、よりかかった背中を浮かせ前かがみにならないと取れそうもなかった。
セントはさやかを部屋に案内すると、自分はせっせとお茶の準備をしに部屋を出ていった。
さやかはその間、キョロキョロと部屋の中を見回した。
その部屋の床には木材が木目揃って敷かれ、壁には白を基調とした壁紙が綺麗に貼られていた。
その様子からすると、自分でリフォームしたのではなく、家が造られた当時のままその姿を保っているようだった。
頻繁にリフォームするイギリス人とは違う、何かイギリス離れした一貫性のようなこだわりがセントの部屋からは感じられた。
部屋の片隅にはベッドが置かれていたが布団は整って敷かれ、生活感は感じられなかった。
(、、、カーテンは青かー、オリーブの木があるなー、髪の毛が一本落ちている、、、)さやかは何一つ見落とすまいとキョロキョロキョロキョロしていて、いっこうに落ち着く気配はなかった。
しばらくして、セントがお茶のセットを運んできた。
白い陶器のコップに白い陶器のティーポット。花柄の皿の上にはビスケットとマカロンが置かれていた。
それをミニテーブルの上に置くと、「お湯を持ってくるね」と言ってセントはいそぎ足で再び部屋を出ていった。
さやかは、運ばれてきたマカロンを一つ手に取るとそれを口の中に入れた。そして、口をもぐもぐさせながら周りを再び見回した。
(、、、髪の毛もう一本見っけ!、、、)セントの部屋にはさやかの目から逃れられるものは何一つ無かった。
すぐにセントは戻ってきた。片手にはとっての付いたクリーム色の魔法瓶を持ち、もう一方の手には紅茶のティーバッグを何種類か持っていた。
そしてその魔法瓶と紅茶のティーバッグを床に置くと、セントはソファーに腰掛けた。
(、、、それを床にそのまま置くんだ〜、、、)さやかは、この男に常識など通じないのは分かっていたものの、果たして頭の中はどうなっているのかと疑った。
セントはソファーに腰を掛けるやいなや、ティーポットに紅茶のティーバッグを入れ、そこにお湯を注いでお茶の準備をし始めた。
「この陶器のコップを見て!」
「このように温かいものを注ぐと温かくなるでしょー」そう言いながらセントは、白いコップにティーポットから紅茶を注いだ。
「この前さやかは運命は神様が決めるって言ってたけど、もしこのコップがプラスチックのコップのように割れないコップだとしたら、神様なんていなくてもいいんだよー。」とセントが言った。
「それは違う。神様はいた方がいいよー」さやかは反論した。
「もしもだよ。この世界が全ての物が壊れない世界で、人間も死なないのだとしたら、神様なんていらないだろ?!」セントはさやかを説き伏せるように話した。
「いるよ!いる!神様はいるよ!」さやかはまたしても反論した。
「お前は馬鹿か!」セントは呆れたように言い放った。
「もしも、人間がこの世界の全てのことをコントロールできるのだとしたら、神様なんていらないんだよー。」
「陶器のコップもそうだけど、、、この世界の全ての物が壊れないで、人間がコントロールできるのだとしたら、神様が助けてくれる必要はないんだよー。」
「だから、そういう世界にしていいのか?って話をしているの!」
さやかは何も言わなかった。
セントにはさやかが話を理解しているかどうかは分からなかったが、セントは一人で語り続けた。
「昔ね。『原爆とプラスチックは人類がつくり出した罪だ』っていう本を読んだことがあるんだけど。。俺はたしかにそうだと思う。」
「プラスチックは人間を駄目にする。」
「人間が全てのことをコントロールすることはできないのに、まるでコントロールできるかのような錯覚が生まれるんだ。プラスチックからはね。」
そう言うとセントは、ビスケットを紅茶につけて少し浸した後、紅茶の水分を吸い取って重たくなったビスケットを大きく開けた口の中に放り込んだ。
そこには、多くの人がイギリスの紅茶文化でイメージするような気品や優雅さは全く感じられなかった。
今まで自らの考えをもっともらしく語っていた男が、紅茶の飲み方には特にこだわりが無さそうに、しかも幼稚とも思える姿で飲んでいることがさやかには可笑しかった。
さやかはこれが愛嬌というものかと彼の振る舞いを理解した。
さやかもそのビスケットを紅茶につけて食べてみたが、ミルク味で甘くて美味しかった。
外では、小鳥とカラスが鳴いていた。
セントとさやかは紅茶を飲みながらその時間を楽しんでいた。
もう40分ほどの時間が経っただろうか。セントが再び口を開いた。
「陶器のコップからは愛が生まれるんだ。優しく丁寧に扱わないとって思うだろ?!それを愛って言うんだ。」
「しかしその愛は、『コップが割れるかも?』という恐れからくるものでもある。」
セントはわざと余韻を残すかのように話していた。
「壊れやすい日常の中からは、愛が生まれてくるはずなんだよ。」
「だからそれがこの世の中の根本だと俺は思ってる」
そう言うとセントはさやかの顔を覗いてきた。
「、、、もちろん、その愛が生まれるのは、さやかの言う神様の影響かもしれないけどね。」
セントが『愛』という言葉を使ったことがさやかには意外だった。
世界一愛が分からない男のようにさやかには見えていたからだ。
勿論、そのようなさやかの思いは、あながち間違ってはいない。
セントは『愛』という言葉は知っていたが、それがどれ程の痛みを伴う物なのかは、さやかを通して知るようになったのだから。
アフタヌーンティーを終えるとセントとさやかは部屋を出た。
階段を降りると、セントの母親が笑顔で挨拶をしに現れた。
「あら〜、珍しいわねぇ〜、友達が来ているなんて!」と母親は随分と機嫌が良さそうに二人に声をかけた。
「彼女が僕の結婚相手さ!」セントが自慢げにさやかを紹介した。
その瞬間、母親の態度が激変した。
「彼女はクリスチャンなのかい?」「クリスチャンでない人と結婚することは許しません。」
母親のその言葉にセントも態度を変えた。「クリスチャン。クリスチャンって。クリスチャンでない人を差別してるだけだろ!」
しかし母親は「彼女と結婚することは許しません」とゆずらなかった。
セントの青春 Ⅰ.
次の日。
セントは朝起きて母親に挨拶するも、母親は「彼女と結婚する事は許しません」の一点張りだった。
「それは日本人だからかい?」「お母さんは差別しているだけじゃないのかい?」とセントは反発するも母親は聞かなかった。
そんな会話を一時間もした後、セントは会社に間に合わないと思い話を切り上げ職場に向かった。
職場に着くとさやかの姿は無かった。いつもならもうとっくに着いている時間なのだが、彼女の気配すらまったく無かった。
普段いかに彼女が作り出すコミュカルとも思える『さやかワールド』が周りを巻き込んで影響を与えていたかが分かるほどに、彼女がいない空間は静まり返り肝心な物を抜かれてしまった無力感のようなものが漂っていた。
仕事がはじまってもさやかが現れる事はなかった。
セントは「まさか?!」と思った。何か不吉な予感がしたのだ。
上司に聞くと、さやかは熱を出し病院に行っているとの事だった。
セントはその日は仕事も手につかず、何か落ち着かなかった。いつもは彼女のちょっとした言動にイライラしていたセントだったが、いざ彼女がいなくなると人々の会話がどこかぎこちなくなり、セントもその空間にいずらくなってしまった。まるで、会社の中のコミュニケーションの均衡はさやかが保っていたかのようだった。
そしてその日の午後、事態は急変した。
さやかが新型コロナウイルスに罹ったとの連絡があったのだ。セント達も濃厚接触者になり、PCR検査を受けなければならなくなった。
2020年にパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスだが、この頃には殆どが終息し、治療薬もワクチンも当たり前のように出回っていた。
しかし、さやかが感染したのは更に新型のコロナウイルスで、ワクチンも治療薬も無いとの事だった。
もともとセントは、新型コロナウイルスというものを信じていない。母親から「あなたが2歳か3歳のころ、世界中でコロナウイルスが流行したのよ」という話は何度も何度も聞かされていた。
しかし、全世界でマスクをした人間が溢れかえるという事はあまりにも信じがたかったし、ロンドンやニューヨークなど世界の主要都市で人の姿が消えるという事も想像が出来なかった。
だから、母親がコロナの話をする度に「それは迷信だ!」と言って一切受け付けなかった。
今回、さやかがコロナに罹ったとの話を聞いた時も、半ば半信半疑でブラックジョークかとすら思ったほどだった。
セントは職場の近くの病院でPCR検査を受けたが陰性だった。他の会社の仲間も皆陰性で、特に問題は無いとの事だった。
やはり、コロナはブラックジョークで、さやかは嘘をついているのではないかとセントは考え込んだ。「昨日の母親の言葉を気にしてるのかな〜?ショックだったのかな〜?」と色々なことを考えた。
上司にも「さやかがコロナというのはジョークですよね?!」と何度も何度も聞き込んだ。
上司もセントが何度も訪ねてくるものだから嫌気がさし、「何で俺の言っている事が信用できないのか?!心配だったら病院に行ってきたらいい。」と病院の名前を教えてくれた。
セントはさやかにスマホからメッセージを送ってみる事にした。
「大丈夫??」とだけ書いて送った。
しかし、それは何時間たっても既読にはならなかった。セントは心配して電話をかけたが、一向に繋がらなかった。
もう日が傾いて来ていた。
(今日はもう諦めようか・・・)セントはさやかが心配だった。しかしどうする事も出来なかった。
さやかに何かあったに違いない事はセントにも分かっていた。ただそれが、コロナなのか何なのかという事はセントには分からなかったのだった。
翌日。
セントは会社を休んでさやかのお見舞いに行く事にした。
もし本当に病気だとしたら、何かさっぱりした物が食べたいだろうからと、途中でプリンとリンゴジュースを買っていった。セントにはさやかの喜ぶ顔が目に浮かんだ。病院までは少し距離があったが、もう直ぐさやかに会えるという喜びから自然と足が弾んだ。
セントは病院に着くと、真っ先に受付に行き、さやかの病室を確認してもらった。セントはやっとさやかに会えるという期待感でいっぱいになっていた。
「大西さやかさんですね。」
「現在、隔離病棟にいるため面会は出来ません。」
セントにはその言葉の意味が理解できなかった。
「あの〜、さやかに会えればいいんですけど。。面会なんてしなくても。これ、渡したいので。」と、セントは鞄からプリンとリンゴジュースを出して説明した。
「ですから、隔離病棟にいるため会うことは出来ません。そちらもお預かり出来ませんので、持ち帰って下さい。」
「隔離病棟って、どういう事ですかっ?!会うことぐらい出来るでしょっ!」セントは反発した。
しかし、「出来ません。」の一言だった。
「どうしてですかっ!!それって、人権の問題ですよねーーーっ!!」セントは凄い勢いで迫った。言葉遣いこそ紳士的ではあったものの、相手を脅迫するかのような勢いだった。
受付の人も一人では対応し切れずに、最後には三人がかりでセントの対応にあたった。
セントには、諦めて帰る事しか選択肢が無くなっていた。
(・・・どうして、さやかに会えないのか?!)セントの心はいきなり重たくなった。心が強く締め付けられ、心の重りが身体へとのしかかり、帰るにしても病院から一歩踏み出す事がやっとだった。
なんとか道端のベンチに辿り着き、そこにドスンと座ると、セントは天を仰いだ。
天を仰いだ頬を涙がつたった。(どうして会えないのか・・・)
セントはさやかを世の中から奪われた気分だった。
セントの心は、まるで泥水に浸かったスポンジのように、溢れ出る悲しみを吸い取って重たくなっていた。
もはやどうする事も出来なかった。
電話も繋がらない。。会うことも出来ない。。さやかがいなくなった世の中でセントは一人取り残されていた。
セントはベンチでずっと泣いていたが、悲しみを吸い取って重たくなった心というスポンジは、身体にのしかかり、身体を動かすこともできないでいた。
腕は肩から下が脱力し、顔は天を見上げ、上半身はベンチに全ての体重を預けてもたれかかっていた。
身体をも動かなくしてしまう重たい心が、セントを潰しかけていた。
(・・・もう、生きられない)セントは一瞬自殺を考えた。
そうして決心した。
悲しみを吸い取って重たくなった心というスポンジを、自らの手で裂いたのだった。
セントの青春 Ⅱ.
あれからどれ程の日数が経っただろうか。
さやかのいない世界にセントは一人取り残され孤独な日々を過ごしていた。
セントがどんなにもがこうとも、どんなに叫ぼうとも、さやかと通じることすら出来なかった。
夜空に向かって手を伸ばしてもさやかに触れることは出来ず、月に向かって囁いてもさやかの声が聞こえる事はなかった。
この広大な宇宙に一人取り残され、そこから脱出することすら出来ない無力さに、セントは歯がゆさを感じていた。
どうする事も出来なくなり、セントは夜空に向かって叫んだ。
俺はこのままこの世界に一人取り残され、孤独な中で生きるのか?
そう思った時、セントは人間の儚さ(はかなさ)を悟った。
その儚さに思いを馳せると、自然と涙が流れ心が洗われた。
セントはその儚さにしばらく浸っていた。
もし、さやかのような日本人が今のセントの状況を見たならば、(孤独で寂しげな状況の中で)心に流れるマイナスな感情に浸れる彼の心を美徳とし、わびさびを感じるとでも言うのだろうが、セントにはこのマイナスな感情に浸り続けられる心の余裕など無かった。
見ると夜は深まっていた。この日の夜は月の光をも消えていくほど闇が深く、セントの心もその闇に呑まれていったのだった。
セントの心はさやかに会えなくなって以来時が止まっていたが、空は今日も暗くなり、また明るくなった。
いつも変わらず流れる雲は、夜空であろうとも昼の空であろうともいつもこの世の中を見下ろして、人間の時とは無関係に動き続けていた。
壮大に動き続ける雲を、動かし続ける広大な空が、セントの心まで動かしてくれるのなら良いのだが、この世の理はそうはなっていない。
次の日も、セントの心はなえたままだった。
この日は土曜日だが、優雅な休日を過ごす気力や気持ちなどセントには無い。
たださやかに会いたいの一心だった。
セントはお昼近くに病院に行った。
さやかに会えないのは分かっていたが、さやかと同じ景色を見たかったし、何かキセキが起こるかもしれないと思ったからだ。
セントは病院の周りをぐるっと一周した。
病院から出てくる女の人を見かけては、セントはドキッとした。さやかかと思ってジロジロ見るのだが、いつも違う女の人で、ガッカリしてうつむくのだった。
セントは病院には入らず、病院の外にあるベンチに腰掛け、空を見上げた。
「さやかもこの空を見ているだろうか?」
空では、昨日夜空を覆って壮大に動いていた雲が、今は小さく分かれ、群れをなして動いていた。
セントはその雲に向かって、さやかに向けた手紙を読んだ。
雲がさやかに手紙の内容を届けてくれるであろうというロマンチックな儚い(はかない)夢にのせて読んだくさい手紙だが、それで自分の心が少しでも楽になるのならそれでよかった。
愛というものは、愛した相手の反応が分からなければ辛く、愛の表現ができなければ尚辛いのだから。
"私の愛しい人へ
グリニッジ天文台に行ったあの日から、
私はあなたの事を忘れられないのです。
私にとってあなたがいない日々は考え
られません。どうして私のそばから
あなたはいなくなってしまったので
すか?
神様は裏切りものです。せっかく
出会わせた二人を離れ離れにさせて
しまったのですから。
あなたと一緒にいられない日々は、
私の心を重りにし、鉛のように重たい
心が私を苦しめるのです。
もし、このままあなたと一緒にいられ
ないのなら、私は生まれてこなかった
方が良かったのです。
あなたと一緒にいたい。
永遠に。"
もちろん、その手紙がさやかに届くことは無かった。
しかし、セントは自分で読んだくさい手紙の余韻にしばらく浸っていた。
話は変わるが、実はこのところのセントは、さやかと離れ離れになった運命が辛すぎて、神様をも信じられなくなっていた。
神などいないのだと開き直ったかのように生きていくのだが、最終的には神様に祈ることしか出来ないという状況に陥っていた。
セントはこの日も、さやかのいない寂しさに耐えられなくなり、神様に祈った。
セントがさやかに会えたのは、それから10日後の事だった。
セントの過去.
「大丈夫だよ」
セントのスマホにメッセージが届いた。
見ると、さやかからだった。
なんでも、今日退院をして家でゆっくり休んでるとの事だった。
セントは久しぶりにさやかと待ち合わせをした。
場所は職場の近くの公園だ。
この日は平日だったが、セントはぱっぱと仕事を切り上げ公園に向かった。
セントが公園に着いてから20分後にさやかはやってきた。
頬はやつれ、身体は痩せ、なにか疲れきった表情だった。
セントはその姿を見て何も言葉が出てこないでいた。
「バカンスはどこに行くの?」セントがなんとか絞り出した言葉がこの言葉だった。
他に言うべき言葉があっただろうと本人も思ったが、とっさに言ってしまった以上、言った言葉を修正するわけにもいかず、さやかの反応を待つしかなかった。
「ねぇ、私がいなくて寂しかったでしょ」
セントの不安をよそに、さやかは今の言葉を聞いていなかったかのようにセントに問いかけた。
セントは何も答えなかったが、目は潤んでいた。
「青い瞳に、金色の髪の毛。あなたは星の王子様なんだから、寂しがらずに堂々と待っていればよかったのよ。」
さやかは唐突に話し始めたかと思うと、先程のセントの言葉に答えるように「バカンスは私は日本に帰るよ」とセントに伝えた。
「実はね、僕は昔(さやかには言わなかったけど)母親と大喧嘩したことがあるんだ。破門されるぐらいの大喧嘩をね。」
セントはやっとの思いで口を開き、さやかがいなくて寂しかったことをさやかに悟られまいと(もう悟られてはいるのだが、セントはそのあたりは鈍感だった)、懸命に話し始めた。
「あれは、小学校5年生ぐらいだったかな~」
「あの時は、無理やり教会に行かされて、教会に行ったら行ったで『祈れ!聖書を読め』って牧師が言うんだ。僕は嫌になって『なんでそんな事をしないといけないのか?神様がそれをしろって言ったのか?』って聞いたんだ。そしたら牧師は『そうだ』って答えた。だから僕は言ったんだ『僕は神様からそんな事言われてない。もう宗教なんて信じない。神様だけ信じて生きる』ってね。それから親と大喧嘩になって、それ以来僕は教会には行ってない。」
さやかはセントの話を親身に聞いていた。
「だから、さやかとの結婚もどんなに母親が反対したって、結婚はできるからね。僕は一度言い出したら誰の話も聞かない性格だってことを親も分かってるしね。」
セントがそう言うと、さやかは「大丈夫だよ」とセントをなだめるように言った。
「結婚はできる。それが運命なんだから。」
セントがなぜそういう話をしたのか、さやかはなんとなくだが理解していたのだった。
「でもさぁ・・・」
セントは今まで不安や孤独で苦しめられてきたことから吹っ切れたかのように、泣きそうな引きつった顔が晴れ、清々しそうな雰囲気で話し始めた。
「何で、学校では宗教の自由が認められているって言っているのに、家では宗教を押し付けられるのだろう?」「僕はキリスト教徒の家系に生まれただろ。だから、家庭教育が宗教そのものだったんだ。僕は小さい時から帰る場所もないと感じながら生きてきたの。」
この宗教という厄介者は、幼い頃のセントの心をずっと苦しめていた。神様はいるのにどうして宗教があるのだろうとも思ったし、死後の世界の事に干渉する宗教は、人間がコントロール出来ない未知の世界の事までも口を挟もうとする図々しさがあるとセントは感じていた。
「私は、宗教のことは分からない。でも神様はいると思うよ。神様は信じた方がいいよ!」
さやかがいきなりセントを説得するかのように話し始めた。
セントはこのさやかの言葉に、多くの大人たちが口うるさく話す言葉のような宗教の匂いを感じなかった。
「さやかにとっての神様って、どういう存在なの?」セントは思わず聞いてみた。
「う〜ん、、、」さやかは悩んで何も答えられなくなったが、ふとこんなことを話した。
「神様はね、サンタさんと同じなんだよ。サンタさんはプレゼントをくれるでしょ。神様は祈りを叶えてくれるの。だから神様は信じた方がいいんだよ。」
セントはそれを聞いて、「これだ!」と思った。
セントはさやかに言った。
「きっと僕達は同じ神様を信じてるんだよ。宗教とは無縁のサンタクロースのような神様をね・・・」
セントはようやく、自分の信じていた存在とは何者かを理解した。幼い頃から神さまに祈り助けを求めて来たけれど、その神さまとキリスト教の教えている神様は違うのだという事を、明確に区別したのだった。
セント、バカンスに行く.
セントはさやかが日本に帰ると言ってから、僕はどうしようかとずっと考えていた。毎年バカンスには、スイスの山々に登るのがセントのスタイルとして定着していたが、さやかと会えなくなるのではという怖さもあり、結局この日本行きの飛行機にさやかと一緒に乗ったのだった。
セントはスイスの山が好きだった。山々に登ると言っても、その頂きに登頂するわけではない。セントはいつも山腹や峠にある山小屋を転々と渡り歩くのだった。
今回はどのルートでどの山小屋に泊まろうかと登山地図を見て計画を立てるだけでワクワクしたし、壮大なアルプスの麓を歩くことは、山から流れる気を浴びるような神秘さがありたまらなかった。
その景色はセントの脳裏に鮮明に残り日々の活力となっていた。
完全にスイスの虜となっていたセントだが、そのスイス行きを諦めてまで日本に来たのには、セントなりの理由もあった。
日本食や禅の文化など日本がここまで浸透した時代はないと思えるほどこの時代の人々は日本をよく知っていたのだが、セントにはその日本文化が表面的なものに見え、日本という国がなにか雲に隠れた存在のように感じていたのだ。
セントは先日日本行きを決心し、さやかのご両親に挨拶に行った時のことを思い出していた。セントが一緒に日本に行きたいと伝えると、さやかのご両親はものすごく喜んでくれた。
しかし、セントとさやかの前の席は空席となっていた。さやかのご両親が直前になって仕事の都合がつかなくなり、行けなくなってしまったのだ。
セントはその事が残念でしょうがなかった。
日本に着くと、さやかはセントに「日本で行ってみたい所はある?!」と尋ねた。
セントはすぐさま「広島、長崎、それから京都」と答えた。
「広島・長崎は遠いよ~ ここは東京だよ。京都ならなんとか行けるかな~」
「でも先ずは、さやかのおじいちゃんの家がある山梨に行かないとね。さやかのおじいちゃんおばあちゃんに会うことが今回の目的なんだから。」
セント達はそこから3時間電車で移動することになるのだが、その移動距離はセントの想像を超えていた。「もう疲れた」その一言しかセントからは出てこなかった。「これだったらスイスの山に登った方がまだ楽だった」と思うほど飛行機や電車の中で座っていただけなのに物凄い疲労感だった。
おじいちゃんの家に着いた頃には辺りは真っ暗になっていた。
駅からは歩くことになったのだが、足元がかろうじて見えるか見えないかという暗さの中、さやかはスマホのライトで前を照らしながら、迷うことなくセントをおじいちゃんの家に案内した。
「まぁ〜、さやかちゃんが彼氏を連れて来たわよ!」おばあちゃんが明るくセント達を迎え入れてくれた。セントは日本語がいまいち分からなかったが、自分が訪れたことをものすごく喜んでくれていて、なんだかホットした。
次の日、さやかはセントを連れて山梨を観光しようと計画を立てていた。
行く場所を念入りに調べて、移動時間までも計算に入れたほぼ完璧なプランだった。
ただ移動手段だけは、おじいちゃんの軽トラを借りて観光すればいいと安易に考えていた。
その日一日おじいちゃんから軽トラを借りることに成功し、さやかのプランは上手く進みそうだったが、ただ一つ問題なのはその軽トラはマニュアル車だということだった。
さやかはセントを助手席に乗せ、得意げにエンジンをかけた。そこまでは良かった。
しかし次の瞬間、いきなり発進したかと思うとすぐにエンジンが止まってしまった。
さやかはエンジンをかけ直したが、またしても急発進し、すぐに止まった。
その後も急発進しては止まり、止まっては急発進した。
そんなこんなで、この10分ほどの間に10mも進んでいない。
セントは時折、椅子に頭を打ちながら、さやかの運転に付き合って乗っていたが、さすがに無理だと思ったのだろう「この車を運転するのは無理なんじゃないか」とさやかに言った。
結局レンタカーを借りて出発した。
おじいちゃんの家の近くにはレンタカーを借りられる店が無かったため、電車で大きな駅まで移動してレンタカーを借りなければならず、かれこれ2時間も時間をロスしていた。
「あ〜あ、さやかのプランがだいなし~」さやかは運転しながらブツブツ言っていた。
セントは運転はしなかったが、イギリスと同じ右ハンド左側通行の道並みは、助手席に乗っていてもなにか馴染み深いものがあった。
さやかはしょうがなくプランを変更していた。
セントには富士山を見て欲しかったから「富士山絶景スポット」とカーナビアプリに入力し、その通りに車を走らせた。
途中、道の両脇が開け、田園風景が広がった場所があった。セントは驚き、さやかに「これは何?!」と聴き込んだ。
「これは田んぼって言うんだよ」とさやかが答えると「まるでスイスのような緑色だ」とセントは感嘆してその風景を見ていた。
さやかとのドライブの時間はセントにとっては新鮮で有意義な時間だった。
1時間ほど車を走らすと小高い丘のような場所に着いた。カーナビアプリが案内した場所だ。
しかし、そこに広がる風景はさやかのイメージしていたものとは違っていた。
富士山からは程遠く、山と山の間にかろうじて富士山が見えているような、とても絶景スポットとは言い難い場所だった。
「こんなはずじゃなかったのに」とさやかはへこんだ。
こんな所にいてもしょうがないからと、当初一番最後に行こうとしていた夜景で有名な温泉に向かってみることにした。
市街地を抜け林道を30分ほど進み、見えてきたのはキャンプ場のような場所だったが、そこには確かに温泉の看板が立っていた。
勿論ここにさやかが案内したのは、さやかが山梨出身だから知っていたという訳ではなく、ネットで調べたら人気スポットとして出てきたから行っただけだった。(さやかは日本よりもロンドンの生活の方が長かったのだから、そこはしょうがない部分でもあったし、何よりさやかのお転婆とも思える生き様に免じて許される事でもあった。)
その温泉には「そっちの湯」と「どっちの湯」の二種類の温泉があったが、この2つの湯は隣接してあるのではなく、離れて作られていて見える景色も違った。
「『そっちの湯』と『どっちの湯』どっちに入る?」とさやかはセントに聞いた。
セントは「どっちの湯に入る」と言った。
するとさやかは「じゃあ、さやかは『そっちの湯』に入る」と言い出した。
「普通さ、温泉に来たら同じ景色を見て楽しむものじゃないの?!」セントは目をまん丸にして、さやかの言葉に被せるように言葉を返した。
「どうせ一緒に温泉には入れないし、別々の景色を味わえる訳だから、そっちの方がお得でしょ!」さやかのこの言葉にセントは呆れ返った。
結局、別々の場所で入浴を済ませると、売店で一緒にアイスクリームを買って食べ、何事も無かったかのように二人は仲睦まじく、目の前に広がる山梨の街並みを眺めたのだった。
セントの悟り.
セントの熱心な希望もあり、バカンスの後半は、京都に行くことにした。
そこでは、とあるお坊さんとの出会いがあった。
セントとさやかは新幹線で京都まで行くと、お寺を転々と訪ねて歩いたのだが、とあるお寺に行った時、お坊さんが現れてお寺の縁側にセント達を案内してくれたのだった。
その縁側からは、質素で何か静寂さを感じる日本庭園が見渡せた。
お坊さんは言った。「まぁ、この寂しげな空間の中に浸り、孤独の中に身を置いてみて下さい。大自然の中で生きるものは、誰しもが孤独なものです。その孤独を受け入れ、自らの意志をしっかり持って自然の中に立ってみることで、大自然との対話が始まり悟りが開けるでしょう。」
セントはさやかに通訳してもらいながら聞いていたが、孤独を受け入れるなど辛すぎると思った。
しかし、セントの目の前には静寂に包まれた日本庭園が広がり、そこに立つ木々は悠々とそして堂々としており、それを眺めていると自らの悩みはとてもちっぽけなものに感じられてきたのだった。
セントは決心した。
セントは自らの意思で孤独を抱き、己という小宇宙と、己を取り巻く壮大な大宇宙との共鳴を感じようとしていた。
孤独の中で堂々と立っている人間だからこそ、自らの信じている神様とも深い対話が出来るのだとセントは悟った。
それだけでも、日本に来た意味があったとすら思えた。
さらに、大宇宙と対話する中で「神様もずっと孤独の中で独りぼっちだったのではないか?!」という哲学的思考がセントの頭の中を渦巻いた。
「そして神様がその孤独に耐えられなくなったから、この世の中を作ったのではないか?!」セントに哲学的想像が生まれ始めた。
「今感じている大自然も人間も、そのようにして作られたのだ。そして人間も作る力を持っている・・・(それは、孤独を感じる存在だという意味でもあるが)・・・」
こうしたセントの悟りとも言える哲学的考察は、今後のセントの人生に変化をもたらした。
それは確かに、仏教がセントの人生観に大きな影響を与えた瞬間ではあったが、セントは仏教を信じることは無かった。
仏教もキリスト教と同じで、死後の世界のことに干渉し、人間がコントロールできない未知の世界の事までも口を挟もうとする図々しさがあるとセントは感じていたのだ。
同時に、さやかの通訳越しに感じるこの日本という国は、人や物を神として祀る癖があるとセントは直感で理解していた。(それは一つの文化として尊重されるべきものだが、セントが信じる神様とは明らかに異なっていた。ここでセントが思い描く神さまを整理したほうが良いかもしれない・・・《セントが思い描く神さまとは、幼い女の子が『神さま。お願い。。』と話す時の神さまであり、何かの教えに染まる前に形成されたアイデンティティの中に既に神さまはいるのだとセントは認識していた。》
さやかはというと、仏像の前で手を合わせて祈っていた。
「神様は自分の心にいるのであって、仏像に臨んでいる訳ではないでしょ?!」というセントの説得にも応じず、さやかは「ご利益があるから」と京都のいろんな場所で手を合わせて祈るのだった。
サンタクロースのような神様はいったい何処に行ったのか?!とセントは疑問に思った。
さやかの信じている神様は、さやかの心の中だけでなく、仏像の中にもいて、いろんな場所にその神様は顔を出すのだった。
それは面白いことに、ご利益がありそうだとさやかが思う場所には必ずその神様がいて、それはお寺であろうが神社であろうが関係なく、同じ神様がやってくるのだった。
さやかの信仰は、全てを超越していると言えばそれまでだが、一つの宗教を本気で信じている者達からすれば、あまりにも都合の良い話だった。
「さやかは宗教を信じているのか??」
「俺は宗教なんて信じて無いんだよ!だから、結婚も宗教の無い人と結婚したいんだ!!」
さやかの行いとセントの信念がぶつかり合い、この二人に破局の匂いすら漂ってきた。
さやかの目は潤んでいたが、セントの尋問とも思える問いかけは続いた。
「さやかの信じている神様は、サンタクロースのような神様ではなかったのかい?どうして、仏像の前で祈るんだい?!」セントは混乱しながら言った。
「それは・・・ご利益があるから。。ここ、パワースポットだし。。」
この言葉にセントは呆れ返ったが、さやかの行いをなんとかセントなりに理解しようとしていた。
そうか・・・さやかには宗教観が無いのだ!
だから、ご利益という(宗教にとってはあまりにも都合の良い言葉)言葉に騙されて、振り回されて生きているのだ。
この国の人々は、オカルトだろうがなんであろうがご利益があると聞けば信じてしまうのだろうか。
セントの考察が正しいかどうかはさて置き、この考察がセントのさやかへの愛を深めたのは確かだった。
それは、セントの母性本能のようなもので、幼い子供のように見るもの聞くもの全てを信じてしまうさやかを守ってあげたいと思ったからだった。
はじまりの物語.
あれから4年後、セントは再び日本にいた。
「オギャー オギャー オゴー」
「やっと産まれた!」セントは立ち上がった。
「この声は、確かに自分の娘の声だ!」(果たして自分の娘が本当に産まれたのかどうか、その事実はまだ分からなかったが、そうとしか考えられなかった)
名前はもう決めていた。『LOVE』だ。(日本語で『LOVE 』って何て言うんだろうか・・・?!)
セント30年(AD2048年)7月6日、セントとさやかは結婚をし、それから2年後の3月、一人の女の子が産まれたのだった。
「ねぇ、名前はもう決めてあるんだけど・・・LOVEって日本語で何て言うの?!」
「LOVEは『愛』って言うんだよ!」
「AI?」
「そう!あい!」
「じゃあ、この子の名前は『AI』だ!」
「じゃあ、こうしよう!日本では女の子には『子』ってつけるのが一般的なの!だから『愛』に『子』ってつけて『愛子』どう?!いい名前でしょ?!」
「AIKO?!・・・いいね〜。いい名前だ。」
こうして、セントとさやかの娘「大西愛子」は産まれた。「トーマス」ではなく「大西」という苗字を選んだのもセントなりのこだわりがあった。
セントには、トーマスというクリスチャンの家系に産まれたが為に、宗教に苦しめられて生きなければならなかったという過去がある。
愛子には自分とは違い宗教に縛られない人生を歩んで欲しかったし、そういう家系に産まれるような運命に変えてあげたかったのだ。
セントは愛子が産まれてから、誕生の祝いに何かプレゼントを送ろうと考えていた。
人生を30年ちょっと生きてきた経験も活かしながら、今まで触れてきた世界観や価値観を総動員して、この世の中で一番愛子に相応しい物を贈ってあげたかった。
プレゼントを選ぶのにそんなに時間はかけられなかった。愛子とさやかが病院から出てくるまでにはプレゼントを選び、愛子が初めて我が家にやってくる時に合わせてプレゼントを贈りたかったからだ。
セントは自らの固定観念を捨てようと努力した。
親や家系の愛子に対する勝手な思いが、愛子にとってしがらみとならないように、どちらかというと斬新なプレゼントを愛子には贈りたかったからそのようにした。
悩みに悩み抜いた末に、セントはククサという木製のコップを誕生祝いに選んだ。
なんでも、北欧ではこのククサを贈られた人は幸せになると言い伝えられているらしい。
このククサの材料は、フィンランドやスウェーデンなどの北部であるラップランドの厳しい自然の中で育った白樺のコブであり、一つ一つ木目や質感が違い同じコップは二つとない事が魅力だった。
しかも、ラップランド地方に住むサミー人達が、一つ一つ祈りながら作っているというなんともロマンチックなコップだ。
しかし、一つ問題もあった。サミー人達が祈る祈りとは、その民族が信じるある種の宗教的な祈りであるという事だ。宗教嫌いのセントなら直感で勘づいたことだろう。
それでも愛子のプレゼントにそのコップを選んだ。
それはセントが固定観念を取り除いて行き着いた答えでもあった。
そこには何千年何万年という歳月が流れ、宗教が人々に人生の豊かさを生み出している事は事実として受け入れざるを得なかっし、セントはそれを尊敬していた。
なるほど、サミー人達のように他の社会から離れた地域で、一つの宗教を持って生きる人たちは本当に幸せなのかも知れない。
愛子にはそうした宗教の良い部分も悪い部分も、世界を構成している一つの要素として理解し味わってほしかったのだ。
愛子が生まれたことはセントの人生にとって大きな変化だった。一方でセント自身も日本に来て愛子が産まれてから大きな決断をする事となる。
(それがきっかけで物語は大きく動いていくこととなる。)
セントは日本に来てから人類の歴史を見つめるようになっていた。
この2000年間、キリスト教の影響を受け人類が築いてきた近代化の歴史は、今やもう古いものとなり退化の歴史を辿っている事をセントは見抜いていた。
果たして、争いの絶えない現代社会を見る限り、キリスト教はそして近代化は本当に正しかったのか?と疑問に思うこともあった。
物質の豊かさは、(少なくとも近代化した社会においては)世の中に溢れている。しかし、精神文明は衰退し、現代社会では自殺も後を絶たない。
セントはそんな世の中のど真ん中で生きるなかで、自分に何か出来ないか本気で考えていた。
もちろん、セントは生活をする上でお金も必要だった。愛子が生まれた事で、それはより一層切実な問題となっていた。
さやかは私が働くからと言ってはくれていたが、セントも何もしないわけにはいかなかった。
なんとかテレワークで、日本にいながらも英語を使って仕事ができないかと試みたが、それは難しかった。
家事や育児は自分がやるにしても一生育児がある訳でもないし、日本にいて何か自分に出来ることがないかと思い悩んでいた。
そんなある日、セントは散歩をしながら閃いた。
「生まれてきた娘を題材に小説を書こう。題名は『愛子の日常』でどうだろうか?」
これがもう一つの『愛子の日常』という小説が書かれた始まりだった。
セントはこの小説を通して、お金を稼ぎたいという思いもあったのだが、何より人々が健全な良心を育むきっかけになってくれればと思っていた。"人類の進むべき道"を示すのではなく、人々の良心を育むことで、良心が人々を導いてくれると心から信じていたからだ。
『根っからの宗教嫌いが書く、何か心が洗われ、良心に響くようなストーリー』それがその小説のコンセプトだった。
・・・こうしてセントによる愛子の育児日記かとも思える物語が書かれたのだった・・・ << 続く >>
【お知らせ】
皆様のご愛読もあり、無事に第一話を完結させることができました。本当に感謝しています。
さて、第二話への期待が高まる中で大変恐縮なのですが、物語の投稿をお休みさせていただきたいと思います。理由は、今の私の人生経験ではこの物語は書き切れないと思ったからです。
少しブランクは空いてしまいますが、どのような形であれ、この物語を完結させたいと思っていますので、しばらくの間お待ちいただければと思います。
皆様とはまたこの物語を通してお会いできる事を楽しみにしております。
p.s. とはいえ、愛子がどんな子に生まれたのか気になる方もいるでしょうから、来週第二話の予告だけ流します。それを見て、また会える日を楽しみに待っていて頂ければと思います。
【第二話予告】
愛子が4歳の時。
愛子はセントと初めてデートをした。
<中略>
その日は真夏の日差しが照らす夏日で、少し歩くだけでも汗が出てくるような日だった。
<中略>
愛子はセントと一緒に街中をぶらぶらと歩いて回った。
セントは愛子の好きなように歩かせた。
<中略>
20分ほど歩いただろうか。と言っても愛子の足で20分だから、そこまで遠くには行っていない。
<中略>
愛子は電信柱の前で急に立ち止まった。
しばらく待っていても電信柱と一体となっているかのように直立して動かなかった。
とうとう痺れを切らせたセントが、
「愛ちゃん何してるの?」
と聞くと、すぐに愛子は答えた。
「日陰で休んでるの。」
見ると電信柱の下から細長い陰が伸びていて、愛子はそこに体がうまく収まるように立っていた。
「たしかに日陰ではあるけれども、そこじゃあ休まらないでしょ!」
「じゃあ、カフェにでも行こうよ!」
<中略>
セントと愛子はカフェの中に入った。
「ここ涼しいねー」愛子は言った。
これは物語の一部です・・・
第二話では、愛子が過ごす日々が描かれる予定です。
きっと何かほっこりするような物語が待っていることでしょう。是非お楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
