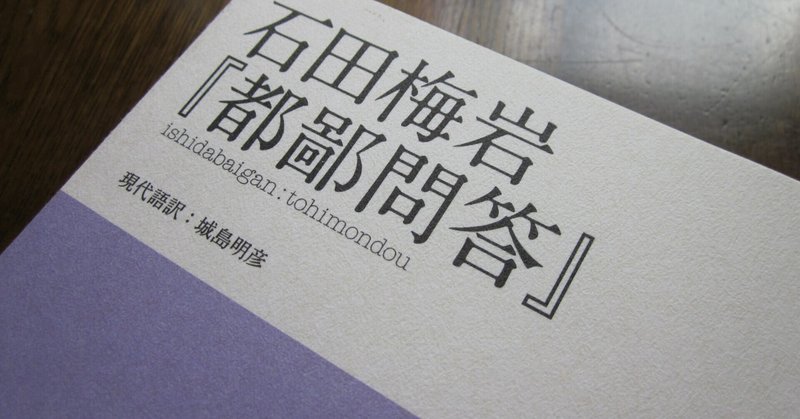
都鄙問答
ここ数年、自分の生き方を探るうえで関心を持っているものの一つに「心学」があります。
その教えの一つ。
「まことの商人は先も立ち、われも立つことを思ふなり」
「正しい商人とは、相手のためになり、自分もためにもなる者をいう」という、お客さまとともに喜び、ともに栄えていこうとする共存の関係を示した言葉です。
これは商売に限ったことではありませんね。
心学は、江戸時代に商家で奉公人をつとめた石田梅岩(いしだばいがん)(1685~1744)が始めた思想・哲学で、「石門心学」と呼ばれています。
この梅岩の教えの基本を記したものが『都鄙問答(とひもんどう)』です。
「都鄙」とは「都会と田舎」といった意味で、梅岩の門弟や身分を超えた様々な人たちとの会話をまとめたものです。
『都鄙問答』は商人の心得について語ったもので、松下幸之助翁を始めとする多くの経営者が愛読している書です。
『都鄙問答』の根底には「正直」「倹約」「勤勉」があります。
梅岩が生きた今から300年も前の時代には、「士農工商」の身分制度の序列にある通り、商業はその価値や役割を低く見られていました。
その時代に梅岩は商業の意義と利益追求の正当性を説きました。この考えは現代にもそのまま当てはまるものです。
以下、断片的ですが、私の生き方の参考にしている教えのいくつかです。
「人の道は一つである。士農工商は貴賤ではなく、その職分の違いである」
「自分のところで余った物を、不足している物と物々交換することで相互間に流通させたのが、商人の発祥」。
「商人の得る利益とは、武士の俸禄と同じで、正当な利益である。だからこそ商人は、正直であることが大切になる。水に落ちた一滴の油のように、些細なごまかしがすべてを駄目にする」
「商人に俸禄を下さるのはお客様なのだから、商人はお客様に真実を尽くさねばならない」。
「真実を尽くすには、倹約をしなくてはならない。倹約とはけちけちすることではなく、たとえばこれまで3つ要していたものを、2つで済むように工夫し、努めることである。無駄な贅沢をやめれば、それでも家は成り立ってゆくものである」
「商人の蓄える利益とは、その者だけのものではない。天下の宝であることをわきまえなくてはならない」
これらは商人にとってだけでなく、人として必要な心がけでもあるのでこの本を私の人生の指針書の一つにしています。
