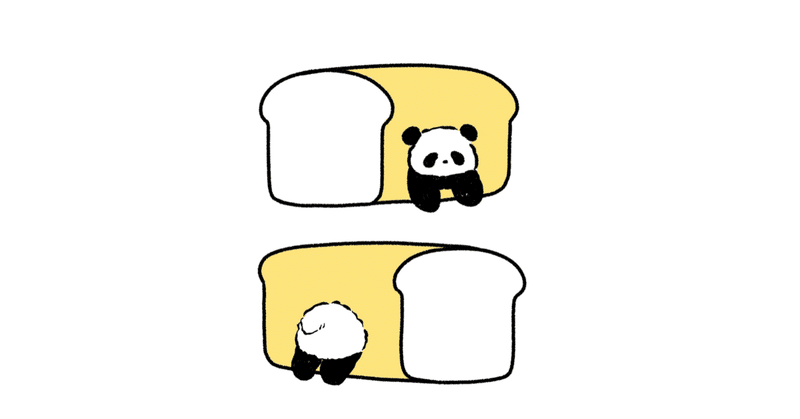
サインコサインと半泣きのパン配りから教えてもらったこと -1ヶ月書くチャレンジ Day23-
こんにちは。まるやまです🍡
家族から充電式の温灸器を借りました。ここ数日ほど寝る前にやっていまして、お手軽でいい感じです。
できるだけ体を冷やさないように暮らしていますが、夏はどうしても長い時間クーラーをつけたり冷たいものを食べたりしますよね。
体の上と下で体温がかなり違うように感じられるのが気になっていました。お腹や足が冷えていると、その温度に体が合わせようとして他の場所でやたら汗をかいてしまうそうです。
おへそから指四本ぶん下のツボ「関元」と、みぞおちとおへその真ん中にあるツボ「中脘」に温灸器を貼って、15分くらいあたためます。クーラーが効いている部屋でも胃腸のまわりがぽかぽか気持ちよくなって、不思議とスッと眠れます。
noteを投稿してから温灸をやって寝るのが最近のルーチンです。
さて、23日目のテーマは「仕事や勉強で1番大切だと思うこと」です。
わたしは「なぜその仕事や勉強をするのか、腹落ちさせること」だと思っています。
この考えが万人に当てはまるのか謎ですが、繊細な気質の方や内側にこもって深く考えやすい方には共感してもらえるかもしれません。
わたしは数学がとても苦手です。
確か高校の数学IAだったと思いますが、三角比の「サイン・コサイン・タンジェント」でつまずき、小テストで延々と赤点を取り続けました。
「覚えるだけなんだけど、どうして分かんないんだろうなあ」
「なんでですかね〜」
首をひねる数学の先生はクラスの担任でもありました。マンツーマンの居残り授業で手厚く教えてくれているのに、わたしはさっぱり理解ができず同じところを何回も間違えます。
消しゴムでしわくちゃになった小テストに向かい、値を求めながらずっと「なんで暗記をしなくちゃいけないんだろう」と考えていました。
それから数学くんとは距離をとって暮らすようになりましたが、中には問題集を繰り返し解くほど好きな単元もありました。
この違いはなんだろう? と考えた結果、理解に苦しんだサインコサインは「どうして学ぶのか分からない」から勉強が続かなかったのだと気づきました。
因数分解は好きでした。
先生が「因数分解を知っていると、なにか問題が起きたときに小さく分解して考えられるようにもなります」と説明してくれたとき、深く考え込む癖があるわたしは「なるほど!」と納得しました。だから楽しんで勉強に取り組むことができたのです。
もうひとつ例を挙げてみます。
結婚式によく使われるレストランでアルバイトをしたことがあります。
各テーブルを回って配膳をするのですが、わたしは「パン係」に任命されました。コース料理だと小ぶりのパンが出てきますよね。
焼きたてアツアツのロールパンをかごに山盛り乗せて、うろうろと練り歩き「おかわりいかがですか?」と聞きつつも有無を言わさず空き皿に新たなパンを置いていく仕事です。
料理の進み具合や、人によっては「もう結構です」とお断りされます。
しかし、パンが残った状態でのこのこ厨房にもどると「空にしてこい!」と怒られて追い出されるのです。まだ半分はカゴに残るパンを掲げて泣きそうな顔で席をまわったこともあります。
でも配膳の仕事は好きでした。
周囲の状況に気づきやすい質は、グラスが空になりそうな方や食事を終えられた方を見つけるのに役に立ちます。ありがたいことにその部分を褒めていただけることもありました。
数学の話と似ていますよね。
パン係は、どうしていらない人にも配らないといけないのか「納得」できていませんでした。配膳の仕事はお客様のニーズを汲み取り、それを満たして喜んでいただくためと「納得」していたから楽しかったのだと思います。
わたしはこの考えに行き当たってから、仕事や勉強がうまく進まないときは「自分の中でなにかが納得できていないんだな」と思うようにしています。
モチベーションが沸かなくて英語の勉強が続かなかったり、仕事のやる気が出なくて取りかかれなかったりという悩みは世の中に溢れています。
その場をどう凌ぐかのライフハックは山のように出ていますし、必要だと思います。
もしその対処でうまく行かなかったら、一旦立ち止まって「自分はなぜこの仕事をするのか?」や「なぜこの勉強をしたいと思うのか?」を腹落ちするまで考えてみると、スムーズに動き出せるかもしれません。
この記事は、いしかわゆきさん著「書く習慣」の巻末で提案されている「1ヶ月書くチャレンジ」を実践しています。
30個のテーマを1日1個ずつ書いていきます。
読んでくださりありがとうございます! いただいたサポートはまるやまの書くエンジンになります☕️
