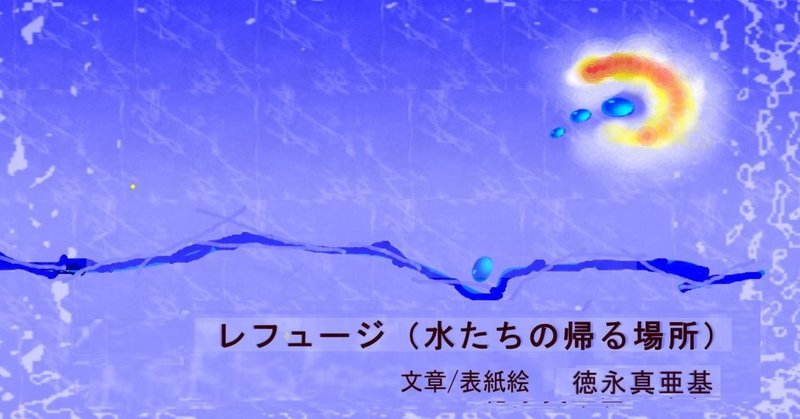
レフュージ(水たちの帰る場所)
1.とにかく川の話から‥‥
とにかく川の話から始めてみようと思う。
そうでもしなければいつまでたっても何もわからないままだし、もはやこれ以上前に進むことさえできそうになくなってしまった。
どこからか弱々しく聞こえていた僕を呼ぶ声、
お前の居場所はそこじゃないよ‥‥
早く戻っておいで‥‥
その声に心は乱されそうになりながらも、競争と桎梏(しっこく)のこの社会で生き抜くためには聞かないようにしてきた僕だった。そうして長いこと自分の気持ちを偽り続けてきたお陰で、ついに行き詰まってしまったのに違いない。本当は生きていくためにこそ、その声に耳を貸すべきだったのだろう。
もう迷うのはよそう。今から僕はその声の意味を突き止めにいこうと思う。たとえそのことによって、悲劇的な結論が導き出されようとも。
僕がこの世に生まれてきた時、すでに父と母がいて、祖母がいた。姉が生まれた三年後に僕が生まれ、その三年後には妹が生まれた。この小さな集団は、家族と呼ばれていた。いつ誰が家族というものを作ることにしたかは知らないけど、僕たちが生まれるずっと以前からそう決まっていた。その方が何かと都合がいいからなんだろう。
家族は僕を他の人と区別するために、ワタルという名前をつけた。そして僕もワタルって呼ばれると、まるで自分のことを呼ばれている気がして返事をしていた。洋服にもどこにも名前なんて書いてないのに。
その証拠にもし着ているものをすべて脱いで、裸でみんなの前に飛び出しても、みんなは僕のことわかっただろう。でも、その時、首から下だけを見て僕の名前を当てるのはちょっと難しいかもしれないから、ワタルっていうのは、僕の顔のことなんだなと思っていた。
だけどそれだって正しくはない。
この顔をめちゃくちゃに作り替えたって、年とってしわくちゃになったって、やはり僕はワタルなんだ。
そしてここは日本で、昭和という時代だった。
ちょんまげを結ったり、着物を着たりしている人はいなくて、みんな洋服を着ていた。裸では寒すぎるということだと思っていたが、ずっと後になって、裸で外を歩いてはいけないと誰かさんたちが法律で決めたからだということがわかった。
他にもたくさんの法律というものがあって、とても一人じゃ覚えられないくらいあって、どうやら僕は生まれてすぐに、その法律というものに関わらないで生きていくことはできないことになっているようだった。
まだある。
飛行機というものが鳥よりも速く空を飛んでいたし、船がトビウオのように水面をかすめて走っていたし、町には車や電車がけたたましく疾駆していた。地球がまあるいことや、その地球には国境というものがあって、他の国とは憎み合ったり、仲良くし合ったり、助け合ったり、戦争をし合ったりしなければいけないことを知った。
普通はひとつ屋根の下に家族で住み、大概は男が毎日会社という所へ行き、女は家庭の一切の雑事をつかさどると決まっていた。
僕が少し大きくなると、男と女はいろんな面で違うということを知った。僕は男に生まれたらしい。そして女の子を意識するようにできていた。もっともっと大きくなってから知ったのだけど、どうやら男と女とは、凸と凹の関係で、合体して愛し合ったり、子供を作ったりしなければいけないのだった。
知るもんかそんなこと。一体誰が決めたんだ。
僕は何一つとして知らされていなかった。
あなただってそうじゃないですか?
自分で「うん、ここならまあ生きていけそうだ」と、この社会を選択して生まれてきたのですか?
あなたが家族を作り、学校を作り、会社を作り、国を作り、法律を作り、時代を作ったのですか?
そんなはずないのに、どうして他人に与えられたものを当然のように受け入れたり、あたかも生まれる前からこの社会をよく知っていたかのように振る舞うことができるの?
僕にはそんな器用なこと、とてもできやしない。
僕は、生まれてきたこの社会を嫌悪しているわけでも非難しているわけでもない。ただ、どう受け止めていいやら、わからなくて面喰らっているんだ。あなたは今生きているこの場所に一度も違和感を感じたことってなかったですか?
それが知りたいんだ。
こんな風に感じるのは僕だけなんだろうか?
他の人から見れば、僕は、慎重すぎて社会に馴染めないでいるただの脱落人間として片付けられてしまうのだろうか?
そんなこと信じられない!
みんなだってこの社会が自分の居場所であることにどこか疑問を感じてはいるけれど、そのことを直視することから逃げているだけに違いないと思うんだけど‥‥。
僕の話を聞いてくれているあなた、途中で投げ出したりしないで最後まで一緒に考えて欲しいんだ。そうしなければ、きっと、死ぬまで自分を騙し騙し生きてしまうことになると思う。
今日までの、この僕のように。
とにかく、そう、とにかく川の話から始めてみようと決心したんだった。
川と言っても、ミラボー橋の下を流れる遠い異国の川や、ライン川とか揚子江とかいった有名な川ではない。僕が生まれて、そして住むこととなった家の、すぐ横を流れていた小さな川のことだ。あの声の意味を理解するためには、生まれた頃の原点に逆上ってみる必要があると考えた時、その川が真っ先に頭に浮かんだ。
そこから考えていけば、きっと何かがわかるに違いない。
2.その川は、静かな住宅街の‥‥
その川は、静かな住宅街の間を縫ってゆっくりと流れる黒い川だった。魚はずいぶん前から住まなくなっていた。海へ向けていらなくなったものを運ぶだけの川だ。(でも本当は、海と呼べるものへ注いでいるのかどうかだって怪しいものだった)
子供が誤って落とした玩具や、洋服や靴や傘やトルストイの人生論や、禅僧や気の触れた裸の男や、それに子供までも流れてきた。僕はそういったものを回転寿司のネタを眺めるように、柵のこちら側から一日中眺めていたものだ。
だけど回転寿司とは違って柵の向こうを流れていくものたちを手に取ることはできなかったし、彼らは二度と再び僕の前には巡ってこなかった。
庭でボール遊びなんかをしていると、柵を越えて川にボールが落ちてしまうことがある。そんな時心臓が止まりそうになり、取り返しがつかないことをしてしまったように泣いた。
柵の向こうには二度とこの世に戻れない死が常に待機していた。それは人間の力ではどうにもできない現実だった。
だけど僕にとっての現実も、他人の作る川に流されているだけの、どうにもできないものだった。
3.何年かごとにやってきた‥‥
何年かごとにやってきた大型の台風の、あの大洪水というものについて書かないわけにはいかない。
あなたは、床上浸水というものがどういったものかわかりますか?
僕がまだ幸福だった頃の話だ。今でも考えるとわくわくする。大型の台風はいつだって大洪水と停電をもたらすんだけど、これがまた最高だった。
その夜、雨や風がいよいよ強くなり、もう台風が襲ってくるのは必至だとなると、父の声が響く。「ワタル、懐中電灯とかなづちを持ってこい!」と。家族や家を守るために、扉や窓を板で補強する仕事を、父は僕に手伝わせるんだ。それは家族の中でたった一人の男である僕を信頼しているからだ。僕も風雨の中で、びしょびしょになって喜んで働く。父の手はどんな嵐でもびくともしない家に仕上げてしまう。
何より恐ろしいのは風の音。激しく吹き付ける雨の音。そして窓の外はと夜を透かして見れば、電信柱も木も家々も、増水した川の激流に、足をすくわれまいと必死で耐えているように見えた。母は恐ろしい嵐に脅えるまだ小さい妹を抱きしめる。
だけど、本当は子供たちはみんなこの日を待っていたんだ。そこには肩を寄せ合う家族がいて、流されてしまわないように暗闇で確かめ合う声が聞こえる。僕たちの心を一つにしてくれるロウソクの灯がある。やがて畳の上にまで水面が上がってくると、濡れないようにお膳の上に小さくひとかたまりになる。まるで大洋のただ中に浮かぶ筏(いかだ)に、肌を寄せ合うように。
神様が与えてくれた、恐怖と冒険に満ちたすばらしい数日間。子供たちは喜びをどうして抑えられよう。
もし僕が流されたら、気づいた母が叫んで父に知らせるだろう。僕は逞しい父の腕に助けられるはずだ。家族と一つになった僕の心は、外の激しい嵐に反比例して、何か霊的な力に導かれ、静謐(せいひつ)な時の中を漂っていた。
でも、もう一つの暮らしを考えてみてほしい。
大洪水はない代わりに家族はバラバラで、ロウソクの灯の代わりに昼も夜も煌々(こうこう)と人工の明かりが照らしている世界を想像してみるんだ。人工の明かりは確かに物の姿を夜でも克明に見せてくれるけど、そのせいで本当の夜を覗くことはできなくなった。
夜は、光の届かない箪笥の後ろだとか床下や天井裏に身を硬くして、もう二度と出てこようともしない。紛れもなく今僕たちが暮らしているこの世界がそうなんだよ。
さっきの大洪水の話の続きだけど、子供らからあの幸福な瞬間を奪ったのは役所の連中だ。奴らは税金を使って、ろくなことをしない。長い年月と大金を投じて川に蓋をして、二度と氾濫しないものに作り替えてしまった。だから、あんな幸福な時をほんの数日でも経験できた子供は僕たちが最後になった。もうあなたがどんなに願ったって、本当の父親にも、本当の母親にも、まして本当の子供にもなれやしない。
だけど僕たち家族だって、そう変わりはしない。幸福な関係はそう長くは続かなかったんだから。
4.いなばの白うさぎは‥‥
いなばの白うさぎは、ワニの上をぴょんぴょんと渡ったけれど、僕より年上の子供たちは、何もない川面を滑るように走って次の橋まで渡ることができた。そんな遊びが子供たちの間ではやっていた。何もすることがない退屈な午後、ぽかんと窓の外を眺めていたりすると、どこからか子供がふいにやってきては、ワニもいない水面を器用に渡っていく。
僕は本当の勇気について考えた。
川を渡ることは果たして本当の勇気だろうか?
困っている人を救ったり、人の嫌がる仕事を進んで引き受けたり、それが本当の勇気であって、川を渡ることは本当の勇気じゃないと思った。でも僕は川を渡れるようになりたかった。
5.川を渡れるようになるなんて‥‥
川を渡れるようになるなんて、考えただけですばらしいことだった。
空手チョップの一撃で家を倒せたり、小石を雲に隠れるぐらいまで高く投げ上げることができるのと同じくらいに、格好いいことだと思った。
小石を蹴りながら四つ角まで出ると、小さなつむじ風が吹いてきて枯れ葉を巻き上げていった。僕は枯れ葉を追いかけて、目に見えない敵にキックを飛ばしながら思った。川を渡れるようになりたいと。そして、家に帰って母の姿を探した。
母は、奥の畳みの部屋に座って繕い物をしていた。後ろ姿が寂しかった。泣いているのかなと思った。
「ねえ、お母さん、どうしたら川を渡れるようになるの?」母は振り返らずに答えた。「そうねえ‥‥、きっと、いつも練習してればできるようになるわよ」
僕は踊りだしたいくらいに嬉しくなった。母の答えは、希望を与えてくれた。川を渡れるようになること、それはきっと母を幸せにしてあげることかもしれない。そんな気がした。
僕は押し入れから布団を引っ張り出し、押し入れの上段に上った。そこから下の布団めがけて飛び降り、着地するまでの間にできるだけたくさん足を前後に動かす練習から始めた。それと並行して地面を川に想定して、長い距離を走り抜ける訓練もした。片足が地面に着くか着かないかの間に、すぐ次の足を前に出す訓練だった。
水の上は、地面のように強い力で踏ん張ることは不可能だし、着水した足が沈まないうちに、次の足を前に出していなければいけない。冬の間中も訓練は毎日続けた。
冬が過ぎて春が来て、母は僕の長ズボンを半ズボンに取り替えてくれた。暖かい風がもものあたりに触れ、かすかな快さがあった。女の子がミニスカートを履いた時もこんな気持ちなんだろうか。ちょっぴり恥ずかしくて、ちょっぴり人に見せたくて、体がちょっぴり軽くなったような。
僕は川を渡れるような予感がした。
風の中を走ってみた。とても体が軽かった。訓練中に作った傷は数え切れなかった。両足に塗った赤チンの数は、僕の密かな誇りでもあった。そろそろ本番で試す時が来たようだ。
橋の上にたち、川を睨んだ。次の橋までは百メートル近くはあるだろう。そこまで一気に走り抜けなければいけない。
勇気のことがまたもや頭の中をよぎった。こんなことが本当に勇気のあることと言えるだろうか。川を渡れたからと言って人が誉めてくれるだろうか。どこか違う気がした。それでも今となってはやるしかなかった。
僕は目をつぶって三回深呼吸をし、「やっ!」と気合をかけて飛び出そうとした。
足が動かない。いくじなし!
よーし、今度こそ行くぞ「えいっ」
上半身が少し動いただけで、またしても腰から下が動いてくれない。何度それを繰り返したことだろう。その日はついに一歩も踏み出すことができなかった。
夜、珍しく父が早く帰ってきた。布団に入ってから僕を呼ぶと、隣に寝るように言い、腕枕をしてくれた。僕は父の体のにおいを嗅いだ。画家だった父は、油絵の材料のにおいが体に染み付いていて、僕はそのにおいが好きだったからだ。だけど、その時の父の体は酒臭かった。僕は早く逃げ出したくなった。
「子供の頃は、喧嘩じゃ誰にも負けたことがない」と父は言った。
「弱い者いじめする奴は、自分より年上だろうと追っかけていってやっつけた。相手が三人だろうと負けなかった。泣いて謝るまでやった」
とても勇気のあることだと思った。川を渡ることも勇気なのかと聞いてみたかったがやめた。
「おとうさん、どうしたら川を渡れるようになるの?」
僕は以前母にしたのと同じ質問をしてみた。父は少し考えてから懐かしそうに「俺も昔はよく川を飛んだなあ」と言った。
父の時代は飛ぶと言ったのだろうか。そうか、もっと空を飛ぶような感覚が必要なのかもしれない。明日は鳥を見て学ぶことにしよう。父が大きないびきをかいて寝てしまったのを見計らって、僕は自分の布団に戻った。
目をつぶると、まぶたの裏をたくさんの鳥が飛ぶので眠れなかった。
6.子供の頃の僕の写真から‥‥
子供の頃の僕の写真から、笑顔のものを捜し出すのは難しい。ほとんどの写真がつまらなそうに無表情につっ立っているだけだ。寝ているうちに他人の家に連れてこられて、目が覚めてみたら周りは他人ばかりだったという感じで、居心地が悪そうにしている。
親戚のいる湘南の海に行った写真がある。三歳くらいの時だったと思う。そこでも僕は、親戚の子供たちやその友達の中で、一人だけ元気がなさそうにしている。
海の近くで育った子供たちは、都会で育っている僕とは違い、みんな健康的に日焼けして逞しそうだったから、ちょっと恐かったし、それに初めて会った人たちを親戚だと言われたって、彼らと仲良くしなければならない理由が見つからなかった。
大人の人たちに何を聞かれても相槌を打つくらいで、なんとつまらない子供と思われたことだろう。
それよりも両親をがっかりさせるのは辛かった。だから、普通の元気一杯の子供のように振る舞いたいのだけど、そう思えば思うほど体は萎縮して、顔はこわばってしまうのだった。僕にとって外の社会という現実は、今にも逃げ出してしまいたいような息が詰まる場所でしかなかったけど、それでも気を使って、いつもじっとその場に留まるようにしていた。
だけど、子供の頃の写真でとても幸福そうにしている写真が一枚ある。僕が一番気にいっているモノトーンの写真。陽の当たるソファーに顔を埋(うず)めて眠りこんでいる写真だ。
その数年後に、僕の家から姿を消してしまったそのソファーだけど、当時、板の間の部屋にがらくたか骨董品のように置かれていた。電車の座席のような生地で、擦れてところどころ濃淡がまだらに見えている。色はえんじだったように記憶している。あるいはグレーだったかもしれないが‥‥。
眠っている僕の背中には、半ズボンを釣っている紐が大きなばってんを描いている。洗いざらしの白い半袖のシャツがすずしそうだ。お尻から下と、右腕の一部と、左の肩口に、まぶしい夏の陽射しが張り付いている。庭の藤棚からの木漏れ日だ。開け放した窓からは、爽やかな風も吹き込んでいたに違いない。
ちょっぴり変色してしまった古い写真の中の僕は、日溜まりに自分の居場所を見つけたネコのように、幸福そうに見える。
7.母の夢は‥‥
母の夢は僕を野球の選手にすることだった。もしくは剣道を習わせることだった。だけど、そのどちらも僕にはやりたくないものだった。
僕は野球というものにあまり興味がない子供だったし、剣道よりもむしろ実践的な柔道に憧れていた。
近所に柔道と剣道を教えてくれる道場があって、料金も安かったので、母が剣道をやってみないかともちかけてきた。僕はもし習わせてくれるなら、ずっとやりたいと思っていた柔道がいいと言い張った。
母には柔道は野蛮なものに思えたのだろう。彼女が理想とする礼儀正しくはきはきした態度を身につけさせるためにも、剣道の方がいいと言った。
結局、僕が折れて剣道を習うことになった。
ところが、生徒が多いせいで、新入りはすぐに練習はやらせてもらえなかった。
他の生徒が練習をしている二時間、板の間でずっと正座をしているのが僕たちのやることだった。そうやってふるいにかけたのだ。週一回の苦痛だけの時間が始まった。
正座組は二十人ほどいて、ある日、ひとりの子供が正座のあまりの苦痛に腹を立てて、座布団を積んである最上段に座った。師範(せんせい)がすっ飛んできて「降りろ」と命じた。
僕たちは、その子がどうするか興味津々だった。彼は何度怒鳴られても頑として自分の居場所を動かないと決めているらしかった。師範は竹刀で彼を叩き、「言うことを聞かないなら、帰れ」と怒鳴った。口を真一文字に結んで、何をされようと動こうとしない彼は、もしかしたらその意志の強さを試されていると勘違いしていたのかもしれない。
三ヶ月が過ぎて見学組は半分以下に減り、やっと苦しい正座から解放され、練習に参加できるお許しが出た。だけど高価な防具を買わなければならないとは聞いていなかったのだ。母がため息をついた。わが家の家計ではそんな余裕はなかった。
忘れもしない。あの日、母が僕のセーターのボタンを留めてくれている時だった。僕は母の顔を見下ろしながら「剣道、やめようか」と言ってみた。母は、ほんの一瞬手が止まったが、すぐに何でもなさそうに「仕方ないわね」と言った。とても優しい声で、涙が出そうになったのを覚えている。僕は母の期待にそえなかったのだ。
もしやりくりが大変でも、剣道を続けさせてくださいと情熱をもって頼めば、母はどんなことをしてでも願いをかなえさせてやりたいと思っていたに違いない。
母の期待にそえないと言えば、他の子供のように快活でない僕は、何度も何度も母を失望させたに違いない。
例えば母が子供たちを連れて遊園地に行こうと決心した日、僕は大喜びだったが、母は、僕に、どこかに隠し持っていた子供用の半ズボンのスーツと蝶ネクタイをつけさせたがった。僕はどうしても、普段のつぎはぎだらけのズボンがいいと言ってきかなかった。
結局、母の思い通りにさせられたが、遊園地のベンチに座っている僕の写真がつまらなそうだったのは言うまでもない。そんな格好をさせられた時から自分じゃないみたいだったんだから。帰り際、「もう、二度とつれてこない」と言われてしまった。
8.ところで、先ほど話した、剣道の道場で‥‥
ところで、先ほど話した、剣道の道場で起こった小さな事件は、僕にとっては、避けて通れないたくさんの重要な問題を提起していた。誰が正しくて、何が正しくて、いったい誰がどうすれば一番最善だったのか。それは、おそらく永遠に解決がつかない問題だろう。
なぜなら、その提起された問題に対する答えは、答える人間の立場の違いの数だけ存在するからだ。
世の中は、これと同じ解決がつかない難問であふれている。答えが一つでないということは、どれも正しいとは言えないということなのに、自信を持って答える人がいるというのはどういうことだろう。この社会に生まれて、たかだか数十年の人間が、確信を持って答えることができるというのは一体どういうことなんだろうか。僕にはうまく理解できない。
この矛盾だらけの社会にあって、「社会に対する不信感で、もはや生きていくことができなくなりました」と嘆く人間があまりにも少ないということが、僕には不思議でならない。
9.『運動会の憂鬱』
こんな秋晴れの空の日
遠くにヘリコプターの折り畳むような音が聞こえてくると
僕の心は悲しくなる
何故か小学生の頃の運動会が思い出される
青空へ攀(よ)じ登ってはたはたと舞っている国旗の音を
連想させられてしまうせいかもしれない
空気を撫で上げるように湧き上がる歓呼の声の真っ只中に
僕の心は取り残されてしまいそうになる
子供の僕は、青空の下では走り回りたくなったけれど
履き慣れない白い足袋(たび)の感触はヒタヒタと気持ち悪かった
おいしいお弁当を食べることは楽しみなのに
赤か白の帽子をかぶらされ
まだ自分の犯した罪さえも知らない囚人は
早く家へ帰りたかった
気持ちのいい風を呼吸することは好きなのに
湿った白線の酸っぱい臭いにはむせ返るだけだった
誰もが通らなければならない儀式を
僕は大人をがっかりさせないように元気よく演じるつもりだったが
項垂(うなだ)れた役者の手足は言うことを聞いてくれず
校庭という舞台の上に立たされた操り人形は
高らかに鳴り響く行進曲に合わせ
手足を大きく動かしているつもりだったが
微妙にテンポは遅れた
僕にできることは
巨大な力に踊らされながらこんな生き恥に泣くことだけだった
泣き声を
空中に停止して監視している
目に見えないヘリコプターのけたたましい音にかき消されながら
10.川を渡れるようになったのは‥‥
川を渡れるようになったのはいつからだか正確には覚えていない。いつの間にか僕は、川の上を走って渡れるようになっていた。
川を渡るコツは、自分が川の気持ちになることだった。
その頃からだ。僕の体の中に水が住みついたのは。
それまでのくみ取り式のトイレから水洗トイレに変わった日、僕は怖くて紐を引くことができなかった。頭の高さよりもずっと上にあるタンクから、勢いよく水が流れ落ちる音を聞くのが恐かった。いつでもすぐに逃げ出せるようにトイレの戸を開けておいてから紐を引き、水が流れると同時に飛び出すのだった。
僕の中に水が住みついてから、体の中を雨が降る時があった。時には、じめじめとすすり泣くように降り続いた。時には水洗トイレのように轟音とともに水が落下した。
逃げ出すための扉がどこにもない場所で、それは今でも続いている。
そして、川は流れた。
学校の校庭では、その水面に桜の花をたくさん浮かべて流れていった。僕にはとても悲しい光景だった。
どんなことをしたって監獄のような学校に行きたくなかった。僕が何をしたって言うんだ。僕がこの世に生まれたいと望んだわけでもない。神様が勝手に僕を作り、生まれてみると学校へ行くことに既に決まっていた。
学校の裏庭で上級生たちは、先生に隠れて水遊びをする。何人かが水に溺れて死に、何人かはそのままどこかに流されて二度と帰ってこなかった。先生たちは困り果てて職員室で話し合った。激論を戦わせ、質疑応答をし、相槌を打ち、弁明し、一大演説をぶち、長広舌(ちょうこうぜつ)を振るい、説き伏せ、泣き落とし、若い女の先生の涙が川に落ち、若くないかわはぎに似たメガネをかけた先生がきれいにまとめ、校長が時計を見て、議事は終了した。
そして、いつものようにジャブジャブと先生たちは川の中を帰っていった。膝まで水に浸かりながら。
教室の中は、いつも雨が降っていた。どこまでもどこまでも落ちていくような雨だった。誰もがそれを目撃していながら、誰もが見えないふりをしているようで、助けてくれと叫ぶ者も、助ける者もいなかった。
川は毎日毎日絶えず流れた。川の流れる音のしない日はないので、人々はそれが川の音であることすら気づかない。
玄関の扉を開けると外は川が流れていた。弁当箱の蓋を開けると川が流れていた。引き出しを開けると川が流れていた。車のボンネットからエンジン音と一緒に川の流れる音がした。人間の力では抗えない、どんなものでも丸ごと飲み込んでしまう流れ。だけど人類が生存し続ける限り流せないものがある。
川はあらゆるものを飲み込んで、そして流してしまうと僕はずっと思っていた。
だけど魂だけは別だった。魂は川の上を自由に飛び回っている。
僕はある魂が、タコのような柔軟な体で、ねりりし、はららしているのを見たし、真っ暗な夜、帽子をかぶり、おわあ、おわあと叫んでいるのを聞いたことがある。
ゆあーん、ゆよーん、ゆやゆよんと、ブランコに乗って自分の骨を眺めているとぼけた魂もいる。
11.子供の頃の僕は‥‥
子供の頃の僕は、大人たちの目には元気のないおとなしい子供のように映ったことだろう。だけど本当はそうじゃないんだ。僕にとって外の社会は見知らぬよそ様の家だった。誰に遠慮することもない自分の世界に浸っている時は、生き生きと快活に飛び回っていた。
子供の頃、僕は壁になったりネコになったりすることができたと言ったら、誰が信じるだろうか。それだけじゃない。僕は透明になったり他の人間に変身したり、人の足音を遠くから聞いたりできた。
僕は忍者だったんだから。
川を渡ることが当たり前のように思えてきた頃、僕はもうそんな遊びに飽きてきた。本当に人の役に立つ、新聞に載るような本物の強盗や誘拐犯を捕まえる、勇気ある忍者少年になりたかった。
僕は白い紙を八センチぐらいの幅に切り、それを五〇センチぐらいの長さになるまでつなぎ合わせ、いつでもポケットの中に入れて持ち歩ける小さな巻物を作った。その巻物に、いろいろな物からヒントを得て自分で考え出した忍術を書き記していった。そしていくつかの術も実際に成功させた。
僕が実際に試してみて成功した術としては、例えばうなぎの術と名づけたものがある。
追ってくる敵に捕まりそうになった場合、敵の両手が僕の体をつかんだその瞬間、自分の体を一回転させると、敵は手を滑らせてつかめない。それを捕まりそうになる度に何度も繰り返すと、永遠に捕まえられないことになる。
他には、頭が悪くて相手の言っていることが理解できないふりをしたり全く違う返答をする術。
気違いのふりをして相手に恐怖感を与える術。これらは知らない大人に叱られた時などに有効だった。
ふくろうの術は、自分の体はそのままで三六〇度見渡せるところからその名がついた。すなわち、後ろを振り向かずに背後の様子を探る方法だ。小さな手鏡を持ち歩くのはもちろん、建物の窓ガラスや、停車中の車のミラーや窓ガラスなどを利用する。背後の人間に気づかれずに目玉だけを最大限に動かして、反射するものをいち早く見つけ出す能力が要求される。
動物の名前がついたもので他に覚えているものは、タヌキの術がある。これは寝たふりの術という意味だ。子供が寝ている際に時々する引きつったような動きを研究したり、寝息のたて方が自然に聞こえるようにその強弱を練習した。昼寝をしていると見せかけて薄目を開け、周囲の人間の反応を観察し、術の完成度を確かめたりした。
実際には試したことはなかったが、敵に攻撃を仕掛ける術としては、ごめんの術、合図の術、落とし物の術、目潰しの術がある。
ごめんの術は、ごめんごめんと何度か頭を下げて謝るふりをして、その下げた頭で相手の顔面を強打し、ひるんだ隙に急所を蹴り上げるというものだ。合図の術は、敵に凶器などを突き付けられた場合、目だけを敵の斜め後ろにほんの少し動かし、あたかも自分の仲間がそこにいるかのように合図を送るふりをし、敵が後ろを振り向いた隙に攻撃をする術。
手にもっている物をわざと落とし、それを拾うと見せかけてその手で相手の急所を攻撃する落とし物の術、ポケットに入れておいた砂を相手の目に投げ付ける目潰しの術。
知らない人の後ろを尾行する練習、高い塀をよじ登る練習、塀づたいに走る練習などもした。
何日も家に帰れず野宿をしなければならなくなってしまった時のために、薬草や食べられる植物の知識も必要だった。山道を疲れないで歩く術や、暗い所でも見える術、目の疲れを取る術や、喉の渇きを癒す術、相手の心を読む術、そして音を立てずに歩く術、音を立てずに速く走る術なども考え出した。
実際、決して足が速いとはいえなかった僕が、音を立てずに速く走る術で走った時に限って、近所の子供たちの誰よりも速かった。
初めはその不格好な走り方を笑っていた彼らも、競争しても勝てないことを知ると最後は尊敬の声に変わっていた。
僕のポケットには七つ道具と称して、伸び縮みするラジオのアンテナ、鎖、壊れた時計(これらは、拾った物だが)、それに小さな鏡、パチンコ、傷薬‥‥などが、いつも入っていた。
12.父の職業は‥‥
父の職業は画家だった。
僕たちの住んでいた家は、父が挿絵を描いて建てたといつも自慢していたが、ようするに本業の油絵ではそれほどお金を稼げなかったということだ。
部屋は四つあり、二部屋が板の間で、二部屋が和室だった。板の間の一つはダイニングルームで、当時としては椅子に腰掛けて食事をとるのは珍しく、父の趣味嗜好が反映されていたのだろう。もう一つの板の間に例のソファーが置いてあった。
屋根裏部屋が、父のアトリエだった。西洋画の画集が本棚に並び、その中には赤面してしまいそうな裸の絵もあった。僕には、何で父がこんな本を好んで見るのか見当もつかなかった。僕の頭は、既に、常識や世間体で物事を判断する大人たちの影響をたくさん受けていた。「裸はいやらしいもの」それは大人たちによって僕の頭の中にたたき込まれた感情だった。
父が絵を描いている時は、絶対に部屋に入ってはいけないと母から厳しく言われていた。だけど一度だけ、父が絵を描いているところを見たくて、わくわくしながら屋根裏部屋へ足音を忍ばせて上がっていったことがある。白いシーツが天井から吊るされていて、その向こうで父が絵を描いているようだった。鼻をつく油絵特有の揮発油のにおいの中で、キャンバスに筆を走らせている音が聞こえていた。
「誰だ? ワタルか?」
父の声に驚いて階段を降りようとした時、緊張感のない妙に馴れ馴れしい口調の女の声がした。父に向けて話しかけた小さな声なので、何て言ったのかは聞き取れなかった。父と女の笑い声がして、僕は二人にからかわれたような気になって逃げ帰った。
見てはいけないものを見てしまった時のように、心臓がドキドキした。
あのシーツの向こうに女が寝ていて、父がそれを描いている。きっと女はいつか見たあの西洋の絵のように全裸に違いない。誰もが洋服というものを着て生活をしている家の中に、まるで滑らかな器物か何かのように女の裸が転がされている。その異常さを想像すると、震えが止まらなかった。
夕方になると、父はモデルの女と連れだって出ていった。窓越しに見た女の顔は、まだあどけない子供のようだったが、父と腕を組んで歩く様は、商売女のように手慣れているようでもあり、そういったところは母よりもずっと大人の女のように思えた。そして父はいつも夜遅く、僕が寝てしまった頃、酔っ払って家に帰ってきた。
そんなわけで、子供の頃の僕は父の顔をあまり見なかったし、話をしたという記憶もあまりない。
母は昔、父の絵のモデルをやっていたらしく、ほっそりとした美人だった。透き通るような白い肌は、頼りない蜻蛉の弱さを連想させて、いつも、守ってあげなければいけないような気持ちにさせられた。
母や僕たちがこちら側の人間なら、父は向こう側の人間のようだった。そして僕の使命は、こちら側のものを守ってあげることのような気がしていた。こちら側は、優しいけれど弱々しくて脆くて、寒いすき間風の吹く世界だった。あちら側は、べっとりと重く、バランスの悪い、見せかけの寂しい世界のようだった。どちらの世界にも言えることは、年中、衣服をズッシリと湿らす雨が降っているということだった。
雨は降り続き、いたる所に川を作った。
川は、いつものようにあらゆるものを容赦なく飲み込んで流していった。
僕たちにできることは、じっと耐えることだけだった。あたたかい光りに包まれるように幸福だった僕の家庭が、だんだんと冷えていき、会話がなくなっていったのは父のせいでも母のせいでも僕のせいでもないと思う。
父としての、母としての、子供としての役目をちゃんと果たせなければ、それは家庭崩壊を意味することはわかっている。だけど、その役目は愛情の上に成り立っていたわけだし、どんな場合だって愛情が壊れていくのは、誰のせいでもない。
僕たちの今生きている社会は、どうしても家族が別々の方角を向くようになっていて、外の世界では、鬱陶しい雨に打たれ、家というのは疲れ切って帰ってくるだけの場所になってしまった。そのせいだと僕は思う。
僕は父の仕事も父のことも、これといって好きではないと思っていた。もちろん嫌いではなかったけれど。
本当は、心のどこかで父の仕事も父のことも認めてあげたかったに違いない。ただ向こうが僕を受け入れてくれなかったから、僕は拗ねて彼らを愛そうとはしなかったのかもしれない。
だけど実際のところ、向こうが僕を受け入れてくれなかったのではなく、僕が常識という曇りガラスを間に立てて向こう側を見ていたのだろうか。父の方が子供の僕よりずっと純粋で、自分に正直だったということかもしれない。
「お前は絵描きにはなるな。絵の世界はちっとも純粋じゃない。むしろ絵の世界ほど純粋じゃない」そう言った父の言葉を思い出すと、父は純粋に絵の世界で生きようとして敗れてしまった可哀想な人間だったんだ、と思わざるを得ない。
13.僕の家から少し歩いた所に‥‥
僕の家から少し歩いた所に、八十坪程の広さの空き地があった。
いらなくなった電化製品や家具やバスなんかが捨ててあり、ほどよく伸びた草むらは、忍者だった僕の隠れ家には最適の場所だった。
捨ててあった冷蔵庫にマジックで同心円を描き、それをターゲットにして、よくパチンコを打つ練習をした。射程距離をのばすだけでなく、走りながらとか、地面に寝転がって打ったりもした。僕の右目と標的を結ぶ直線上に、パチンコの中心と小石が来るように合わせて、息を止め一気に放つ。
照準を同心円の中心に合わせた瞬間の、世界が凝縮されたような気分が好きだった。
僕はその単純な形の中に、世界をギュッと押し込めて小石を放った。
父を虜(とりこ)にしている絵の中の女たちの重たく熟れた乳房に向けて、大人たちのつまらない日常や嘘や母を苦しめる貧しさや不幸に向けて、僕の行く手を遮る物や僕を混乱させる不可解な物に向けて、そしてもちろんこれから戦っていく悪党に向けて、何発も何発も打ち込んだ。
そんな僕をいつもじっと見ていたのは「優しいおじいさん」だった。
それは打ち捨てられたボンネット型のバスで、窓ガラスは全て割られていたが、座席はそのままだった。車輪はついてなく、少し左へ傾いている姿は、まるで僕に向かって微笑みかけてくれているようでもあった。
パチンコで失敗してうっかり独り言を漏らしてしまった時など、誰かに聞かれてしまったような気がして辺りを見回すと、いつも物知りの優しいおじいさんのような暖かい彼の視線があった。
忍者の訓練に疲れると、バスの屋根の上に乗り、寝そべって空を見上げた。人間は、空を見上げると、勇気や自信が湧いてくるのは何故だろう。僕は、やがて一緒に戦ってくれることになる有能な仲間の出現を感じた。僕の無言の命令にも迅速に行動してくれる頼もしい仲間。
僕には分身の術はできなかったが、ポケットに入るくらいの小さな人間を作れば、敵に見つからず行動させることができるし、どこへでも一緒に連れて歩ける。
生物が細胞でできているなんて知らなかった頃だ。形状が似た物を集めてきて、それを人間の体と同じに配列し組み合わせれば、人間ができないわけがないと考えた。
例えば血の代わりに薄めたケチャップ。血管の代わりに細い透明なビニールの管。脳みその代わりには台所のみそ。目玉にはビー玉。髪の毛には黒い毛糸。胃には小さな風船。歯には白い石ころ。骨には針金。それらのものを組み合わせれば、本物の人間が作れるに違いない。
粘土を買ってきて人間の形に広げ、その上に図鑑を見ながら内蔵を置いていく。困ったのは心臓だ。図鑑には、心臓は精巧なポンプですと書いてあった。水に浮かせて空気を送ると両足を蹴って泳ぐかえるのおもちゃがあったので、そのポンプの部分を切り取って使った。
口の部分から細いホースを引き、胃の役目をする小さな風船につないでビニールテープでとめ、風船のもう一方に穴を空け、再び細いホースを肛門まで通す。これで消化器官の通路はできあがった。
次はポンプに細い透明なビニールの管をくっつけ、人体を一周して、やがてポンプのもう一方の端に戻るようにした。
最後にポンプの上の管をはずし、そこから水で溶いたケチャップを入れてできあがりだ。図鑑通りに内蔵を並べ終えてから、その上を人間の形に粘土で覆った。毛糸の髪の毛を生やし、ビー玉の目と石ころの歯をはめ込み、耳と鼻の穴を空けた。
出来上がった物はとてもポケットには入りきらない物になってしまったけれども満足だった。後は僕が作った人形に生命が宿ることだ。
窓ガラスと障子に囲まれた日当たりのいい縁側が僕の部屋で、ミカン箱が机がわりに置いてあった。彼をその上に横たえて、毎日、夜寝る前と朝起きてからの二回、両手を合わせて祈った。彼に命を与え賜え、と。
僕が寝ている間に動いているかもしれないと思って、夜中、布団から抜け出して、そーっと障子を開けてみることもあった。学校へ行っていても、彼が歩いてすぐ近くまで来ているような気がして、窓の外を見てばかりいた。
さて、皆さん、僕の泥人形は動き出したと思いますか?
そんなバカな話には付き合ってられないよ、とあなたは言うかもしれない。だけど七日目の朝に彼は話し始めた。それも、想像もしなかったような方法で。
つづく
ここから先は
¥ 200
長い文章を読んでくださりありがとうございます。 noteの投稿は2021年9月27日の記事に書いたように終わりにしています。 でも、スキ、フォロー、コメントなどしていただいた方の記事は読ませていただいていますので、これからもよろしくお願いします。
