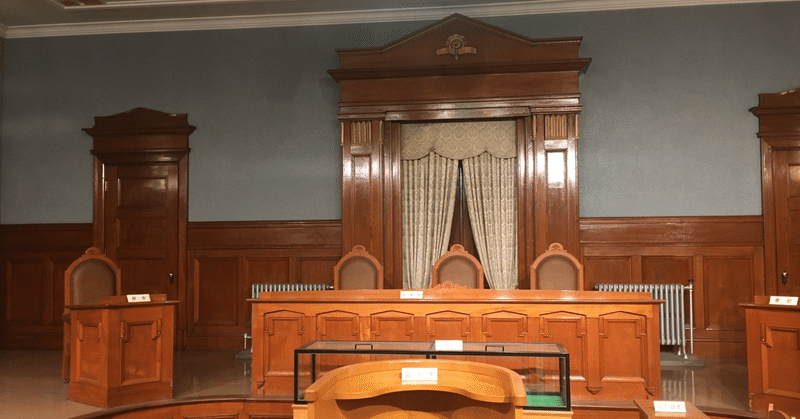
大島訴訟(その1)【やんわり租税法 No.3】
こんにちは、マークです。今日も一緒に勉強していきましょう。
今回は初の判例を取り上げてお届けするnoteです。
取り上げる判例は大島訴訟(最高裁昭和60年3月27日大法廷判決)と呼ばれる事件です(別名「大嶋訴訟」、「サラリーマン税金訴訟」)。
この判例は税法関連の中でも最も有名な判例の一つです。
争点としては比較的シンプルなものではありますが、No.1で取り上げた租税法律主義やNo.2で取り上げた租税平等主義の考え方も判例の中で示されており、とても興味深い判例なのでじっくり見ていきましょう。
今回はまず原告の主張と裁判所の判断の勉強に留めて、次回はちょっと深めに考察をしていきたいと思います。
とはいえ、裁判を扱うので今回も少し難しい部分も出てくるかもしれませんが、このnoteの本旨に沿って、なるべく簡単な表現を心がけていきますね。
ではさっそく全体の流れをみていきましょう。
1.どんな事件か
D大学の教授だったX(原告)は、法律上は確定申告の義務がありましたが、給与所得者(サラリーマン)に対する課税は憲法14条1項(法の下の平等)に反しているとして、確定申告を行いませんでした。それに対して当然税務署は課税処分を行いましたが、これを不服としてXが税務署長(≒国)を相手取り、訴えたものです。
2.Xの主張
Xの主張は大きく分けると以下の太字で示した部分です。これらを理由として平等権が侵害されている、と主張したわけです。細かい点は後程説明していきますので、言葉の意味を考えすぎず、なんとなく読んでいってください。
⑴給与所得は事業所得等のように必要経費の控除が認められていない。
⑵給与所得者は事業所得者等と比べ捕捉率が高く、不利益な扱いを受けている。
⑶事業所得等には各種の特別措置があり、給与所得に比べ優遇されている
では、⑴~⑶の主張の細かい点を、なるべく簡潔に見ていきましょう。
まず、⑴からです。所得税法では私たちが日常生活で得たお金は10種類に分けられ、それぞれ異なる方法で稼ぎ(所得)の計算がされ、その額を基に課税がなされています。
入ってきたお金まるごとが「収入」で、税金の計算に使うのは「所得」です。
そのうち、サラリーマンがもらったお給料から得た稼ぎは「給与所得」、お店を経営している個人が得た売り上げから得た稼ぎは「事業所得」として分けられています。
このうち、給与所得は給料の額から「給与所得控除」というあらかじめ決められた概算の額を差し引いて税金が計算されます(給料-給与所得控除)。
一方、事業所得は「必要経費」という、売り上げを得るために必要な経費を個別に集計して売り上げから差し引いて計算されます(売上-必要経費)。
そこでXは「サラリーマンは給与を得るために使ったお金が事業所得の必要経費のように差し引けないのは事業所得者と比べ、不公平だ」と訴えたわけです。
次に⑵について。「サラリーマンの給料は会社など雇い主から支払われるもので、いくら稼いだかはしっかりバレるのに、事業所得者は売上漏れや、必要経費の水増しがあってもバレにくいのは不公平だ」という主張(バレる確率の格差=捕捉率の格差)です。
なんていうか、身もふたもない主張ですね。笑
そして⑶です。税法では、そのときどきの時代の政策に合わせて税金や稼ぎの減免が認められています。そこで「合理的な理由がないのに他の所得者(医者や農家)がサラリーマンに比べ色々な特例があるのは不公平だ」と主張しています。
Xは主にこの⑴~⑶の主張を根拠に給与所得者に対する課税は憲法14条1項の規定(法の下の平等)に反して無効であると訴えたわけです。
なるほど、確かに言われてみるとそうかな、なんて思えませんか?
かくいう僕も実は昔に同じことを考えたことがあります。
また、時代背景として、当時サラリーマンの数がどんどん増えたことや、高度経済成長期を経て重税感が増したという潮流に乗って、大島訴訟は一般社会の中でも大きな話題となったようです。
3.裁判所の判断(判旨)
結果としてXの上告は棄却(訴えが退けられること)されました。Xは原告であり、控訴人であり、上告人でした。
つまり結果として第一審から最高裁まで全ての裁判で主張が認められなかったわけです。
裁判所の判断は以下のようなものでした。
まず⑴の主張に対しての判断です。
①憲法14条1項における「平等」は単に全ての人を同じ扱いをするというものではない(違う性質の人に同じ扱いをするとかえって不平等を招くこともある)。
②つまり、憲法14条1項は「絶対的な平等」を求めるものではない。
③また、税金を納める要件を決めるのは難しく複雑であり、たくさんの情報や技術を必要とする。
④そこで税法を定めるときは、正確な資料やノウハウを持っている立法府(国会)に判断を委ねるしかない。
⑤よって、法律を定める目的が正当であり、明らかに合理性がないような場合でない限り、その法律が憲法14条1項に反するとはいえない。
このように判断し、給与所得の計算上、事業所得等と同様に必要経費が引けなくとも問題はないと考えました。
またここでは給与所得者同士でも解釈次第(例えば経費を入れるかどうかの判断など)によって税額に差が出ることや、その判断が正しいかどうか行政(税務署)がチェックするのに費用がかかってしまう、などの点も考慮されました(最小徴税費の原則)。
次に⑵に対する判断です。
①バレるかバレないかは法律を定める上の問題点ではない。
②つまり税務行政(税務署側)がしっかりチェックされれば所得間の格差はなくなる。
と立法の不備ではなく、行政上の問題だよ、と判断しました。確かにおっしゃる通りではあるのですが、私見を述べれば行政側の運用ができるように法律を整備してあげるのは立法側も協力するべきでは?とちょっと同情してしまうところですが、どうでしょうか。
そして⑶に対しては、
①(定められている優遇措置の合理性の有無はともかく、)仮に、優遇措置が合理性のないものだったとしてもそれは優遇措置それぞれの「有効性」に影響を与えるものであって、立法そのものについては憲法に反して無効とはいえない。
と判断しました。これは⑴の判断を踏まえてのものでしょう。
つまり、大島訴訟において主張された所得区分の違いによる課税の方法の違いが法の下の平等に反するか否かは、以下のように考えることができます。
「所得区分によって課税の方法が異なるのは、各種区分の性質を踏まえたものであって、立法者が合理的に定めたものであれば、その区別は憲法14条1項に反するものではない」
今回はこのようにまとめさせていただきます。いかがでしょうか。なんか堅苦しいかなー。
ちなみに、この判決の2年後には特定支出控除という規定ができ、一定の場合には給与所得者も支出に基づく控除ができるようになりました。
ただ、この特定支出控除も使いにくいもので、平成30年のデータでは適用者数が1,704人でした。給与所得者が同年5,911万人と思うと適用者数はかなり限定されていることがわかります(0.003%未満!!)。
裏を返せばそれだけ給与所得控除の額が大きいとも考えられますね。
僕の力不足で今回はちょっと「やんわり」ではなくなった感がありますが、重要な判例なのでできるだけポイントを細かく押さえさせていただきました。
さらに、次回も大島訴訟です。笑
今回の内容を踏まえて、より深く見ていきたいと思います。
概要については今回で一通りさらってあるつもりなので、次回のものについては興味のある方のみご覧いただければOKかと思います。
ではまた!お読みくださりありがとうございました。
《参考文献》(発行年順)
金子宏「大嶋訴訟について−給与所得課税のあり方−」税大ジャーナル
2007年
金子宏「租税法(第二十三版)」弘文堂 2017年
谷口勢津夫「税法基本講義(第6版)」弘文堂 2018年
公益財団法人 日本税務研究センター編「憲法と租税法」日本税務研究セン
ター 2020年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
