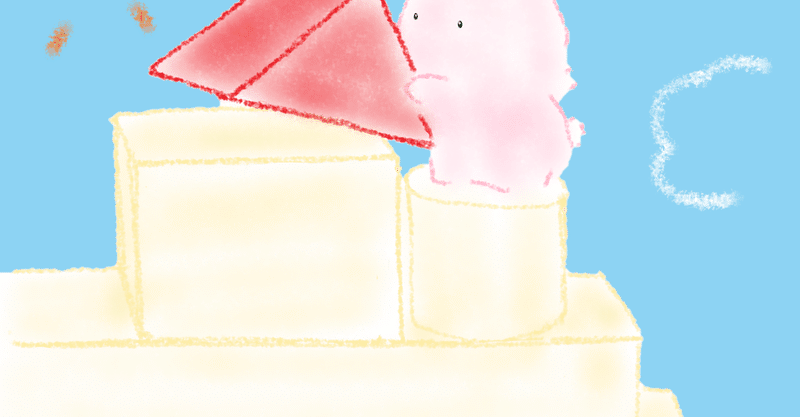
子どもを一人の人格として見て、社会の主体を育てる。
北海道にて、新しく「自由な学校」をつくっているNPO「まおい学びのさと」です!
代表・細田孝哉の過去記事をnoteに、アップしています^^
さて、今回は「子どもを一人の人格として見て、社会の主体を育てる」という内容。
前回の記事と併せて、ご覧ください♪
では、いきます!
↓ ↓ ↓
学習活動だけでなく、行事や日常生活も含めた学校生活そのものが
自由で民主的なものでなくてはならないということだ。
生活の中で一人一人の子どもを、身体的にも精神的にも未熟な分、見守り、支援する必要はあっても、大人より劣った存在として接するのではなく、人格としてはあくまでも対等な個人として見ることが大切だ。
自由な学校では、日常的な問題や行事づくりなどを学校構成員全体のミーティングで全員が対等な立場で話し合っていくことが必要になる。
「子どもは未熟で大人に従うべきものだ」
「大人は子どもに社会のルールを教え込む責任がある」
「半人前の子どもには大人と同じ発言権はない」と、うそぶく人もいるが、では、どこまでが子どもで、どこからが大人なのか。
子どもは大人より劣るのか。
確かに政治的には一応保護や支援の必要がなくなる年齢を一つの区切りとして選挙権や成人を設定せざるを得ない。
だが、実際は大人と子どもの境目に明確なものはなく、大人でも身体や精神に多くの保護や支援が必要になるのは当たり前である。
それでも一人一人は独立した個人であり、支援の必要性の多い少ないに限らず、どんな能力差があり、どんな個性があろうとも、人は一人の人間として尊重されるべき存在である。
知識や技能、経験の多い少ないだけが人の価値ではないし、どんな判断でも一人の判断として尊重されるべきだ。
とりわけ失敗を重ねながら学び成長する場である学校では、子どもの未成熟も発達過程の一段階であり、人格的不足と見なすべきではない。
大人だって同様に、人は常に発達の一過程にあり、大人も子どもも一人一人を学校社会の一構成員と見なすべきである。
大人も子どもも一人一人がその能力や経験を生かし精一杯考え判断し意思表明することが大切で、説得力があれば年齢に関係なく全体に認められるはずだ。
だから後述する「きのくに子どもの村学園」の全校ミーティングでも、多数決による単純な似非民主主義ではなく、とことん議論を尽くしみんなの納得を探ることが大前提だが、最終的な投票は生徒(子ども)たちも教員・学校スタッフ(大人)たちも一人一票である。
一般社会は選挙権を年齢で区切っても、学校は将来の社会の構成員が発達・成熟して巣立つ場として、その意思決定には全構成員が対等な立場で参加する民主的な体制をとらなければ主体的な参加意識が育つわけがない。
立法・司法・行政の三権を剥奪され、大人のロボットのままに据え置かれていては、いつまでたっても自立した社会人になれるわけがない。
もちろん学校はそうした失敗を重ねながら成長する場という特質があるからと言って、決して社会と隔絶され保護された温室ではない。
学校も大きな社会の中の一社会であるから、子どもたちの活動や学校の判断を学校内だけに留まらせず。地域社会とつながり、実社会から支援や教えを受けたり、逆に提案や支援をしたり、行政や企業にも働きかけるなど、相互のやり取りが子どもたちの思考や行動力・社会性の発達を促すことになるだろう。
どのような人も一人の人格として尊重され、対等な存在として認められ、社会に参加することが本当の民主主義を育てることになるのではないだろうか。
よろしければ、学校設立・運営へのご支援をお願いいたします。
