
今月読んだ本 (13)
2024年4月
今月もkindleで読んだ本の紹介から。今月はTED CHANG "EXHALATION"を読みました。日本語訳では「息吹」として文庫本になっています。 最近、Netflixで放送された「三体」を見ました。三部作の原作の第一部を映像化したものですが、実に見事な出来でした。原作をうまく世界向けにアレンジしているんですが、大事なところはきっちりとおさえている。例えば、冒頭の文化大革命のシーン、三体ゲームの中の人間コンピュータのシーン、船が強靱な超極細合成ロープによって真っ二つになるシーンなどなど。改めて「三体」という作品の面白さを再確認しました。この「三体」の著者はヒューゴー賞を受賞した中国人SF作家の劉慈欣ですが、彼の作品を翻訳してアメリカの読者に紹介した中国系アメリカ人のケン・リュウもまた優れたSF短編の書き手としてヒューゴー賞やネビュラ賞を受賞しています。そして、今回読んだテッド・チャン。彼は台湾出身のアメリカ人SF作家です。彼ら三人を頂点として、今や世界のSF界は中華SFの時代と言ってもいい状態ですが、かつてのSF少年だった私は、小松左京や筒井康隆の全盛時代にアメリカ国内で彼らの作品を紹介する人がいたらなと、今になって残念に思っている一人です。他にもそういう往年のSFファンは多くいるでしょう。今からでも遅くない。
さて、テッド・チャン。年をとって、長らくSFから離れていた私は、当代最高のSF短編作家だと言われる、テッド・チャンの名前を映画「メッセージ」の原作者として初めて知りましたから、最近のことです。彼はとても寡作で知られていて、映画の原作になった短編を含む「あなたの人生の物語」とこの「息吹」という二冊の短編集が今までに出版されているだけです。その二冊の短編集がいわばベスト版のようなもので、ほとんどの収録作品がそれぞれヒューゴー賞などの賞を受賞している名作ぞろい。表題作の「息吹」はクラークの名作「宇宙のランデブー」を抽象化したような作品でした。たしかに、一作一作がこれだけの密度と完成度で書かれていては、寡作になるのも無理はないと思います。長年のSFの読み手でもある松岡正剛さんは、最近、この「息吹」を「千夜千冊」で取り上げられました。そこで、テッド・チャンについてこんな風に書いています。「読む者の思索の植え込みに「SF的校閲」を作動させる才能にはそんなにお目にかかったことがない。科学的仮説にもとづく校閲を忍ばせる才能だ。」いかにも編集工学者松岡さんらしい文章で、やや難解ですが、単なる突拍子もないアイデア勝負ではなく、科学的あるいは哲学的知見にもとずいた深い思索があるということでしょう。私もそう思いました。テッド・チャンの作品は、読者を思索に誘います。
ここで余談。先ほどNetflixの話をしましたが、「冬ソナ」以来の韓流ドラマファンである私は、いつもは韓ドラばかり観ています。今月は「涙の女王」に夢中になりました。あり得ない設定だけれども波瀾万丈。「愛の不時着」以来の面白さ。まあ、同じ脚本家だから当然か。でも、韓ドラの困ったところは、読書の時間が減るところです。こまった、こまった。
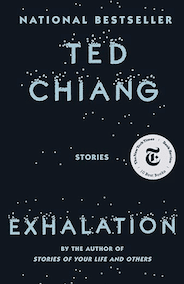
次に読んだのは、松浦寿輝「名誉と恍惚」。文庫本で上下二巻。1300枚の大長編です。松浦さんは私よりも三歳年下ですが、著者経歴を見ると、詩人、小説家、批評家、東京大学名誉教授。受賞歴は高見順賞、吉田秀和賞、三島由紀夫賞、芥川賞、芸術選奨文部大臣賞、読売文学賞、鮎川信夫賞、萩原朔太郎賞、毎日芸術賞、その他と続いて、この作品で谷崎賞を受賞しています。私の本棚にはミシェル・フーコーの文庫版コレクションがあるんですが、この訳者の一人が松浦寿輝さんということで、もうとんでもない業績の持ち主なんです。ここまで凄いともう別世界の住人だと思われて、作家としての人気に響くのではないかと思います。まあ、松浦さんは人気作家というタイプではないですね。作家として遇されているのかどうかもわからない。話がそれますが、この松浦さんが新聞で文芸批評を書いていた際に、村上春樹の新作について「なにかだまされたよう」と書いて、村上ファンの内田樹さんが怒っていたことを今思い出しました。
さて、「名誉と恍惚」のことです。結論を先に書くと、とても面白くて長さを感じさせませんでした。戦前戦中の「魔都」と呼ばれた上海が舞台のサスペンス小説です。上海の共同租界で警察官を勤めていた日本人男性が日本軍の謀略の犠牲になりながら、なんとか生き延びて復讐を誓う物語。この時代に魅力を感じる人は多いようで、数々の映画や小説が書かれました。私が好きな作品では、カズオ・イシグロの「わたしたちが孤児だったころ」や、J・G・バラードの「太陽の帝国」などがあります。バラードの自伝的作品である「太陽の帝国」は映画になりましたね。この「名誉と恍惚」も映画になるんじゃないかと、解説の沢木耕太郎さんが書いていました。沢木さんはこう書いています。「映画化に際しての問題は、金がかかりすぎる懸念があるというところかもしれないが、それ以上に、台詞の多くが中国語だということかもしれない。つまり、そのような中国語を操れる、若く魅力的な日本の男優がいないというところが最大の問題かもしれないのだ。」
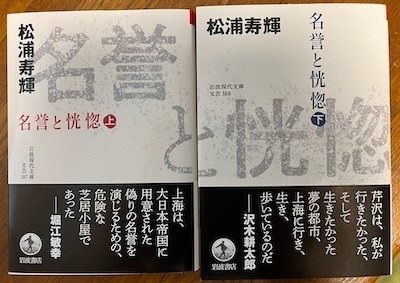
次に読んだのは、これも上下二巻の文庫本でした。橋本治「源氏供養」です。橋本さんは私よりも二歳年長でしたが、惜しくも70歳の若さで亡くなられました。「桃尻娘」でデビューした橋本さんは、もう天才としか形容の仕様がない人で、私の憧れの人の一人でした。私と同年で、同じく橋本治ファンだった内田樹さんには、なんと「橋本治と内田樹」という対談集があります。まえがきに内田さんがこんなことを書いています。橋本治と同時代に生きられて、よかった。なぜなら、橋本治の書いたことは同時代批評ではなく「祝福」だったから。橋本さんは、日常的だけれど根源的、瑣末なことにこだわっているようでいてことの本質に及ぶ。それが「橋本治的」ということである。橋本さんの書き物にはだから「橋本治」的なスピードがある。だからこそ、「窯変源氏物語」9千枚を三年間で書き上げるようなことができたのだ。
さて、この「源氏供養」は、単なる現代語訳ではなく、光源氏の視点から語り直した、橋本版の「窯変源氏物語」を書き上げた橋本さんが、改めて「源氏物語」について書いた長文エッセーです。まさに「瑣末なことにこだわっているようでいてことの本質に及ぶ」源氏物語論でした。たぶん、これから源氏物語を読む人にとっての最良のガイドブックになるのではないかと思います。そこには、本家の「源氏物語」を徹底的に読みこんで「窯変源氏物語」(私は未読ですが、)を書いた橋本さんならではの鋭い指摘が満ち満ちているわけですが、また、自らこれだけの長い物語を書いたからこそ、千年前とは言え、同じ作家仲間の紫式部の苦労もよくわかったんでしょう。「源氏供養」という題は、「紫式部さん、ご苦労様」という意味でつけたそうです。「鋭い指摘」の例をふたつだけ書いておきましょう。まず、「源氏物語の記述は、心理描写の向こうに情景が見えるように書かれている。近代人や現代人は、心理は自分の心の中に持っていますが、前近代の人間というのは心理を心の中には持っていない」という指摘。もうひとつは、「源氏物語」の登場人物の年齢についての驚くべき記述でした。まるで読書探偵のような推理の結果、橋本さんが得た結論は驚くべきものでした。当時の天皇は12歳くらいで父親になっていたかもしれないというのです。女性だって、12歳で結婚して14歳で母親になるのは異常ではなかった。十代前半の光源氏がどうやらあまり欲望がなかったようなのは、早すぎた結婚のせいかもしれないというんですね。どうやら、源氏物語の世界の登場人物達は、私たちが想像するよりもずっと若い、思春期を知らない人たちの物語だったようです。

次に読んだのは、林佳世子「オスマン帝国500年の平和」。先月、柄谷行人さんの「帝国の構造」を読んで、かねてから気になっていたオスマン帝国の歴史を詳しく知りたくなりました。塩野七生さんが描いた歴史エッセーの数々をイスラム側から読み直したような部分もあって、なかなか面白い本でした。オスマン帝国が現在のトルコ領内からではなく、バルカン半島から勢力を伸ばしたのだということや、オスマンの皇帝が就位すると兄弟をみんな殺す習慣ができたのは、かつて内部分裂に苦しんだからだという記述などはとくに興味深かった。現在の中東問題はトルコ問題だと言う人がいて、それはこの地域がかつてはオスマン帝国の領土だったからですが、林さんは、オスマン帝国はトルコ人の帝国でもイスラムの帝国でもなかったと指摘しています。その帝国内では、ユダヤ教徒もキリスト教徒もともに平和に共存していたからです。だからこそ、この本の最後に書かれた、今の中東の人々が、かつてはオスマン帝国の民として、500年間もともに平和に暮らしていたという共通の記憶を思い出してくれたらという林さんの願いに大きくうなずきました。残念ながら、ガザやパレスチナの現状はますます悪化しています。「民族主義」という病のせいです。現在、善とされる「国民国家」というものが、果たしてこのままでいいのかと自問せざるを得ません。

最後に読んだのは、これも文庫本で、岸政彦+柴崎友香「大阪」でした。他所から大阪にやってきて市内に定住した岸さんと、大阪で生まれ育って今は東京に住む柴崎さんが、それぞれの大阪について書いたエッセー集というより、これは短編小説集ですね。夫婦とも学者で、子供のいない岸さんが、愛する大阪の街で成長する自分の子供の姿を見たかったと書き、美容室を営む母に反抗して家庭でも学校でも居場所のなかった自分の居場所をつくってくれたのが当時の大阪の街だった、だから今も街のことを書き続けていると書く柴崎さん。そんなしみじみとした両人の文章がたっぷり収録されています。今は同じ大阪とはいっても岸和田市に住んでいる私は、柴崎さんより20年ほど前に、柴崎さんの隣の区で生まれ育ったので、彼女の書く大阪にはとても親近感を抱きますが、柴崎さんも岸さんも、大阪をただノスタルジックに描くことはしていません。大阪という大都市の嫌な面もしっかりと書いている。でも、愛があるんですね。岸さんは作家でもありますが、本業は社会学者です。それぞれの街を語る膨大なインタビューをまとめた煉瓦のように分厚い「東京の生活史」や「大阪の生活史」を編集するなど、素晴らしい仕事をされていますが、この「大阪」は、まさに岸さん自身による極私的「大阪の生活史」でした。彼はジャズマンでもあったんですね。その青春時代は実に興味深い。というわけで、この本は大阪にゆかりのない人たちにも是非読んでもらいたい本でした。
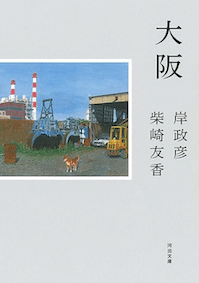
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
