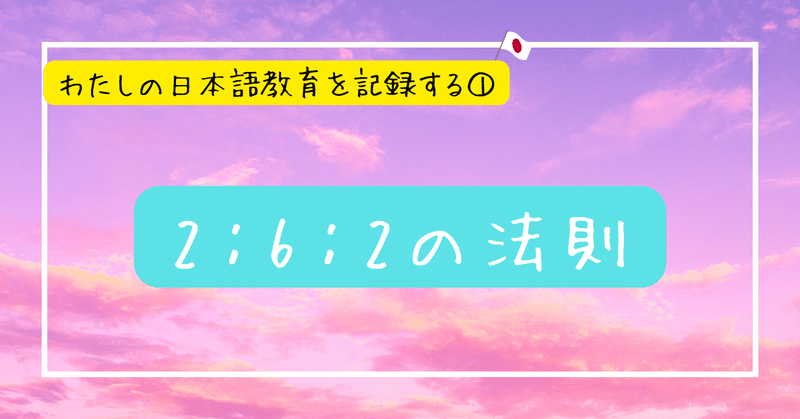
わたしの日本語教育を記録する①『2:6:2の法則』
『2:6:2の法則』をご存じでしょうか?
以前、一度に300人以上の日本語学習者を1人で教えていたことがあります。(約30人クラス×13クラス)
クラスによって年齢やレベルは様々なのですが、同時期にテストをやりました。テストを作成したのは私、採点も私です。
採点していると色々なことがわかります。
「この子はやっぱりこの問題よくできてる」「同じカタカナの間違いが多いなー」「この子話すのはけっこうできるけど書かせるとミスが目立つ」
など、
色々思いながら各クラス採点していったんです。
点数も記入していきます。
それで、13クラスもあるので、8クラス目の採点になったときに気が付いたのですよ。
「なんか、できてる/できてないの比率って、クラスごとで同じじゃない!?」
レベルは様々なはずなのに、同じ割合で、「良くできてる/ふつう/できてない」が構成されてる感じがしたのです。
そこで、実際に人数を点数ごとに区切ってみました。
すると、見事に「よくできてる:普通:できていない=2:6:2」だったのです、どのクラスも!!
すごーい!!おもしろい!! と思った私は、
試しにクラス内で、体感として、私を「好き/普通(別に気にしていない)/嫌い」な学生に振り分けてみたんです。
そしたら、あら不思議!!また「2:6:2」になったのです。
その後、
そういえばそんな話ネットで読んだことあるなと思って調べてみると、
『2:6:2の法則』(『262の法則』とも)でわんさか情報が出てきました。
それを知ってから、私はあんまりクラスの学生に好かれているとか嫌われているとかを気にしなくなりました。
どうせ大多数は「別に普通。どうとも思っていない」から。
そして2割にはどうやったって「嫌い」と思われるから。
好かれても自分を過大評価しない。だって法則だから。
テストではなるべく「良くできる」層を増やしたいと奮闘しますし、結果はついてきます。そしてもちろん、問題の難易度にも左右される。(でもそれでもだいたい262になることが多いのだけど)
一方で、人間関係は努力ではどうにもならない部分が必ずあります。
だから私は、日本語のクラスでは毎回、学生との関係においては『2:6:2
の法則』を信じて、気楽に仕事をするようにしています。
※先日、息子を連れて初めて遠出をしてみました。
移動に疲れた息子、目的地に着いた途端、ぐずりまくり、
楽しみにしていたことの半分もできないまま帰ってきました。
子連れで出かけるのってしんどいです。
「トライ&エラー」をモットーに生きている私ですが、もうこれはトライ
する気になれない…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
