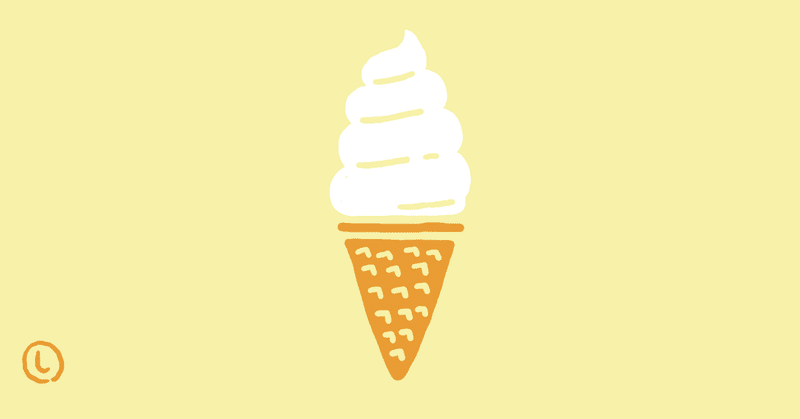
アポロと霜淇淋
旅行好きの祖母を台湾・台南に招待したのは2018年4月のことだった。
岡山市内、交通の便が良い街中に住む祖母は、喜寿を過ぎてなおフットワーク軽く、旅行会社のパッケージツアーにしょっちゅう参加していた。
それも、気の向くまま、国内外問わず。
彼女の夫であり旅行の良きパートナーでもあった祖父は、還暦で教職を退職後、悪性腫瘍により逝去している。
私が祖母との台南旅行を計画した背景には三つの要因があった。
ひとつは、祖母と一度、二人きりでの旅をしてみたかったこと。
二つ目は、格安航空会社(LCC)であるタイガーエア台湾が岡山ー台北便を増便したタイミングで利便性が高まったこと。
そして最後は、5泊6日という勤め人にとって贅沢な時間を創出するため、”おばあちゃん孝行”を建前としたことである。
本当のところ、祖母は健康な状態で長生きしたいと願う私の最も身近なロールモデルであり、無意識の部分でもかなり影響を受けていると思う。
そんな彼女と旅をすることで、どんな新しい気づきや変化が生まれるだろうかと、出発前からかなりワクワクしていた。
さて、ここでもうひとつの前書きを記しておこう。
当時、私は地元・岡山から瀬戸内海を挟んだ隣街・高松で会社員をしていたのだが、台湾人の彼氏と遠距離交際をしていた。大学での台湾留学時代に旅先の街・台南で出会った彼との交際は既に4年目に突入していた。
前年には、彼が幸運にもワーキングホリデー・ビザを取得し(ビザは抽選だった)1年間高松に滞在した結果、家族公認の関係にまで発展していたのだった。
そういうわけで、時々まとまった休暇をとっては台南に遊びに行く私にとって、彼氏の独り暮らしのマンション一室は第二の家であり、祖母との5泊6日の台南旅行は私にとって台南帰省計画でもあった。
旅行は台北で1泊した後、台南に4泊。立ち寄る観光スポットの目星はつけつつ、祖母のペースに合わせて柔軟に旅を楽しむことを心がけた。
台北では、台北101と国父紀念館を観光。私お気に入りの小籠包が美味しいレストラン「蘇杭餐廳」に祖母を案内し、ふたりで小籠包と繊細な味の中華スープに舌鼓を打った。
台南へは台湾の新幹線・台湾高速鉄道で移動。私はいつも通り彼の部屋に宿泊し、祖母には事前に彼が手配してくれた同じマンション内にある民宿の一室に宿泊してもらった。
当時、Airbnbの台頭も手伝って台南でも民泊ブームが過熱しており、インターネットで検索すると、なんと同じマンション内の1階にある美容室が奥にある空き部屋を民宿として運営していることが判明。部屋は民宿用に改装されており、トイレ・シャワー、Wifi、テレビ付き。祖母も快適に過ごせそうな部屋だと判断したのである。
台南では主要な観光地を祖母、私、そして彼氏の3人で巡ったはずなのだが、あれから数年の月日が過ぎた今、正直あまり覚えていない。
今思い返されるのは、祖母を台南のマンションに案内したとき彼女の口からぽろりと出たあの一言だ。
「あら、ここにもファミリーマートがあるのね」
マンション1階には祖母が泊まった美容室の他に洋服店、オムライス専門店、そしてファミリーマートが入居していた。
台湾ファミリーマートは現地で「全家」(チュエンジャー)と呼ばれ、すでに30周年を迎え、大手コンビニエンスストアの一つとして都市風景に溶け込んでいる。日本のファミリーマートも出資する合弁会社であり、看板は控えめに「全家」の文字が加わっている以外はほぼ同じデザイン、店内の商品陳列レイアウトも日本の店舗と似通っており、日本からの輸入商品も多く並ぶ。店員の制服姿や背後に並ぶタバコ棚など、レジ付近を見渡した印象は一見日本の店舗と変わりがないように見える。
ただ、店内に入ったときにふわっと鼻腔に入ってくる「匂い」が明らかに違う。ホットスナックの種類や味が日本と異なるからだ。日本で見かけない小ぶりな電気鍋の中には「茶葉蛋」という茶黒い汁に浸かったゆで卵、「關東煮」と書かれた台湾式おでんは日本とは味も具材も少し異なる。
この1階の「全家」には、ときどき彼と一緒に「霜淇淋」(アイスクリーム)を買いに行く。店員はコーンまたはカップの選択を促し、私たちは決まってカップを選ぶ。
店員が1つのカップにくるくると手際よく絞り出してくれた「霜淇淋」を、ふたりで小さなプラスチックスプーンを使い、分け合って食べる。「全家」の「霜淇淋」は、台南の長い猛暑期間を楽しくやり過ごすための甘味の一つとなっている。
そして、祖母や私、日本の家族にとっては、もうひとつの忘れ難いファミリーマート、「ファミリッテ」がある。
私が4歳の頃、まだ元気だった祖父は、私が両親に連れられ祖父母の暮らす岡山市内マンション一室に遊びに行くと、よく隣のビル1階に入居するファミリーマートに私を連れ出し、お菓子を買ってくれたものだ。
祖父は毎回、お菓子は何がいいかと私に聞いた。
私のお気に入りは、「アポロ」だった。
三角形でコロンとしていて、ピンクでイチゴ味の粒チョコレート。
ピンクのかわいいものが大好きだった4歳の私の心をとらえた。
祖父はいつからか、そのファミリーマートのことを「ファミリッテ」という愛称で呼び、足繁く通っていた。タバコを吸う人だったので、タバコを買いに行っていたのかもしれない。
祖母や母もつられて「ファミリッテ」と呼んでいたので、私にとって物心ついて初めて親しんだコンビニエンスストアは「ファミリッテ」だった。
祖父が亡くなった後、「ファミリッテ」もしばらくして店を畳んでしまった。祖母の家のベランダからも見えていたビル1階にあったはずの「ファミリッテ」のことを、家族も徐々に話題にすることはなくなっていき、私もすっかり忘れていた。そのため、祖母の口から出たあの一言を耳にするまで、私の意識に長らく「ファミリッテ」が浮上することはなかった。
しかし、台南で祖母の発した一言から「ファミリッテ」にまつわる記憶が蘇り、私の頭の中でぐるぐると巡った。「全家」と「ファミリーマート」も途中から仲間に加わって、私の頭からしばらく離れてくれなかった。
ふと、コンビニエンスストアはある種のパラレルワールド(並行世界)なのではないか、という考えが芽生えた。パラレルワールドとは、同じように見えるが少しずつ違う現実世界が同時並行に存在する世界であり、SF世界だけでなく理論物理学の世界でもその存在について研究されている。
例えば「全家」「ファミリッテ」は、どちらも私が一定期間慣れ親しんだファミリーマートの店舗で、その全体的な空間デザインは非常に似ている。1階テナントであり、店に入ると入店音が鳴る。いつものアレ(「アポロ」や「霜淇淋」)が欲しくなる。
もちろん陳列商品の種類や前述の「匂い」の違いなど、細かな相違点はあるものの、日々の暮らしの中でコンビニエンスストアを利用する場面はほぼ同じだ。
世の中のほとんどのコンビニエンスストアは画一化されたシステムや空間デザインが導入されているという特徴があり、そういった店舗空間が、パラレルワールドを感じさせる装置となっているのかもしれない。
その後、台南のマンションに居を移し台湾側で暮らす時間が増えたことで、パラレルワールドを感じさせる装置は他にもあることに気づいた。また次の機会に記したい。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!(*゚v゚*) お問合せはTwitterにてお願いいたします。
