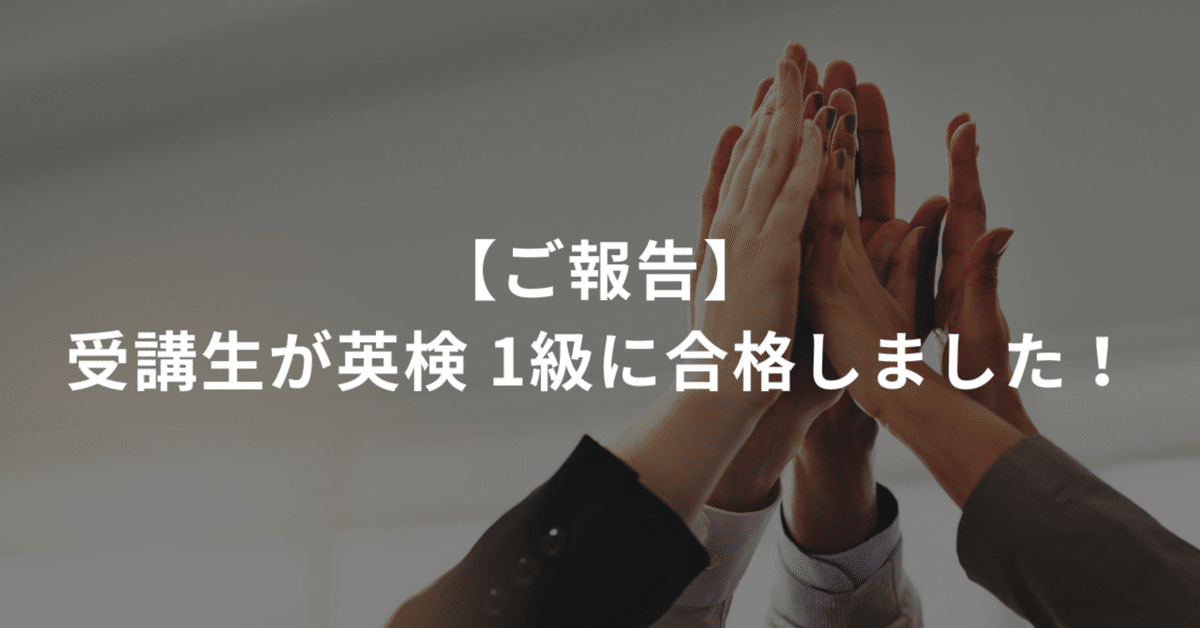
【ご報告】受講生が英検 1級に合格しました!
Ryoです!
先日の英検で
ある受講生の方が
目標としていた
1級に合格しました!
お喜びの声
↓
今回はその方が
英会話を習得するに至った経緯を
お届けします!
英語を勉強していて
英会話は苦手という方には
きっと参考になると思います。
英語上級者でも陥る英語学習の穴
英語の単語や文法を学ぶほど
陥ってしまう思考があります。
「正しく難しい英語を話さなければいけない」
これです。
その結果、
自分の既に知っている単語や文法を
使いこなすための練習をやめてしまいます。
翻訳機や辞書に
頼るようになってしまうんです。
本来、日本人が既に知っている
単語や文法だけでも
上手に使いこなせれば
かなりのことが表現できます。
ところが、インプット過多の私たちは
既に持っている知識を使いこなす前に
新しい知識を取り入れようとしてしまいます。
自分の頭に浮かんだ日本語を
英語でそのまま伝えることに
躍起になってしまうのです。
私たちは
日本語ネイティブです。
ですから当然、
頭に浮かんでくる日本語は
かなりレベルの高いものになっています。
それを、そのまま英語に直そうとすると
当然ながら使う英語も相応のレベルが要求されます。
英会話で必要なのは
既に持っている知識と技術の中で
言いたいことを工夫して表現することです。
頭の中に浮かんでくる日本語を
子どもに説明するように
シンプルにするための柔軟性。
これは、翻訳機や辞書に頼っていては
決して身につきません。
翻訳機の使い勝手が
どんどん良くなっている現代だからこそ
本当に英語を話せるようになりたければ
それを手放す勇気が必要です。
短くシンプルに表現する練習
今回、英検 1級を突破された平山さんは
英語を話すことに強い苦手意識を抱いていたそうです。
よく英検 1級の二次対策で使用される
【英検 1級面接大特訓】
という教材があります。
ここには模範となる 1級の二次試験の
模範解答例が掲載されています。
その英語のレベルは
非常に高いものです。
難しい語彙や
複雑な文法のオンパレードです。
そこで平山さんは
「丸暗記」という方法を
選択されたそうです。
この学習方法は
スピーチの型を覚える上では
有効な学習方法だと思います。
しかし、汎用性がないのが
この学習方法のデメリットです。
仮にスピーチは乗り越えられても
その後のQ&Aのセッションで
辛酸を舐める結果になってしまったそうです。
そこで、徹底して
【自分の言葉で表現する】
という学習方法を選択してもらいました。
言い方が分からない内容も
絶対に翻訳機や辞書を使わないこと。
これが私と平山さんの
唯一の約束事でした。
練習をしながら
平山さんは流暢さが高まっていくのを
実感されていたそうです。
同時に
「こんな簡単な表現で本当に合格できるのか」
と不安になったそうです。
複雑な表現でなければ
伝えられないような内容は
そんなに多くありません。
必要があるなら
複雑な文法や難しい語彙を
使えばいいのです。
必要がないのなら
無理して使わない。
実際に練習の中では
トピックに必要な
最低限の語彙は習得していただきました。
例えば安楽死を議論するのに
euthanasia 「安楽死」
という単語を知らなければ
議論がしにくいですよね。
それ以外は
とにかく短く、シンプルに
言いたいことをまとめる練習です。
自分の言葉で表現しているから
表現が定着するのも早く
幅広く応用して使えるようにもなりました。
何より、シンプルな文を
豊富な副詞と接続詞で
ロジカルに繋ぐのがとても上手でした。
ちょっとの思考の工夫で無限の英語表現を
平山さんが3ヶ月のセッションで得た
最大の成果は
自分の言いたいことを
自分の言える表現で伝えられる
という思考の柔軟性だと思います。
例えば、
「私、親バカなんです」
と言いたいとき。
「親バカって英語で何ていうんだろう…」
と考えて言葉に詰まってしまう人は
まだまだ思考の柔軟性に
改善の余地があります。
「親バカってことは子供が
めっちゃ好きってことだから…」
と考えられる人は
思考がとても柔軟な人です。
I love my kids very much.
と親バカ発言をすることで
自分が親バカであることを
相手に伝えることが
できるかもしれません。
正解は一つだけではありません。
自分の伝えたいメッセージは
無限の手段でもって
相手に伝えることができるはずです。
そんな英語の奥深さを
たっぷり堪能された平山さんは
英検 1級に合格したあとに
「ここがスタート地点です」
と語られていました。
平山さんの今後の活躍を
これからも応援しています!
本当におめでとうございます!
それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
