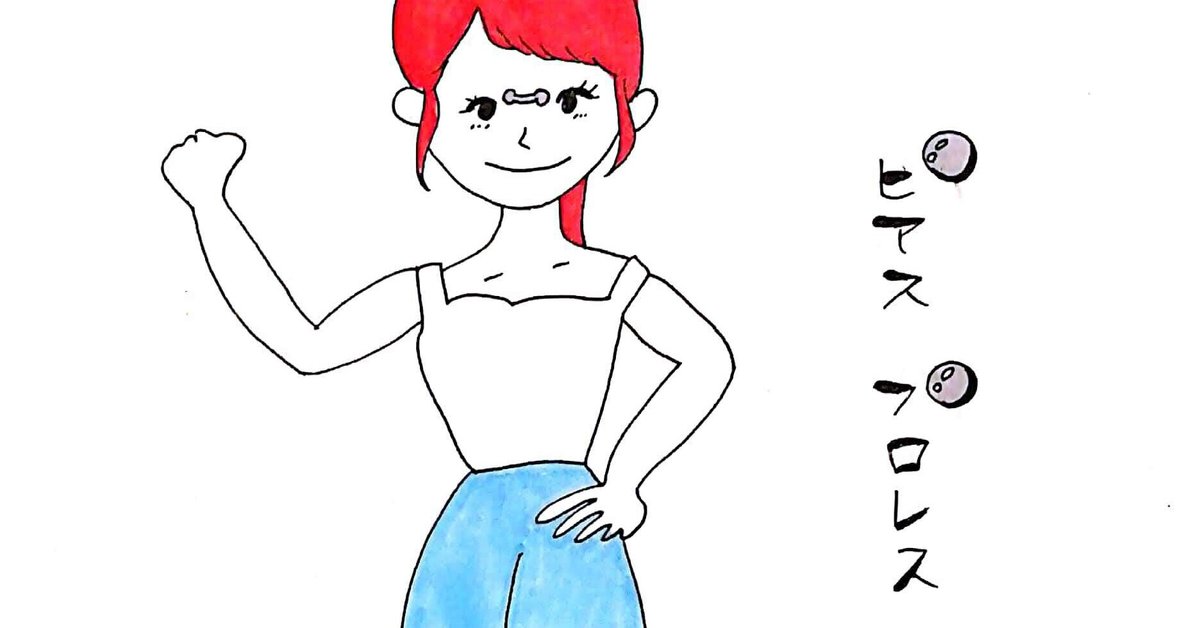
ピアスプロレス
(無断転載禁止)
とある路地。無数のピアスを顔中に空けた女性たちの張り紙。野獣のように牙をむき出した顔が載せられていた。昔は何の店だったのだろうか、人気のない店舗の前には白黒テレビが無造作に置いてある。よく見るとそのいかれた怪獣たちの争いがノーカットで流されていた。粗く暗い映像だった。一般客を対象としていないことは明らかだった。誰のためのものなのか。私の理解には及ばないと直感的にわかった。
プロレスの全盛期は昭和であろうか。平成生まれの私にとってプロレスはテレビの懐かし映像で見たり、年のいったお笑い芸人が話しているのが耳に入る程度だった。バラエティの罰ゲームでその存在を知ったダンプ松本、ブル中野。テレビ越しに見ても同じ人間と思えないくらい迫力があった。
その路地。地下へ伸びる真っ黒な階段。その入り口にあるテレビ広告は私の目を釘付けにさせた。今までとは桁違いの刺激は私を魅了した。
私は呆然と立ち尽くした。
しばらくすると、プロレスラーの集団が10人ばかり列をなしてやってきた。こちらに目もくれず、薄暗い階段を降りてゆく。全員女性。といっても女性を捨てきったように見える。刈り上げが大半だ。しかも一部伸ばした長い毛は揃いも揃って赤色だった。そしてピアス。尋常ではない量だ。街では出会うことができない量である。プロレスラー同士は会話もなく俯き加減でその闇に飲まれていく。その姿は人間らしさの面影はなく一種の奴隷的な相貌だった。
この人たちは私の想像出来ないような過去があり、現在があり、未来があるのだろう。
当時、私は東京都の郊外の町に住んでいる高校生だった。名前はマリアで、容姿は中肉中背。物語に描かれるのであれば、脇役にもなれないそんな女だと自覚している。教室にただ居る人。目立った特徴はない。悩みが人一倍あると感じて生きてきたが、客観的に見るとなんの変哲も無い幸せな家庭で育ってきた。そして高校生にもなると自分の将来について少なからず考える。この先、大学へ行って就職して結婚して子供を産むのだろう。そして、気づいたら平均寿命の86歳になって、人生短かったなあと思いながら死んでいくのかと予期していた。なぜなら、今までの経歴が度のつくほど平均的であり、今の自分も昔の自分が想像した姿だったからだ。そんな私はいつしか普通である自分にコンプレックスを抱くようになっていた。何をしても自分の才能は見つからない。努力したって平均点。努力しなくても平均点。うんざりだった。誰の口からも批判や讃称は出てこなかった。ある意味、欠点のない人間であるため、周囲の人は私のことを「なんでも(そこそこ)できる人」と捉えていただろう。平均的であるにもかかわらず、友達と呼べる友達はいなかった。なぜなら、このコンプレックスにもならないコンプレックスに共感してくれる人はいないと私が諦めていたからだ。
そして、現状を逸脱することこそが自分を成立させることのように思っていた。いわゆる自分らしくない場所・人・ファッションに興味を抱くようになった。YouTubeで歌舞伎町のドキュメントや貧困女性の実態や大家族の番組を見漁った。自分では味わうことのできない人生を追体験しようとしたのだと思う。音楽は負のオーラ満載で過激なことを言う弾き語りの人や、歌詞が暗に作詞者の幼少期の不幸を歌ってるような人の曲をよく聴いた。自分と違っているからかっこいい。一般家庭じゃなくて格好いい。普通じゃないレッテルを貼られているのがかっこいい。この人たちを非凡人というのであれば、私はすぐ天才と結びつけていた気がする。憧れを抱きつつ、自分はその世界に飛び込むことができないというもどかしさがさらに追求心を高めた。まるで二次元のイケメンしか愛せない腐女子のように、無い物ねだりをしていたのだ。
私は高校3年生になり、私の親類縁者全員が通ってきた大学受験をする必要があった。神学校であったため、周りの子達は熱心に勉強をしていた。そのため、人の真似をして私も勉強をした。平均点は全国模試の上位10%に入るような集団。普通の定義がよくわからなくなる環境だった。「周りにいる人が全てというのはただの錯覚でしかない」と頭では理解していた。しかし、理論と体感とのギャップは存在し続けた。
古典の授業。今日も無意味な時間がやってきた。からっぽの50分。教科書の書いてあることしか言わない先生。やたらと生徒に質問を投げかけ答えさせようとする。この先生は生徒とコミュニケーションを取れていると思っているのだろう、いつも満足げな表情である。私はこの人と目を合わさないようにしていた。ぼけーっと教科書を眺めて、時が過ぎるのを待つ。週1回私の人生の50分を浪費する。いつかこの感覚が麻痺して時間のもったいなさを感じなくなってしまうのではないか。今日も周りの人間は何食わぬ顔で椅子に座っている。いつも通り空白の時間が流れると教室中の人間は感じていたに違いない。
しかし、その日はほんの少し違った。私がトイレに行くために席を立ったからだ。この波は授業中何度も経験したやつだ。しかし授業早々この波が襲ってくるのは初めてだ。残り時間が長すぎて頭が真っ白になってくる。痛みのピークが来るたびに手汗をかき必死でこらえた。先生に「トイレに行ってきます」と言うのが恥ずかしい。今まで、授業中にトイレに行きたくなったことは何回もあった。その度に、限界を見てきたが最終的には授業が終わるまで耐え続けていた。その時だけ、神に願っていたのだった。しかしこの日、神は言うことを聴いてくれなかった。この日は限界の限界に達した。波が少しマシになった時と問題を解く時間が交差した時を見計う。そして、できるだけ静かに席を立ち先生にだけ聞こえる声で「保健室行ってきます」と言った。できるだけ体調が悪そうにゆっくりと教室を後にした。そして、ドアを閉めた瞬間にダッシュした。足音は響かせてはいけない。かかとをつけずにトイレまで走った。
やっとこさ間に合い便座で一息つく。あっという間に、死を見るほどの腹痛が嘘のように姿を消していた。トイレから出た後、保健室に行く必要がある。しかし、性格の悪そうな顔をした保健室の先生と対面する気になれなかった。かといって教室に戻ってしまうと保健室に行ってないことがバレてしまう。どこに身を隠すか迷った。と同時に、今置かれている状況そしてこの非日常感に興奮していた。平和に流れる時間を自分の力で打破した爽快感。たまらない。このまま走って自分の知らないところに行きたい。私の知り合いがいなくて、誰も私の行動を思いつかない場所に。その時、授業の終わりを告げるチャイムが流れた。あれから30分も経っていたようだ。もう先生は教室にいないはずだ。帰ろう。
教室に戻るとクラスメイトはご飯を食べ始めていた。あまり話をしたことのない子が声をかけてくれた。体調が悪く早退するという旨を伝え、その子以外とは言葉を交わさずに教室を出た。追いかけてくる者はもちろんいない。下駄箱を通り抜けると、見慣れた景色がなぜか新鮮なものに見えた。
テスト期間中でしか乗ることのできない空いた電車に揺られる。車窓から普段見ることのない景色を目で追い続けていた。そして、電車を降り、自分の部屋に直行した。親は共働きのため、もちろん家にはいない。制服を着替えて、お年玉の貯金財布から全額を取り出した。滞在時間10分という驚異のスピードで家を出た。行き先は決まっていなかった。知り合いがいない街、新しい街に行きたかった。直感で大阪に狙いを定める。大阪行きのぞみ号に乗り込んだ午後14時過ぎ。
新幹線の車窓からはどこまでも続く畑と連なる山が流れていく。そこに住んでいる人と私は一生出会う事がないんだろうなと思った。ホームを降りた。新大阪駅は東京にありそうな駅だった。
ホームの階段を降りようとした矢先、母から電話がかかってきた。母の帰宅時間であることに気づく。電話に出てしまうと現実に引き戻されそうな気がしたため、コールボタンを押すという選択はできなかった。かといって心配されても、警察に捜索願を出されても困る。考えた結果、真顔の自撮りを撮って送った。すぐに返信が来たが、内容は大体予想できたため未読のままにした。さあどこへ行こう。
案内表示に従って、ローカル線と思われる電車に狙いを定める。初めて見る漢字の組み合わせである。終点はわからない。電車は揺れ続けた。車窓からは低層のアパートや錆だらけの土管が見えた。貧困丸出しである。ガヤガヤしている大阪のイメージとは全く違う。この各駅停車で何駅見送っただろうか。人気のないホームと朽ち果てた看板はなぜか私を惹きつけた。そして、この大阪らしくない駅で降りてしまったのだった。そこは無人駅で駅員も居なければ改札設備もない。ただ切符入れがあるだけの小さな駅だった。無賃乗車し放題だなと思った。しかし、ここに来たいと思う人は限られてるだろうなと思い直し、お得感が一気に冷めた。
ぶらぶらと道を歩いていると、どうやら小さな商店街に入っていたようだ。商店街と言っても店は一つも空いておらず、街灯もポツリポツリとついているだけである。雨が降っていないのにジメジメした感じがした。前方に目を向けると、動くものを捉えた。よく見ると古いテレビには白黒の映像が流れていた。そしてあの団体。
女プロレスラーの行列が暗がりに消えた後、年配女性二人が歩いてきた。俯き加減でもなく、負のオーラを漂わせているわけでもなかった。顔中にピアスを開けているわけでもなかった。だから、短髪赤髪にもかかわらず私はその二人を普通の人間だと認識した。そして、プロレスラーたちと比べると格段に話しかけやすそうに見えた。好奇心の赴くままに声をかけた。普段は知らない人に声をかけることは、私の性格上ありえない。しかし、人目が気にならないこの地では大胆な行動が自然とできた。
「すいません。お時間大丈夫ですか」
宗教の勧誘あるいは素人ナンパ師かよと自分でツッコミを入れたくなった。胡散臭い声かけだった。
「はい」
と優しそうな方のおばさんが低い声で答えた。私は続けて、
「さっきの方々はプロレスラーですか」
と問うた。今度は笑われた。そして、
「日本で一番強い女プロレスラーだよ。あんたが知るようなプロレスラーよりもずーっとね。心も体も並外れた力があるんだよ」
と言った。気になる。もう一人の年配女性が帰りたそうにしてるが、ここで話を終わらせるわけにはいかない。思い切って、
「私奢るんで一緒に夕食どうですか」
と誘ってみた。するとまた、笑われた。
「こんな若い子にご飯誘われるとはね。面白い子だね。よし行こうじゃないか、アルも来るかい?」帰りたそうにしていた人はアルという名前らしい。私には聞こえない声で何かを呟き、プロレスラーたちと同じように暗闇の階段に消えていった。
優しげなおばさんはサチさんといった。サチさんの車でチェーンの居酒屋に来た。サチさんはお酒を飲み、私はジンジャエールを飲んだ。
「それって家出ってやつ?警察に私が誘拐しったって思われるのも面倒だし、とっとと帰った方がいいんじゃない?」
「いえ。家を出たわけじゃないんです。現に母ともメールのやりとりをしてますし。どちらかというと学校を出たって感じですかね。学校出。」母には自撮りしか送ってないことは言わなかった。ここで返されるわけには行かなかったからだ。
「で、今日の行くあてあんの?」
「ないです」
わざと人懐っこい笑顔をサチさんに向けた。
「助けてくれるよねって顔で見てるけど期待しないでよ。高校生か。うちのプロレスラーには高校生はいないなあ。十四の子が一人いてあとは二十歳以上の子たちだよ」
全く区別のつかなかったプロレスラーの中に私より年下の子がいるとは思わなかった。
「なんであの人たちはプロレスをやっているんですか。しかもプロレスと言っても普通のやつとはなんか違う感じがするんですけど」
最初に感じた疑問をぶつけてみた。
「そうだね、一般的なプロレスとの違いは選手の本気度かな。これは試合を見たらすぐわかるよ。で、やる理由は人それぞれだね。それを言ってくれる子もいるけど、言いたがらない子もたくさんいる。だから、私は察して、道場と試合の場を提供してあげることしかできない」
訳ありな人が多いことはその風貌でわかる。あのプロレスラーの姿が目に焼き付いて離れない。気になることも多かったが、珍しく自己顕示欲が開花した。そして、ひたすら自分の話をし続けた。生い立ち、学校の授業のつまらなさ、将来の不安。脈絡なく飛び飛びに話した。慣れない長話。ここぞとばかりに思いの丈を吐き出した。今日会ったばかりだからこそ、包み隠さず話せたのかもしれない。今日で最後かもしれないという思いが自分を強くさせたのだろうか。私が夢中で話してる間、サチさんは笑顔で頷いてくれた。その笑顔に助けられて、また話を続けたくなるのだ。私の話を遮ることはしない。そして、ちょうどいいタイミングで相槌や刺さるコメントをつけてくれた。トイレに行こうと立った時、ふと目にした時計の針は12時を回っていた。
「もうこんな時間ですね。久しぶりに思いっきり人と話した気がします。今日はどこか、寝る所を探します」
目線を外す。
「どうせ行くあてないんでしょ。強がらなくていいよ。今日は寮の空き部屋使っていきな。狭いけどね。」
そっと包み込むような言葉が降りかかる。サチさんは今日出会ったとは思えないほど親しみがある。まるで親戚のおばさんのようだ。とにかく、今日の行き先が決まってホッとした。
「ご厚意感謝します」
かしこまってお礼を言うとサチさんはさっきと同じようにくすっと笑った。
夜道を歩くと冷たい風が体を冷やす。あたりを見回しながら歩く見慣れない道。自分の存在とこの世界との違和感が肌で感じられる。隣にいるサチさんだけが心の拠り所である。連れてこられたぼろアパートのほとんどの部屋から光が漏れていた。2階建てのそのアパートは古く、天井に貼られている蜘蛛の巣を見る限り掃除は行き届いていないようだ。サチさんは私の前を歩き2階の角の部屋で止まった。大家さんが持っているような大量の鍵がついたホルダーから器用に鍵を見つけ出し、ドアを開けた。
「この鍵は一個しかなくて渡せないけど。明日の朝、10時に1回来るから、それまではこの部屋にいといてね」
サチさんはそう言うと私の返事を待たずに出て行ってしまった。部屋の空気は滞っていた。シーンと静まり返った部屋にポツンと立っている自分を俯瞰する。初めてのワンルーム。一人暮らしの気分だ。汚く小さな部屋だったが、私は密かに興奮を覚えていた。トイレ付き風呂なし。キッチンは流し場があり、ガスはついていなかった。お風呂に入りたかったが、諦めるしかなかった。服は着ている服しかないため、このまま寝るしかない。幸いベッドと布団はあった。いつ洗ったかわからない布団に抵抗する力は残っていなかった。布団に入った瞬間、意識がなくなり深い眠りについた。
目を覚ましたのは、チリンチリンという聞きなれないベルの音が耳に入ってきたからだ。数秒ほどで昨日の出来事がフラッシュバックし、非日常感に浸った。しかしすぐにベルが鳴ったことを思い出し、急いでドアを開けた。見ると、サチさんが笑顔で立っていた。
「昨日の服のまま寝てたんだね。ご飯できてるから下の部屋においで」
このアパート全体が寮ということなのだろうか。
下の階は上と同じように没個性なドアが並べてある。一番奥の部屋に連れられ入った。大家さんのために作られた部屋なのだろうか。それともいくつかの部屋の壁をぶち抜いたのだろうか。私が寝ていたところより数倍広い部屋だった。きれいに掃除がされているが、生活感たっぷりで物が多い。机を見ると一食の朝食が置かれてあった。食堂用の大きな机に一人分の食事だけがポツリとあるのはなんだか寂しいなと思った。
「ご飯出来てるから早く食べな」
人生で何回も聞いたことのあるはずの一節が新鮮に聞こえた。ご飯、味噌汁、目玉焼き、海苔という簡素なものだったがやけに美味しい。ひたすらご飯を頬張った。
「これ、部屋着とジャージね」
とサチさんの声。
サチさんの手元を確認すると灰色のスウェットと青のジャージだった。サチさんの中では私はプロレスを始めるという前提があるのだろうか。脳裏に昨日見た赤髪の行列がよぎった。私の返事を待たずしてサチさんは続けた。
「今からジャージに着替えな。練習もう始まってるから行くよ」
サチさんに連れて行かれたのは廃校になった小学校だった。朽ち果てた校舎は、人を寄せ付けない威厳を放っていた。サチさんは、当時の体育館と思われる建物へずかずかと入っていく。その中に入った途端、汗の匂いと凄まじい風景が飛び込んできた。昨日は俯き加減で活気のなかった赤髪の女性たちは、尋常でないエネルギーを放ちながら動いていた。私たちの姿に目をくれる者は一人もいなかった。突然、サチさんが大声で叫んだ。
「集合!」
練習の途中だったにもかかわらず、ピタッと動きを止めこちらに向かって勢いよく走ってくる。そして、私たちの前で綺麗に整列した。顔をよく見ると、すべての目線はサチさんの方に集まっていた。
「高校生の家出娘のマリア。今日から一緒に練習するからいろいろ教えてあげて。」
そう言い終わるとサチさんを含めすべての視線が今度は私に向けられた。
「マリアです。これからお世話になります。宜しくお願いします。」
咄嗟の一言は定型文だった。サチさんだけが笑顔で、それ以外人たちは表情ひとつ変えなかった。しかし、拍手は送られた。そして、見覚えのある人物がこちらに向かってきた。無愛想なアルさんだ。
「部活はなんかやってた?」
怒ってないのに怒っているように聞こえるタイプの口調だなと思う。
「陸上部に入ってましたが、高1の頃にやめてそこから何もやってないです」
真実を告げた。もともと運動神経は中の上くらいだった。運動した方が健康に良いだろうという理由だけで陸上部を選択した。しかし、入ってみると運動神経が上の上である人しかおらず、中の上だった私は陸上部の中では下の下になってしまったのだ。努力では周りに追いつくことができないと早々に悟り、プライドを守るために高1の夏でやめてしまったのだ。
「そうなんだ。見たところ、運動神経は悪くなさそうだね。プロレス経験はないよね?」
プロレスという言葉でさえ、私の人生の中に登場したのは数えるほどしかない。
「全くの初心者です。」
「じゃあ、プロレスについて少し説明しないといかんね」
そう行って私を体育館の隅に連れて行き、こう言った。
「ここでのプロレスはスポーツではない。パフォーマンスなんだよ。つまり、選手は観客に見せることを意識しておかないといけない。。戦う相手は全員一緒にやってきた仲間だけだ。でも、情が移り過ぎたら本気さが観客に伝わらない。逆に、本気で負かそうとしたら相手が死んじゃう。このせめぎ合いで試合は成り立ってる。この感覚を養うためにみんな必死で毎日鍛えてるんだよ」
知らなかった。プロレスは競技ではなく見せるためのエンターテインメントというわけだ。プロレスもボクシングも格闘技も全く違いがわからなかったが、プロレスとそれ以外に分けることができそうだ。
「んで、いかに熱い試合にするかは選手の体力とスキルにかかってる。体力つけるために筋トレは毎日欠かさずやる。スキルは教えてくれる人がいないから、自力で調べたり先輩を真似たりして習得する。以上」
そう言い終わるとスタスタと練習場に戻ってしまった。と思ったら、手招きして私を呼んでいる。私もいよいよスポーツ選手かと思い、苦笑した。アルさんの元へ行くとその隣には赤髪で派手な赤色の服を着た女の人が立っていた。顔を見るとぎょっとした。ピアスが唇に一つと眉に五つそして耳には数え切れないほどあるのだ。しかし、その人はスタイルが良く綺麗だった。
「マイ、基本的な筋トレとアップこの子に教えてあげて」
「わかりました」
マイと呼ばれた女性はアルさんに軽くお辞儀をした後、よろしくと言った。
「よろしくお願いします。マリアです。」
ピアス顔に対峙することに慣れていないが、平然を装う。
「練習中は私語厳禁だから後でまた話そう。じゃあ早速アップから。体育館の周りを5週走る。できればずっとダッシュで。それが終わったらラジオ体操第一と第二」
「はいっ」
と言ってみたものの、理解が追いつかない。ラジオ体操は小学生の頃以来、一回もしていない。第二に至っては、曲さえも覚えていない。ラジオ体操というワードに気を捉えているのも束の間、
「じゃあ一緒にやっていくよ」
外に出てマイさんは走り出した。それに続くようにして私も走った。想像以上の速さでついていくことができない。久しぶりの全力疾走で、足がもたつく。足が絡んで転びそうになった。陸上部を辞めてから、運動という運動をやってこなかったため、体力の衰えをひしひしと感じた。マイさんは待ってくれない。そして、後ろを振り返ることもない。マイさんのまっすぐ前を向いて走る姿はかっこよかった。こんな後ろ姿の人が顔中ピアスまみれであることを誰が想像できるだろうか。
昔から、走っている間は考えることが多かった。よくランニングハイになって無心になれると言う人がいるが、私には当てはまらなかった。その時に見ているものについて考えを巡らせるタイプだった。陸上部時代、二列に並んでみんなで走りこんだ。前に走っている人の着ているジャージの値段について考察した。ポニーテールの揺れの尊さに気づいた。スポーツ万能で全身に筋肉が付いているにもかかわらずお尻の脂肪は筋肉に変わることがない女の子の特徴を発見した。これらは自分だけの世界に入り込めた貴重な時間だったと思う。4週目。そろそろ息が切れてきた。足に乳酸という重りが溜まってきているのがわかる。もうマイさんの後ろ姿は見えなくなってしまった。そのうち、私に追いついてきて私の走っている後ろ姿も見られることになるのだろう。考えを巡らせる余裕はあるが、自分のフォームに気を配る身体的余裕はない。後ろから聞こえていた足音がパタリとなくなった。マイさんはすでに走り終えたのだろう。5週目。ラスト一周。私はペース配分が苦手だ。体力が全く残っていない。端から見ると、やる気のないように見られるかもしれない。しかし、自分ではどうすることもできない。完走まで3、2、1とカウントする。やっとのことで走り終えた。しかし、息が切れてふらふらした。しかし、涼しい顔をしているマイさんを見ると、弱音は吐けなかった。
「じゃあ、次はラジオ体操ね」
マイさんはケータイを取り出し、あの聞き覚えのある曲を流し始めた。ラジオ体操第一は覚えてるようだ。自然と体が動きだす。前にいるマイさんの動きは美しかった。ラジオ体操のプロではないかと思うほど、しなやかだった。体側を伸ばす時は、まさにばね仕掛けのようだ。ラジオ体操をする体力はもう残っていないと思っていたが案外できるものである。走ることでは使わない筋肉をほぐしている感覚がした。こんなに真面目にラジオ体操をしたのは初めてである。第一が終わるとマイさんはすぐさまスマホを手に取り、第二を流し始めた。これも聞き覚えがあった。マイさんの動きを見よう見まねで体を動かした。奇妙な動きの連続である。この時ばかりは無心に体を動かしていた。
「10分休憩。休憩はあそこのベンチね。」
ベンチに座るやいなや、マイさんが声をかけてきた。
「で、なんでここ来ることになったの?」
簡単に今までの経緯を述べると、驚いた顔でこう言った。
「こんな素直に話してくる子は初めて。ここの人たち過去とかあんまり言いたがらないんだよね。」
「じゃあ私はマイさんの過去は聞かないほうがいいですかね。」
深刻にならないように注意しながら言った。
「私?全然訳ありじゃないよ。なんてゆうか普通の大学生。最近休んでるけど、まあ大学生ってそんなもんだからね。で、14歳の妹もここでプロレスやってんの。マナっていうんだけど、私がやってたら変に興味持っちゃったみたいで。ある時、私の練習に隠れてついてきたことがあったんだ。そのことをサチさんが知って妹も練習させてもらえることになったんだよ」
姉妹でプロレスとは、なんとも奇抜な展開である。
「じゃあ次、本格的な練習するよ。」
マイさんは元気に立ち上がり、体育館に向かった。10分の休憩では、疲労は癒えなかったが仕方がない。体育館に入ると、他の人たちは練習を続けていた。体育館の隅で筋トレを教わった。陸上部で一通りの筋トレは制覇してきたつもりだったが、ここでは通用しなかった。全ての筋トレが独自で考えられたものだったからだ。動作がゆっくりにもかかわらずじわじわ効く感じがした。そのせいで私の衰えた筋肉はたちまち悲鳴をあげた。ひたすら、マイさんの指示に従って伸縮を繰り返した。脳みそを空っぽにして、ひたすらマイさんのペースについていった。色々なパターンの筋トレを繰り返した。そして、やけくそに体を動かすことしかできなくなった時、サチさんの声が聞こえた。
「練習終わり。整列」
全員駆け足で整列し、礼をした。練習後は皆疲れ果てたのだろう、頭を垂れて列をなして歩いて帰った。私が初日に見た光景そのものであると分かっていたが、あの時の淀んだ空気を感じることはできなかった。
ここでプロレスをしている人たちは集団生活をしている。私は寮の小さい空き部屋を使わせてもらうことになった。他の人は二人一組で一つの部屋を使っている人がほとんどだ。空き部屋があったのは少し前に一人のプロレスラーが失踪したかららしい。そして運良く、その部屋が私にあてられたのだった。買い出し・炊飯・掃除・洗濯は全て分担して行っている。新入りである私はマイさんとペアになって家事を担当するようになっていた。マイさんは4歳年下のマナという妹がいる。マナは人懐っこく、初対面の私にも明るく話しかけた。両頬にピアスを開けていて、それがえくぼのように見える。マイさんとマナは性格が全く違うが、お互いを受け入れている感じする。二人を見ていると、姉妹への憧れが強くなった。マイさんは大学生であるが、今は休学している。大学の講義中、この授業は今の自分には必要ではないと確信したと言う。反発するにはタイミングを逃したらこの先はないと考え、休学を決意したらしい。そして、その日に休学届けを提出したのだった。しかし、マイさんは大学を休学することをポジティブに捉えている。来るべき時が来たらその時に大学に戻ると言う。社会に一度出てしまうと、反発は難しいと悟っているようだった。だから、大学生活というモラトリアム期間で自分の中に潜む違和感を解消しようとしているようである。私も月日が経つと自動的に大学生になってしまうのだろうか。この状況の儚さを噛み締める。ここで生きている時間を寄り道している状況と仮定すると、いずれ本道に帰っていくのが自然であろう。
初日から数日が経ち、ここで一緒に暮らす人たちの顔は全員覚えた。生活も慣れた。そして、毎朝欠かさず親に自撮りを送っている。親は返信を何通も送ってきている。自分の感情が揺れそうでメールを開くことはできない。しかし、つい自分の安否を知らせてしまうのだ。両親と離れて気づいたことは、案外普通に生きられるということだ。寮のメンバーの食事を作ること。洗濯機を何回も回して干すこと。力を込めて床を雑巾掛けすること。慣れれば、ストレスなくできるものだ。マイさんとのペア制度も家事分担の行程を一周した時点でなくなった。寮の一員として、自立することができたのだと思う。
今日は、休みの日である。一週間のうち日曜日だけは練習がない。この日はそれぞれが自由な時間を過ごすのだ。マイさんは街に出かけるらしくメイクを施している。普段のすっぴんも綺麗なのだが化粧をする一段と美しく艶っぽくて大人びて見えた。
「マナはいつも一日中寝てるから、マリアは好きにして過ごして。じゃあ行ってくるわ」
マイさんは、明るくそう言うとすぐに部屋から出て行ってしまった。好きに過ごせと言われたが、私は何をしたらいいのか分からなくなった。実家にいた頃は、学校の課題、受験勉強、動画鑑賞など学生の義務とそれに付随する誘惑がたくさんあった。だから、時間はあっという間に過ぎ、暇を感じることさえなかった。しかし、今は義務も誘惑もない。あるのは自由だけだ。手持ち無沙汰にリビングへ行く。いつもは用意されている朝食はなく、机の上は整然としていた。冷蔵庫を開くとヨーグルトが大量に入っていた。一つ取り出し、椅子に座る。そして、甘いヨーグルトを食べた。最後の一口を食べ終えた時、アイという女の子が気だるそうに部屋から出て来た。アイの存在は知っていたが話したことは一度もない。アイが誰かと話している姿をほとんど見たことがない。運動神経が悪いのだろうか。練習中は、動くたびにふらふらと転びそうになっている姿がよく目につく。アイは転びそうになりながらも同じ練習を何回も繰り返すのである。
「おはようございます」
できるだけ明るく声をかけた。アイは表情を変えずに頭を少し下げるだけだった。私は一旦目を逸らした。しかしすぐに、アイの顔を確認すると初めて目があった。何かに怯えたような表情が垣間見えた。目があっただけなのにその体はビクッと反応し、すぐに目を背ける。そして何事もなかったように、通り過ぎた。その時、私はかつてないほどの好奇心にかられた。他人にそこまで執着しない私がこれほど誰かに惹かれるのは珍しいことである。この空間は自分の感覚までも歪めてしまっているのだろうか。俯き加減のアイは、私と同じように冷蔵庫からヨーグルトを取り出し、私が座っている所と一番遠い席に座った。一切、私の顔を見ようとしない。私はアイの顔をずっと見ていた。アイは端正な顔をしている。綺麗系のマイさんとは違って可愛い系である。あと少し堂々と振舞っていれば、確実にモテるという感じだ。アイの笑顔が見たい。衝動的にそう思った。
「アーイアイ、アーイアイ、お猿さんだよお〜」
静まり返る部屋。やってしまった。乳幼児のテーマソング、アイアイの歌を大声で歌ってしまったのだ。アイの名前と掛けたのだが分かりにくいボケであり、かつ分かったところで笑えない。病的なこの自分の衝動が恐ろしい。そして、それを人に見られているというのも恐ろしい。ふと我に帰り、恐る恐るアイの様子を確認する。私の後悔とは裏腹に、アイの口角は上がっていた。わずかだが、表情が柔らかになったのである。やってよかった、そう思った。客観的に見ると私は滑っていたのかもしれない。しかし、私は確実にアイの反応に救われたのだった。だから、私は滑っていないと心の底から思える。
翌朝、私は一番乗りで席についた。するとアイが現れ、私の隣にちょこんと座った。話しかける様子もなく、ただただ私の隣に座ったのだ。この些細な変化が嬉しい。物理的距離は心理的距離という心理学の知識は頭の中に入っている。昨日の一件が一つの起爆剤になったことは言うまでもない。ここでも一発何かかましたい気分だ。
「高橋愛、はるな愛、どっちも愛してるウYeah!」(ラップ)
ノリの良さだけが取り柄ですというような人が作りそうなクソつまらないラップを披露した。なぜか、アイの前では羞恥心がなくなる。バカにされることはないという安心感から生まれた状態なのか。アイを見た。また、歯を見せずに声を出さずに口元だけで笑っている。滑り芸を堂々とテレビで披露するお笑い芸人の気持ちがじわじわと分かる。たとえ、自分が恥をかいたとしてもその姿を見て一人でも笑ってくれればやり甲斐はある。アイの笑顔を見れるのは特別嬉しい。心を閉ざした人の笑みは普通の人の大爆笑よりも価値があるに違いない。プレミアがついているようなものだ。そして、私は味を占めた。アイに会うたびに粗悪なギャグを連発するようになった。アイの僅かな変化を見るのが快感になった。
ある朝、いつものように一番に席に着くとこの日もアイは私の隣に座った。そしてギャグを一発カマそうと思った瞬間、アイが口を開いた。
「ピアス開けなよ。」
それは、か細く幼い子が発するような声だった。初めてアイが話しかけてくれたので私は舞い上がった。そして、食い気味に話しかける。
「ピアス!?確かにみんな開けてるしね。アイはどこでピアス開けてるの?」
アイは顎と眉頭そして鼻にピアスを開けている。噂によると舌にも空いてるらしいが、まだ確認はできていない。
「spiderっていうとこで開けてる。」
根掘り葉掘り質問していくと、spiderは初めてプロレスラーたちと出会った商店街にあることが分かった。どんよりとした商店街の記憶が蘇る。思い返すと出会った日以来、その場所を訪れることはなかった。
「今度の日曜日に連れてってよ。場所わかんないし」
正直、一人であの商店街に行くこと自体勇気が出ない。今の生活への入り口であり、出口である気がするからだ。そこに行くと、この非日常空間が一瞬にして消えてなくなってしまうかもしれない。一人だと何が起こるかわからない。自分の心に従うと思いもよらぬ道を踏み出す可能性が高い。いまの現状がそれを証明している。とりあえず今は元に戻るわけにはいかない。もっとこの世界を深掘りたいからだ。アイが私を私の望む道に導いてくれるだろう。アイはコクリと頷き、ヨーグルト口に運んだ。
ピアスに対して偏見はないつもりだが、私の親類にはピアスを開けている人は一人もいない。つまり、ピアスを開ける開けないという会話は家で飛び交ったことがないのである。自分の意識がピアスに向くことがなかったため、それに対する好き嫌いの感情はない。ピアスへの思い入れがないからこそ、開けるのに抵抗がないのかもしれない。今更、あえて強い覚悟を持つことはない。「郷には郷に従え」の感覚で開けるのだ。開けよう。携帯を取り、いつものように自分の顔を写す。ピアスなしの姿を母に送ることができるのは数日の命かもしれない。ピアスを開けた私の姿を母はどう思うのだろうか。
日曜日。いつもより早く目が覚めた。紅茶を入れ、いつもの椅子に座った。そして、最後のピアスなし姿の自撮りを母に送った。寂しい気は全くしない。むしろ、清々しい。紅茶を飲み終えた時、アイが姿を現した。今日はいつもの水色のパジャマ姿ではなく、すでに着替えていた。黒いシャツに黒いレースのスカート。なかなか似合っている。おはようと言うとおはようと返してきた。アイの口数は日に日に増していた。と言っても、相変わらず私以外の人とは話さない。私の質問にはうろたえずに答えることができるのだ。マイさんから「マリアはどんな人にも順応できて、まさに理解のプロだね。」と言われたことがあった。自分では気づかなかった能力がここにきて発揮し出したのかもしれない。
見慣れない道を歩く。約1ヶ月間、家と練習場の行き来だけだったため、不思議とワクワクする。アイの横顔もなんだか嬉しそうに見えた。
「どこに開けるか決めた?」アイが小さい声で話しかけてきた。
「正直、決まってない。けど、みんなが開けてないところがいいな。耳とかはありきたりで面白くないなーって。アイは最初どこ開けた?」
アイはこっちを向いて舌を出してくる。見ると舌の真ん中に丸い銀色の金属が見えた。
「一発目、そこ開けたんだ。すごい!痛くなかった?」アイは首を横にふる。
「みんなが開けてないところで、パッと見て気づかないところに私は入れたかった。みんなと違うことをするのはそれだけで価値があると私も思うよ」
どうやら私の意見に賛成しているらしい。そして、このプロレス団体の人は全員spiderでピアスを開けてもらっていること、慣れると痛くないことを教えてくれた。
アイが立ち止まり、私の方を見た。筆記体のspiderの文字が見える。真っ黒でいかにも重そうな扉。普通に歩くと気づかず通り過ぎてしまうような場所であった。一見さんお断り感が漂っていた。入るのが躊躇われたが、アイは臆することなく扉を開けた。アイについてそっと私も入る。中は想像以上に明るい。奥には店主と思われる人がこちらを向いている。頭にヘッドドレスをつけたロリータファッションの女の人だ。原宿系の雑誌を立ち読みした時に見たようなゴスロリだ。ピアス屋にも関わらず顔には一つもピアスが空いていなかった。
「アイちゃん久しぶり!お友達?めづらしいね!今日、開けてくの?それとも、お友達の付き添いかな?」とても早口で質問を投げかけた。アイは最後の質問に対してのみ
「はい、マリアをお願いします」と返事をした。
「マリアちゃんっていうのね!可愛い名前!私はミミ!よろしくね!マリアちゃんはピアス開けんの初めてかな?見た感じどこにも開いてないけど」
「まだ開けてないです。しかも、まだ開けるところ決めてなくて。できれば私たちの団体の人がまだ開けてないところが良いです」
ミミさんは声を出して笑った。
「アイが最初に来たときも同じようなこと言ってた!普通、耳から始める人がほとんどだけどね。うーん」
ミミさんが私の顔をじっと見てきた。
「あっ!ここはどうかな!」
そういうと私の眉間のあたりをミミさんの指が触れた。
「ここに、ボディピアスを通すの!まち針みたいに!ブリッジっていう名前なんだけど、これならあなたの仲間達とは被らないよ!」
確かに、そこに開けてる人は見たことがない。眉頭に開けている人はいるが、眉間を串刺しにしている人はいない。しかも、それなら左右対称で美しいかもしれない。
「それでお願いします!あっ、おいくらですか」
今までお金のことが頭に浮かばなかったのが不思議である。自分の財産といえば残高三千円弱のPASMOとお年玉の数万円しかない。ピアスの相場が分からないため、気がきでない。
「あなたたちの団体の人はただで幾つでも開けれるんだよ!なぜなら、この店はピアスプロレスのスポンサーの一つだから!」
ピアスプロレスという聞きなれない言葉。
「あなたたちは私のピアスの広告塔でもあるの!試合を見に来る人の中にはピアスを見に来る人もいるくらいだよ!選手たちはみんな似合ったピアスをつけているからね!選手たちを見て開けたくなった人は、みんなspiderに来てくれるの!選手自身もピアスを努力の証って思ってる人が多いの!だから、試合のたびに一つずつ増やすレスラーも結構いるよ!」
稼ぎのほとんど無さそうなプロレスラーたちが大量のピアスを開けている理由がわかった。
「よろしくお願いします」
ミミさんはゴム手袋をし、針を用意する。針を見た瞬間、自分の鼓動が高鳴るのを感じた。アイは緊張感が全くない様子で横のソファでちょこんと座っている。もう引き返すことはできないと、腹をくくった。
「始めるよ!」
ミミさんの高い声が頭に響いた。そのタイミングで目をぎゅっとつぶった。すかさず
「力入れちゃダメだよ!眉間にシワが入っちゃうから!薄っ目を開けてるくらいの感じで!」
と言われた。仕方なしに目はそのままで、歯を食いしばった。激痛を覚悟する。針が左の眉間から入り右の眉間へ抜けていく。マチ針で止められる布の気分を味わった者はこの世に何人いるのだろうか。痛いが意識を失うほどではない。痛みはじわじわと続いた。この痛みが消える気配は全くない。このまま、この痛みと生活し続けなければならないのかと不安になるほどだ。
「よし!綺麗に開けれた!お疲れ様!」
ミミさんから手鏡を渡された。見ると、赤くなった眉間にピアスが突き通されていた。自分の眉間と思えないような違和感があった。しかし、左右のバランスは完璧で、まさに私が望んでいたフォルムになっていた。
「明日になると赤みが引けて、腫れが落ち着くから楽しみにしててね!なんかあったらいつでもここに来てね!」
「ありがとうございます。ミミさんにやってもらえてよかったです」
衝動的に手を伸ばし、握手をした。
帰り道、アイは何回も私の眉間についてるピアスを見た。その顔は私以上にニコニコしていた。
「似合ってるよ。なんか日本人じゃないみたい。」
「インド人的な?」二人で笑った。
次の日の朝、起きてすぐ洗面所の鏡で自分の顔を確認する。赤みが収まっていて当たり前のように金属が刺さっていた。目を大きく見開こうとすると鈍い痛みを感じるが普通にしてると痛みはない。そして、ケータイで写真を撮った。母はどう思うのだろうか。今撮った写真を消去し、笑顔を作って撮り直す。このピアスには笑顔が似合ってるなと思った。昨日、アイと笑い合ったことが脳裏に浮かぶ。自分のやる気ボタンと仮定して送信ボタンを押してみた。
「来月、試合があるから今日から試合前練習のメニューになります。基本的に全員出ること。じゃあ今日も一日頑張りましょう。お願いします」
「お願いします」
サチさんの挨拶で練習が始まり、各々が練習を始める毎日だ。しかし、今日はサチさんの最初の一言がいつもと違うことにすぐ気づく。
「マリアは入ったばっかりだから、まだ試合に出られないね。1ヶ月に1回試合があるんだよ。ちょうどマリアと出会った日が前回の試合だった。そうだねえ、次かその次の試合くらいがあんたのデビュー戦になるんじゃないかな」
「わかりました。でも、試合のやり方とか全然わかりません。今まで、筋トレや走り込みばかりで1対1で対戦練習したことないです」
「よし、わかった。1ヶ月半、試合に向けての練習をするか。レナ!」
サチさんはレナという女性を呼んだ。顔はもちろんわかるが、挨拶くらいしか会話したことがない。レナさんはクールな印象だ。そして、いつもユイさんという優しそうな女性と一緒にいる。
「レナは今月の試合、出ないよね。マリアの練習付き合ってくれる?」
「いいですよ。ビシバシ鍛えます。」レナさんは、冗談っぽく笑顔でそう言った。
この日から、レナさんとのマンツーマン特訓が始まった。レナさんはいつもハキハキとした口調で話す。と言っても剣がある感じではなく、楽しい人だ。
「試合の練習は、とにかく人と取っ組み合うこと」
レナさんは私の腕に手を伸ばす。次の瞬間私の体は宙に浮いた。そして、瞬く間に床に押さえつけられた。
「こんな風に両肩を床につけて3カウントを取られたらアウト。それと、リングの外に20カウント以上出ていたらダメ。あとは物を使わないこと。ここのプロレスはこの3つくらいしかルールがないんだよ。競技というか、一種のパフォーマンスだからね」
プロレスはパフォーマンスとサチさんも言っていた。プロレスを見たことがないため、想像がつかない。レナさんの攻撃から抵抗できなかった硬い体を起こしながら、レナさんの話に耳を向ける。
「だから、基本的に相手の技を受ける。で、自分が攻撃を始める直前だけ避けて、そこで初めて相手を攻める。技を受ける時も力を入れてないと、ふらついて怪我する。だから、受けの練習もしっかりする。相手と攻防のリズムが合った時、良い試合になる」
タックルの練習、投げ技、蹴り技。プロレスは様々な格闘技を複合させたものなのだろうか。レナさんは実演しながら説明していく。私はレナさんの攻めに対して、踏ん張ることができない。そして、あっけなく倒れた。体が吹っ飛ばされるたびに、自分のちっぽけさを思い知る。この時ばかりは小さな子供になった気分になった。
この場所では、プロレスに没頭するしか時間の使い道はない。周りに流されながら暮らしてきた日々とは正反対だ。臨むべき対象があり、それ以外の誘惑はほとんど存在しない。毎日、レナさんと向き合い取っ組み合う。帰宅後は筋トレや走り込みをするというのが日課だ。過去の日常が非日常になり、非日常が日常になった。しかし一方で、今の生活が自由な日常なのかは分からない。抑え込んでいた自分を解放したのか、狭い所に自分を押し込んだのかどちらなのだろうか。ただ一つ、理想の自分と仲間が望む自分の姿が初めてマッチしたと確信が持てる。だから、 プロレスの練習漬けになることに不信感を抱くことはないのだ。
ある日の練習中、サチさんに「レナとの取っ組み合いが絵になってきたね。」と言われた。笑顔を返したが、心の中では全く笑っていなかった。レナさんとの力の差は歴然だった。レナさんの体幹の強さ、無駄のない筋肉は私の皮膚を通してひしひしと伝わってくるのだ。やればやるほど力の及ばなさが身にしみた。だから、練習量を増やた。メニューを厳しいものに変えた。このプロセスをひたすら繰り返す毎日だった。
今日は試合の日だ。と言っても私は出ない。私とレナさん以外のレスラーの試合だ。この日は珍しく、私よりみんなは早く起きていた。マイさんの綺麗な横顔が目に入る。濃いアイメイクはマイさんを別人に見せた。そんなマイさんは、マナに化粧をしているところだ。マナは心地悪そうに、目を開けたり閉じたりしている。
「みんな外出てー並んでー」
サチさんの大きな声が聞こえた。すぐさま、レスラーたちは外に出て整列した。試合会場まで縦一列に並んで行くらしい。私とレナさんは一番後ろについた。サチさんとアルさんを先頭に歩く。
商店街に入る。Spiderの看板を確認し通り過ぎる。白黒のテレビ看板が見えた。初めてサチさんと出会った思い出の場所だ。そこで、みんな一斉に立ち止まった。相変わらず白黒のテレビ看板にはプロレスの映像が荒々しい画像で映っていた。しかし、あの時の違和感は姿を消している。今では純粋な懐かしみを感じるだけだった。真っ黒な階段を降りた先には、想像以上に大きいリンクとそれを囲む観客席があった。私とレナさんは観客席の列の席に座り、ほかの選手たちは裏の部屋に消えていった。隣に座ったレナさんはゆっくりと私に話し聞かせた。
「初めて、プロレスを見たときの記憶は鮮明に覚えてる。ちょうど私がマリアくらいの年の頃、プロレス好きな先輩に連れられてここにきたんだ。今までの人生の中で一番刺激的で。まあなんというか、陳腐な言葉になっちゃうけどそこから人生が変わったんだよね。プロレスはもともと親が好きで小さい頃よく見に行ってた。でも、どれも男の試合だった。迫力はあるけど、洗練されてない感じ。あんまり綺麗じゃなかったんだよね。暴力を武器に持った獣にしか見えなかった。だから、プロレスとは距離を置いてたんだ。」
男性への嫌悪感が伝わってくる。以前、マイさんからユイさんとレナさんは付き合ってるという話を聞いた事がある。プロレスがきっかけであるのかは定かでないが、一因ではあるかもしれない。レナさんは続けた。
「この団体の試合の特徴は1:1でやることかな。他の団体は対戦相手以外の人がリングに上がってきたりするんだよね。もしかしたら、うちらの団体が一番正々堂々と試合をしてるのかも。」
プロレスラーの顔中にピアスが開いていて、一見するとプロレスの中でも邪道に見えるピアスプロレス。しかし、レナさんはこれを洗練された戦いだと言う。初めて出会ったプロレスがこの形でよかったなと思った。
続々とお客さんが入ってくる。いかにも、プロレス好きのおじさんや身体中にタトゥーの入ったイカツイお兄さん、なかには若い女性もいる。その中に知っている顔を発見した。ミミさんだ。私たちに気づき手を振っている。手を振り返す。ミミさんが私の隣の席に腰を下ろす。そして、私から口を開いた。
「毎回、見にきてるんですか?」
「見にきてるよ!試合の後にいっぱいピアスの予約がくるからね!レスラーたちを見てると開けたくなるらしい!ピアスの種類を知ってもらえる場にもなってるの!全選手がピアスを開けているのはここだけだからね!」
「え、ここで試合するにはピアスが絶対条件なんですか?」
「ううん違うよ!誰も何も言ってないのに、ここの子達は私のところに来てピアスを開けたがる!誰かに言われたのって聞いても自分の意志だって言うんだよ!マリアも含めて!」
試合開始にアナウンスと音楽が流れる。そして、レフリーが選手の名前を紹介した。第一戦はエリ対マイ。二人は繋いだ手をあげながらリングに上がる。エリさんはアルさんの娘で20歳くらいだ。冷たい感じのするアルさんとは違って、明るい人だ。よくマナの遊び相手になっている。面倒見がよく、良いお姉ちゃんという印象だ。エリさんとマイさんは年も背も同じくらいで、どちらが勝つのか予想がつかない。レフリーが笛を吹くのを合図に試合が始まった。まず、先に攻めに入ったのはマイさんだ。エリさんの腕を取り、背負い投げる。早くもレフリーにカウントされるが、2カウント目に起き上がるエリさん。そしてすぐ、ロープに向かって走り、背中でバウンドさせてその勢いでマイさんの腹を腕で叩く。リングが狭く感じるほどのダイナミックな動きである。マイさんは吹っ飛ばされたが、今度は助走をつけて飛び蹴りを食らわした。エリさんもマイさんも攻撃を受けたらすぐ攻めの姿勢になる。攻めと受けが凄まじい早さで変わっていくのだ。エリさんのパワー力とマイさんのテクニック力の勝負というところだろうか。会場中の人が息を飲んで二人を見守っていた。力が拮抗した攻防が続いたのだが、ついにエリさんが大きく仕掛けた。マイさんを肩に背負ってリングの外に投げ出したのだ。つまり、場外戦である。私たちの目の前にマイさんが無抵抗に落ちた。マットは敷いてあるのだが、リングから落ちた時の衝撃は到底吸収できない。マイさんの風貌は痛々しげだった。顔のピアスから血が滲んでいた。これで試合が終了かと思ったのも束の間、マイさんはエリさんの方をギロリと睨み勢いよく立ち上がったのだ。そして、リングを囲むロープの上にバランスよく立ち手を振りかざしたかと思うとエリさんに向かって大きくダイブした。マイさんはエリさんに覆い被さり二人は一体となって倒れた。レフリーのカウントが入る。3つ数え終わり、ゴングが鳴った。マイさんの勝ちだ。たちまち、観客の歓声と拍手の波が襲う。二人は始まった時と同じように手を繋ぎ、その手を高くあげ深々とお辞儀をした。そして、裏に去っていった。初めて見た試合。まさか、血を見るとは思わなかった。顔にあるピアスは自分に向けられた凶器同然であることを理解した。自分の体に埋め込まれた凶器は自分にのみ激痛を与える。真っ赤な血がその痛みを表していた。。しかし、私は怖さを全く感じなかった。むしろ、赤い色の血の鮮やかさと二人のキリッとした目つき、ダイナミックなパフォーマンスに惹きつけられた。リアルさを脳に直接突きつけたような衝撃があった。
興奮冷め止まぬまま試合は続いた。アイ対マナ。若いペアだ。観客席に笑顔を振りまくマナ。緊張した面持ちのアイ。始まりの笛が鳴り響いた。まずはマナが勢いよくアイの腹に蹴りを入れる。身軽なアイの体は吹き飛ばされるように落ちた。アイが起き上がらないうちに、マナは蹴りを連続して入れる。マナの瞬発力は誰も叶わない。持ち前の運動神経の良さを生かして、間髪入れず攻撃を仕掛ける。耐えて起き上がろうとするアイ。起き上がるのを阻止するように延々と続くマナの蹴り。しかし、不思議とアイの姿は弱々しくは見えなかった。やられっぱなしなはずなのに、力に抗う強さがそこにあった。マナの目を捉え、全くそらそうとしない。そんなアイに対して目をそらすマナ。ただ自分の足とアイの腹を凝視しているのであった。マナは力任せの攻撃をしていた。一方、アイの目はマナの目に勝っているように見えた。マナは最後のトドメの飛び蹴りをするのだろうか、助走をつけるためにアイから離れた。そして、勢いよくアイに向かって走り、足をあげた。しかしそのわずかな間に、アイは重たい体を起き上がらせ避けたのだった。マナが空振りし隙を見せた時、アイはマナ目掛けて突進した。手を使うわけでも足を使うわけでもなく全身をぶつけたのだ。そして体当たりの瞬間さえも顔を背けずマナの体に飛び込んだのだった。怯えというものが一切ないように見えた。ぶつかると痛いというのが分かっているのに全力で突っ込むのだ。正気ではない。マナは来たる攻撃にどうすることもできず顔を斜め下に背ける。マナの横顔とアイの正面の顔が衝突した。顔のいくつものピアスは痛みを倍増させているに違いない。鈍い音とともに二人とも倒れこむ。すかさずアイがほふく前進でマナの上に乗っかった。マナはすかさずアイの上に覆いかぶさる。レフリーのカウントが始まる。アイは全身をよじらせながら、マナを除けようとするが力が及ばない。最後の最後まで抵抗したが、長い3カウントは終わりを告げた。マナはゆっくりと立ち上がり観客にお辞儀をする。そして、力を全て出し切って倒れているアイを起こし、今度は二人でお辞儀をした。アイはマナの肩に腕を回し、支えられながらバックヤードに向かっていく。二人の後ろ姿は私の目を釘付けにさせた。相手のことをじっと見ていたアイ。常に全身全霊で立ち向かっていたアイ。最後の1カウントまで全身に力を入れていたアイ。脳内で色んなアイの姿が浮かんできた。私に持っていないもの、そして必要なものをアイは持っていると確信した瞬間だった、私は衝動的に試合を終えたアイを追いかけていた。心配の気持ちからの言動ではない。アイを見ていたい、それだけだった。
アイはベンチに座らされていた。そして、サチさんが消毒液を染み込ませたコットンでアイのピアスの周りの血痕を手慣れた手つきで拭き取っていた。
「かっこよかったよ、アイ。」
初めてアイに声をかけた。短い言葉だが重みが違う。これは本物だ。今までで見た人たちの中で一番強くて美しかった。プロレスは試合の勝ち負けではないという意味がわかった。試合で負けても、精神的に勝っていることがある。観客の一人である私の心を熱くさせた人。それが勝者なのだ。あの日のアイの目の輝きと顔中の真っ赤な血は一生忘れることはないだろう。
試合の翌日、めずらしく家でパーティが行われた。豪華な食事が並べられ、普段の景色とは全く違っていた。ワイングラスが配られ、一人ずつワインが注がれてゆく。未成年かどうか聞いてくる人は誰もいない。マナをふと見てみると、当たり前のようにワイングラスを持っていた。
「ピアスプロレスのスポンサーになってくれてる人がお祝いに差し入れしてくれるの」
隣にいたマイさんが教えてくれる。
「スポンサーってミミさんですか?」
「うん、ミミさんもピアスのスポンサーだね。でも他にもスポンサーがいて、特に提携を結んでるわけではないけど寄付金をくれる人が意外とたくさんいるんだ。足長おじさん的な人がね。この団体の維持費も全てそれで賄ってる」
なるほど、住む場所やご飯はその人たちからの寄付で成り立っているのか。
「さすが足長おじさんですね。こんな美味しい食事まで出してくれるなんて。そういえば、今日のパーティって優勝者のお祝いって事ですよね。試合に勝ったらトロフィとかもらえたりするんですか」
「そうだね。優勝者は何ももらえないんだけど、スポンサー賞っていうのがあって一番勇姿を見せたレスラーに100万円支給されるの。今回もアイがその賞をもらうらしいよ」
どおりで誰が優勝したのかという話題が上がらないはずだ。試合成績ではなく、勇姿で評価されるということらしい。通常のスポーツというのは勝ち負けにこだわる人が良しとされる。しかし、そこには生まれつきの体格・練習環境など、本人の努力と無関係のところで差が作られる。これは埋めることのできない差である。オリンピックに出るような選手は、親もその競技に精通していて幼少の時から練習している場合がほとんどだ。だから、スポーツ選手になるのは手遅れという状況が生まれるのである。自分の将来をぼんやりと考え出す私のような高校生は、もう叶うことのない夢の存在に気づくのである。しかし、ピアスプロレスにおいてバックグラウンドは関係ないのだ。フェアなのか、アンフェアなのか私には測れない。しかし、始めた時期に関係ないのは私にとって好都合である。サチさんがパンパンと手を叩く。みんながサチさんに注目し、一瞬にして静けさが漂う。
「みんな、試合お疲れ様。今日はゆっくり楽しんで!乾杯!」
周りの人とグラスを交わし、慣れない手でグラスを口に運んだ。ぶどうのアクというアク全てを抽出したような味だった。しかし、飲めないこともない。
「じゃあ今回のスポンサー賞受賞のアイから一言もらいましょう」
サチさんはそう言ってマイクをアイに手渡す。アイはおどおどしつつもポツリポツリと話し始めた。
「前回に引き続きこの素晴らしい賞を取ることができました。えーっと、私はみなさんより力がないと思います。だから、全身全霊でぶつかるしかなくて。でも、それがこのような結果に繋がったんだと思います。ありがとうございます」
拍手が送られる。パーティの始まりだ。めずらしく賑やかな雰囲気だ。近くにあったワインのボトルを手にし、アイの元に駆け寄った。
「優勝おめでとう!」
そう言って、まだワインが残っているアイのグラスにワインを目一杯注いだ。
「優勝じゃないって。賞もらっただけだよ。」
「そうだったね。あー、私も次から試合出なきゃいけないのかー。プロレスって想像以上に奥が深いから、考えてるうちに分かんなくなるよね。でも、アイの試合は頭で考えなくても凄いっていうのは伝わったよ」
「ありがとう。なんて言うんだろう。人に感動を与えようと思って試合することは私にはできないんだよね。全部が全部、自分のためにだけに練習も試合もしてる気がする。他の人は人に見せることも意識して努力している。だから、本当はこういう人たちが評価されなきゃいけないんだと思う。人に寄り添って共感できてるってことだからね」
「私、アイが評価されなかったらやる気になってなかったかもしれない。だって、他人の評価だけで動いて、それが評価されたら学校と同じじゃん。心からパッとするものを私は求めてたんだと思う」
「マリア、今日えらい真面目だね。初めて話した時、アーイアイ!とか言ってる変な子だったのにね」
ニヤニヤしながらそう言ったアイ。私に見せる表情がここ数週間で一気に柔らかくなったなと感じる。
「キリストの生みの親、マリア様に向かってなんだ、その態度は!」
「ほらすぐそうやってボケだすー」
二人でクスクスと笑った。
「でもなんかマリアが来てくれてすごく私救われた気がする。キリストだけに!今まで、こんなフランクに話せる友達なんていなかったし、私に興味をひたすら持ち続けてくれる人いなかったんだ。」
「いやいやこんな可愛い顔してるんだから、誰でも興味持つでしょ」
「私の顔って今、可愛いんだね。よかった」
ボソッと言ったアイの言葉に背筋がゾクッとした。自分の可愛さを認識してないのだろうか。
「どっからどう見ても可愛いでしょ。なんでそんなこと言うの?」
アイは若干悩んだ表情を見せたが、すぐ口を開いた。
「私、2年前整形したんだ」腹をくくったのか間髪入れず話を続ける。
「私って昔から人の言動にすごく過敏な性格だった。ほんの少し注意されただけで私の心には深く刺さっちゃう。なんで、そんな事言うんだろうって思うの。私の言動は悪くないはずってね。自分の内面を否定することは私のプライドが許さない。だから、行き着いた結論は自分の顔が悪いから人から嫌われているってこと。その説が一番しっくり来る理由に思えた。自然と美人の子が目に入るようになる。その子はいつも人からちやほやされてて幸せそうなんだよね。対して努力もしてなさそうに見えるのに全部うまく回っている。羨ましさを感じて、自分は絶対そっち側の人間になってやるって思ったの」
「で整形に走ったってこと?」
「うん。いじっていくうちに周りの態度も変わっていった。何もしなくても笑顔で話しかけられるし、可愛いねって言ってくれる。本当の自分は何も変わってないのに私を見る人の目尻が下がるの。嬉しくないわけじゃないけど、自分ってなんなんだろうって考え始めちゃって。内面を見ようとしてくれる人はどこにもいなかった」
わかるような気がする。顔が良くても悪くても人の内面を見るのも見られるのも難しい。顔の偏差値までも平均である私の内面を深く知ろうとする人はほとんどいない。毎日、通り一遍の日常会話をさらっとこなすだけなのだ。うなずく私を横目にアイは続ける。
「でネットサーフィンしてたら、たまたまこの団体を知ったんだ。そのホームページに乗せられてたプロレスラーの姿は、その時自暴自棄になっていた私と重なって。あの必死さに乗って、自分の顔も中身も全部ぶち壊したくなっちゃって。あの時は死ぬ事も全然怖いって思わなかった。どうせ死ぬなら暴れまわって人に見せびらかして死んでやろうと思ったの。今考えると、逆に無敵な状態だよね。衝動的にピアスプロレスを訪ねたんだ」
初めて、アイは過去を語ってくれた。聞きたいなとは思っていたが、直感的に聞いてはいけないことだと勝手に勘ぐっていたのだ。
「あースッキリした!なんか隠してるつもりはないんだけど、やましさみたいなものがあって。マリアに言えてよかった」
再び、互いにワイングラスを向かい合わせカランと心地よい音を鳴らす。
次の日の朝、昨夜のパーティの面影はない。机には、いつものように朝食が並べられていた。昨晩は強烈な試合を目にし、興奮冷めやまぬままのパーティだった。そのせいで落ち着いて一人で考える時間がなかったなと思う。めずらしく、ずっと周りに人がいる状況だった。人と長時間一緒にいるのが不得意な私であったがストレスは感じなかった。一人でいる時の素の私を出せていたのかもしれない。普通の人の生活はこれが絶え間無く続いた状態なのだろうか。今日も笑顔の自撮りを送る。我ながら、笑顔を作るのが上手くなって来たなと感じた。
私はサチさんにお願いして、試合練習を継続してもらった。レナさんとの取っ組み合いもコツがつかんで来た。レナさんの攻撃を受けて投げ倒されても、もう痛みを感じることはない。慣れは恐ろしいもので感覚をも麻痺させてしまうのだ。いくら投げ飛ばされても、軽いクッションに落ちる感覚である。全身の筋肉が床からの衝撃を緩和しているようだ。
レナさんは、
「マリア。あんた短期間でよくこんなに強くなったね。誰とでも戦えるレベルだと思うよ。」
と言った。喜んだ顔をして見せるのだが、内心では引っかかっていた。体力がつき、テクニックが身に付いたのは実感できる。しかし、前に見たアイの試合を思い出すと方向性が違う気がするのだ。鍛えるほど、そのズレが浮き彫りになっていく。アイは一体どこから圧倒的な輝きを生み出しているのか。
私は、夜に1時間のランニングに行くことを習慣にしている。今日に限ってはこの習慣を壊し、アイを散歩に誘うことにした。風呂上がりのアイに声をかけると、
「髪乾かしてから行くから先行ってて。すぐ追いつくから」
と言った。言う通りに先に外に出た。真っ暗な空を見上げて、深呼吸をする。今まではドアを開けた瞬間からダッシュと決めていた。そのため、外に出ても空を見上げたことがなかったと気づく。できるだけゆっくり歩いた。夜の空気は昼間の空気とは全く違う。音が消え、光が消え、ホコリっぽさがまるでない。涼しい風は私の体に浸透した。夜の時間はこんなにも静かにゆっくり流れているのに、私はひたすら心拍数をあげさせてたんだな。後ろから誰かが走ってくる音がする。アイなのは分かっているがあえて振り返らない。思えば、アイは練習時間以外で筋トレやランニングをしてる姿を見たことがない。
「お待たせ」
アイの笑顔が暗闇から現れる。口元だけ笑顔を作りアイの笑顔に答えた。その後、重たくない沈黙を続けた。話したいタイミングで口を開いた。
「アイ。なんでそんなに強いの。どうしたら私が強くなれるかわかんない。だって、こんなに努力してるけど違和感が残るの。アイは日中しか練習してないでしょ。アイより練習してる人たくさんいるよ。なのに、なんでアイが評価されるの。どうしたらいいかわからないよ」
話して行くうちに感極まり、涙が浮かんだ。急に感情的になる私の心に私自身が戸惑う。アイへの妬みとか憧れではない。ただただ分からないのだ。
「そうだね。マリアの言いたいことは分かるよ。でもね、私的にはみんなの方が羨ましいんだ。プロレスは多かれ少なかれ、自分の体に痛みが伴う。私は死が怖くない時期が長かったから、痛みなんてどうでもよかった。死を目前に怖がって目を背けるのが自然な人間の反応だと思う。なんて言えばいいのかな。恐怖心がなくなると死へのリスクが高まる。だから、私みたいな人間は短命不可避だと思う。この生き方は、あまりオススメはしないよ。でも、ピアスプロレスだけにこの生き様を反映させるのであれば、精神を鍛えるってことに行き着くのかな。マリアは十分体を鍛えたから、次は精神を鍛えた方がいいかもね」
精神か。波に乗るだけの生活はブランクと言えるだろう。これは精神活動に対する怠惰が原因に違いない。不満を持ちつつ、しかしなす術もないと諦めて社会の波に乗っていたのだろう。確固たる自分の弱みが見えた気がした。
「私は死が怖い。だけど、恐怖心の先に死があるとは限らないと思う。死を予期して、恐怖心に立ち向かわないのは違うよな。自分の体に染み付いた思い込みを取っ払いたい。恐怖心を乗り越えた先にあるものは、嫌いなものではないと言うことを証明したい。きっと、自分から求めないと恐怖を感じるものに出会えないと思う。だから、人生において寄り道してでもそういうものに対面して行きたいんな。」
「応援してる。マリアは私の希望だよ。」
次の日から私は精神強化練習へと移ることにした。サチさんにその旨を伝えると、呆れた顔をされたが、
「マリアは行動力がありすぎて、考えが見えないよ。いいよ、好きにしな。もともと、自分でここに飛び込んで来たんだもん。なんでも、ありだよ」
と言い、受け入れてくれた。サチさんが絶対的な味方でいてくれるのは私を含めてレスラー全員にとって心強い。
バンジージャンプを選んだのは直感だった。単純にやりたくないものを考えた結果、一番最初に頭に浮かんだものがこれだったからだ。久しぶりに電車に乗り、遊園地前駅で下車した。チケットを買い、一人でゲートへ進む。もらったパンフレットの地図を確かめ、足を進める。黄色い風船のような巨大なマットレスを目が捉えた。その横には、鉄パイプで簡単に作られた足場がそびえ立っている。簡易な階段を登り頂上に立つことを想像しただけでも、私の手のひらは緊張で湿ってくる。その時、ジャンプ台に続く階段をスタスタと上がっている男の子の存在に気づく。下には数名の仲間がいるようで笑顔で手を振り返している。子供の方が深く考えない分、バンジージャンプが得意なのではないか。と思った矢先、急に少年は立ち止まった。最後の数段になって、足取りが重くなっているようだ。そして、慎重に1段1段ゆっくり上がっていった。頂点にたどり着いた少年は否応なしに金具をつけられている。上にいた係員は慣れているのだろう、心配する様子を一切見せない。少年はすぐさま飛び位置に立たされた。少年の表情はこちらから確認できない。
「バンジージャンプ、3、2、1、GO!」
スピーカーからカウントが聞こえたが、少年は飛ばなかった。虚しく沈黙が流れる。少年は後ずさり、後ろを向きスタッフに何か言っているようだ。そして、スタッフに支えられながら元来た階段を降り始めた。顔が確認できる距離まで来ても、その少年は仲間の方に顔を向けることはしなかった。ただただ白い顔で下を向いているだけだった。仲間はこの少年を馬鹿にするのだろうか。それとも、やろうとした志を評価するのだろうか。
帰りたいという感情が押し寄せてくる。ダメだ。考え出したら、頭の中で適当な理由をつけて行かない方に持っていってしまうだろう。私はそういう人間だ。何も考えない。何も考えない。そう心の中で唱えながらスタッフにチケットを渡した。一通り説明を受け、階段を上がるように指示された。何も考えない。足元だけを見て唱え続ける。足元から絶対に目をそらしてはいけないことは分かる。冷たい鉄の手すりに私の手汗をなすりつけていく。上に行くほど、心なしか風が強くなっているように感じる。眉間のピアスが風圧で皮膚を圧迫させ、若干痛む。しかし、そんなことはどうでもいい。何も考えない。最後の一段を登り切った瞬間、顔をあげた。こちらに目をやる係員とその向こうの青い空が見えた。そのまま顔を動かさず、前の一点だけ見つめ、前に出て金具を取り付けてもらう。
「手をバッテンに組んで倒れるようにまっすぐ飛んでね。いってらっしゃい」
手短に説明する係員の言葉に返事はできない。ただゆっくりとすり足で前進するのだった。足の先で飛び台の先端を感じる。正面の青い空。一点という概念が存在しないところに一点を見出し凝視し続ける。スピーカーから合図が聞こえる。さっき聞いたから言ってる内容は知っているが、文字を捉えることができない。音が途切れた時、私は垂直に空気に向かって倒れた。味わったことのない浮遊感。生きている人が味わってはいけないものを感じた。死へのリアルな道のりは三途の河ではなく、この浮遊空間にあるのだろうと思った。それと同時に、自分の体を含めて世界のものというもの全てが消える感覚に囚われた。それは、しがらみを全部取っ払って自分の魂だけが解放された感覚に近かった。この魂の先端は心臓でも脳みそでもなく眉間のピアスであると確信した。この金属が取っ掛かりとなって魂が体より先行して来る。今の私の核はこのピアスなのかもしれない。怖いとか嬉しいとかいう感情は生まれない。ただ、ありのままの事実を受け入れるだけだった。
見ていた景色が青から緑。緑から黄色に変わった。マットに近づくとゆっくり降ろされた。体に力が入らない。飛んでいた間は魂が抜けていたが、降りた瞬間にそれは体に入り込んだ。まだ、身体に馴染むのに時間がかかっているようである。スタッフが駆け寄り私の体から金具を取り外し、笑顔でお疲れ様ですと言った。口を開いたが声が出なかったので、軽く会釈した。開放感が爆発したはずであるのに、金具で体を固定されていたのは矛盾が孕んでいるなと思った。再び、飛び台を見上げる。あんな高いところから飛んだんだ。今起こった出来事を自覚し始める。あの場所で下を向いていたら足がすくんで一歩も動けなかっただろう。今おかれている瞬間を省みた瞬間、立ち止まり、悪くいけば後ずさりする。
これは、バンジージャンプの場に限らない。リスクを考え躊躇した瞬間、スピードもパワーも半減することはプロレスにも言えるのではないか。考えることで悪いループにハマるくらいなら、頭を空っぽにして突き進んだほうが良い。考えるのは、全て終わった後でもいいんだ。その一瞬は、わずかな時間とためらいが命取りになる。これによって、今後の人生が左右されると言っても過言ではない。もう一回飛ぼう。
そう思った瞬間バンジージャンプのゲートへ行き、さっきと同じ手順を踏み階段を上がる。今回は足元を見るのではなく前を向き、駅の階段を上がるのと同じペースで上がった。前を見ると自分がこれから踏みあげようとする段差が流れるように見える。その端は一刻一刻と高さを感じさせる風景に変わってゆく。しかし、そちらに焦点を合わせることは決してしない。なぜなら、今のスピードとパワーを半減させる要因は全て排除しなければならないからだ。最後の一段を登りきり、さっきと同じスタッフが例のように手慣れた手つきで金具をつける。今回はスタッフの顔を確認するし風景も少し見渡して見る。気持ち良い快晴の空に初めて気づく。目から情報を入れるように意識する。見たものをそのまま全て受け入れるだけだ。そこから消化をする、つまり思考を巡らしてはいけない。飛び台の先端までサクサク歩く。スピーカーからの合図。今回は一語一語聞く余裕がある。
「バンジージャンプ、1、2、3、GO!」
大気に身を委ねる。無重力そして空気抵抗による風が私を包み込む。先程の落下時は飛び降り自殺者のように体が硬直していたが、今は飛び込みの水泳選手のように体をしならせることができる。こうすることで体を魂のスピードに合わせることができる気がする。浮遊途中で身を起き上がらせ、足先からマットへ着地した。身に降り注がれた事柄を享受し、生命力の純度をあげる。それこそが、私に足りなかったものだ。これをプロレスに転じなければならない。
その日の夕飯の時間、いつものようにみんなでテーブルを囲う。私の顔を見るや否や目つきが変わったねと数人に言われた。目が見開いて顔つきがパッとしているらしい。
「ふーん、バンジージャンプして来たんだー面白いね。考えただけでも、ひやってするわ」レナさんが食事の支度をしながら行った。
「正直私、高所恐怖症の気があったんですけど、腹をくくって飛びました。荒治療も兼ねてやってみたら成功しましたよ。今の体とか過去とか全部取っ払って魂みたいになるのは人生で初めてでしたよ」
「魂って怖いね。死ぬ時に自分が魂だけになるのに近いのかな。いやー、プロレスの精神の鍛え方として斬新だわ」
マイさんも楽しそうに会話に加わる。
「いやー、精神の鍛え方がこれしか思いつかなかったんですよ。でも、あの飛んだときの感覚をプロレスの試合で発揮できれば無敵な気がします」
「よっ!期待の新人ルーキー!アイの王の座を奪えるかなー?」
レナさんがからかってくる。
今の私ならやってのけることができるかもしれない。時間の隔たりで圧倒的なアイの試合の記憶が薄れて、そう思えるのかもしれない。だとしても今は、自分のやり方を信じ遂行するだけである。アイの様子をパッと見ると、穏やかな顔でご飯を口に運んでいた。
とうとう試合1週間前になった。そして、選手全員の試合練習メニューが始まった。試合に出る全てのプレーヤーと取っ替え引替えして取っ組み合うのだ。どの選手もパワーがあり、取っ組み甲斐がある。そして、自分の鍛えた体の成長が実感できた。きっと試合でも引けず劣らずプレイをすることができるだろう。アイとのプレイも他の選手と同じくいい勝負だった。アイは私との練習はフィット感があってやりやすいと言った。私も同じように感じていた。アイは
「もしかしたら、力が拮抗してるのかもしれないね」
とニコニコしながら言った。
「よく目が合うよね。自分を鏡で見てるような感覚になる」
「わかるわかる。目が似てきたかも。これはどっちが勝つかわからないね」
「練習だとお互いの力を図るの難しいよね。だって、この前後でも練習が続いているから。全力と全力がぶつかった時どうなるんだろ。ほんと、どっちが勝つかわからない」
1週間の試合練習は怒涛のように過ぎた。時間の感覚が狂っている。1日が颯爽と過ぎ行くのである。このまま、すぐに歳をとって生を全うしてしまうのではないか。
試合当日の朝、サチさんから真っ青の衣装を渡され、これで出るように言われた。アイの衣装は私の衣装の型と同じもので色は真っ白だった。きっとこれでリングに出たら、敵というよりアイドルのようなユニットに見える気がする。一緒に練習して来た仲間がリング上では争う。仲間同士で戦うからこそ、本気になれるのかもしれない。何をしても何をされても許すことができる関係を手に入れることができた。これは私の人生において大きいことである。
「そうだ、マリアも化粧しないとね」
マイさんの声が聞こえた。そして、メイクポーチからたくさんのメイク道具を出し並べた。目を瞑っててと言われ、なされるがままメイクされた。マイさんの動きが止まった時、目を開ける。鏡には今までで一番美しい自分の顔が映っていた。
「すごい!自分じゃないみたい!」
鏡の前で笑顔を作る変わった自分をしみじみ観察する。眉間の金属が勲章だ。ここにきて、身も心もそして顔までも変わったのだ。少し前の自分と今の自分はかけ離れている。もちろん、今の自分の方が圧倒的に好きだ。
1ヶ月前は列の一番後ろでひっそりと歩いていた。しかし、今は列の真ん中で堂々と歩く。端から見ると正真正銘ピアスプロレスラーだ。晴れ渡った空の下、商店街を闊歩する。真っ暗な階段をゆっくり降りる。懐かしのリングが現れ、大きく深呼吸する。ここが私の舞台、私の居場所だ。慣れない衣装に身を包み、一瞬で成長した自分がここにいる。周りには生活を共にしてきた仲間がいる。個性が強くて、かっこいい自慢の仲間たちだ。今日は初めてみんなと写真を撮った。メイクで顔はいつもと違っているが、話し方・笑顔はいつもと同じである。みんな揃って笑顔でレンズに向かう。この温かい1枚の写真を一生大切にするだろう。勇気を出して母にこの写真を送った。素敵な仲間に囲まれた自分、笑顔の自分を今なら堂々とさらけ出すことができる。
試合が近づくと、みな揃って椅子に座る。話をする人はおらず、緊張した面持ちだ。賞を取りたいと思っているのか、怪我を恐れているのかわからない。ただ一つ確かなことは、私がワクワクしているということ。サチさんが私とアイの名前を呼んだ。
アイの後に続く。そして、眩しい光に照らされたリングの上に躍り出た。観客がいるはずだが、ぼやけてよく分からない。ただ白い光に照らされたリングとアイの姿だけがくっきりしている。レフリーの笛とともに試合が始まった。先に動いたのはアイだった。アイは私に突進した。私はアイと共に倒れこむ。アイは、レフリーがカウントを取る前に私の体から離れた。そして、私が起き上がるのを待つのである。私はすぐに起き上がりアイに突進する。そして、アイを倒した後すぐアイの攻撃を待った。なぎ倒し、倒される攻防が続く。キックでの戦闘や場外戦になることはない。至って正攻法な戦い方を互いにした。私の攻撃は100%アイに当たり、アイの攻撃も100%受ける。相手の体を押さえつけて、レフリーにカウントを取られるような戦い方ではない。投げ倒し、ぶつかるだけだ。これは、どちらかが自然と動かなくなるまでこの勝負は続くことを意味していた。私たちの視界にはレフリーや観客は入っていない。ただ、相手のみを見据えるのである。しかし、相手を負かすのが目的ではない。自分の極限を見にいくのだ。一撃ごとに体が重くなってくる。攻撃を受けるたびにアイの表情を確認する。そして、この痛みは自分だけのものではないことがすぐに分かる。勝ち負けの争いではなく、協力して戦っている感覚だ。初めての試合、一発勝負。時間が決まっていた練習とは違い、試合では時間の拘束はない。必死に取っくみ、投げ倒す。何回も何回も起き上がるアイと私。ピアスプロレスの試合、いやアイとの試合に限っては体力勝負ではない。精神勝負だ。息が切れて、うまく空気を吸い込めない。しかし、私のしたいことは自分を怠けさせることではない。長らく怠けてきた精神力を奮い起こし、今まで強化してきたのだ。変わった自分は、少なくともこの状況下では一瞬たりとも甘やかしてはいけないのだ。
どれくらい長い攻防だったのだろうか。気がつくと、病院のベッドに横になっていた。アイも隣で横になってまだ、目を覚ましていない。生きている。それだけで十分だ。満たされた心と共にもう一度、深い眠りにつくことにした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
