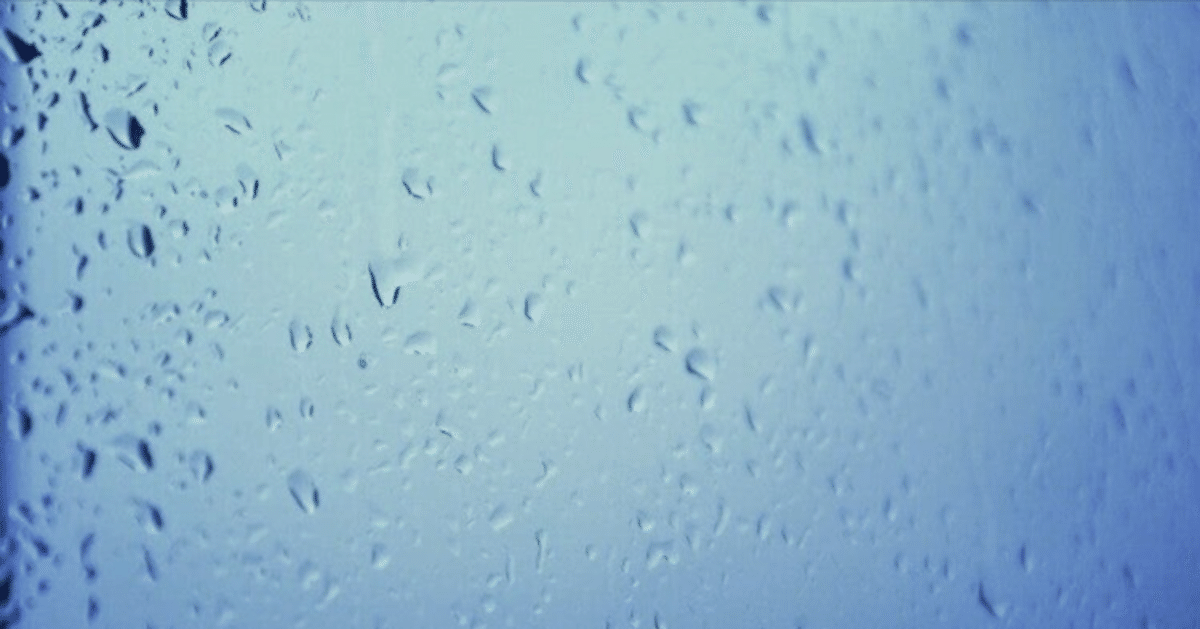
その色のあせるまえに
BFC4。二回戦作品。幻の。

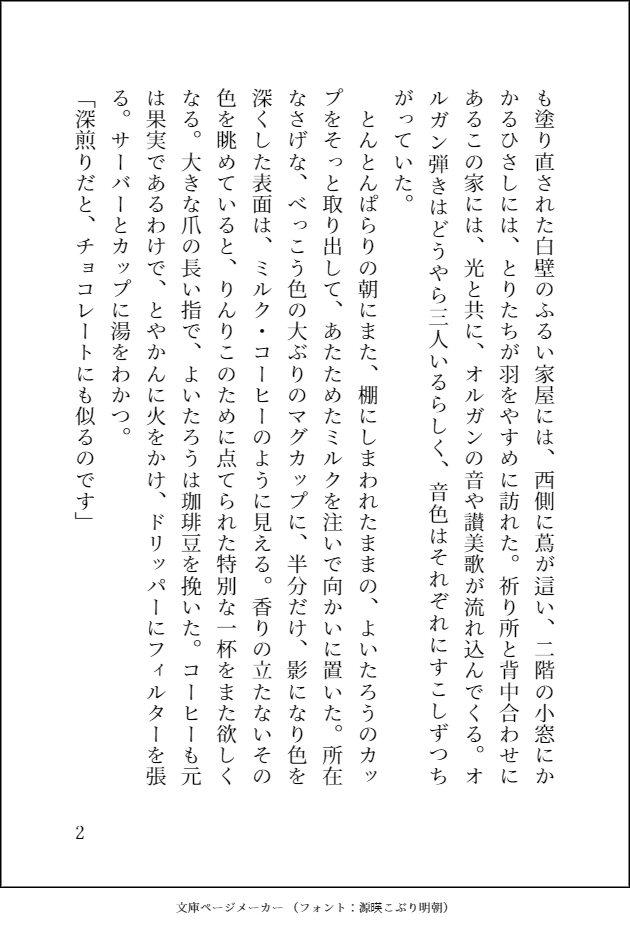




雨音のあるあけがたにだけ、りんりこはふかくよく眠る。律された雨だれの、ときに不規則なリズムに心をあずけ、からだをあずける。とん、ぱら、とん、と、天窓を打つ音を、めぐる血潮の、その流れと細胞の、すこやかであるさまに重ね、心地よく、まぶたをとじたまま眠魚の数を数え続けた。
…千百六十三、千百六十四、千百六十五。
眠魚が羊になって羊が白色の綿あめに変わって、気がついた。雨とばかりにおもっていた音は、愛した雨の水の玉などではなく、陽の光を孕む木々の種子の落ちくる音色であった。眠りのこないのは、当然だった。やがて、しらと明けはじめた夜の、寝室のカーテンの隙間から雲をまとった光が差し込み、世界が、ぐるんとでんぐりがえる。夏の季には、五時よりもっと早い時間から。秋を過ぎると五時半、やがて六時、六時半。朝の入口がうしろに下がり、細く長い光は、角度を変え、明るさを変え、その日の天気や、うつりかわる季節のかけらをはこんできてくれた。幾度も塗り直された白壁のふるい家屋には、西側に蔦が這い、二階の小窓にかかるひさしには、とりたちが羽をやすめに訪れた。祈り所と背中合わせにあるこの家には、光と共に、オルガンの音や讃美歌が流れ込んでくる。オルガン弾きはどうやら三人いるらしく、音色はそれぞれにすこしずつちがっていた。
とんとんぱらりの朝にまた、棚にしまわれたままの、よいたろうのカップをそっと取り出して、あたためたミルクを注いで向かいに置いた。所在なさげな、べっこう色の大ぶりのマグカップに、半分だけ、影になり色を深くした表面は、ミルク・コーヒーのように見える。香りの立たないその色を眺めていると、りんりこのために点てられた特別な一杯をまた欲しくなる。大きな爪の長い指で、よいたろうは珈琲豆を挽いた。コーヒーも元は果実であるわけで、とやかんに火をかけ、ドリッパーにフィルターを張る。サーバーとカップに湯をわかつ。
「深煎りだと、チョコレートにも似るのです」
細引きの豆は、沸いた湯に泡立ち、香りがほどける。苦みの走る、ひりついた異国の味の、はちみつとミルクを入れると格段においしくなることは、よいたろうが教えてくれた。
「黄金の光、乳白のせせらぎ」
銀のさじで、漆黒をかきまわす。焦がした果実のようなアロマが立ち込め、甘さと香ばしさと引き立つ。カップの内側で三つの流れが一つになり、ふっくらとした唇を濡らす。ぽてりと短い舌を包み、のどの内側をなぞって、落ちる。なめらかな一筋は、螺旋を描きながら、胸を通り、腹を抜け、やがて手指の先端にまで行き渡る。母の、決して、欲しがらない、姉が決して知ることのなかった、未知なる、ひらかれた魔の味。焼けるように甘い、山菫を閉じ込めた砂糖菓子に手を伸ばし、りんりこは、ながいこと味わっていない、あの琥珀色の液体をおもいだしながら、よくばりすぎるからだを鎮めるように、冷めてしまったミルクを一気に流し込んだ。
秋も冬も、寒かった。春も夏も、冷たかった。
島に住むようになると、男も、女も、そこで新しい所帯を持つらしいとうわさを聞いた。そんな話はうそだとおもうが、確かめようはなかった。慰めることにだけ長けた、美しい人間の住まう区画ができたとも聞いた。お手紙をうけとったところで、本当のお気持ちなど知ることなどできない。よいたろうさんは、自分のことなどもうお忘れになっているのではないかしら、文字にするだけならばどのようにでも何とでもお書きになれますでしょうに、などと、よくないおもいを巡らせてしまったりもして、今、ひとり待つ身のりんりこの肌は、冷たい。勇敢に家を出た広い背中を恋しく、切なく、焦がれるようにおもい出し、ああ冷たい、寒い、寒い、と呟いた。そうして、ひりひりと掠れ、湿った心を焚き上げるように、よいたろうに会いたい、よいたろうが愛しいさびしい恋しい、と呪うように書きつけた手紙を、涙入りの蝋で封じる。
この世界で最も冷たかったその肌を、よいたろうは、持てる熱のすべてで包んでくれた。彼の温度移るころにようやく、りんりこの肌にも血潮が巡り、うすく、あでやかな桃の色が頬に差して。二人のための広すぎるベッドに横たわる夜、か細いからだは、まったくもってあたたまらない。りんりこを覆う毛布は十二分にあまり、夜の風を自由に通した。冷え切った尾骨に、温度が恋しい。信じられるのは、かき抱くあの腕と、ぬくもりそのものであった。おおきな手のひらの、抱き寄せる逞しさをおもい、自らの指を自らの肌に押し当てこすり合わせた。肌をさすれば、熱がおこった。指の腹の、我がふかい谷の底のその奥を這いまわるあのさまを、睦言をなぞりながら、なめらかな渓流の、その源を確かめて、こねまわす肌にぬくもりの帰って来ることを願った。隙間風をうめるよう寝間着を重ね、仰向けで前を合わせた。ちいさな貝ボタンを開けるのは、よいたろうの役目であった。
「夜に飛ぶ蝶が、新月に海に落ちてそのまま貝になる」
「うそ」
枕元の巻貝から、島の波音が響く。
「よいたろうさん」
ぐしょ濡れで待ちぼうけなど、大嫌い。
よいたろ「う」の音を仕舞う小さな穴に、のこる気配は吸い込まれ、白い肌にぽてりと開いたまま、みずみずしく滲んだ赤は行き場をなくす。目を閉じて、羊に乗って海を渡る。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
