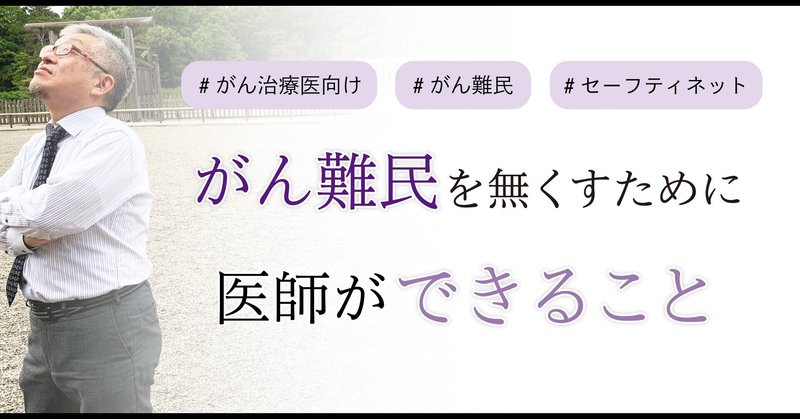
がん難民をなくすために、治療医のあなたに考えてほしいこと【医】#3
こんにちは、心療内科医で緩和ケア医のDr.Toshです。緩和ケアの本流へようこそ。
緩和ケアは患者さん、ご家族のすべての身体とこころの苦しみを癒すことを使命にしています。
今日のテーマは「がん難民をなくすために医師ができること」です。今日はがん治療医の先生にお話します。
動画はこちらになります。
治療医の立場として可能な標準治療があるにもかかわらず、民間療法やがん放置療法を選ぶ患者さんがいます。その後、がんが悪化してしまって、再びあなたのもとにその患者さんが治療をしたいと言ってきたときに、あなたはどう考えるでしょうか。
今日はそのような状況になった時、がん治療医のあなたにぜひ考えていただきたいことについてお話します。
この動画でがん難民と呼ばれる患者さんが少しでも減り、患者さんを安心させてあげられる医師が増えればうれしいです。
今日もよろしくお願いします。
患者さんをがん難民にしないためには
先日、私が詰め所でカルテを書いていた時、そばで30代後半の医師が同僚と話していました。
「もう、嫌になったよ。あの患者さん、僕が一生懸命、抗がん剤治療のことを説明しているのに、全然理解していない。何回言っても分かってくれない。結局、抗がん剤治療はしないって。残念だ。抗癌剤したら、命は伸びるのにね。」
私は聞くつもりは全くなかったのですが、つい聞こえてしまいました。こうした場面を、臨床医の先生方は自分が体験したり、あるいは聞いたりしたことはあるのではないでしょうか。
がん治療をしないと選択した患者さんを、先生方はどうしますか?
自分でしないと決めたのだから、それはそれで仕方がない、患者さんの自己決定を尊重します、と思われる方も多いかもしれません。
では治療しないのだから、ここには来なくていい、と患者さんに言いますか。あるいは、黙って外来に来なくなる患者さんもいるかもしれません。
日々先生方が診察している患者さんがとても多いことは私も知っています。
忙しいこともわかります。でも、あえて先生方にお願いしたいことがあります。
もし、患者さんが抗がん剤治療をしないと言って、離れてしまった後に、がんが悪化してあなたのもとに帰ってきた時には、快く受け入れてあげてほしいと思っています。それが、たとえもう抗がん剤治療をすることができない状態になっていてもです。
患者さんとそのご家族は、抗がん剤治療を提示された時、とても悩みます。
現在はネット社会で、誰もが、様々な情報を得られる時代です。
抗がん剤治療に関しても、様々な情報が飛び交っており、その内容は玉石混合です。抗がん剤はすべて悪だとか、副作用のない優しい治療で末期がんが治った、といった話が、ネットで検索すればすぐに出てきます。
その結果、抗がん剤治療をしないという選択をしてしまう患者さんも少なくありません。そういう人は、先生方から見ると、間違ったがん治療を選択してしまっている患者さんかもしれません。そして、それはご本人の選択だから尊重するということも必要でしょう。
でも、もう一度、患者さんが先生を頼って帰ってきたら、快く受け入れてあげてほしいと思います。もしそうでなければ、その患者さんは、いわゆるがん難民になってしまうからです。
どこにも行き場がなくなって、困り果て駆け込んできた患者さんを、ホスピス時代に私は何人も診てきました。
一旦、自分で抗がん治療をしない、あるいは民間療法をすると決めても、がん患者さんの多くはがんが進行していきます。痛みなどのつらい症状が起こっても、どこにも頼るところがない方々が殆どです。そんな患者さんを、どうか受け入れてあげてほしいのです。
さらにもっと踏み込んで言うと、患者さんが抗がん治療をしないあるいは他の民間治療をするという選択をしても、先生方の外来で、その患者さんを診てあげてほしいのです。
患者さんが、あなたの提示した治療法を選択しなかったとしても、外来診察は続けてください。あなたが患者さんの気持ちと思いを理解し、患者さんを見守ってあげることで、患者さんはとても安心すると思います。
患者さんを理解すること
もう一度、先ほどの先生の話に戻ります。
彼は「一生懸命、抗がん剤治療のことを説明しているのに、全然理解していない」と言いました。本当に患者さんは、理解していないのでしょうか。
この部分を厳しく言えば、理解していないのは私たち医師の方かもしれないと思うのです。
私たち医師は、学生時代・研修医時代に、患者さん・ご家族に、いかに正しく病状や治療法を伝えるか、ということを学びます。
正確に伝えて、理解してもらったうえで、承諾書を書いていただき、治療に臨むことがいかに大事か、それがインフォームドコンセントなんだ、と少なくとも私はそのように学んできました。したがって、どうしても「相手に伝える」という部分に力点を置いてしまうのです。
コミュニケーションの中でも、どのように相手にわかりやすく伝えるか、という部分に焦点が当たってしまいがちです。しかし、コミュニケーションとは、一方的に伝えることではありません。相手の考えや気持ちを受け取ることも必要です。
相手に伝え、相手から受け取るという、双方向の交流がコミュニケーションなのです。
先ほどの先生の会話に戻ると、先生は一生懸命伝えてはいますが、患者さんの気持ちや思いを受け取ってはいないかもしれません。おそらく患者さんは、理解していないのではなく、葛藤しているのだと思います。
がん患者さんは、治療方針など様々なことで、いつも葛藤していることを知って欲しいと思います。
私たち医療者には患者さんを理解する態度が必須です。患者さんの思いを聴いて、受け取ってあげてください。患者さんの思いをこころから理解することができたら、患者さんの選択をこころから尊重できるようになります。
そして、あなたの理解と存在がセーフティネットになり、患者さんを安心させるのです。
大学病院での体験
60代前半の、診断されたばかりの胆管がんの男性患者さんが、消化器内科の医師から緩和ケア外来に紹介されてきました。
「積極的抗がん治療は希望されない患者さんですが、今後痛みなどの症状が出現する可能性があるので、併診をお願いします。」という内容でした。
肺に転移がありステージⅣではありましたが、まだまだ元気で、抗がん剤治療の適応は十分あるように思えました。
「今のあなたは十分抗がん剤が有効だと思えますが、抗がん剤治療はしないのですか?」と聞きました。
すると彼は「先生も消化器内科の先生と同じことを聞きますね。僕は自分で決めたんだ。ステージⅣの胆管がんなんだからどうせ治らない。それなら苦しい抗がん剤はしないで、好きなことをして過ごしたい。でも痛みが出てきたら嫌だから、ここを紹介してもらったんだ。よろしく頼むよ。」と言いました。
隣にいた奥さんはやや悲しげな表情でしたが、患者さんの言葉にうなずいていました。
私は診察の後、消化器内科の主治医に電話で聞いてみました。「先生、抗がん剤治療をしない人なのに、先生が外来で診られるんですか?」
すると主治医は、「そうなんですよ、僕は抗がん剤を勧めたんですが、患者さんが頑なにやらないと言いまして。でも、そのまま診療終了にしてしまったら、すぐに痛みが出てきて患者さんが困ると思ったので、先生にもお願いしたんですよ。抗がん剤治療をしないと余命も半年もないと思いましたし、私が最期まで見ようと思いました。無理なお願いですが、先生も一緒に診てください。」と言いました。私は快く承諾しました。
その後も、私たちはその患者さんを外来で診察を続けました。痛みが出てくると私が鎮痛薬を出し、閉塞性黄疸になると、消化器内科に入院し、処置をして再度外来診療になりました。病院に来ることが難しくなると、在宅チームも紹介し、最期はホスピスに紹介してそこで亡くなりました。
これは診断した医師が、抗がん剤治療をしないという患者さんの意思を受け取り、そのことを尊重し、そして最期まで責任をもって診療にあたったケースでした。
最期まで患者さんは安心して過ごし、感謝して旅立たれました。私はこのような医師が、私の近くにいることに誇りをもっています。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
私は、緩和ケアをすべての人に知って欲しいと思っています。
このnoteでは緩和ケアを皆様の身近なものにして、より良い人生を生きて欲しいと思い、患者さん・ご家族・医療者向けに発信をしています。
あなたのお役に立った、と思っていただけたたら、ぜひ記事にスキを押して、フォローしてくだされば嬉しいです。
また、noteの執筆と並行してYouTubeでも発信しております。
患者さん・ご家族向けチャンネルはこちら
医療者向けチャンネルはこちら
お時間がある方は動画もご覧いただき、お役に立てていただければ幸いです。
また次回お会いしましょう。さようなら。
ここまでお読み頂きありがとうございます。あなたのサポートが私と私をサポートしてくれる方々の励みになります。 ぜひ、よろしくお願いいたします。
