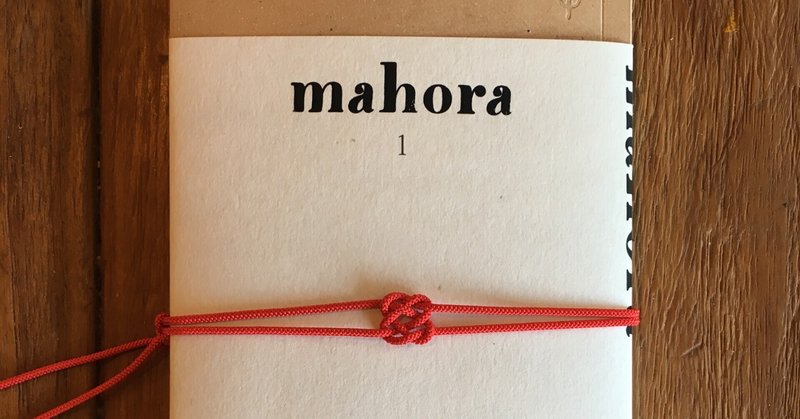
[創刊号]編集後記に代えて
1. アユタヤの石像
丹念に長いあいだ取り扱ってきたものを見ているうちに、自分の心からほしいままなものが取れたのじゃないか。ほしいままなものが取れさえすれば、自然は何を見ても美しいのじゃないか。
岡潔『人間の建設』(小林秀雄との共著/新潮文庫)
タイ、アユタヤ歴史公園。14世紀半ばから18世紀後半にかけて栄えたアユタヤ王朝が遺した、大小さまざまな遺跡群のひとつ――確か、観光名所としてはさほど有名でもない遺跡に、その石像がありました。そんなに大きなものでもない。遺跡の中心に位置しているわけでもない。建物の廻廊跡に数メートルおきに並ん編集後記に代えてでいるうちの、取り立てて特徴のない像だったと思います。表面はだいぶ風化していて、黒ずんでいました。ほかの像と同じく盗掘に遭ったのでしょう。無残にも胸から上が削がれ、頭部もなく、肩から腕にかけての大半も失われていました。左手は肘の関節の辺り、右手は手首から五本の指先にかけてだけが残され、座禅を組んだ両膝の上に置かれていました。左の膝頭も欠けている。男女の別もつきません。仏像なのかどうかも定かではありません。
なぜだか私は、その像が気になったのです。瞬間的に、美しいと思いました。けれども、そう思った理由はわからない。答えを探すように、像の失われた部分を想像していました。右手首が、手の平で右足の膝の下の辺りをそっと抑えているように見える。私の目は、見えない右手をなぞりました。腕から肘、肩にかけての稜線、腕の太さや、軽さ、あるいは弾力。華奢なのか、そうでないのか。雄々しいのか、たおやかなのか。見ることのできない、相貌と眼差しは、憂いているのか、微笑んでいるのか。毅然としているのか、まだ幼いのか。だけど、像の本来の姿なんて、わかるはずがない。想像が勝手に泳ぐのと対照的に、残された胸から下と坐した下半身は、じっと動かない。
季節は夏でした。気温は四〇度を超えていたかもしれません。写真に収めたその石像は、強い逆光のなかで静かに佇み、私の記憶に留まり続けました。
2. 不完全であること
余白や余韻、予感や直感、欠損や暗示、曖昧さやはかなさといった言葉で日本の文化を説明した書物は、枚挙に暇がありません。侘び・寂び・軽み、空、幽玄、粋といった美意識にしてもほとんど同じで、特に西洋の文化と対比しながら、どこか「不完全」であることがその特徴であるとされます。例えば、すべてを塗らない、書かない、言わない、つくらない。代わりに、佇む、残る、浸透する、気配がする。一〇〇としては現れないが、決してゼロにはならない。説明を請うても「察しろ」と叱られたり、「野暮だな」と言われたりしそうで、頭で理解するのはなかなか苦労します。でも確かに、一面に咲き誇るバラよりも、せいぜい一週間で散りゆく桜のほうに目が奪われるという感情は、共感できます。
小説家・ドイツ文学者の竹山道雄は、ゲシュタルト心理学を用いて日本の芸術を説明しようとしています[1]。曰く、例えばコンパスで計ったような正確な曲線を保つ中国の陶器は、鑑賞者の精神や感情を規定してしまう。「このように鑑賞してください」と、筋道がたてられているわけです。しかし、形がいびつで表面にむらがある日本の陶器には、鑑賞の〝答え〞がない。そ
の代わりに、対象を安定した形で捉えようとするゲシュタルト=形態による知覚が働き、鑑賞者は想像力で対象の形を補おうとする。つまり、欠けた部分やむらのある部分を埋めようとするわけです。この時鑑賞者は、対象を前にしてはいるけれど、対象ではなく、対象の背後にあるものを見ようとするのである、と。
[1] 竹山道雄『日本人と美』(新潮社)
対象は形ある物質ですから、有限です。大きさや重さは決まっています。けれども対象の背後にあるものを想像することは、対象の有限性には制限されません。自由に想像できるわけです。この、鑑賞者の想像力の働く余地のある「不完全さ」があるゆえに、対象はむしろ無限に近づくことができるのだと、竹山は続けます。ただこれは、日本の文化や日本人の美意識だけが持つ特徴というよりは、何かを見て、感じる時の、人の心のありようの次第だと思うのです。なにも日本だけが特別なのではないだろう。想像することはすべての人間に許された行為です。重要なのは、その「不完全さ」を、どんな想像で埋めるのか、ということです。
3. 自分とは何か
さて、ここで唐突に話題を変えます。
〝自分〞とは何でしょうか。
かつて「自分の皮膚の外側はすべて〝異郷〞である」と言った文化人類学者がいました。自分以外のことはよくわからない。ということは、逆に言うと、自分のことだけはわかる、ということでしょうか。ところが、自分とは何かを証明することは、考えてみると、とても困難です。
生物学者の福岡伸一は、「動的平衡」という概念を使って、生物の〝生命〞を考えていきます[2]。人間の細胞は、絶えず生成と消滅を繰り返している。六〇兆個あるとも言われる人間の細胞は、血も肉も骨も内臓もつねに生まれては消えることを繰り返していて、たった数年で肉体のすべてが新しい細胞に入れ替わるとさえ考えられています。しかしそれ以上に重要だと思えるのは、自分の細胞が誰かや何かの一部になり得ることです。つまり、自分の手の皮膚の、外気に触れている部分の細胞が、ある瞬間に肉体を離れ、分子となって宙を飛び、風に吹かれて、誰かの口に入り、その人の体の一部となる。あるいは海を渡って南極まで漂い、クジラに飲み込まれて潮となって噴き出て、南極の海の一部となる――ということだって考えられるわけで
す。身体とは、自分という存在を離れて移ろい消えゆくものであり、自分以外の誰かや何かの一部になり得るもの。だとしたら、自分という存在を、少なくとも物理的に証明することなんて、不可能である。そんなことをしても意味がないとさえ、思えてきます。
[2] 福岡伸一『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)
では、精神的にはどうでしょうか。精神科医のカール・グスタフ・ユングは、人間の「無意識」には、個人が生きていくなかで自ら獲得していくもののほかに、もうひとつ、人間が生まれつき遺伝的に備わった「集合的無意識」があると述べました[3]。例えば、「愚者(トリックスター)」。人間の社会的ルールから逸脱したような、非合理的・不可解な存在であり、同時に神と交信するなどの特別な能力を備えている彼らを、なぜ世界中の神話や伝承で――あるいは人々の夢のなかでさえ――神に近い存在として崇拝するのか。それは、誰かに教わったわけではない。けれどもそうするものだと知っている。なぜなら人間は、そうしたモチーフ――ユングは「元型」と呼びます――の意味を、太古の記憶から受け継いでいるからである。つまり人間の無意識の、少なくとも一部は、自分という個人ではなく、言ってみれば〝人
類の全体〞に属している。遠い過去から、現在を貫き、遥かな未来まで、微動だにしない〝全体〞の一部として、個人の精神がある。
[3] カール・グスタフ・ユング『元型論』『続・元型論』(ともに紀伊国
屋書店)、『ユング自伝1・2』(みすず書房)
もうひとつ例を挙げましょう。仏教哲学者の鈴木大拙は、日本人の宗教意識である「日本的霊性」が現れるもののひとつに、「禅」を挙げています[4]。禅とは、合理的・論理的な理解を越えたものであり、したがって言葉によっては説明できないとしながら、大拙は、言葉を尽くして、なんとか伝えようとします。象徴的なのは「AはAであってAではない、ゆえにAである」という即非の理論です。何か=Aを理解する時、一般的に人は言葉による定義や社会的な常識などによって、Aをとらえます。例えば、「雲は白い」と言
う。だが、白とは何か。虹には色の境目がないが、雲を「白い」と言ってしまった瞬間に、言葉の定義や通念などによって「白」の色の境界が定められてしまう。つまり「雲は白い」という時、「白」以外の白では見えていないわけです。だから「白」を捨てないと、本当の白は見えてこない。
[4] 鈴木大拙『日本的霊性』(岩波文庫)、また以下は『鈴木大拙 続・
禅選集1〜3』(春秋社)も参照した
この白とは、言葉や常識、思想や観念を越えた、〝そのもの〞としか言えないものです。「白」という言葉からこぼれ落ちる、すべての白を持つ白〝そのもの〞。なにも白だけに限らない。花でも虫でも人でも、そして自分や個性と言い換えてもいいでしょう。あらゆる限定を越えた、無限の広がりに〝そのもの〞がある。禅は、そうした〝そのもの〞を強く肯定します。
その中に自分より以上のもの感ずると、自分というものがなくなる、そのなくなったところから、自分というものがある、ということになる、そこ
に有難い気分がわくのである。
鈴木大拙『鈴木大拙・続禅選集2 禅とは何か』(春秋社)
自分というものはある。確かにある。けれども、自分以上のものがあると感じる時、自分はなくなるのだが、同時に、自分という〝そのもの〞があることに気づく。――言葉で考えるとまったく矛盾していますが、繰り返すと、禅とは言葉による理解を越えたものです。ないけれどもある、という、矛盾や二元論的な対立を越えたところを目指すわけです。そこにおいて「有難
い」、つまり喜びに似た尊さがあるのだ、と大拙は言います。悟りとはそのような状態のことを指すのかもしれません。
4. 自我を超える
ところで、自分以上のものとは何でしょうか。神のような存在でしょうか。あるいは死? 生命? 私はこう思います。――太古の昔から受け継がれてきた営為であり、人間の近代文明が支配しようとしてきた自然であり、現代もなお解明できない宇宙。あるいは、すぐそばにいる隣人の心であり、名も知らぬ誰かの痕跡であり、いつかどこかで見たかもしれない風景であり、自分が死んでいなくなった後の世界で生きている誰かの言葉である、と。
おそらく、漠然としたものではない。厳然としたものでもない。もっと具体的な、自分の手で触れられそうなもの。あるいは、もっとやさしくて、馴染んだもの。気づけば自分のすぐ脇にいるような、あるいはすでに自分のなかにある/いるようなもの。それらは、自分を形づくるもの、自分を自分たらしめるものであるけれど、だからと言って自分に属するものではなく、むしろ自分が属している。自分は、自分以外のすべて=全体に属している。自分とは、全体の一部でしかないのです。
ここで話題にする自分のことを、仏教用語では「小我」、哲学や精神分析学、また一般的な言葉では「エゴ」と言うようです。端的に言うなら、エゴを越え、捨て去った時、全体に属している自分という〝そのもの〞の存在に気づくことができる。あるいは、自分が属する全体という存在に気づくことができる。本書に採録したように、「正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである」と宮沢賢治が言うのは、土に触れるという日々の小さな営みが、遥かな宇宙全体へ直結することを謳ったものです。そのように、ささやかなエゴが放棄され、「世界が一の意識」となる時、「農民芸術」という、ひとつの美が現れるのである、と。
冒頭に挙げた数学者・岡潔の言葉は、この心象を物語っていると思うのです。岡はある日、奈良の博物館で正倉院の布のきれの展示を見ていたと言います。三時間ほど丹念に見、ようやく館の外に出ると、周囲に松が生えている。それまで松を見ても「いい枝ぶりだ」などと思うことはなかった。けれども、目にするどの松のどの枝も、よくできているように思われた。なぜか。「自分の心からほしいままなものが取れた」からだと言います。
「ほしいままなもの」とは、「自分が欲するもの」という意味ではないでしょう。辞書的には、自分のやりたいように、思うように振舞うこと、とでも言えますが、むしろ、そのように振舞う自分=エゴということでしょう。つまり、自分の心からエゴが取れた。その時に、自分を自分たらしめるものに気づいたのでしょう。自分と、松の枝が、同じ「全体」の一部である。「全
体」を通してつながっている。もっと言えば、だから、松の枝ぶりに、自分の姿を見た。かつて自分だったものの欠片、いつか自分になるであろう欠片を見たのでしょう。岡は別のところでこんなふうに言っています。
外界はすべて懐かしく、そうであるということが嬉しいという、これが大宇宙の心です。
岡潔『数学する人生』(森田真生編/新潮社)
岡の言う「大宇宙」、つまり全体を意識することを、「懐かしい」という言葉で説明しています。岡は松の枝ぶりを見て全体を思い、また松の枝ぶりに自分の姿を見て、懐かしいと思ったのでしょう。そしてこの時初めて、「美しい」という、情緒が現れたのです。
5. 美という情緒
私がタイのアユタヤで大破した石像を見て、瞬間的に美しいと思ったのは、像に自分の姿を見たからなのでしょう。正確に言えば、像の失われた部分を、かつて自分だった/いずれ自分になる欠片で埋めていた。埋めることで、全体に通じていた。全体につながろうとしていた。ゲシュタルトの話で言えば、私は像の欠損に自分を見、そして自分以上の存在で欠損を埋めて
いたのです。だから像は美しくなった。私にとって美しいと感じることができたのです。
つまり人は、何かを見て美しいと思う時、その何かとつながることができるのです。例えばひとりカフェに座っていて、窓から射す日の光が、店の棚にあるグラスに反射している。その様を見て、美しいと思ったとする。その時その人は、数年前もこの店のこの席で、誰かが同じような風景を見ていたのかもしれないと、思いを馳せることができる。あるいはカップに注がれたお茶を飲み、美味しいと感じたとする。その時その人は、このお茶の葉はどこからやってきたのだろう、そのカップは誰がつくったのだろうと、想像する
ことができる。こう考えると、美しいという情緒は、誰かや何か、そして全体につながるためにある。そのための装置や扉、回路や手段でしかない――そうとさえ、思えてくるのです。
繰り返しますが、これはなにも日本人だけに許されたことではない。美しいという情緒は、生まれつき自分のなかに備わったものであり、身近な何かや、親しいものに触れた時に、ふと頭をもたげるものなのでしょう。だから誰であれ、何に対してであれ、起こり得ることなのです。そう、ある人は花と森と人の日常の接点に、ある人は京都・美山の暮らしと集落の遺跡を発端に展開する物語に、ある人は千葉・鴨川の里山の偉大なる日常に、ある人は長く暮らしに息づいた結びという人の営為に、ある人は大地を踏みしめながら仰ぎ見た銀河に、ある人は皮膚の下にある骨と血という野性に、ある人は人間と人間以上の存在を食がつなぐという世界のありように、ある人たちは羊毛などの暮らしの風景と身近な隣人と重ねた出会いと会話のなかに、美しいという情緒が芽生え、全体を見たのでしょう。それは『mahora』と題したこの本に、すでに記してある通りです。
最後になりましたが、本書にご寄稿いただいたみなさんをはじめ、デザインを引き受けてくれた須山悠里さん、ウェブを構築してくれた藤本圭さんに、感謝を申し上げます。みなさんがいなければ、『mahora』というこの本を世に見ることはできませんでした。そしてこの本を手に取ってくださったみなさんと、私がこれまで出会うことのできたすべての方々に、御礼を申し上げます。
『mahora』は本書が創刊号となります。内容はもちろんですが、装丁、印刷、流通、販売など、本にまつわるあらゆる場面で、やりたいことはまだまだあります。それも少しずつ、小さな成果をいくつも積み上げていくことに喜びを感じながら、実現していきたいと思います。そしてまた次号刊行の折、みなさんと再会できることを、楽しみにしています。

2018年6月 夏の匂いを増した風が吹く夜に
『mahora』編集・発行人 岡澤浩太郎
多くのご支援ありがとうございます。木々や星々は今日も豊かさを祝福しています。喜びや健やかさにあふれる日々をお過ごしください。
