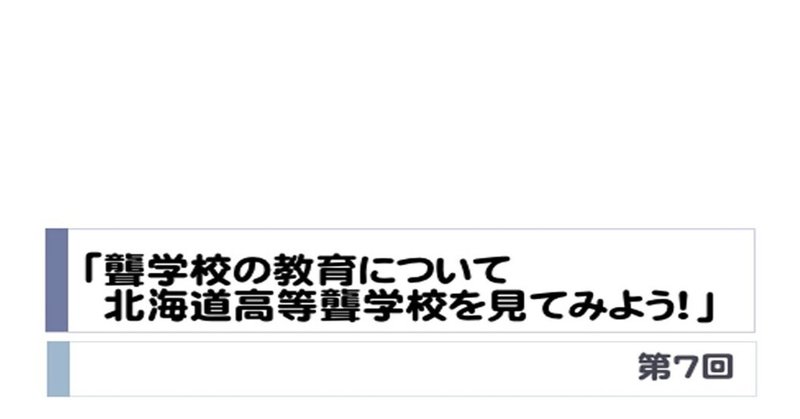
ろう学校とはどういう場所?
乳幼児から高校卒業までの18年間、学んだのは「ろう学校」である。聞こえる人が通う普通学校での選択も必要だと考えたこともあったが結局ろう学校育ちで、学齢期が終わったのである。卒業式が終わった今頃は、必ず学年末テストが控える時期であり、この期間が私にとっては嫌いな時間だったことを覚えている。
私だけではなく、卒業生の多くは同じ気持ちだろう。そりゃ無理もない笑!一緒に学び、語ったり部活動で汗を流したりと過ごしてきた先輩方の濃い時間をテスト勉強で離れてしまう気持ちが整理出来ずに切り替えなきゃいけないということであった。これは生徒だった自分に言い聞かせると、言い訳できなかった。大人になって教師として働いて逆に立つと卒業生たちには、申し訳ない位の気持ちもある。でも毎年恒例として続くことは、どうしようもない。実に裏をいうと、結論は大人の都合である。生徒主体ではなく、学校経営として大人の事情を考えてのスケジュールのために生徒の気持ちを見てあげるという甘い考えはないのである。そこが私に取っては、良い選択だろうかと疑問に感じていると振り返っている。
とさておき、「ろう学校とはどんな場所か。」という本題になる訳だか、私は耳が聞こえない世界として象徴づけるものと多く聞くイメージではなかった。一言でいえば、単なる普通学校と変わらない。でも聴覚障がいをもつ生徒を受け入れるので、中学部までの教育課程をそれぞれが全て同じ状態で終わっているとは限らず、各学校でバラバラな実態のまま一つの場所に集まることの特別な場所だと感じる。だから中には中学レベルを理解していない生徒もいるし、高校レベルに付いていける生徒もいるなど同じスタートラインに立っていないという空気感が最初はある。
またもう一つ、北海道ならの特徴だか聴覚口話法の指導法を徹底していた時代が長かったためにその背景で育ってきた児童生徒が多い状況だった当時は、手話が主体である児童生徒に対して口話でつい会話してしまうということも当たり前な風景だった。そのため、手話が主体だった生徒は距離が離れてしまうなどの人間関係が悪くなるとそこで改めて気付いてお互いに歩み寄ろうと新たなコミュニケーションの構築に努力するということも多い訳である。(※このコミュニケーションについてを第7回「北海道高等聾学校を見てみよう!」で取り扱っているので、ぜひ視聴してもらいたい。)
残念なことに最近は、SNS(LINEやFacebook)によって顔を合わせないコミュニケーションツールの流行で直接、顔合わせるような会話する機会が減少してしまっているのだ。そこで人間関係のトラブルが起きてもおかしくない訳である。聞こえる世界だったら、「いじめとか不登校」とかあることもよく聞かれるが、聞こえない世界ではいじめとか不登校という社会問題になることはほとんど聞いたことない。今の聞こえない生徒というのは、いじめという概念がわからないということである。お互いに聞こえないとわかっているからこそ、同じ人間として接する。そして会話が通じていれば、なんとかなるという感じで自然に生活していく場所だから、なかなか憎めないのだ。
変なトラブルで人間関係が揉めたり、嫌になったりする問題は私も数多く経験しているし、みんな同じである。しかし、時間が経つとお互いに冷めきって謝罪してよりつながりを大切にするという事がろう学校としての日常的茶飯事である。「ろう学校」というのは前述のようなことがあって、1年ぶりとか2年ぶりとかで短いスパンで母校に遊びにいくとか、後輩つながりで情報が入ってきたりするなど母校を身近に感じることもある。私は、たまたま教職員として勤務していたので、年齢が離れていても若返りのように接する機会も多く、生徒からみると年齢の差を感じないただの社会人として見られていたという笑。中にはきちんと大人として接してくれるけど、私はそれが固いのは嫌いだったので、あえてふざけていたイメージをちょっと出しているつもりが、うまく伝わってくれたかどうかは別とする。
また一般高校と違うのは、卒業したら母校に遊びに行くという卒業生が多いという風潮だ。だから年齢が離れていても後輩たちのためにと足を運ぶことによって、新たなコミュニティが生まれる。そして伝統を引き継いでいくこともあれば、経験したことを懐かしく共感したりするなどの会話もある訳である。ろうコミュニティーは、ろう学校で作られてくるという暗黙の知であるとする。
一般高校に通う聞こえる人は、卒業後は足を運ぶことってあまり考えない。だから何かの機会で訪ねるというと「●年ぶりだなー。」とかという想い出に浸すことはかなり時間が経つわけである。そんな風に「ろう学校」というのはロールモデル的存在としても重要な効果を活かせる場所でもあり、障がい者のキャリアとして見えるビジョンでもある姿がコミュニティーを通して考えさせられるという機会は、とても大事である。
ところがある日、後輩つながりで在校生の実態を聞いてびっくりした。コロナ禍によっていつもの日常とは、違う生活の厳しさを経験していることで、つまらないし青春を楽しんでいない(教師とのコミュニケーションも下がっているという厳しい不満も・・・。)という声を聞いたばかりである。現場から2年離れている間に、こんな気持ちを抑えながらも学び続けている在校生を意識していなかったとすると申し訳ないぐらいだ。もしあの時に勤務していたら、何かのアクションは起こして生徒の成長を応援していきたかったと思っている。実にもったいないと綴じておく。そして卒業した生徒の新しい旅立ちをどこかで応援して行きたい。
