
歴史地理学者の千田稔さん 学術研究の人生を邁進、幅広い見識で諸活動
「人生100年時代」といわれるが、その第四コーナーを回った現在、時にふれ来し方を振り返る。順風満帆とは言えない人生の過程で、その後の人生に大きな影響をもたらせた、キーパーソンともいうべき出会いがあった。歴史地理学者で、奈良県立図書情報館館長の千田稔さんは、まさにその一人だ。
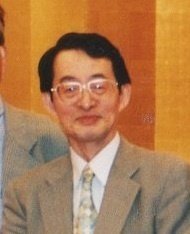
新聞社の記念企画で、歴史上実在した玄奘三蔵をテーマに一大プロジェクトに挑んだ私にとって、羅針盤のような役割を担っていただいた。私の書斎には、知己を得て、千田さんから贈られてきた著書は20数冊を数える。そこには私の知らなかった世界が広がり、なお好奇心にあふれる情報に満ちている。
朝日新聞社と薬師寺の協力関係の橋渡し
私が朝日新聞社の文化企画の仕事に携わっていた時、1999年の創刊120周年記念プロジェクトに「シルクロード 三蔵法師の道」をテーマにした学術調査や展覧会、シンポジウムを提案し、採用された。「戦争の世紀」と言われた20世紀末に、「アジアの世紀」とされた21世紀に向けて、玄奘の実践した生き方を検証し、現代人が学ぶべき指針を発信できればとの趣旨だった。
当時、奈良県では、1988年に奈良シルクロード博覧会を開催したのを記念して、財団を発足させシルクロード政策を進めていた。その柱が国際シンポジウムで、朝日新聞社および日本ユネスコ協会連盟とともに隔年で催していたが、それまでシルクロードを経て日本に伝わった仏教伝来については取り上げてきたことがなかった。
世知辛いこの世相の中で、7世紀に中国の長安(現在の西安)を出発し、天竺(インド)まで仏教の経典を求めて17年もかけ旅をした三蔵法師・玄奘の旅は何と夢とロマンに満ちていることか。学芸部編集委員で国際シンポジウムのスタッフでもあった高橋徹さんとの喫茶店の雑談が発端だった。三蔵法師・玄奘をテーマにすれば、創刊記念事業と国際シンポの課題を併せて解決できる可能性がある。私は直感的に「これだ」と確信した。

「三蔵法師の道」企画が、なら・シルクロード博国際交流財団と協議し、国際シンポジウムのテーマに決まったことで、次の課題は薬師寺の協力を取り付けることだった。薬師寺は法相宗の大本山で、玄奘ゆかりの寺だ。しかし朝日新聞社と薬師寺との関係は、必ずしも十分良好とはいえなかった。朝日新聞社が東大寺の大修理や法隆寺の壁画修復などに力を入れてきた経緯もあり、敷居が高かった。しかも高田好胤管主の憶えもよくなかった。

1996年4月、私と高橋さんは当時執事長だった安田暎胤副住職らに応対していただいたが、それまでの両者の関係について不満の様子だった。 しかし今回のテーマが薬師寺が顕彰する玄奘ということで、協力していただけるがことが約束された。この橋渡しをしていただいたのが高橋編集委員の長年の友人だった千田さんだ。安田夫人の恩師が千田さんの父だったこともあり、関係改善が円滑に進んだ。

千田さんは1942年、奈良県生まれ。1966年に京都大学文学部卒業後、京都大学大学院文学研究科地理学専攻博士課程へ。1970年に大学院を中退し、追手門学院大学文学部講師に。そして文学部助教授を経て、1976年に奈良女子大学文学部助教授、89年には教授となる。1992年、文学博士(京都大学)となる学位論文は、「古代日本の歴史地理学的研究」であった。
その後、1995年から2008年まで国際日本文化研究センター教授を務め、帝塚山大学特別客員教授はじめ、 平城遷都1300年記念事業協会理事、人文地理学会会長なども歴任した。この間、古代日本の歴史地理学的研究についての業績により、1994年に浜田青陵賞、2007年に奈良新聞文化賞を受賞、2021年瑞宝中綬章を受けている。
まさに学術研究一筋の人生を歩んでこられたが、洒脱で気配りの長けた人柄で、周囲から人望と信頼を得ていた。千田さんの助言があったればこそ、薬師寺とのパイプになったと言えよう。
衛星画像を活用し、「三蔵法師の道」探る
私が千田さんを知ったのは、国際日本文化研究センター教授の時だった。「三蔵法師の道プロジェクト」は、国際シンポジウムだけでなく展覧会や学術調査を三本柱としていた。千田さんは歴史地理学の泰斗であり、暗中模索の学術調査の要としての大役を担っていただくことになる。
千田さんと高橋さんの人脈で、国際日本文化研究センターはじめ、奈良女子大学、奈良県立橿原考古学研究所、滋賀県立大学などへと支援の輪が広がった。研究者と朝日新聞のスタッフは、何度も奈良女子大学の研究室に集まり勉強会を重ねた。時には勉強会後に酒席をともにし懇親を深めた。

調査の方法や手段などについて語り合う中で、「三蔵法師の道研究会」を発足させた。1997年春、研究会の発会式を開き、代表は千田さん、幹事役に高橋編集員が担った。実地調査の度に、その都度専門の研究者が加わり、メンバーは朝日新聞社スタッフを加え20人を数えた。
山や川といった地形、集落や道路などの過去の景観を復元するのが、歴史地理学の方法だ。そのためには、過ぎ去った時代の遺跡を見つける大縮尺の地図や精度の高い空中写真が必要となる。そこでアメリカが1960年代に撮影した高度の偵察衛星写真が注目された。
千田さんと奈良女子大学の小方登助教授(地理情報科学、後に京都大学大学院教授)が、文部省の科学研究費によって東アジアの歴史景観の復元を試み、その成果は公表されていた。 「玄奘は厳しい氷山の天山山脈をどこで越えたのだろうか」が最大のナゾで、研究会では文献調査を基に、新たな手法として宇宙から届けられる地図を活用した。人工衛星が撮影した高解像度の写真を使って古道や遺跡を分析し、実地踏査で確認していく、いわば「衛星画像考古学」といえる試みだった。


現地への調査隊員は考古学や地理学、建築史、仏教学、歴史学など幅広い専門学者らで構成、メンバーを変えながら拠点地域に派遣した。五次にわたり、四次調査には、千田さんも同行した。人の足と動物の背中だけの玄奘の旅とは違って、ジープやヘリもチャーターして、広大な地域をカバー。また撮影位置などが分かるGPSカメラなどの機材によって多くのデータを得た。
陸路とヘリの調査や、キルギスの遺跡分布などを分析し、ベデル峠が妥当と判断するなど、多くの成果を得た。中央アジアはロシアから独立し、やっと仏教遺跡の発掘などが進み始めていた。調査の結果は随時紙面化し、その報告書は『三蔵法師のシルクロード』(1999年、朝日新聞社)として出版した。


また学術調査での朝日新聞カメラマンによる記録写真は1万枚を超え、ピックアップした150点の写真展は、玄奘のルートに沿って展示された。この中には、玄奘が長期間滞在した高昌城跡や中国とキルギスタンの国境のベデル峠などの空撮写真が含まれ、わが国で初公開になった。また未知の旧ソ連領域のほか、古代城壁や仏教遺跡などの写真資料も得られた。
千田さんは「衛星写真で想定した遺跡を確認する手法はとても効果的だった。玄奘が西域記に記した風景をよみがえらせることができた」と振り返った。雲をつかむような無謀なプロジェクトは、千田さんの指導によって、道が拓けたのだった。
日本史・思想史など多岐にわたる著作の数々
学術調査を皮切りに足掛け4年取り組んだ「シルクロード 三蔵法師の道」プロジェクトは、シンポジウムをはさみ、1999年末、東京都美術館での展覧会を最後に、すべてを終えた。一連の企画を支援していただいた千田さんとの関係も絶たれるはずであったが、その後、折に触れお会いし、交流が続けられた。何よりも驚くべきことに、毎年のように出版された著作が次々と贈られてきたことだ。私の本棚の一角には「千田著作コーナー」が設けられている。

贈呈本は『平城京の風景―人物と史跡でたどる青丹よし奈良の都―(古代三都を歩く)』(文英堂、1997年)に始まる。著書の中で、千田さんは「時折、私は奈良を歩きたくなるのは、古代というよりは、日本という国の素性を実感できるからだ。例えば、東大寺の大仏に、世界を過剰に意識したしおらしい国家意識を読みとることができる」と記し、次のような文章も、私の脳裏を刺激した。

奈良の寺を訪ねるたびに、私はある種の「渇き」を感じる。京都の寺で
はそんな経験がない。むしろ「湿っぽい」空気が漂う。なぜなのだろう
かと思う。京都の寺の庭がそのような印象を与えるのかもしれない。そ
ういえば、奈良の寺では伽藍に視線が奪われてしまう。人は天平の伽藍
に包み込まれて、おのれの小さな存在にとまどうのだ。そして、存在の
確かなありかを求めてさまよう心は砂漠を行く旅人のように、「渇き」
を感じる。
さらに著作は、『王権の海』(角川選書、1998年)、『高千穂幻想―「国家」を背負った背景』(PHP新書、1999年)、『邪馬台国と古代日本』(NHKブックス、2000年)、『飛鳥―水の王朝』(中公新書、2001年)、『聖徳太子と斑鳩』(学研M文庫、2001年)、『地名の巨人吉田東伍―大日本地名辞書の誕生―』(角川叢書、2003年)、『古代日本の王権空間』(吉川弘文館、2004年)と、多岐にわたる。
著作は、日本史・思想史・東アジア交流史などの分野での研究成果を発表し、特に古代日本の宮都と中国の都城の象徴性の比較研究に力を注いでいる。また、古代東アジアにおける道教の研究を推進し、道教が古代日本社会において大きな役割を果たしていたことを明らかにした。高橋編集委員および福永光司・京都大学名誉教授との共著である『日本の道教遺跡』(朝日新聞社、1987年)や、『日本の道教遺跡を歩く-陰陽道・修験道のルーツもここにあった-』(朝日選書、2003年)なども本棚に並ぶ。
2005年以降も、『伊勢神宮―東アジアのアマテラス―』(中公新書、2005年)、『地球儀の社会史―愛しくも、物憂げな球体』(ナカニシヤ出版、2005年)、『古代の風景へ』(東方出版、2007年)、『平城京遷都 女帝・皇后と「ヤマト」の時代』(中公新書、2008年)
『飛鳥の覇者-推古朝と斉明朝の時代』(文英堂、2011年)、『こまやかな文明・日本』(NTT出版、2011年)、『まほろばの国から1』(飛鳥書房、2012年)、『古事記の奈良大和路』(東方出版、2012年)、『古事記の宇宙(コスモス)―神と自然―』(中公新書、2013年)と続く。
さらに『古代飛鳥を歩く』(中公新書、2016年)、『聖徳太子と斑鳩三寺』(吉川光文堂、2016年)など専門の地理学から歴史書や文化図書に及ぶ。千田さんの著作には、書斎に閉じこもって研究を重ねるというより、歴史的な場所に足を運び、五感で確かめるといったものが多い、「歴史を学ぶとは、万巻書籍で囲まれた密室を、打ち破ることなのだ。閉じこもることではない」と強調する。
シルクロードや古都・奈良の今後に持論
千田さんを知って四半世紀になる。この間、著作を通して数多くの情報と歴史への視点を与えられた。もちろん著作だけでなく、千田さんの国際日本文化研究センター退官慰労の集いなど各所でお会いし、時に触れ酒席をご一緒し懇親を続けている。その見識や人柄から大いに学ばせていただいた。

出会いとなった「シルクロード三蔵法師の道」プロジェクトの中心であった1999年6月の奈良県立美術館での特別展開幕の記念パーティーが奈良ロイヤルホテルで開かれた際は、「三蔵法師の道研究会」のメンバーもこぞって参加した。中央アジアからインドまで五次にわたった調査の思い出を語り合った。とりわけ代表を務めた千田さんの笑顔は印象的だった。


翌年の2000年12月に催した拙著『夢しごと 三蔵法師を伝えて』の出版祝賀会では「、発起人を引き受けられ、「がむしゃらであったが、一途に夢を追い求めていた」と、評価していただいた。

朝日新聞社との関係を取り持ってもらった薬師寺ではしばしば交流した。毎年5月の玄奘三蔵院での「玄奘三蔵会大祭」の法要で顔を合わせた。当時、国際日本文化研究センターの初代所長であった梅原猛さんもお見えになったこともあり、記念写真も残っている。



2006年4月には、薬師寺の安田暎胤管主(現・長老)夫人の安田順惠さんが社会人入学した奈良女子大学大学院で学位を取得した「玄奘取経の交通路に関する地理学的研究 CORONA衛星写真と現地踏査を基に」の祝賀パーティ―では、指導に当たった千田さんが、祝辞を述べた。会場には、その時の片倉もとこ・国際日本文化研究センター所長(2013年死去)も同席されていた。


千田さんは2008年春、13年間務められた国際日本文化研究センター教授を退官した。その記念講演会と慰労のパーティーが開かれ駆け付けた。片倉所長や安田順惠さんらとも和やかに語る宴も思い出となった。



千田さんは奈良県立図書情報館の館長を2005年の開館時から務めている。2014年春、館長室に訪ね、懐旧談ともに、一部ルートが世界遺産になったシルクロードについて所感を伺った。シルクロードと日本のつながりに関し、奈良や京都の街づくりは、唐の都の長安をモデルにしたと考えられている。
これに対し、千田さんは「古代ローマの都市にも碁盤状の街づくりが見られローマンタウンと称されています。長安の街の原型はヨーロッパにあり、影響があったのではないかという仮説も考えられます。もちろんシルクロードを通してのことです。今後の研究が待たれます」と、興味深い話に及んだ。
シルクロードの今後についても「ロマンをかきたてられることも事実ですが、現実を直視しなければ。観光の対象としてだけではなく、政治の問題も見据えなければなりません。古道がやがてハイウェイに取って代わり、消え去るように、現在のシルクロードの概念も変容してきました。現にシルクロードは各所で分断されているではありませんか」と、楽観論に釘を刺していた。
ユーラシア大陸を経てローマに至る広大な道について、2000年春から「シルクロード検定」が実施されている。その事業のスタートに関わった私は、関西から有力識者に呼びかけ人への協力を要請することになり、千田さんにも加わっていただいた。私にとって、人生のキーパンソンであり、知識の宝庫でもある。
最後に、シルクロードの東端に位置する古都・奈良の今後についても持論を展開しているので書きとどめておく。これは奈良県が促進している歴史追体験『記紀万葉』の「指揮者に聞く」の第2回に登場して、同じく古都の京都との比較から次のような見解を示している。
「古都」と言ってしまうと同じように考えますが、奈良と京都は質が全
然違うんですよ。平安時代に日本の文化を創り上げた京都は鎖国的な状
況でしたが、奈良は開放的で、大陸や朝鮮半島の文化を入れて融合させ
ようとしました。しかも、京都が1000年の都だったのに対して、奈良の
都は70数年。それなのに、その短い間に、奈良の都は、仏教を受け入れ
るという重要な役割を果たしました。奈良は日本の国家の始まりの場所
です。その重要さを今の日本人はしっかりと理解できていないんじゃな
いかなと思います。日本のことを本当に知りたいと考えている人は、ぜ
ひ奈良に来てほしいですね。奈良の、こういう底力が認識されると、も
っと奈良が脚光を浴びる時代が来ると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
