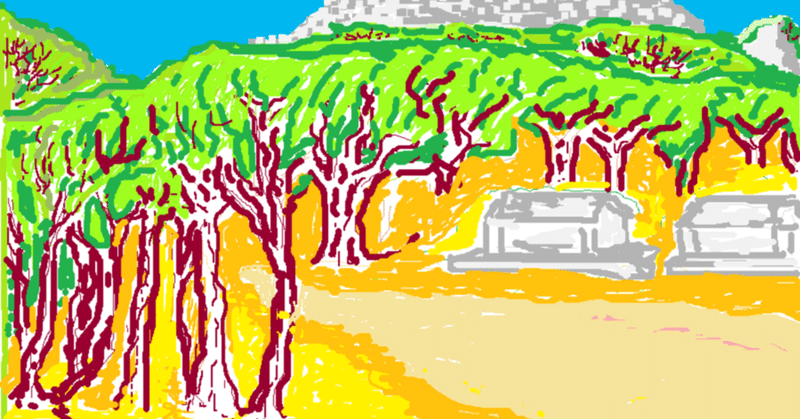
三人の魔術師:番外編 モノベさんの日常11「剽窃……どんなゲラも価値があると思っている。プロ意識を込めた赤字や注記はたいせつな思いが表現されている。むやみに捨てられない」〈日々の校正日記②〉~」
新年度から正社員になることが決まった。
契約社員として入社して1年近くで、ここまで仕事に恵まれるとは…驚きにくわえ感謝でしかない。
印刷局での現場の校正からいまは本社内の校閲部にいる。社史だとか全集なども担当する。
しかし、現場の印刷局の校正の中でも、クライアントから「ミスができないからより重点的なプロ校正を」という依頼があるケースで…本社内校閲部に校正が回ってくることがある。
校閲部は全部で二十数人、実際に校正校閲を作業する人間は常時10人くらいだ。あとは社史編纂編集部だとか全集編集部とかにまたがって仕事をする人たち。
10年以上前に社長の方針転換で、社史や全集、個人史、自費出版の書籍や冊子を積極的にやりだした時期があったそうだ。
ただウェブの時代にシフトしつつあり、事業は縮小傾向にある。出版社、印刷会社、紙媒体を扱うどの会社も縮小は免れない時代になった。
仕方がない話だ。その間隙を縫って、校正正社員に60を超えてなるというのもありえない厚遇といえた。
いずれなくなるからといいながら、失われていく技術扱いをして校正技術を軽く見る人間もいたが…人間のやることは根本は変わらないと思っている。
終わろうが終わるまいが技術をみがくだけだ。
社史も全集もやりがいのある仕事で、貢献したい気持ちが強くなる。
しかし、どんな仕事でもつまらないと思ったことがない。
31からこの仕事をやってきた。
飽きたことがないのだ。
不思議なことだった。
その代わり人間関係にはすぐ嫌気がさす。
仕事を数多く経験してきたのは、フリーであることもあったのだが、ひとが嫌だったことが主だった。
功罪あるがよかったのは多岐にわたるジャンルを経験できた。おかげでやったことがない仕事はあまりでくわさなかった。
何かしらの知識を経験として伝えられる喜びはこの年になればわかる。年々強くなるように思う。
とはいえ、どんな仕事も簡単にできるわけではない。
精神的にも心を揺さぶられず平穏に仕事はできないたちだ。
著作権だとか権利関係や薬機法や日本語の乱れに悶々とするのも常のことだ。今回もまた厄介な会社からの仕事でひりひりとした時間を耐えることになった。
あるコラムの署名原稿だった。ある映画のあらすじや作品の背景などをライターがユニークな視点で解き明かす長寿コラムでのことだ。
校閲の流れで映画のホームページをみた。
本文の内容との照合をしていたときに、内容がコラムの文とほぼ同じであることに気づいた。
感想や主張もほぼ同じ。
ふつうはばれないように語尾や文体をかえるものだが、それすらない。
映画のホームページには文章のクレジットがない。
可能性としてはコラムの署名原稿を書いた人間と映画のホームページの文章を書いた人間が同一人物という可能性もある。
しかし、よく考えると映画の関係の団体とこの会報冊子の団体にまったく関係はなかった。
ということは仮にライターが同一人物であっても、原稿料は二重にとっていることになろう。
内容が剽窃になる可能性を指摘して、校正校閲ゲラを戻した。その日のうちに担当する編集部の人間がやってきた。
「モノベさん、例の映画のコラムの件ですが…。あ、ありがとうございました。いつも線引きで書いたり分かりやすい統一指定ありがとうございます。先方もいつも喜んでくれてます」
「そうですか、喜んでいただいてうれしいです。例のコラムの確認はしましたか?」
「う~ん。実はこの仕事は間に編集プロダクションが入っているんで任せました。ボクもサイトを確認しましたが…剽窃は間違いないですよね。まあうちには直接被害は来ないんで、任せました。結果お知らせします」
「そうですか…よろしくお願いいたします」
結果はそのまま掲載された。
担当の人からは、編集プロダクションもスルーしたとのことだった。
事情があるないは分からなかったが、こういうことが平気で問題にもならないとは…物を書くという価値はいまのこの業界では、著しくかろんじられているのではないかと感じざるを得なかった…。
しばらく本文が頭に入ってこなかった。
私は控えゲラでも捨てるのを躊躇する。
資料価値としてだけでなく自分の校正校閲が好きだからだ。
どんなゲラも価値があると思っている。
プロ意識を込めた赤字や注記はたいせつな思いが表現されている。
むやみに捨てられない。
かのライターさんは、どういう気持ちであのようなことを行ったのか?
自分の作品が好きでないのだろうか?
自分なら自分の作品はかわいくて汚したりなどはとてもできない。
ましてや他人の書いたものを自分のものとして愛せるわけもない。
余計なことかもしれないが、そんな行為をして自分を傷つけることになりはしないかが心配になる。
自分の作品が好きでないのだろうか?
もやもやした気分でしばらく校正を続けざるを得なかった。
