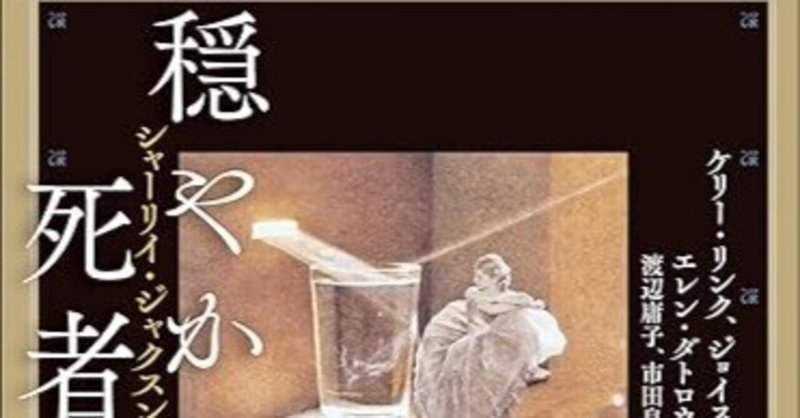
日記:20231126〜「穏やかな死者たち シャーリイ・ジャクスン・トリビュート」〜
小説家シャーリイ・ジャクスンに魅せられた作家たちが、ジャクスンの作品へのオマージュを捧げた書き下ろしアンソロジー『穏やかな死者たち』を読んだ。
参加している作家で読んだことがあるのはケリー・リンクとジョイス・キャロル・オーツだけだったけど、大好きなシャーリイ・ジャクスンのトリビュートということで期待して読んでみた。期待以上の読み応えで大満足。
【ネタバレを含む感想です】

M・リッカート「弔いの鳥」
悪意を含んだ微妙な人間関係を遠回しに仄めかす手法や、語り手のモラルが壊れた行動の描き方が、とてもジャクスンらしい。終盤にデローレスの幽霊が当たり前のように顕現するあたりは、ジャクスン流のホラーというよりも、マジック・リアリズムやアンリアル小説の領域かと思った。うまく消化できない読後感にもやつくところもシャーリイ・ジャクスンっぽい。
エリザベス・ハンド「所有者直販物件」
巻中でも特に好きな作品。何が起きたのかをぼやかしたまま、取り返しのつかないことが起きてしまったことを示唆する終わり方は、怪談小説の典型ではあるけれど、主要な登場人物が50〜60代の女性たちという点がユニーク。若くはない女性たちが無人の空き家で一夜を明かす秘密の冒険が、読んでいて心の躍るような、切なくなるような感覚に襲われる。
ショーニン・マグワイア「深い森の中で――そこでは光が違う」
配偶者の支配から逃れようとする女性が怪異に遭遇し、結果的に支配から解放される。この作品も直接的な表現を省略し、曖昧なやりとりから事態が暗示される。シャーリイ・ジャクスンよりも、『寝煙草の危険』『わたしたちが火の中で失くしたもの』のマリアーナ・エンリケスや、『兎の島』のエルビラ・ナバロを思い出した。
カルメン・マリア・マチャード「百マイルと一マイル」
スーパーナチュラルな要素はなく、サイコ・サスペンスから派生した作品と言えるかもしれない。心に闇を抱えた人間の異常な行動を当事者の側から描いている。セクシャリティの問題も含め、非常に繊細な作品。
カッサンドラ・コー「穏やかな死者たち」
惨殺事件の発生により周囲との関係を絶ち孤立した村で人間同士の不信や差別が露わになり、やがて次々と事件が連鎖していく。直接的な残酷描写と同じくらい、凝り固まった価値観で生きる人々のグロテスクさが強烈。乱暴に突き放すようなエンディングは、エリック・マコーマックの作品を思い出した。
ジョン・ランガン「生き物のようなもの」
好みとは別に、ある意味で最もシャーリイ・ジャクスンらしい作品。ジャクスンの未発表作品と言われたらうっかり信じるかもしれない。
カレン・ヒューラー「冥銭」
ジャクスンではないけど、ホラー小説の名作「猿の手」系列の作品なのかなと思った。読んでいて不快になる厭さ、薄気味悪さは傑出している。帰ってきた死者たちは、生者自身の後悔を具現化した存在なのか、それとも死者を物語化することで贖罪しようとする生者の甘えた願いを嘲笑う存在なのか。どちらにせよ、皮肉この上ない。
ベンジャミン・パーシィ「鬼女」
ジャクスンらしさと作品としての好みや面白さは必ずしも一致しなくて、本書の中では長めのこの作品はあまりシャーリイ・ジャクスンっぽさは感じなかったけれど、田舎を舞台にしたホラーとしては出色の出来栄え。謎めいた冒頭が、どう現在につながっていくかも含めて、完全に心を掴まれたまま読み耽った。映画的というか、映像が浮かんでくる描写も良い。
ジョイス・キャロル・オーツ「ご自由にお持ちください」
最も短い掌編。これはちょっとどう受け止めればいいのか、難しい作品だった。もしかしたらジャクスンの育児本(「野蛮人との生活」)を下敷きにして、子育てする母親の暗部を描いたのだろうか。
リチャード・キャドリー「パリへの旅」
家族を毒殺した家の壁に、殺された家族たちのシルエットのような黒カビが広がっていくという怪異現象と、犯した罪を隠そうとする主人公と、好人物だけどどこか抜けているジェイムソンの噛み合わない会話に湿った不気味さが漂っている。不安に追い詰められ破滅していく様子が、どこか虚ろで息苦しくも薄気味悪くもある。
ポール・トレンブレイ「パーティー」
居心地の悪いパーティに出席した同性カップルのお話。これは難しかったなあ。休憩所で見つけたものが何だったのかも分からなかった。恥ずかしながら解説求む。
スティーヴン・グレアム・ジョーンズ「精錬所への道」
いちばん好きな作品。こういう小説が読みたかったと言えるくらい好き。ジャクスンらしさという点では弱いかもしれないけど、ジャクスンに惹かれた作家が書いたと思うと、より愛着が募る。ジャクスンの作品はたとえば江戸川乱歩のように、「あの頃」への痛みや恥ずかしさも含めたノスタルジアを感じる人も多いのではないか。ホラーと郷愁は本当に相性が良い。
この三人だけだ。昔からそうだった。この先もずっと。
この先はきっと最高だろう。
ずっとそうだった。
ジェフリー・フォード「柵の出入り口」
ちょっと衝撃的だった。いかにもリアリズム的なかっちりした書き出しから、気づいたら想像を絶する法螺話のような物語が展開する。それでいながら荒唐無稽にならず、端正で地に足のついた語り口のまま進むのがすごい。邦訳が何冊か出ているようなので、別の小説も読んでみよう。
ジェマ・ファイルズ「苦悩の梨」
自傷行為を通じたはみ出しものの少女同士のあやふやな関係性。これもマリアーナ・エンリケスを思い出した。あと『アホウドリの迷信』に収録されていた「アガタの機械」や「最後の夜」などの作品も。自傷行為や儀式の内容はエグいけど、同級生から受けるいじめの幼稚さが意外でもあり、リアルでもあった。主人公の勇敢さを称える場面もありながら、良い話のまま終わらせないところも、とても誠実に描かれている。
この世界ではほかのみんなはなにをしても許されて、わたしたちはなにをしても許されない。せっかく似た者同士の二人の変人が互いを見つけ、共感し合い、いっしょに物語をつくり、その物語を信じているかのように自分を欺き……とにかく信じているかのようにふるまっているのに。
ジョシュ・マラーマン「晩餐」
面白かった。背景が一切説明されていないディストピア世界でのヒリヒリするような緊迫感が伝わってくる。要所要所で「数学」にまつわる言葉遊び的な描写が出てくるのも面白い。着想の卓抜さに終わらず、深い読後感が続く。
ジュヌヴィエーヴ・ヴァレンタイン「遅かれ早かれあなたの奥さんは……」
これも少し難しかった。家族や配偶者などの「男性」からの庇護の形を借りた支配を受ける女性たちと、支配から自由になろうとする彼女たちを待ち構える暴力、がテーマなんだろう。意味深なタイトルは、彼女たちの復讐が始まることを示唆しているのかもしれない。
レアード・バロン「抜き足差し足」
ノスタルジックな少年時代の回顧録のような物語に、文字通り忍び足で不吉な影が迫り、驚愕の結末を迎える。ラストの描写はマンガで表現するのがいちばんしっくり来るような気がする。
ケリー・リンク「スキンダーのヴェール」
最後にとんでもない小説が待っていた。「柵の出入り口」と並び、異色作だらけの本書の中でもとびっきりの異色作。完全にドラッグの幻覚としか思えないシーンが延々と続く中で、鹿が出てきて嬉しかった。ですます調の語り口も含めて、おとぎ話的な雰囲気でもあるのか。
ミハル・アイヴァス「もうひとつの街」にもちっちゃいヘラジカが出てくる描写があったけど、欧米の幻想作家にはときどき鹿が登場する。日本の作家ももっと幻想の霧から現れる鹿を描いてほしい。
話し終えて、彼女がアンディに「お休みなさい」というたびに、彼はすぐさま眠りに落ちました。そして、朝になって目をさますたびに、夢見の状態で卒論を書き進めたことにも気づくのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
