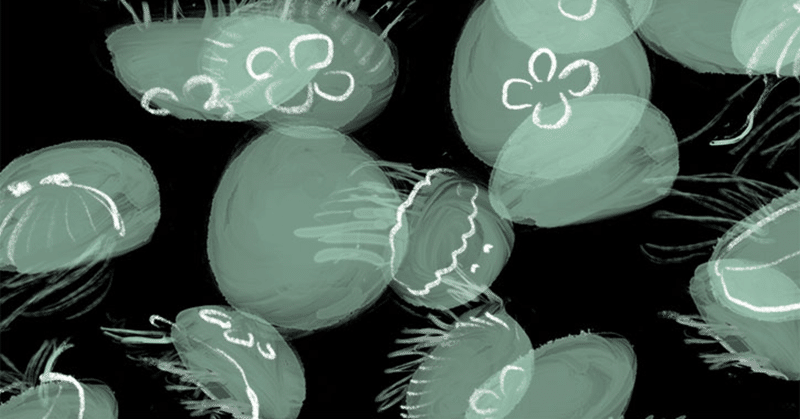
砂の女[し:シーフードヌードル]
「心配しないで、私は海に帰るだけだから」
彼女はそういって病院のベッドで眠った。
そうして二度と目覚めなかった。
長い間手入れされずに伸びた髪は彼女を繭のように包み込んでいた。
30年という短い人生のうち3年間を彼女はこの病室で過ごした。
彼女は生前、宝石を集めるのが趣味だった。
病室の本棚には集めた宝石を円形に並べて配置していた。
そのとき、眠る彼女の耳からはさらさらとした砂が流れ落ちた。
僕はそれをこっそりと瓶に集め病院を後にした。
「私ね。海で生まれ育ったのよ。」
彼女はよくそういって地元の海を思い出していた。
そのくせ彼女は両親の話をするのを極端に嫌がった。
僕がその考えに至ったのは彼女の死から1週間が過ぎたあたりだった。
思いついてからは早かった。僕は会社に長期休暇を申請した。
僕は彼女の故郷へと向かった。
彼女の故郷には、海があってそこで生まれ変わった彼女は今も泳ぎ続けている。
行きの新幹線でそんな夢を見た。
そして彼女の地元へとたどり着くと、そこは想像とは全く違う世界だった。
そもそも彼女の地元に海はなかった。
彼女の地元は四方を山に囲まれた盆地だった。
近所にはシーフードヌードルの工場がデカデカと建っていて、多くの住民がそこで働いているらしい。
僕はその日混乱した頭で予約していたホテルにチェックインしてベッドに入った。
ベッドに寝転がると何故か少しだけ泣いた。
次の日は、とにかく街を歩いて散策してみることにした。
どこかに彼女の海があるかもしれない。
僕は街の不動産屋に行って海は近くに無いかと尋ねたが冷やかしだと思われて追い返されてしまった。
交番や案内所でも結果は同じだった。
疲れ果てた僕は、気が付くとシーフードヌードルの工場の前に来ていた。
彼女の言う海とはこれのことだったんだろうか。
僕は工場前の自販機でシーフードヌードルを買うと、帰りにレンタルビデオ屋でAVを借りた。
ホテルに着くと湯を沸かしながら借りてきたAVを再生した。
しばらくすると部屋全体に下卑た喘ぎ声が響き始める。
僕はそれを眺めながら出来上がったシーフードヌードルをズルズルすすった。
部屋には喘ぎ声と麺をすする音だけが響いていた。
初めて交わった時彼女はひどく痛がった。
初めてなのか?と尋ねると彼女は水を浴びせられた猫みたいに不機嫌な顔で小さく首を振った。
それ以降も彼女はたまに痛がる素振りを見せた。
彼女のコロコロとした短い喘ぎ声は汐の満ち引きのように心に深く染み入ってくる反面、抉るような痛みを僕に植え付けた。
気が付くとAVはとっくに終わってブルースクリーンになっていた。
フォークに麺がだらしなく絡みついている。
僕は残りの麺をスープと一緒に流し込むとカップをごみ箱に捨てた。
ッカコっというだらしない音が部屋に響いた。
彼女はここにはいなかった。
そんな当たり前のことを突き付けられた僕に昨日の涙の続きが迫ってきた。
いつの間にか泣きつかれて眠ってしまったらしい。僕はその音に目を覚ました。
それは彼女の声のようだった。
僕はとっさにテレビをみた。しかし、テレビは相変わらずブルースクリーンのままだ。
よく聞くと音は部屋の外から聞こえる。
窓を開けると外は豪雨だった。
木々が雨に打たれる音が響いている。
僕はテレビのチャンネルをニュースに変えた。
ニュースでは緊急速報が流れていた。
この豪雨でここら辺一帯は洪水になったらしい。
一部停電になったところもあるみたいだ。
階下を見ると、早くもホテルの一階部分は浸水してしまっていて海のようになっていた。
30年に一度の大洪水だとニュースキャスターが話している。
30年に一度…
僕はベッドの脇に置いていたカバンから彼女の砂を取り出すと、窓からそれをさっと捲いた。
砂はまるでそこだけ晴れているみたいにゆっくりと落ちていった。
海に砂が舞い降りると、一瞬ばしゃばしゃっと水面が大きく揺れた。
なにかがこっちを見つめている気がした。
私は海に帰るだけだから
僕は廊下に飛び出して非常階段を駆け下りた。
彼女だ、彼女が今そこにいる。
二階から一階に降りようとしときに水面が目の前に迫った。
この中だ、この中に今も彼女はいる。
僕は思いっきり水に飛び込んだ。
身体をひやっとした液が包み込んでいく。
僕は深く深く潜った。
建物一階分しかないはずの海はなぜかどこまでも深く続いていた。
水によって緑がかった街はまるで荒廃した文明の遺跡のようだった。
ホテルもレンタルビデオ屋もシーフードヌードルの工場も、もう何百年も前に人々が放棄した世界に見えた。
海底に着くころには周りの圧力で少し耳がキーンとなっていた。
僕は一か所だけ地面が白くなってるところを見つけ。そこまで歩いた。
それは僕の撒いた彼女の砂だった。
パラパラと撒かれた砂は誰かがそこに集めたように円形に綺麗にまとめられていた。
僕は座り込んでその砂の形をしばらく眺めていた。
僕はそれを永遠に眺めていられるような気がした。
しかし、人間の僕にそんな事ができるはず無かった。
今更ながらに息が苦しくなっていることに気が付いた。
土台無理な話だったんだ。
彼女に会いたくてここまで来たのに、彼女を見ることもないまま死んでしまうらしい。
僕も海に帰れるんならそれもいいのかもな。
彼女との未来に思いをはせながら僕は目を閉じた。
「やめて!来ないで!」
気づいたら僕はびしょ濡れでホテルのベッドに寝ていた。
ぐっしょりと濡れた床にはシミが出来ていてドアまで続いている。
辿ってみようかと思ったがやめた。
やめて!こないで!
あれは彼女だったんだろうか。
声には嫌悪のようなものがこもっていた。
僕は体調が優れず数日部屋で過ごした。
数日間ホテルに籠っているとやがて水も引いて、階下の海は初めから無かったみたいに消えてしまった。
僕の長期休暇も限界に来ていた。
僕は荷物をまとめると、一度帰ることにした。
また、いつでも会いに来れるさ。
帰りの新幹線の売店でシーフードヌードルが売っていた。
帰りの新幹線で食べようと、手を伸ばしたが、思いとどまって引っ込めた。
僕は普通の醤油ラーメンのカップヌードルを買うと、新幹線の中で食べた。
ズルズルと多きな音が車内に響く。
隣の男が訝しげにずっとこっちを見ていた。
そんなことは気にも止めずに僕は麺を口に押し込んでいった。
湯の量を間違えたのか、塩辛くてまるで海の水を飲んでいるみたいだった。
その後、僕は彼女の居るシーフードヌードルの街に二度と行くことはなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
