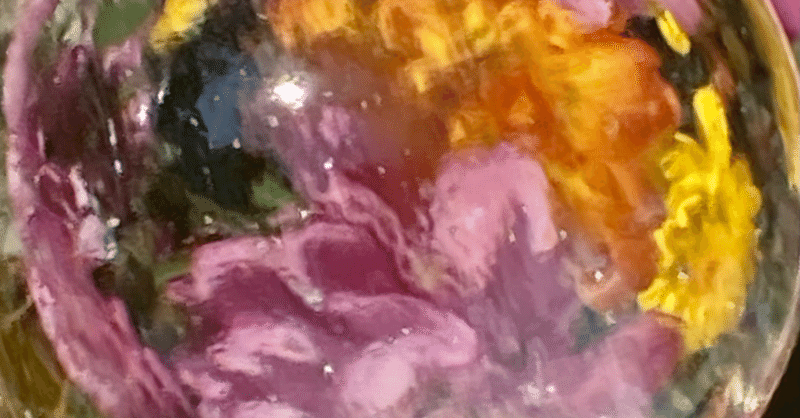
ものづくし
〈前書き〉
清少納言の「ものづくし」とは何の関係もありません。
「うつくしきもの」や「もののあはれ」の「もの」ではなく
「物」物体そのもの・・・のこと。
(「物質」というとずれてしまいそうなニュアンスの「物」)
物に誘われ、物に運ばれていく世界の風景を
描いてみたくなりました。
第一話 針箱の付喪神
道具も、長年使っていると精霊が憑き、付喪神とやらになると聞く。
つくもがみ・・・九十九神とも書く。
私が母から受け継いだ裁縫道具などは、
祖母の代からのものも多く残っていて
まさに、今にも付喪神にならんとして、
針箱の中でその時を待っている・・・
かのように思えてもくる。
針山しかり(中身は当然髪の毛である)、糸切り鋏しかり、
ヘラしかり、待ち針しかり
多くけ・小ちゃぼ・布団針などの縫い針しかりである。
おもちゃのマーチよろしく、針箱の中の道具たちが
人の寝静まった深夜に箱を飛び出して行進・・・
いや、練り歩く、などということは、まさかあるまいが。
秋も深まらんとする11月末日の午後、
畳の上に赤いチェック柄のフリースを広げ
私は、冬に備えて部屋着用のロングスカートを縫おうと
馬鹿げた妄想を繰り広げながら、指をせっせと動かしていた。
窓際では飼い猫のチャトラが、ひだまりの中で午睡している。
風のない、おだやかな秋の日であった。
昼間に妙な妄想をしたせいかどうか、
その夜、眠りばなにチクリ!と首筋を刺された感触があり
まさか針が・・・と、跳ね起きた。
冷静に考えれば、そんなことのあるはずはない。
昼間使った針を一本仕舞い忘れたとしても
畳の上ならばまだしも、布団の中はあり得ない。
布団は夜寝る間際に敷いたのだ。
しかし、チクリ!の正体を探し当てぬ限り、この後安眠はできそうにない。
虫の類だとしたら、気持ち悪いではないか。
私は部屋の灯りを点け、目を皿のごとくにして
枕周りを念入りに調べてみた。
何もない。
首筋に手をやってみる。
血が出た様子はない。腫れてもいない。
最初のチクリ!の後は、痛みもない。
はたと、パジャマの襟をまさぐってみると
豈はからんや、そこにちいさな棘のようなものがついていた。
つまんでよく見ると、栴檀草である。
針でもなく、虫でもなく、ほっと安堵する。
(栴檀草は「ひっつき虫」とも呼ばれるが、断じて虫ではない。)
それにしても、こんなところに栴檀草とは。
いつどこでひっつけたのか、皆目見当もつかない。
洗濯物を取り入れる際か、猫が外でつけてきたものか・・・
ひとしきり考えてみたが、わからぬまま再び布団にもぐりこみ、
灯りを消した。
すっかり冷えた体を縮めて丸くなる。
明日からは12月。夜はもう充分に寒い。
秋は、深まるだけ深まったのだ。
私の寝床に栴檀草を忍び込ませるほどに。
一人、カーテンの向こう、窓の外に広がる夜を思った。
私の呼吸が、夜を吸い、夜を吐く。
それは波を生む。
鼻先が波打ち際そのもののような心持ちになっていく。
波に揺れる小舟を漕ぎ出すように、
私は、一息ずつ、眠りの沖へと誘われ始めていった。
「うまいこと、いったわ。」
「うん。ええ具合や。」
クスクス、カラカラ、キキキ・・・と、笑い声。
それは針箱の中から聞こえてくる。
最初の声は確か、待ち針。続いての声は裁ち鋏だ。
私は、夢と現の狭間で考える。
見てもいないのに、声が誰のものかがわかるのは、
夢が紛れ込んでいるからに相違ない。
頭では眠っていないつもりでも、実はかなりの部分が眠っているのだ。
そうだ、そうに違いない。
私は、夢と決め込んで声たちの会話を楽しんだ。
「しかしあれやな、待ち針はんは化けるのが上手い。」
「あそこでひっつき虫に化けるなんぞ、ヘラのわてには思いもよらん。」
どうやら針山とヘラの会話らしい。
そこへ待ち針の声。
「針の姿のままでチクリ!と刺すのんは、ちと可哀そうかと思て、な。
イノコヅチでも良かってんけど、咄嗟に栴檀草になってもたんや。」
「巻き尺殿ならサザエあたりか。」
「ウニの方が刺すのには良かろうが。」
カラカラ、キキ、クスクス・・・小さき物たちの笑い声が続く。
「まあ、今日の所はこれくらいにしといたろ。」
「そやな。あとは鯨はんに任そうか。」
「そうしよ。そうしよ。」
声が静まっていく。
我が家の裁縫道具たちは、既に付喪神であったかと
私は、少し満足な心持ちで深く眠りについた。
第二話 鯨尺
その夜、夢を見た。
私は岩の上に立っている。
周りは黒潮の海だ。
荒れている。
眼前に姿を現した一頭の鯨。
でかい。
が、鯨にしては小さい方なのか?
私は鯨に詳しくなくて、種類もよくわからない。
黒く大きなその背に人を乗せている。
男だ。燕尾服を着て口髭を生やしている。
(昼の正礼装をモーニングコートというが、燕尾服は夜の正礼装のこと。
ちょっと違う。)
男は大口を開いて笑っている。
全身びしょ濡れで、何がそんなに楽しいのか、
波しぶきを受けながら鯨の背に乗り、
座ったり立ち上がったりと、せわしなく動く。
滑って落ちないのか。うまく乗りこなしている。
あの男、どこかで見たことがある。
そうだ、弥生ちゃんのお父さんだ。
弥生ちゃんとは、私と同い年で、小学校の時の同級生だ。
彼女のお父さんには数回会ったことがある。
口髭を生やした、ちょっと西洋かぶれ風の変わった人だったなあと思い出す。
鯨の上の男とは、どこか違う気がしないでもない。別人かもしれない。
しかし、既に・・・
私の頭は弥生ちゃんに糸をかけ、手繰り寄せ始めていた。
弥生ちゃんは私と同じ姓で、永尾弥生という。
私の名は永尾さつきだから、同じクラスになれば必ず出席番号が並ぶ。
私の後ろが弥生ちゃん。
同じ姓だが親戚ではない。
五月生まれだから「さつき」と名付けた私の親と
三月生まれだから「弥生」と名付けた彼女の親は
どこかしら似通った思考法の持ち主だったかもしれないが。
長身でオカッパ頭の私と、
小柄で、長い髪を三つ編みにして両耳の脇に垂らした弥生ちゃんとは
見た目が違い過ぎて見間違われることなどなかったが、
姓が同じなために、男子たちには
「永尾大」「永尾小」と呼び分けられたりもした。
教師の中には「永尾五月(ごがつ)」「石尾三月(さんがつ)」と呼ぶ者もいて
酷いネーミングセンスだと思ったが
本人はいたって真面目な様子であったから、
案外、冗談のつもりはなかったのかもしれない。
ザッブーン!
と、大きな波が私の体にかかる。
そうだ、海の夢だった。
私は岩の頂上に這い上がってみたが、波から完全には逃れきれそうにない。
弥生ちゃんのつながりから、思わず小学校時代に意識が入りかけていたが
また海に戻された。
相変わらず髭の男は楽しそうに鯨乗り、いや鯨とともに波乗りをしている。
大声で笑っているようなのだが、波の音が激しすぎて、
男の声が私にまで届かない。
髭の男は、私を海に誘っているかのようにも見える。
鯨の上は楽しいぞ、と。
しかし、私は足がすくむ。荒れ狂う海は恐い。
鯨に乗って楽しんでいる髭男を、羨ましいとも思えない。
私は、恐いのだった。
目が覚めた。
朝だった。
猫は先に起きて、廊下でニャーと鳴いている。
コトリ、と押し入れで物音がした。
襖を開けてみたが、特にこれといった怪しい物影は見当たらない。
もしも鼠であれば、猫が放ってはおかないだろう。
私は布団をたたんで押し入れにしまった。
ふと押し入れ下段の隅に、長めの物差しが横たわっているのが目に入る。
立てかけてあったはずの鯨尺が倒れたらしい。
先ほどの音は、その音だったかもしれない。
そうに違いないと、一人合点する。
母や祖母は着物を縫ったが、私は洋裁しかしない。
和裁は今後もする予定はないから、鯨尺は不用品だ。
それでも、年季の入った鯨尺は捨てるに忍びず、
押し入れの隅に立てかけたままにしていたのだった。
メートル法を使う洋裁と違って、和裁では「尺」を使う。
また同じ「尺」でも、曲尺(カネジャク)より一尺が長く、
曲尺の一尺二分五寸が鯨尺の一尺に相当する。
そこまでは私も知っていた。知識として。
しかし、鯨尺という言葉の由来までは知らなかった。
てっきり普通の尺より長い(大きい)からだと思い込んでいた。
何気なく辞書を引いてみると、全然違った。
「昔、裁縫用のものさしを鯨の髭で作ったことに由来する。」とある。
驚いた。
鯨の髭・・・か。
昨夜の夢が思い浮かぶ。
鯨に乗った髭の男。
うちにある鯨尺は当然のごとく木製だが、
なんとなく夢との関連性がないとも言えない。
いや、やっぱり、ない。
いや、あるのか?
モヤモヤした気持ちも、
朝の洗濯や掃除をしているうちにどこかに紛れてしまった。
〈ちょっと休憩〉
ここまでは、2019年暮れから2020年年明けにかけて書きました。
まだまだ続く、というか
むしろここからが本番なのですが
なんだか書く気になれなくて、そのままになっていました。
ようやく重い腰があがってきて
今日から続きを書いていきます。
見える「もの」は見えないものに触れている・・・
そんな言葉を聞いたのが私が二十歳の頃。
その時、うわっ!と、心が震えたのを思い出します。
続きをアップするまで少し時間がかかると思いますが
どうぞ気長にお待ちください。
そして、このお話を
お気軽に楽しんでいただけたなら幸いです。
第三話 置き薬
午後、裏の納戸の片づけをしているとき
玄関チャイムが鳴った。
ピンポーン!
あれ?
うちの玄関チャイムって、こんな音だっけ?
少々訝しみながらも、「はいはい」と玄関へと急ぐ。
「ちわーっ!」
男性の声だ。
さっき車が停まる音がしていたから、きっと宅配便だろうと見当をつける。
またチャイムが鳴る。
ピンポーン!ピンポーン!
「はいはい、はい」と、私も少し大きめに声を出す。
後ろ手に閉めようとした裏口のドアが風で勢いよく閉まり
私の右手の四本の指をがっつりと挟みこんだ。
免れたのは親指だけ。人差し指から小指まで、しっかりとドアに挟まれて
痛いこと、この上ない。
思わずうめき声をあげ、左手で指を包み込むようにしながら
私は玄関の戸を開けた。
そこには男が一人、立っていた。
私の顔(きっとしかめっ面をしていただろう)と手を見て
「大丈夫ですか?・・・血が出ていますよ。」と言った。
確かに、私の右手の中指が切れて血がにじみ出している。
男は中背の痩せ型で、柔和な顔つき。
年のころは五十過ぎといったところか。
宅配業者ではなさそうだ。
制服を着ていないし、車に社名も入っていない。
「あ、はい。大丈夫です。」
全然大丈夫ではなかったが、早く用事を済ませて薬を塗りたい。
絆創膏を貼りたい。
そんな気持ちが顔に(全面的に)表れていたに違いない。
「どういうご用件でしょうか?」
と、私は早口で聞く。
「あ、や、どうも。私は富山の薬売りです。」
は?・・・薬の押し売りか?
「不審に思われるのも無理はありません。若い頃、ここの大奥様にお世話になった者です。」
祖母の知り合い?
「こちらのお庭にゲンノショウコがあるでしょう。それを摘ませていただいておりました。」
そこまで言うと、男はまた私の右手に目をやり、
「話せば長くなります。私の話より、そのお怪我の手当を先に済ませられた方がよろしいかと。」
願ってもいない提案だ。できれば私もそうしたかった。
私は力強くうなずいて、
「すみませんが、いったん失礼して指の手当てをしてきますね。」
と言った。
しかし、男は、これまた私以上に力強く首を横に振り、こう言った。
「私にその指の治療をお任せください。私は薬屋です。」
男は玄関からは入らず、右手に回って縁先に背中の荷物を下ろした。
大きな風呂敷包みである。
あれ?
そんな荷物を持っていただろうか?
しかも、驚いたのは男の服装だ。
まるで時代劇の「水戸黄門」が地味になったようないでたち。
私はそのような服装をなんと呼んでいいのか知らない。
甚平のような、作務衣のような、下はもんぺのような・・・
頭には頭巾を被っている。
え?
さっきまで、その男はどんな格好をしていたのか思い出せないが
ともかく、こんなではなかったことは確かだ。
宅配業者の服装ではないと思ったことなら覚えている。
では、では、どんな服装だったかしらん・・・と
いくら頭をめぐらしても出てこない。
私があっけにとられている間に、男は風呂敷を開き
中の木箱・・・それもそうとう大きな木箱を縁側に置いて
私に、そこに座るように促した。
「手を見せて下さい。」
男は私の右手を取り、傷や腫れを確かめた。
そして箱から何種類かの薬瓶を取り出し、するすると包帯も取りだし
手際よく手当てしていく。
あまりの見事なその動きに、私は感嘆の息をもらした。
「もう大丈夫です。しばらく痛みはあるでしょうが、今夜一晩の辛抱ですよ。」
と言って、やわらかく笑った。
ズキンズキンとしていた、さっきまでの痛みがずいぶん遠のいている。
「ありがとうございます。」
私は素直に頭を下げた。
何がどうなっているのかを考える暇もなく事が運んでいったため
「何か変だ」と思う気持ちにさえなれなかった。
そのとき、家の前に停まっていた車にエンジンをかける音がして
ほどなくその車は発進した。
あれは、この男が乗ってきた車ではなかったのか?
男はまたやわらかく笑った。
あれは私の車ではありません。ご近所の誰かのでしょう。
私は車に乗りませんから。
ほら、と男は自分の方に手を向けて
「私はご覧の通りの薬屋です。富山の置き薬と言えばわかりますか?
電車を乗り継いで、基本は歩いて行商に出ます。」
富山の置き薬・・・
確かさっきもそう言っていた。
そして大奥様にお世話になった・・・とも。
ああ、思い出した。
私がまだほんの小さな子どもだった頃、祖母を訪ねて薬売りが来ていたな。
確かに、この男のような恰好をしていたような記憶が微かにある。
その頃は祖母も母も健在で、いや、祖父もいて、
さらに叔父夫婦とその子供達もいっしょに大勢でこの家に住んでいたのだ。
私の母は、いわゆる出戻りだったから、父はここに住んだことはないが。
にぎやかだった昔が思い起こされた。
そうだ。紙ふうせんをもらって、いとこたちと遊んだ。
あの、紙のふうせんをたたくときの手の感触がよみがえってきた。
「これでしょう。」
男は、私の脳裏を見透かしたかのように木箱から紙ふうせんを取り出した。
私の顔がぱっと明るくなるのを自分でも感じて、少々気恥ずかしい。
ペッちゃんこの紙ふうせんに、息を吹き入れて膨らませてくれた祖母。
「確か、さつきさんというお名前でしたね。」
男が笑う。
「ええ、ええ。その通りです。よくご存じで。」
「私は、若く見られますが、実年齢は相当なものでしてね。
昔、そう、あなたが子供の頃に何度もお会いしているのですよ。
もう、五十年以上になりますかね。
時代は変わりましたが、私のいでたちは変わりません。
ただ、もう薬を置いてくれる家が少なくなったので、
売り歩く機会も減ってしまいましたが。」
そこへ猫がやってきた。私と薬売りの間にちょこんと座る。
ちらりと男を見てから、くるんと丸まって日向ぼっこを決め込んだ。
「猫ほど縁側に似合う生き物はいないでしょう。
最近は縁側のある家も珍しくなりました。残念なことです。」
「ここで長話もなんですから、中へどうぞお入りください。
お茶でも・・・。」
と、私は腰を上げた。
「いやいや、お気遣いなく。それに、今日一日は水をお使いにならないように。」
そうであった、そうであった。
痛みが引いていたため、うっかりと怪我のことを忘れていた。
「と言っても、全く水を使えないのも不便でしょうから、ゴム手袋をなさって。
少々なら大丈夫ですよ。お風呂ではお気をつけてください。
右手を高く上げて。
なに、明日にはもう包帯を取ってもらって構いません。
傷は浅いものでしたし、骨も異常ありませんでしたから。」
男はそこで一息つくようにして、縁から立ち上がり空を見上げた。
師走になったばかりの、高く青い空だった。
空気は冷たいが、その分どこか清浄な心持ちがする。
「今日こちらに伺ったのは、薬を売るためではありません。
置きっぱなしになっていた薬の回収と、裏庭を見せていただきたくて。」
裏庭?
「大奥様も奥様もすでにお亡くなりになっていることは存じ上げております。いろいろと事情がありまして、つい、置き薬の回収を忘れてしまっていたのです。」
私は何も聞いていない。
祖母からも母からも。
既に二人は他界していて、置き薬がどこに保管されているのかわからない。
裏庭と言われても、あるのはミカンの木と梅の木が数本ずつ。
そしてその周りを囲うように、つまり外壁代わりに槙の木を植えてあるだけだ。
その時の私は、何のことやら?・・・という顔をしたに違いない。
薬屋は言った。
「御心配には及びません。薬の置き場所はわたくしが存じております。
ただ、勝手に入らせてもらうわけにもいきません。
それで、こうしてお伺いしたわけです。」
はあ。
「さっそくですが、裏庭に入らせていただいてよろしいでしょうか。」
薬箱なら居間にあるのだが・・・。
クエスチョンマークを頭の上に三つほど浮かばせたまま、私は頷いた。
裏庭へと男の足は進む。
「昔のままでありがたい。」
勝手知ったる様子で男は犬走に添って裏手へと向かう。
私は慌てて男の前に出て、木戸を開け裏庭へと案内する。
「置き薬は・・・、あそこです。」
と、男は一本の槙の木の根元を指さした。
足早に木に近づくと、しゃがみ込んで小さなスコップで根元を掘り始めた。
え?・・・スコップ?・・・
いつ手にしたのか?
男は、そんな私を気遣うようなそぶりもなく黙々と土を掘る。
何が埋まっているのだろう?
しばらく掘り返した土を、今度はサクサクと戻し始める。
最後に上部を均して、
「終わりました。」
と、男は俯いたままふうと息を吐いた。
そばで見ていた私は、とにかく呆気に取られて、返事もおぼつかない。
「これで心残りはありません。置き薬は解体いたしました。」
立ち話もなんですから、どうぞ中へ・・・と言う私に
男は首を横に振り
「いえ、先ほどの縁で水を一杯いただけますか?
多少のご説明も必要でしょう。そこでお話させていただきます。」
私たちは縁側に戻った。
猫が毛づくろいをしている横に男が座る。
私は急須に入ったお茶と湯飲みを用意した。
「水で良かったのですが・・・。」
と言いながらも、男は美味しそうに喉を鳴らしてお茶を飲んだ。
あの・・・と、私は問いかける。
さっき薬の解体と言っていたが、その前は薬の回収と言っていなかったか?
回収と解体ではまるで違う。私の聞き間違いだろうか?
疑問はあり過ぎるほどあったが、まずそのことが聞きたかった。
「はい。大奥様とのお約束で、薬がまだ使用可能な状態ならば回収を。
もう不可能な状態ならば解体を、ということになっておりました。
掘り返してみたところ、もう形をとどめていないほどに朽ちておりました。
なので解体を。」
どういう薬なのか?
なぜ、あんな場所に埋めてあったのか?
私はそんな話を祖母からも母からも聞いたことがない。
疑問は次から次へと出てくる。
「大奥様だけが知っていたことです。
奥様・・・さつきさんのお母様はご存じありませんでした。
もちろん、その他の家族の方々も。
あの薬は・・・」と、男は語り始めた。
それは、飲み薬や塗り薬ではなかった。
怪我や病気を事前に回避する作用を持っていたということだ。
何という薬か、その名前は教えることはできない。秘薬中の秘薬。
家内安全のお守りのような、お札のようなものに近い。
木の根元に埋めることで、その木が養分として薬を吸い上げ
成分を葉から空気中に散らすのだ。
年月が経てば、当然効力は消えるが、
その時期は短く見積もっても祖母の寿命よりは長くなりそうであった。
祖母が他界したら、速やかに回収するよう頼まれていた。
というのも、その薬は
祖母にとっての良い気がめぐる様に調合されていたため、
祖母が亡くなれば、この家に住む者たちに
どういう風に作用するか見当がつかないからであった。
「速やかに・・・と言われていましたのに、こんなに遅くなり
申し訳ありません。」
男は立ち上がった。
猫もアクビしながら伸びをする。
「さつきさん、これからは自由ですよ。」
え?・・・どういう意味?
「これまで、あなたは長い間、大奥様の夢の中で暮らしてこられた、
そういう意味です。」
はあ・・・。
今日何度目の「はあ」だろう。
薬屋の説明で疑問の大部分は理解できたが、
それでも、理解を越えたところで何もわからないままの自分がいる。
全てが、まるで夢のような話である。
「今日は町に出て見るといいでしょう。
夕方には、すっかり違う世界になっているはずです。」
男は風呂敷に包んだ大きな木箱を背負い、
「それでは、ごきげんよう。」
と言って、門を出た。
猫が門柱に駆け上がり、見送る様に男の行く先を見ていた。
第四話 キツネ
師走に入ると、途端に夜が早く来る。
日に日に冬至が近づくせいだ。
午後はあっという間に過ぎゆき、部屋には西日が斜めに差し込み始める。
私はその時間帯が大好きだ。
暮れてしまう直前の、傾いた太陽が放つ柔らかい日ざしの中で
ゆったりと珈琲を飲むのが日課である。
そうだ。珈琲豆が切れていた。
明日は豆を買いに行こうと昨日思ったことを不意に思い出す。
薬屋が来て、そんな予定も吹っ飛んでしまっていたのだ。
日はまだ高い。
急いで洗濯物を取り入れ、出かける準備をした。
買うのは珈琲豆だけでよい。
町まで歩いていこう。重い荷物もない。
そう言えば、薬屋が言っていた。
今日は町に出るとよい、と。
他にも何か言っていたが、思い出せない。
なんだか妙なことを言っていた気がする。
何だっけ?
わからない。まあ、いい。出かけよう。
空気が少しもわっとしてきた。
小春日和・・・というより、
本当に春のようなかすみが遠くの山にかかっている。
さっきまでのキンと研ぎ澄まされた空気感が
いつの間にか消えている。
あまり寒くなくて、歩くにはちょうどいい。
いつもなら通らない道も通ってみたくなる。
近道だけれど、車ではまず入れない路地や、
少し遠回りだが、静かな公園の横手の道など。
なんだか気分がいい。
鳥のさえずりも大きく響いて聞こえる。
思わず歌いだしたくなるような、そんな気分。
あれ?
あんなところにキツネがいる。
公園の脇の茂みの中から、一匹のキツネが私の方に顔を向けている。
キツネなんて、ずっと昔に見たきりだ。
子供の頃、近所の人がキツネに化かされた話を
母からよく聞かされたものだが。
まだその頃は、キツネもタヌキも里で見かけることがあった・・・
などと思って立ち止まっていると、キツネが近づいてきた。
堂々たる歩みである。目は私を凝視している。
どうした?、キツネ。
私はおっかなびっくりキツネに声をかけた。もちろん心の中で。
「やあ。」
キツネが喋った!
「また君と話ができるようになるなんて、驚いたよ。」
いや、驚いているのは私の方だ。
「いったい君に何が起きて僕たちと話せなくなったのか、
君は知らないんだね。いいさ、そんなこと。
こうやって再会できたんだ。
また君んちの裏庭にも行くさ。
みんなにも伝えておくよ。大宴会といこうじゃないか。
それじゃ、な!」
キツネはそれだけ言うと、急ぐように踵を返して去っていった。
何が何だか、わけがわからない。
悪い薬品でも吸い込んだのか?
薬品?・・・薬?・・・
薬屋が、解体したとか言っていた、それと何か関係あるのか?
つい先ほどまでのいい気分が一気に冷める。
ただの幻聴?・・・病院に行った方がいいのだろうか?
動揺しながらも、頭の片隅でちょっと喜んでいる自分がいることに気付いてもいた。
キツネと話せるなんて、ウキウキしちゃう・・・
それを更に抑え込む圧力が発動しているのもわかる。
いや、待て。今はともかく珈琲豆だ。
珈琲豆は、すぐ先の喫茶店で売っている。
量り売りで、注文を受けてから炒ってくれる。
店内に広がる珈琲の香りがたまらない。
私は足早に喫茶店へと向かった。
第五話 珈琲豆
重い木戸を開いて中に入る。
「いらっしゃいませ。」
カランカランというベルの音とともに店員の声。
客はまばら。店内のテーブルは半分以上空いている。
しかし、空いていようが混んでいようが私には関係ない。
豆を買いに来ただけだから。
マスターがカウンターの向こうからこちらを見て、ニコリとする。
「サントスを200グラム。」
私がそう言うと、
「いつもの、ですね。ちょっと待ってくださいね。」
と明るく笑う。
カウンター席に座っていた女が振り向き、私を見て声を上げた。
「さつきちゃん!」
驚いた。
驚くのは今日何度目だろう?
女は、昨夜の夢の弥生ちゃんであった。
いや、正確には、鯨の上で波乗りをしていた髭男・・・
弥生ちゃんのお父さんらしき人が夢に出てきただけなのだが。
「久しぶりねえ。元気にしてた?」
弥生ちゃんは小学校の時にイギリスから帰国して
私と同じクラスになったのだ。
確か、中学校の途中でまた海外に引っ越していたはず。
それきり会っていない。
「奇遇だわ。昨夜、あなたのお父さんの夢を見たのよ。」
・・・それであなたのことも思い出していたところだった、
とは言わなかった。
「お父さん、元気?」
「父は他界したわ。昨年の今ごろね。」
え?・・・悪いことを聞いてしまった。
なにも、久しぶりの再会に
いきなり相手の父親の話題なんか出さなくてもよかったのに。
なんてバツの悪い・・・。
「気にしないで。父は、死ぬ間際まであなたに会いたがっていたわよ。」
そう言って、弥生ちゃんは微笑んだ。
「ちゃんと夢に現れたのね。」
何?・・・何、言ってるの?
怪訝な顔をする私に弥生ちゃんは言った。
「さつきちゃん、聞いてないの?
・・・やっぱり知らされてなかったんだ。
あなたのお父さんは、私の父よ。」
一言も口をきけなくなった私に、彼女は奥のテーブルを指さした。
「あそこに座ろう。ここで会ったのも何かの縁。
さつきちゃんとは一度ゆっくり話したかったのよ。」
促されるままに奥のテーブル席につく。
マスターがメニューとお水を持ってくる。
「私はブレンドコーヒーを、ホットで。」
私もそれに倣う。ともかく何も考えられない。
「豆は、お帰りになるときにお渡ししましょう。
ご用意しておきます。ごゆっくり。」
マスターは言った。
いったい、どういうことなのだろう?
私の父が弥生ちゃんのお父さん?
「順序があっちこっち飛ぶかもしれないけれど、
ともかく黙って聞いてちょうだい。」
弥生ちゃんは話し始めた。
私の両親は、私が二歳の時に離婚した。
原因はよくわからない。ただ祖母の強い意向だったらしい。
父は一つだけ条件を出した。
それは、母と私の姓を変えない、
つまり父の姓、永尾のままにしてほしいというものだった。
離婚の際には、新戸籍を作れる。
旧姓に戻ってもいいし、そのままでもかまわない。
「さつきちゃん、戸籍謄本、見たことなかったの?
それを見ればすぐにわかったことなのに。」
住民票なら何度も見たが、戸籍謄本なんて見たことがない。
私は結婚もしたことがないし、祖父母の葬儀も母の葬儀も
すべて伯父が取り仕切ってくれた。
戸籍謄本や抄本が必要になる場面など、
これまでの私の人生には一度もなかったのだ。
海外貿易の商社マンだった父は、母と離婚したあとイギリスに渡った。
そこでバツイチだった弥生ちゃんの母と知り合い、再婚。
「私の名前ね、本当は佐代子なのよ。弥生じゃないの。
父は、五月生まれでさつきと名付けた娘がいるから、
三月生まれの私を弥生と呼びたいって。
母はね、ちょっと変わった人で、
そんなの全然気にしなかったのね。いいわよって。
私もその案に賛成だったしね。弥生って、かわいい名前だって。
前の父が呼んでいた名前を捨てたかったってのもある。
あんまりいい思い出じゃなかったからね。
父は、あなたも少しは知っていると思うけど、
相当の自由人だったでしょ。
母も父に負けず劣らず自由人で、
そのおかげで私は海外でも日本でも、
人目を気にせずに生きてこれた。」
自由人・・・か。一般的には変人とも言う。
少し風変りな親子だったなと、昔を思い出す。
「何度かうちにも遊びにきてくれたわよね。
あれね、父がさつきちゃんに会いたがったからなの。
でも、できればさつきちゃんの家の人には内緒でって。」
ああ、そうだった。
そう言われていたのに、私はうっかり夕飯の席で話してしまったのだ。
今日、弥生ちゃんの家に行ったと。
そのとき一瞬、団らんの空気が凍り付く気配があった。
〈あの家とうちとは関りがありません。〉
祖母はキッパリとそう言った。
私はそれを、私と同じ苗字だけど親戚関係ではない、
というふうにとったのだ。
子どもの勘違い。
しかし、どこかでうっすら何かを感じ取ってもいた。
これ以上深入りしてはいけないと。
そういうことだったのか。
「私、娘がいるんだけど、葉月って名前なの。
八月生まれだからよ。もちろん、父の名づけ。
可笑しいでしょ。
もしも十二月生まれだったら師走になってたのかしら?
父の言い分はこうよ。
生まれた時節の空気感を一生身にまとってもらいたいからって。
さつきちゃんが生まれたとき、裏庭の蜜柑の木は花が満開で、
それはそれはかぐわしかったのですって。
五月の薫りと言えば、父にとっては蜜柑の花だって言ってたわ。」
なんだ、サツキの花ではなかったのか。
でも、蜜柑の花の匂いは大好きだ。だから、ちょっと嬉しい。
私は病院ではなく、祖母の家で生まれたと聞いている。
産婆さんが取り上げてくれたという話だ。
お産の前後は実家に帰るのが昔は普通だった。
そのとき、父もあの家に来ていたのだな。知らなかった。
一度も足を踏み入れたことがないのだと思い込んでいた。
「私は今、シンガポールに住んでいるの。
シンガポールからの留学生と知り合って、それで結婚して、娘が一人。
年に一度、12月から1月にかけて長い休みをとって日本に帰国する。
そういうのがもう数年続くかしら。
今もそう。昨日日本に着いたばかり。
父が亡くなったときも、その帰国期間中だったのよ。」
そこで一息ついて、また続ける。
私は一言もしゃべれず、ただうなづくばかりだ。
「病気じゃなかったわ。
ある意味、自分でこの世からおさらばしたってとこかな。
ええ、自殺なんかじゃなくってよ。
なんて言えばいいのかしら。
もう充分この世を満喫しました、みたいな。
体が衰え切る前に肉体を脱いじゃった、みたいな。
遺言らしきものはあったわよ。
通夜も告別式も不要。坊主は呼ぶな。骨は海に撒いてくれって。
父らしいでしょ。
私が夫と娘と一緒に帰国して、その翌日の朝のことだった。
キッチンに立っている母に、父はブランデーを要求したの。
朝からブランデー?・・・って、私たちは笑ったけれど
父も笑いながら、乾杯がしたくてね、と言った。
そして上等のグラスにブランデーを自分で注ぎ入れて、
手のひらでいつものように転がして、こんなことを言ったの。
――お前たちのおかげで最高の人生が送れた。
さつきが一緒ならなお良かったがのだが・・・。ありがとう――
そして一言、乾杯!って言ってから一気に飲み干して。
そのまま、そうよ、本当にそのまま、座ったまま動かなくなったのよ。
なんか変だ、と思ったら、もう死んでいたの。
救急車呼んで病院へ。検視解剖に回されて、刑事もやってきて
けっこう大変だった。
ブランデーに毒か何か入ってたんじゃないかって疑われたの。
当然よね。自殺か他殺か、二つに一つしかないじゃない。
その状況じゃ。
でも、何も検出されなかったのよ。
他にも怪しい所は皆無。
結局死因は心不全。」
ふう・・・と、弥生ちゃんは一息ついてコーヒーを口にした。
私も飲んだ。
いつコーヒーが運ばれたのだろう。
弥生ちゃんの話に夢中になっていて、それすら気付かなかったのだ。
彼女の話は続く。
「それが一年前。
墓参り?・・・そんなことしないわよ。
墓には入れてくれるなって、遺言にあったもの。
母はね、さつきちゃんをウチの子として育てたかったらしいの。
あなたのお家、ちょっと窮屈そうじゃない?」
私は自分の家を窮屈だと感じたことはなかった。
穏やかで、特に不満もなく
・・・何不自由なく育ててもらったと思っている。
「まあ、ウチの父や母からすれば、
どこの家庭も窮屈に見えたでしょうけど。
弥生に姉妹がいたらいいのにって。
海外にしょっちゅう突き合わされて、あちこち落ち着くところがなくて
友達ができてもすぐに別れなきゃいけない・・・
それでも、姉妹がいたら素敵ねって。
変かしら?・・・そうね、一般的には変かもしれない。
でも、そういう人なの。
だから、たまには遊びに来て。私がいなくても。
きっと母も喜ぶわ。
父の夢を見たのですってね。その話も是非してあげて。」
そうだ、鯨の背に乗って波乗りをしていた。
楽しそうに、豪快に笑っていた。
私は昨夜の夢を思い出す。
私はなんだか泣きそうになっていた。
私の知らないところで、私を愛してくれている存在がいたなんて。
日はかなり傾いてきた。
私たちが座る奥のテーブルにも、夕陽が斜めに差し込んでいる。
もう、すぐに暗くなるだろう。
「さつきちゃん、話を聞いてくれてありがとう。
あなたの話は全然聞かなかったけれど、
これからはいつでも聞けると思うから。
今日はもう帰らなきゃね。ウチの家族は誰も心配しないけれど。」
弥生ちゃんはクスっと笑った。
「信頼し合っているのよ。お互いに。
ウチは自由人の集まりなの。」
私も一人暮らしだから、誰からも心配されない。
ただ、猫がそろそろ寂しがっている頃だろう。
私たちは席を立った。
会計を済ませて珈琲豆を手にした時、弥生ちゃんが言った。
「あら?・・・さつきちゃん、手を怪我してたの?
私、自分の話に夢中で全然気づかなかったわ。大丈夫?」
私も忘れていた。
思い出したら、少々痛みが戻ってきた。
珈琲豆を持った私の両手を、弥生ちゃんは自分の両手で
優しく包み込んでくれた。
「今日会えて、本当に良かった。
必ずウチに来てね。私は年明けまで日本にいるから。
私が留守でもかまわないから。
お願い、約束よ。」
私はその時、どんな顔をしていただろう。
あまりの怒涛の事実開示に、戸惑いもあり
でも、どこか嬉しく、頭の整理が追い付かない。
複雑な表情をしたに違いない。
失礼に当たらなければよいが。
いや、弥生ちゃんに失礼なんて気持ちは無用だろう。
私たちはそれぞれに岐路についた。
早く家に帰りたかった。一人でゆっくり考えたかった。
道々浮かぶ考えは、取り留めなく、
断片となって頭の中を行き交う。
そして、その断片は、次第に私の中にそれぞれの居場所を見つけ、
次から次へピタリピタリとはまっていくようだ。
私は、これまでの自分の人生を不幸だと思ったことはない。
特に苦労もした覚えはない。
それでも、自分の中に、何とも言えない居心地の悪さはあった。
隙間がある感じ。胸と腹の間に空白のエリアがあって、
うまく力が入らない感じ。
空っぽのような空虚感。
それが、今日の午後から急激に埋まり始めた。
たくさんのパズルのピースが勝手に飛んできて、
みずからの位置に自然と収まるように。
血のつながりなど、どうでもいいのかもしれない。
一緒に暮らさなくても、こんな形の家族があっていいのかもしれない。
弥生ちゃんの家族の中に、知らない間に自分も入っていたのかもしれない。
そう思うと、なんだか胸のあたりがあたたかくなった。
そうだ、早く帰って猫にただいまを言わなければ。
きっと玄関で待っている。
抱きあげて頬ずりしよう。いつものように。
第六話 物たちの歌
玄関を開けると上がり框に猫が座っていた。
まるで旅館の女将が三つ指ついて
「いらっしゃいませ」と言うような風情で。
私が抱き上げようとすると、猫は素早くクルリとお尻を見せて
スタスタと奥に入っていく。
なあんだ。
と、私は少々がっかりのような安堵のような複雑な気持ちになる。
もしかしたら昼間のキツネのように
人語を喋るようになっているのではないかと
一抹の不安、いや期待を持っていたのだ。
さっさと上がれと言うように、
猫は自分専用のお椀の前でニャーと鳴いている。
はいはい、はい。
ごはんにしましょうね。
キャットフードをお椀に入れると、猫はわき目もふらず食べ始めた。
私の方はあまり食欲がわかない。
昼の残りで簡単に済ませようと思う。
食器や鍋をたくさん洗うのも面倒だ。なにせ、この手である。
しかし、痛みはもうほとんどない。
明日には包帯を取って良いと薬屋も言っていた。
針も持てるだろう。
私の仕事は主に針仕事である。
仕立屋の下請けをしている。他には洋品店からの依頼で直しもする。
あと、冬限定で、近所の中高生に編み物を教えることもある。
男の子は来ない。編み物をする男の子にはまだ会ったことがない。
裁縫や料理は、男性のプロも多いのに、編み物では聞かない。
私が知らないだけか。
女の子が集まるとお喋りに花が咲く。
そのときばかりは、この静かな家も明るい声でにぎわう。
そろそろそんな季節だ。
ストーブに火を点けて
ササッと夕食を終える。
体が温まると、動きたくなくなる。
ほんの少しなのに、食器洗いが面倒になった。
ビニール手袋をつけるのも面倒だ。指もまだ少し痛い。
食器は朝まで洗い桶に浸けておこうかしらん、と思う。
これまでそんなことはしたことがない。
そんな発想もわいたことがない。
祖母がいたら、きつくたしなめられただろう。
《何をするにも後片付けが基本中の基本ですよ》
《何事も終わりが肝心》
祖母の声が脳裏によみがえる。
ああ、そうか。ふとわかった。
弥生ちゃんの言っていた「窮屈」の意味が。
私は、祖母にも母にも、叱られたことがない。
それは、私の方が先回りをして叱られないように行動したからだ。
私の行動の規範はすべて祖母にあった。
祖母が無理強いしたわけでもないのに。
私がみずから進んでそうしたのだった。トラブルを回避するために。
トラブル?
どんなトラブルを想定していたのだろう?
子ども心に、何か良くないこと。怖いこと。
それでは、まるで、私は祖母の機嫌取りのために
自分のルールを設定していたことになる。
自分で、みずから。
それなら、それなら、ルールを変更すればよいのではないか。
私のルールなのだから。
今夜は食器を洗わない。それでいい。
なんだか、すっきりした。
すっきりしたら、途端に眠くなってきた。
ストーブを消して、コタツに入る。
猫も一緒に入る。
こんな時間に寝てしまったら・・・
イケナイという言葉が頭に浮かぶが、すぐに打ち消す。
かまうものか。
ルールの変更だ。私の好きにすればよい。
部屋の電気もつけたまま、あっという間に寝てしまった。
目が覚めたのは深夜だった。
一瞬、ここがどこだかわからない。
・・・ここは、どこなのだ?・・・
そうだ、ここは私の家の居間だ。
コタツで寝るなんてこと、したことがなかったから
目覚めた時に目に入る光景が新鮮だった。
いや、違う。
そうじゃない。
本当に新鮮なのだ。
部屋中が、なんだか明るくてクリアなのだ。
よく知っているはずの自分の家が、微妙に違う家に見える。
猫はコタツから這い出て、私の顔を覗き込んでいる。
私はもう一度呟いた。
・・・ここは、どこなのだ?・・・
――ここは、君の【今】だ。居間ではなく。――
猫か?
猫が喋ったのか?
――違う。よく周りを見てごらん。照明を消して。
そうだな、ストーブを点けるといい。
部屋を見るにはちょうどいい明るさになる。――
男性の声である。どこかで聞き覚えがある懐かしい声だ。
私は少しふらつきながら起き上がった。
寒い。ストーブを点けよう。
それから、次は電気を消せばいいのか?
よくわからないが、他にすることもない。
胸のずっと奥の方で、何かワクワクしてくるのを感じている。
この感じ、懐かしい。
照明を消して、驚いた。
部屋の中がチラチラと、小さな灯りでいっぱいだったのだ。
それらは全て、物が放つ光だった。
ごく微かな灯りだが、確実に光っている。
しかも暖かい。
特に強く輝いているのは針箱だった。
私は針箱を開けてみた。
すると、中の裁縫道具たちが、いっせいに声を上げた。
――さつき~!!――
――さつき~!!――
――さつき~!!――
私の名前を連呼する。
――わてらの計画、うまくいったんやな――
――待ち針はん、鯨尺はん、ええ仕事しはりましたなあ――
――お手柄ですなあ――
彼らの声は、決して大きくはない。少し高めの可愛らしい声だ。
それぞれに特徴があり、だれが喋っているのか、ちゃんと聞き分けられる。
私は目を丸くして針箱の中を覗き込んだ。
――台所も見てやってや~――
糸切狭が言う。
私は居間から台所の方を見た。
微かに光っている。
慌てて台所に足を運ぶ。
やはり、台所の調理道具たちも光っていた。
まな板、包丁、鍋に窯、薬缶・・・
洗い桶、中に浸けた茶碗と小皿と箸。
ああ、もう何もかもがチラチラと小さく光を放っているのだ。
台所は家の北側にある。流し台の前の窓もほんのり明るい。
窓の外は裏庭である。
私は、サッと窓を開けた。
師走の夜の空気が部屋に流れ込む。
寒いとは思わなかった。
なんて気持ちのいい夜風だろう。
裏庭の木々の葉っぱは、
まるで露がついたように光の珠が浮かんで揺れていた。
光の粒子が、雨のように庭一面に降り注いでいる。
蜜柑の木の下で、キツネが「やあ!」と言った。
「もうすぐ友達もおおぜいやってくるよ。
あの提灯行列が見えるだろう。」
小さな赤いともしびがいくつも連なって
私の家に向かっているのが見えた。
そうか、そうか。思い出してきた。
私は小さい頃、この裏庭でよく遊んだものだ。
いとこたちと遊ぶより、一人で遊ぶ時間の方が長かった。
一人・・・と言っても、私にとっては一人ではなかったのだ。
キツネもいたし、アナグマもいたし、ミミズクもいた。
しかし、周りの人の目には、
私が、野生の小さな動物たちに囲まれて、
独り言を言っているようにしか映らなかったようだ。
祖母はそんな私を心配した。
キツネに化かされる、と言って
動物を裏庭から追い払ったのだ。
夢見がち、空想好きの私を祖母は好まなかった。
実際的で役に立つ習い事をさせられた。
針仕事もその一つ。
今では、それが私の身を助けてくれているのは事実。
祖母なりの愛情だったと思う。
「あの婆さんも、気の毒と言えば気の毒だったな。」
キツネが言う。
「あんなに道具たちに慕われていたのに
とうとう道具の歌を聞くこともなく死んじまって。」
そうなのか、祖母は道具たちに慕われていたのか。
「もちろんさ。物が人を嫌うなんてこと、あり得ない。
人が聞く耳を持たなくても、物は語りかけている。
人が物を使うとき、物はその動きに合わせて歌うんだよ。
人と物の息がピッタリ合ったとき、物は本当に嬉しいのさ。」
ああ、わかる、その感じ。
懐かしい。
「僕はここの婆さんに嫌われちゃったからね。
あるとき、急にこの庭には入れなくなったよ。
まるで結界が張ってあるみたいに弾き出されてさ。」
それはきっとあれだな。
あの薬屋の言っていた秘薬とやらが
槙の木の下に埋められた時なのだろう。
「道で君を見かけても、もう君の目は僕を映さなくなった。
声も聞こえないようだった。
仕方ない。
まあ、いいさ。またこうやって話せるようになったんだから。」
「君ももう大人だから、
周りに怪しまれないように装うこともできるだろう。
本当はさ、誰でも物の歌が聞こえるし、
動物とおしゃべりもできるんだがなあ。
もったいないなあ。
自分の片側を、つまり人生の半分を
見ないようにして生きているんだからね。
本当の自分は、いつでも物と一緒にいる。
本当の自分は、いつもハッピーな場所にいる。
ハッピーな気分のときは、
本当の自分に寄り添っているっていう証拠なんだ。」
そこで猫がニャーと鳴いた。
私はちらりと猫を見る。
「猫や犬は賢いから、人とは話せないフリがうまいんだよ。
ちゃんと、全部伝わってるよ。」
そうなのか・・・、
なるほど、と思い起こせる場面がいくつもあった。
そうだ、こんな感じで話していたのだ。小さかった頃は。
母が怪しんだのも無理はない。
祖母には聞こえなかったのだ。
それでも物たちに慕われていたと。
母はどうだったのだろう?
父はどうだったのだろう?
父は、もしかしたら知っていたかもしれない。
――みんな、知ってるのですよ。本当は。秘密でもなんでもない。
ただ、忘れているだけ。
さつき、お前も、そうだったでしょう?――
え?
お祖母ちゃんなの?
――ええ、ええ。
そこのキツネさん、私は気の毒な人ではありませんよ。
生きている時に知らなかったというのは、
少々残念なことではありますがね。――
お祖母ちゃん・・・
――さつきは、生きている間に幸せにおなりなさい。――
祖母の声はそれきり聞こえなくなった。
ふと、我に還り
それにしても、と私は考える。
キツネはいったい何者なのだ?
私の小さい頃を知っているとなると、そうとうの長生きだ。
あり得ない。
いや、もう何もかもがあり得ないことだらけの一日だ。
キツネは言った。
「僕はね、あの頃のキツネと個体としては別のキツネなんだよ。
今はこのキツネの姿を拝借しているんだ。
あの頃、一匹の子ギツネがずいぶん君になついていたからさ。
本当の僕の正体は・・・、
ねえ、さつき、君ももう薄々気付いているんだろう。
僕は君だよ。本当の君自身だ。
僕と君とで、一人の《さつき》なんだ。」
うそ・・・
いや、うっすらそんな気がしていたのも事実だった。
キツネは続けて言う。
「もうこの姿は必要ない。今から僕は元の場所に戻るよ。
君の心の中心に、小さくなり過ぎて見えなくなった点が一つある。
そこが僕の本来の居場所だよ。
用意はいいかい?」
用意と言われても困る。
「そっと目を閉じて。ただ、そのままでいい。」
目を閉じると、私の足裏が温かくなった。
そのぬくもりは次第に体を上昇してきて、全身をホカホカと温めてくれる。
指先から、頭のてっぺんまで、たっぷりと張ったお湯に浸かったみたいに。
今まで入ったどんな温泉よりも心地いい。
もしかしたら、子宮の中の羊水はこんな感じなのかもしれない。
ぬくもりと安心と希望で満ち満ちた羊水。
ゆらりゆらり、深いくつろぎの中でゆっくり呼吸する。
体の内部から声がした。
――これで完了だよ。――
目を開けてみた。
相変わらず家の中はチラチラと光っている。
窓の外、木の下ではキツネが座って、キョトンとした顔をしている。
キツネはもうしゃべらない。
声は私の内部から届いた。
――こんなふうに話すのも、これが最後だよ。
もう、僕たちは一人だから、言葉を使って話す必要がない。
これからは、君の言葉が僕の言葉だ。――
――良かったね、さつき!――
そのとき、居間も台所も、物たちの大合唱で埋め尽くされた。
祖母を慕い、愛した物たちの歌声は
母のことをも愛していたと伝えてくる。
そしてまた、さつきのことも。
そうだ。
癒されない過去など一つもないのだ。
私の中に
前を向き続ける、もう一人の私がいる限り。
《 完 》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
