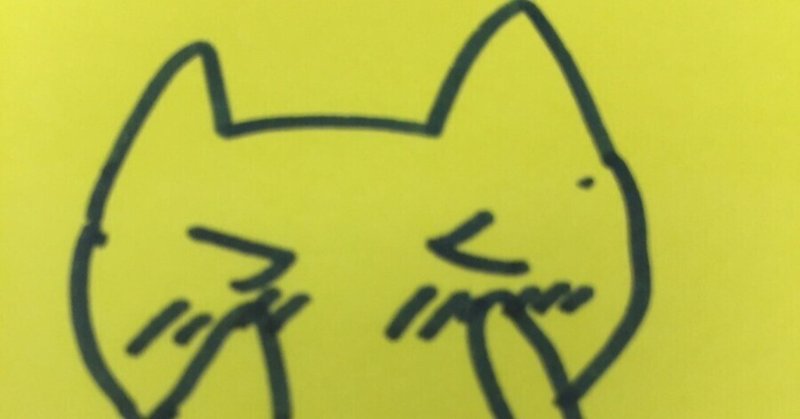
原書講読 WALTER BAGEHOT『PHYSICS AND POLITICS』4(2)
It will be said that this argument proves too much. For it proves that not only the somewhat-before-history men, but the absolutely first men, could not have had close family instincts, and yet if they were like most though not all of the animals nearest to man they had such instincts. There is a great story of some African chief who expressed his disgust at adhering to one wife, by saying it was 'like the monkeys.' The semi-brutal ancestors of man, if they existed, had very likely an instinct of constancy which the African chief, and others like him, had lost. How, then, if it was so beneficial, could they ever lose it? The answer is plain: they could lose it if they had it as an irrational propensity and habit, and not as a moral and rational feeling. When reason came, it would weaken that habit like all other irrational habits. And reason is a force of such infinite vigour—a victory-making agent of such incomparable efficiency—that its continually diminishing valuable instincts will not matter if it grows itself steadily all the while. The strongest competitor wins in both the cases we are imagining; in the first, a race with intelligent reason, but without blind instinct, beats a race with that instinct but without that reason; in the second, a race with reason and high moral feeling beats a race with reason but without high moral feeling. And the two are palpably consistent.
この議論は行き過ぎていると言われるかもしれません。なぜなら、〔この議論に従うと〕それは、比較的最近の人々だけでなく、まったく最初の人間も、親密な家族関係を築くための本能を持っていなかったことを示すからです。
しかし、もし彼らが、すべてとは言わなくとも〔彼らの〕ほとんどが、人類に最も近い動物のようであったなら、そのような本能を持っていたはずです。アフリカのある酋長が、一夫一婦制を「猿のよう」だとして不快感を示したという興味深い話があります。
人類の半ば獣のような祖先が存在したとすれば、彼らはほぼ確実に、このアフリカの酋長や他の人たちが失ってしまった貞節の本能を持っていたでしょう。
では、それがそれほど有益だったのなら、どうして彼らは失うことができたのでしょうか。答えは明白です。彼らは、それを道徳的で理性的な感情ではなく、不合理な傾向や習慣として持っていたために、失うことができたのです。
理性が目覚めれば、それは他のどの不合理な習性と同じように、貞節という習慣を弱めるでしょう。そして理性は、計り知れないほど活発な力であり、比類なき効率で勝利をもたらす武器であるため、貴重な本能が徐々に衰退しても、理性自体が着実に成長し続けるのであれば、問題にはならないでしょう。
私たちが想定している2つのケースにおいても、より強い競争者が勝利を収めます。第一に、盲目的な本能を持たないが知的な理性を持つ種族は、本能を持ちながらも理性を欠く種族を打ち負かすでしょう。第二に、理性と高い道徳性を持つ種族は、理性はあるが道徳性が低い種族を打ち負かすでしょう。そして、この2つの結果は明らかに矛盾しません。
There is every reason, therefore, to suppose pre-historic man to be deficient in much of sexual morality, as we regard that morality. As to the detail of 'primitive marriage' or 'NO marriage,' for that is pretty much what it comes to, there is of course much room for discussion. Both Mr. M'Clennan and Sir John Lubbock are too accomplished reasoners and too careful investigators to wish conclusions so complex and refined as theirs to be accepted all in a mass, besides that on some critical points the two differ. But the main issue is not dependent on nice arguments. Upon broad grounds we may believe that in pre-historic times men fought both to gain and to keep their wives; that the strongest man took the best wife away from the weaker man; and that if the wife was restive, did not like the change, her new husband beat her; that (as in Australia now) a pretty woman was sure to undergo many such changes, and her back to bear the marks of many such chastisements; that in the principal department of human conduct (which is the most tangible and easily traced, and therefore the most obtainable specimen of the rest) the minds of pre-historic men were not so much immoral as UNmoral: they did not violate a rule of conscience, but they were somehow not sufficiently developed for them to feel on this point any conscience, or for it to prescribe to them any rule.
そのため、先史時代の人間は、私たちの考える性道徳が大きく欠けていたと考える理由は十分にあります。
"原始婚" や "婚姻なし" というような、大まかな区分けで語られる "性的関係" の詳細については、もちろん議論の余地は多々あります。
マクミラン氏とラボック卿はどちらも熟練した論理学者であり慎重な調査者であるため、非常に複雑で洗練された彼らの結論を丸ごと受け入れることを求めてはおらず、またいくつか重要な点で彼らは意見を異にしています。
しかし、主要な問題は、繊細な論理付けに依存するものではありません。広い観点から言えば、先史時代の人間は妻を得るためにも守るためにも戦いを繰り広げ、強い男が弱い男から最高の妻を奪い、反抗的な妻、移り変わりの気に入らない妻は新しい夫に殴られたであろうと考えられます。
(現在のオーストラリアのように)魅力的な女性は何度もそのような変化を経験し、背中にはそのような懲罰の跡をいくつも背負っていたことでしょう。そして、人間の行動の中でも最も具体的で追跡しやすく、そのため残された痕跡も鮮明な主要な領域である"性的関係"において、先史時代の人間の心は不道徳というよりはむしろ無道徳だったと言えます。
彼らは良心というルールを破るのではなく、単にこの点において十分に発達しておらず、良心を抱くことも、良心が自分たちにルールを規定することもできなかったのです。
The same argument applies to religion. There are, indeed, many points of the greatest obscurity, both in the present savage religions and in the scanty vestiges of pre-historic religion. But one point is clear. All savage religions are full of superstitions founded on luck. Savages believe that casual omens are a sign of coming events; that some trees are lucky, that some animals are lucky, that some places are lucky, that some indifferent actions—indifferent apparently and indifferent really—are lucky, and so of others in each class, that they are unlucky. Nor can a savage well distinguish between a sign of 'luck' or ill-luck, as we should say, and a deity which causes the good or the ill; the indicating precedent and the causing being are to the savage mind much the same; a steadiness of head far beyond savages is required consistently to distinguish them. And it is extremely natural that they should believe so. They are playing a game—the game of life—with no knowledge of its rules. They have not an idea of the laws of nature; if they want to cure a man, they have no conception at all of true scientific remedies. If they try anything they must try it upon bare chance. The most useful modern remedies were often discovered in this bare, empirical way. What could be more improbable—at least, for what could a pre-historic man have less given a good reason—than that some mineral springs should stop rheumatic pains, or mineral springs make wounds heal quickly? And yet the chance knowledge of the marvellous effect of gifted springs is probably as ancient as any sound knowledge as to medicine whatever. No doubt it was mere casual luck at first that tried these springs and found them answer. Somebody by accident tried them and by that accident was instantly cured. The chance which happily directed men in this one case, misdirected them in a thousand cases. Some expedition had answered when the resolution to undertake it was resolved on under an ancient tree, and accordingly that tree became lucky and sacred. Another expedition failed when a magpie crossed its path, and a magpie was said to be unlucky. A serpent crossed the path of another expedition, and it had a marvellous victory, and accordingly the serpent became a sign of great luck (and what a savage cannot distinguish from it—a potent deity which makes luck). Ancient medicine is equally unreasonable: as late down as the Middle Ages it was full of superstitions founded on mere luck. The collection of prescriptions published under the direction of the Master of the Rolls abounds in such fancies as we should call them. According to one of them, unless I forget, some disease—a fever, I think—is supposed to be cured by placing the patient between two halves of a hare and a pigeon recently killed.[7] Nothing can be plainer than that there is no ground for this kind of treatment, and that the idea of it arose out of a chance hit, which came right and succeeded. There was nothing so absurd or so contrary to common sense as we are apt to imagine about it. The lying between two halves of a hare or a pigeon was a priori, and to the inexperienced mind, quite as likely to cure disease as the drinking certain draughts of nasty mineral water.
Both, somehow, were tried; both answered—that is. Both were at the first time, or at some memorable time, followed by a remarkable recovery; and the only difference is, that the curative power of the mineral is persistent, and happens constantly; whereas, on an average of trials, the proximity of a hare or pigeon is found to have no effect, and cures take place as often in cases where it is not tried as in cases where it is. The nature of minds which are deeply engaged in watching events of which they do not know the reason, is to single out some fabulous accompaniment or some wonderful series of good luck or bad luck, and to dread ever after that accompaniment if it brings evil, and to love it and long for it if it brings good. All savages are in this position, and the fascinating effect of striking accompaniments (in some single case) of singular good fortune and singular calamity, is one great source of savage religions.
同じ議論は宗教にも当てはまります。確かに、現在の未開宗教や先史宗教のわずかな痕跡においては、多くの点が非常に曖昧で難解です。
しかし、一点、明らかなことがあります。未開宗教は全て幸運をベースとした迷信に満ちていることです。未開人は、偶然のお告げを今後の出来事の兆候であり、特定の木は幸運をもたらし、特定の動物は幸運をもたらし、特定の場所は幸運をもたらし、無害に見える行為(本当に無害なものも含めて)は幸運をもたらすと信じています。
その種類は多岐にわたり、また逆の、不運を招くものの存在も信じています。そして、未開人は、「運」や「不運」の兆しと、私たちが言うところの「神」、〔すなわち〕善悪を引き起こす存在とをうまく区別することができません。未開人の心の中では、示唆するものと原因となるものがほとんど同じです。これら〔兆しと神〕を一貫して区別するには、未開人をはるかに超えた冷静な頭脳が必要です。彼らがそう信じるのは極めて自然なことなのです。
彼らは人生というゲームを、そのルールを知らぬままプレイしているのです。自然法則という概念がなく、病気を治そうとしても、真に科学的な治療法など全くわかりません。何かを試すにしても、試行錯誤に頼るしかありません。
実際、有用な現代の治療法も、このような手探りの経験的方法で発見されたものが多くあります。リウマチの痛みを止めたり、傷を早く癒す温泉があるなんて、何とありえないことでしょうか。
少なくとも、先史人類にはその理由をうまく説明することはできなかったでしょう。しかし、驚くべき効能を持つ恵まれた泉の存在についての偶然の知識は、おそらく、医学に関するいかなる確かな知識にも匹敵するほど古くから存在していたに違いありません。
間違いなく、当初は単なる幸運で、これらの泉を試して効果を発見したのでしょう。ある者が偶然それらを試して、奇跡的に治癒されたのです。
この一例で人間を導いた偶然は、いくつもの事例で彼らを誤った方向に導きました。ある遠征隊が古い木の下で出発を決断した際、運良く帰還し、その結果、その木は幸運で神聖なものになりました。別のある遠征隊はカササギが横切ったために失敗し、カササギは不吉なものとされました。また別の遠征隊は蛇が横切った後に驚異的な勝利を収め、その結果、蛇は大きな幸運の象徴 (そして未開人が区別できないもの、すなわち幸運をもたらす強力な神) となったのです。
古代も医学も同様に非合理的でした。中世後期になっても、単なる偶然に基づく迷信に満ちていました。〔イングランド、ウェールズの裁判所の〕記録長官の指揮下で出版された処方集は、私たちが空想と呼ぶようなものにあふれています。
そのうちの1つによると、記憶が正しければ、ある病気、熱だったと思いますが 、最近殺されたウサギとハトの半身の間に患者を置くことで治癒するはずだとされています。[7] このような治療法に根拠がないこと、そしてその発想はたまたまうまくいったことから生じたものであることは明らかです。
〔とはいえ、〕私たちが〔この迷信について〕想像しがちなように、常識はずれであったり、不合理であったわけではありませんでした。ウサギやハトの半身に挟まるという行為は、理論的には、また経験のない心にとっては、不味い鉱物の水を飲むのと同じくらい病気の治療に効果があるように思えたでしょう。どちらも、何らかの理由で試され、どちらも「効いた」のです。
つまり、どちらも最初、または記憶に残るある時点において、目覚ましい回復が続きました。唯一の違いは、鉱物の治癒力は持続的で常に起こるのに対し、ウサギやハトの近接性は平均的な試行では効果がなく、試したケースでも試していないケースでも同じくらいの頻度で治癒が起こるということです。
理由を知らない出来事を熱心に観察する精神の本質は、何か素晴らしい幸運や不運の連鎖を見出し、それ以降、それが悪をもたらせば恐れるようになり、それが善をもたらせば愛し憧れるようになります。
すべての未開人はこのような状態にあり、印象的な出来事 (個別のケースでの) 、とりわけ顕著な幸運や災難がもたらす魅惑的な影響は、未開宗教の大きな源泉の一つとなっています。
[7] Readers of Scott's life will remember that an admirer of his in humble life proposed to cure him of inflammation of the bowels by making him sleep a whole night on twelve smooth stones, painfully collected by the admirer from twelve brooks, which was, it appeared, a recipe of sovereign traditional power. Scott gravely told the proposer that he had mistaken the charm, and that the stones were of no virtue unless wrapped up in the petticoat of a widow who never wished to marry again, and as no such widow seems to have been forthcoming, he escaped the remedy.
スコットの伝記を読んだ方なら、彼が庶民の崇拝者から腸炎の治療法を提案されたことを覚えているでしょう。
その手法は、彼が12本の小川から集めた滑らかな12個の石の上に一晩中眠ることでした。大変骨な作業でしたが、これはどうやら万能の伝統療法だったようです。
スコットは真剣な顔で彼に説明しました。「魔術の道具を間違えておられる。石は未亡人、それも二度と結婚する気のない未亡人のペチコートに包まなければ効かないのだ」と。そんな未亡人は見つからなかったため、彼はこの奇妙な治療を免れたのでした。
Gamblers to this day are, with respect to the chance part of their game, in much the same plight as savages with respect to the main events of their whole lives. And we well know how superstitious they all are. To this day very sensible whist-players have a certain belief—not, of course, a fixed conviction, but still a certain impression—that there is 'luck under a black deuce,' and will half mutter some not very gentle maledictions if they turn up as a trump the four of clubs, because it brings ill-luck, and is 'the devil's bed-post.' Of course grown-up gamblers have too much general knowledge, too much organised common sense to prolong or cherish such ideas; they are ashamed of entertaining them, though, nevertheless, they cannot entirely drive them out of their minds. But child gamblers—a number of little boys set to play loo-are just in the position of savages, for their fancy is still impressible, and they have not as yet been thoroughly subjected to the confuting experience of the real world and child gamblers have idolatries—at least I know that years ago a set of boy loo-players, of whom I was one, had considerable faith in a certain 'pretty fish' which was larger and more nicely made than the other fish we had. We gave the best evidence of our belief in its power to 'bring luck;' we fought for it (if our elders were out of the way); we offered to buy it with many other fish from the envied holder, and I am sure I have often cried bitterly if the chance of the game took it away from me. Persons who stand up for the dignity of philosophy, if any such there still are, will say that I ought not to mention this, because it seems trivial; but the more modest spirit of modern thought plainly teaches, if it teaches anything, the cardinal value of occasional little facts. I do not hesitate to say that many learned and elaborate explanations of the totem—the 'clan' deity—the beast or bird which in some supernatural way, attends to the clan and watches over it—do not seem to me to be nearly akin to the reality as it works and lives among—the lower races as the 'pretty fish' of my early boyhood. And very naturally so, for a grave philosopher is separated from primitive thought by the whole length of human culture; but an impressible child is as near to, and its thoughts are as much like, that thought as anything can now be.
ギャンブルにおける運という要素に関して、現代のギャンブラーたちは、未開人が人生のあらゆる出来事に付随する「運」について抱くのと非常によく似た状況に置かれています。そして、未開人がいかに迷信深い存在であることは、私たちもよく知っています。
現代でも分別のあるホイスト〔トランプゲームの一種〕プレイヤーでさえ、ブラック・デュースには「運が悪い」という、確固とした信念ではありませんが、ある種の印象を抱いており、クラブの4が切り札として引かれた際には、不運をもたらす「悪魔の寝台柱」として、心の中で穏やかではない呪詛を呟いたりします。
もちろん、大人になったギャンブラーたちは、そんな考えを長引かせたり大切に育んだりするようなことはしないくらいの、一般的な知識や体系化された常識を持ち合わせています。彼らはそのような考えを持つことを恥じてもいますが、にも関わらず、頭の中から完全には追い出すことができません。
この点においてはしかし(but)、ルーレットに興じる子供たちのような、幼いギャンブラーは、未開人とほぼ同じ立場にいます。なぜなら、彼らの想像力はまだ強く影響を受けやすく、現実世界での否定される体験によって徹底的に鍛えられていないからです。また、幼いギャンブラーたちには偶像崇拝があります。
少なくとも、何年も前に私が所属していた少年ルーレットプレイヤーグループは、他とは違う大きさで綺麗に作られた「幸運の魚」という存在に、かなりの信仰を寄せていました。
私たちは、その魚が「運をもたらす」という力への信仰を、最高の形で示しました。大人たちがいない時はそれを奪い合ったり、羨ましい持ち主から他の多くの魚と交換しようとさえしました。あの魚がゲームの偶然によって自分の手から離れた時、私は間違いなく何度も大泣きしました。
哲学の尊厳を唱える人々は、もしそのような人がまだいるのなら、私にこのような些細な例を持ち出すべきでないと忠告することでしょう。そんな例はバカげたことだと。
しかし、現代の思想のより謙虚な精神が何かを教えているのであれば、それは小さな事例の持つ根本的な価値を明らかにしていることではないでしょうか。
多くの学術的で精巧なトーテム、氏族の神、何らかの超自然的な力で氏族に仕え、見守っている獣や鳥についての説明が、伝統的な社会の間で実際に機能し、生きている「幸運の魚」ほど現実と近いとは思えません。これは当たり前でしょう。
なぜなら、重々しい哲学者と原始的な思考の間には、人間文化の全てが隔たっているからです。しかし、感受性豊かな子供はその〔隔たりがないため原始の〕思考に近く、似た考えを持っています。それは、現代において得られるものとしては最も近いと言えるでしょう。
The worst of these superstitions is that they are easy to make and hard to destroy. A single run of luck has made the fortune of many a charm and many idols. I doubt if even a single run of luck be necessary. I am sure that if an elder boy said that 'the pretty fish was lucky—of course it was,' all the lesser boys would believe it, and in a week it would be an accepted idol. And I suspect the Nestor of a savage tribe—the aged repository of guiding experience—would have an equal power of creating superstitions. But if once created they are most difficult to eradicate. If any one said that the amulet was of certain efficacy—that it always acted whenever it was applied—it would of course be very easy to disprove; but no one ever said that the 'pretty fish' always brought luck; it was only said that it did so on the whole, and that if you had it you were more likely to be lucky than if you were without it. But it requires a long table of statistics of the results of games to disprove this thoroughly; and by the time people can make tables they are already above such beliefs, and do not need to have them disproved. Nor in many cases where omens or amulets are used would such tables be easy to make, for the data could not be found; and a rash attempt to subdue the superstition by a striking instance may easily end in confirming it. Francis Newman, in the remarkable narrative of his experience as a missionary in Asia, gives a curious example of this. As he was setting out on a distant and somewhat hazardous expedition, his native servants tied round the neck of the mule a small bag supposed to be of preventive and mystic virtue. As the place was crowded and a whole townspeople looking on, Mr. Newman thought that he would take an opportunity of disproving the superstition. So he made a long speech of explanation in his best Arabic, and cut off the bag, to the horror of all about him. But as ill-fortune would have it, the mule had not got thirty yards up the street before she put her foot into a hole and broke her leg; upon which all the natives were confirmed in their former faith in the power of the bag, and said, 'You see now what happens to unbelievers.'
この手の迷信で最悪なのは、簡単に作り出され、消し去るのが難しいという点です。ちょっとした幸運が、数々の呪いや偶像の幸運をもたらし、その地位を固めた例は枚挙に暇がありません。おそらく、たった一度の幸運さえ不要かもしれません。
もし年上の子供が「この可愛い魚は幸運なんだ、もちろんそうだろ。」と言ったら、下の子どもたちは皆信じてしまい、一週間も経たないうちにそれは崇拝される偶像になるだろうと確信しています。そして、未開人の集団における賢者、経験を司る年長者にも、迷信を生み出す同じ力があるのではないかと疑っています。
しかし、一度作られてしまえば、それを根絶するのは非常に困難です。誰かが「このお守りは絶対効く、使うたびに効果がある」と言ったとしても、それを反証するのは簡単でしょう。
しかし、「この可愛い魚はいつも幸運をもたらす」とは誰も言いません。あくまで「大体そうだし、持っていた方が持っていなかったより幸運である可能性が高い」と言われてしまう危険性さえあります。
フランシス・ニューマンは、アジアでの宣教師としての経験を記した興味深い記録の中で、その好奇心をそそる例を紹介しています。彼が遠隔地でやや危険な遠征に出発する際、現地人の使用人はロバの首に神秘的な予防的効能があるとされる小さな袋を結びつけました。その場所は混雑しており、町民全員が見守る中、ニューマン氏はこれを迷信を否定する機会と捉えました。
彼は最高のアラビア語で長々と説明し、周囲の恐怖の中、その袋を切り落としました。しかし、運悪く、ロバは30ヤード(※約27.4m)も進まないうちに穴に足を踏み入れて脚を折ってしまいました。これに、村人たちは全員、以前の袋の力への信仰をさらに強め、「ほら、不信仰者の末路だ」と語ったのです。
Now the present point as to these superstitions is their military inexpediency. A nation which was moved by these superstitions as to luck would be at the mercy of a nation, in other respects equal, which, was not subject to them. In historical times, as we know, the panic terror at eclipses has been the ruin of the armies which have felt it; or has made them delay to do something necessary, or rush to do something destructive. The necessity of consulting the auspices, while it was sincerely practised and before it became a trick for disguising foresight, was in classical history very dangerous. And much worse is it with savages, whose life is one of omens, who must always consult their sorcerers, who may be turned this way or that by some chance accident, who, if they were intellectually able to frame a consistent military policy—and some savages in war see farther than in anything else—are yet liable to be put out, distracted, confused, and turned aside in the carrying out of it, because some event, really innocuous but to their minds foreboding, arrests and frightens them. A religion full of omens is a military misfortune, and will bring a nation to destruction if set to fight with a nation at all equal otherwise, who had a religion without omens. Clearly then, if all early men unanimously, or even much the greater number of early men, had a religion WITHOUT omens, no religion, or scarcely a religion, anywhere in the world could have come into existence WITH omens; the immense majority possessing the superior military advantage, the small minority destitute of it would have been crushed out and destroyed. But, on the contrary, all over the world religions with omens once existed, in most they still exist; all savages have them, and deep in the most ancient civilisations we find the plainest traces of them. Unquestionably therefore the pre-historic religion was like that of savages—viz., in this that it largely consisted in the watching of omens and in the worship of lucky beasts and things, which are a sort of embodied and permanent omens.
さて、このような迷信について、今話したいのは、軍事的観点から見て非効率であるという点です。運についての迷信に動かされる国家は、他の点では同等でも、そのような迷信に囚われない国家の思うがままになってしまうでしょう。
歴史においても、我々が知っている通り、日食に対する恐怖によるパニックは、それを経験した軍隊を破滅に追いやったり、必要な行動を遅らせたり、破壊的な行動に走らせたりしてきました。占いに相談するという習慣は、それが誠実に実践されていた時期、そして先見性を装うトリックになる前の時期においては、古代史において非常に危険なものであった。
さらに深刻なのは未開人たちの場合です。彼らの人生は前兆に満ちており、常に呪術師に相談することを求められます。何かの偶然で簡単に翻弄され、もし知的に一貫した軍事政策を策定することができても(中には、戦争においては他の何事よりも先見の明がある未開人もいる)、それを実行に移す段階で、些細な、本来は無害なものだが彼らの心の中では不吉な前兆と見なされるものによって気を逸らされ、注意を散漫にされ、混乱や逸脱させられる危険性があります。
前兆に満ちた宗教は、同等の条件下にある宗教を持たない国家と戦えば、軍事的に不利な立場に置かれます。そのため、国家の存亡すら危ぶまれるおそれがあります。
もし初期の人類が全員、もしくは大半が前兆を持たない宗教か、あるいは〔そもそも〕宗教を持たなかったとしたら、前兆を基盤とする宗教は世界中のどこにも根付くことができなかったでしょう。圧倒的な多数が軍事的な優位を享受する中で、前兆信仰を持たない少数派は淘汰され、消滅してしまっていたはずです。
しかし、現実は真逆です。世界中にかつては前兆信仰に満ちた宗教が存在し、今もなお多くの地域で根付いています。未開人たちは誰もがそれを持ち、古代文明の奥深くにもその明らかな痕跡を見つけることができます。
疑いなく、先史時代の宗教は未開人の宗教に似ていました。つまり、前兆の観察と幸運をもたらす獣や物体の崇拝を中心としていたのです。これらの獣や物体は、いわば具現化された恒久的な前兆なのです。
It may indeed be objected—an analogous objection was taken as to the ascertained moral deficiencies of pre-historic mankind—that if this religion of omens was so pernicious and so likely to ruin a race, no race would ever have acquired it. But it is only likely to ruin a race contending with another race otherwise equal. The fancied discovery of these omens—not an extravagant thing in an early age, as I have tried to show, not a whit then to be distinguished as improbable from the discovery of healing herbs or springs which pre-historic men also did discover—the discovery of omens was an act of reason as far as it went. And if in reason the omen-finding race were superior to the races in conflict with them, the omen-finding race would win, and we may conjecture that omen-finding races were thus superior since they won and prevailed in every latitude and in every zone.
先ほどの前段落で述べた「験担ぎは軍事的に不利であり、文明の発展を阻害する」という主張に対して、おそらく以下のような反論が上がるでしょう。
「そもそも験担ぎがそれほど有害で人類を破滅させるようなものなら、そもそもどの民族も採用しなかったはずではないか。なぜ世界中で見られるのか。」と。
確かに、人類の先史時代の倫理観の低さも同様の反論に直面しました。しかし、ここで重要なのは、験担ぎがすべての状況で有害になるわけではないという点です。
験担ぎが有害になり得るのは、同等の実力を持つ民族同士が争っている場合に限られます。なぜなら、験(げん)の発見自体は、初期の人類にとってそれほど突飛なものではなく、薬草や水源を発見するのと同じような合理的行為だったからです。
前述したように、験を発見することは、初期の人類にとって「発見」であって、「発明」ではありません。験の存在を信じるか信じないかは、どちらが合理的かという議論ではなく、その民族が置かれた環境や文化的背景に大きく左右されます。験担ぎによって導かれた行動が有効に働き、敵対する民族に勝利を収められたなら、その時点で験への信仰を持つ民族の方が理性的だったと言えるでしょう。
そして、歴史を振り返ると、事実として験担ぎは世界各地の様々な気候帯、地域で広がっていました。つまり、験担ぎを持った民族が勝利を収め繁栄していったことが、その合理性の一つの証明と言えるのです。
In all particulars therefore we would keep to our formula, and say that pre-historic man was substantially a savage like present savages, in morals, intellectual attainments, and in religion; but that he differed in this from our present savages, that he had not had time to ingrain his nature so deeply with bad habits, and to impress bad beliefs so unalterably on his mind as they have. They have had ages to fix the stain on them selves, but primitive man was younger and had no such time.
あらゆる点において、私たちは、先史時代の人間は基本的に現代の未開人と共通点が多く、道徳観、知的能力、宗教においても似ていたという考え方を維持します。
しかし、彼らが現代の未開人と異なる点があるとすれば、それは悪い習慣に染まり切っていなかったり、悪い信仰を頑固に信じ込んでいなかったりする点です。現代の未開人は長い年月をかけて汚れを染み込ませてきましたが、原始の人間はもっと若く、そのような時間を持っていませんでした。
I have elaborated the evidence for this conclusion at what may seem needless and tedious length, but I have done so on account of its importance. If we accept it, and if we are sure of it, it will help us to many most important conclusions. Some of these I have dwelt upon in previous papers, but I will set them down again.
この結論を裏付ける証拠については、不要に長く退屈に思えるような詳細さで述べましたが、その重要性ゆえにそうしたのです。この結論を受け入れ、確信を持てるのであれば、それは非常に重要な多くの結論への手がかりとなるでしょう。そのいくつかについては過去の章で詳しく述べましたが、ここで改めて記しておきます。
First, it will in part explain to us what the world was about, so to speak, before history. It was making, so to say, the intellectual consistence—the connected and coherent habits, the preference of equable to violent enjoyment, the abiding capacity to prefer, if required, the future to the present, the mental pre-requisites without which civilisation could not begin to exist, and without which it would soon cease to exist even had it begun. The primitive man, like the present savage, had not these pre-requisites, but, unlike the present savage, he was capable of acquiring them and of being trained in them, for his nature was still soft and still impressible, and possibly, strange as it may seem to say, his outward circumstances were more favourable to an attainment of civilisation than those of our present savages. At any rate, the pre-historic times were spent in making men capable of writing a history, and having something to put in it when it is written, and we can see how it was done.
第一に、この結論を受け入れることで、いわば歴史以前の世界が何を目指していたのか、部分的に理解できるようになります。
歴史以前の世界は、知的な整合性、つまり、つながりがある、一貫性のある習慣、穏やかな享楽を暴力的な享楽よりも好む傾向、必要に応じて未来を現在よりも好む永続的な能力といった、文明が誕生するのに欠かせない精神面での前提(pre-requisites)を作り出していました。たとえ文明が誕生したとしても、これらの前提が失われればすぐに衰退してしまうでしょう。
初期の人類は、現代の未開人と同様に、文明の土台となるような「前提」を備えていませんでした。しかし、現代の未開人とは異なり、初期の人類はそれらの能力を習得し、訓練を積むことができました。
なぜなら、彼らの性格はまだ柔軟で影響を受けやすく、さらに奇妙に思えるかもしれませんが、外的環境も現代の未開人よりも文明を達成しやすい状況にあったと考えられるからです。
いずれにせよ、先史時代は、人類が歴史を書き、そこになにか内容を盛り込むことができるような存在に成長するまでの時代でした。そして、その過程がどのように行われたかについて、私たちは知ることができます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
