インハウス弁護士のExit戦略 #LegalAC
法務系アドベントカレンダー2020 16日目のエントリーです。
伊藤雅浩 さんからバトンを繋いで頂きました。
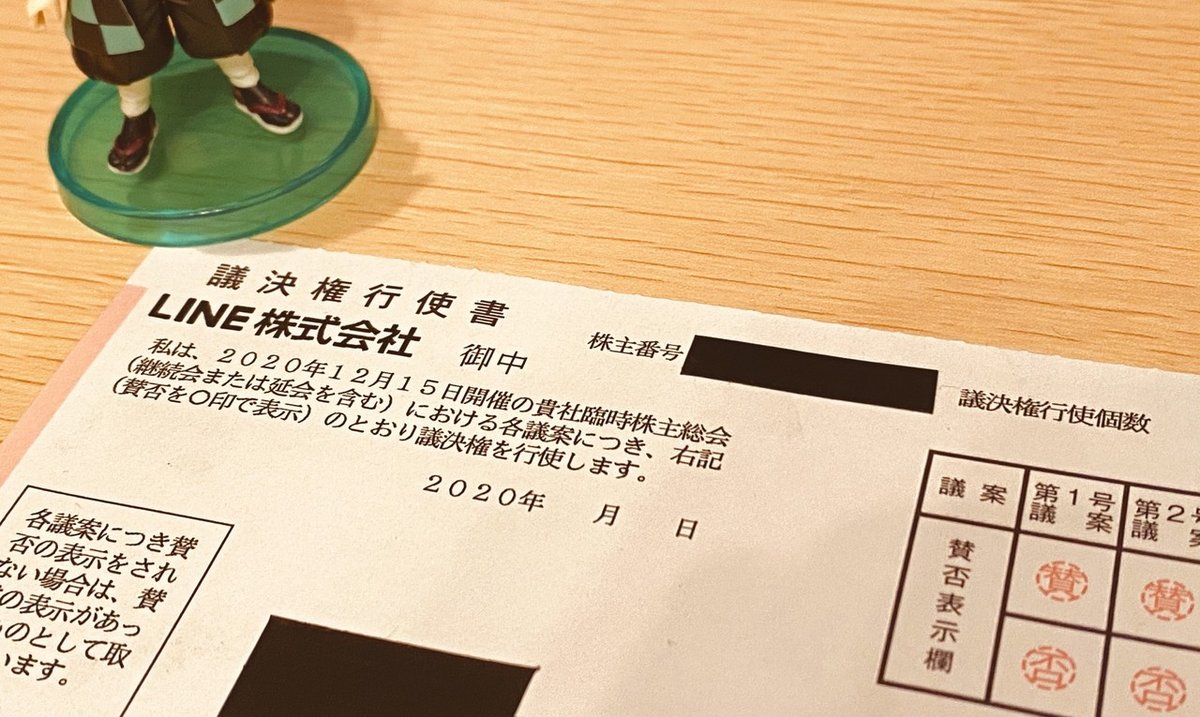
はじめに
このエントリを書いている2020年12月15日、私がインハウス弁護士として勤務しているLINE株式会社の臨時株主総会が開催され、すべての議案が提案どおり可決されました。
議案は同社株式29,165,333株を1株に併合するもの(要はスクイーズ・アウト)と付随する定款変更で、翌年1月4日に株式併合が効力を生じます。
そのため、本年12月29日をもって同社は上場廃止となり、ヤフーとの経営統合を進めることになります。
特に意識していたわけではないのですが、結果的に、自分自身も12月29日を最終出社日とし、来年1月3日付でLINE株式会社を退社します。
このエントリでは、自身のキャリアを振り返りつつ、インハウス弁護士を志望されている方や、プライベート・プラクティス(法律事務所)との間でキャリア選択を迷われている方の一助になると幸いです。
ここに描かれた事ごとがあなたの知っているものに近く、ここに現れた人々があなたの知っている人に似ていたとしても、それは歴史の偶然であり、必然である。
"銀河英雄伝説 Die Neue These" 第1話「永遠の夜の中で」
給与テーブルと管理職
コロナ禍とテレワークの普及に伴い、ジョブ型の労務管理と成果評価型の給与体系が注目されています。
しかし、ジョブ型・成果評価型の仕組みを導入したケースでも、多くの会社では、所定の給与テーブルの中で「区分×職級」の組み合わせをあてはめていることが多いと思います(例:国家公務員の俸給表)。
この場合、昇給というのは(手段として)職級を上げることを意味するわけですが、非管理職と管理職が同一の給与テーブルに載っている会社では、インハウス弁護士のような専門人材はある問題に直面します。
それは「管理職にならないと、ある段階から昇給しなくなる。」ということです。
これは専ら人事労務のシステムに起因する問題で、会社として昇給してあげたくても、そのためには「昇進」させないといけないことになります。
インハウス専門の兼副業事務所を経営している関係で、若い弁護士資格を持つ方々からキャリア相談を受ける機会が多いのですが、その悩みの一つに「管理職になりたくない」というものがあります。
悩みを細かく聞いていくと、その原因には、「専門性を生かした仕事がしたいのだけれど、上長(管理職)を見ていると、それ以外の仕事が多そうだ。」とか、「社内の交渉ごとが多く、生産性が低そう。」といったものが見られます。
これは(専門性や生産性の話は別として)事実認識としては正しく、専門部署であっても、管理職である=部下がいれば、必ずマネジメント業務が発生し、自身の部署を代表しての他の部署や経営陣との折衝も少なからず発生します。
このような側面は、会社員のキャリアとして考えれば当たり前のことなのですが、弁護士、特に司法制度改革以降の「法務博士(専門職)」の学位に拘り過ぎると、会社員らしい働き方を忌避する傾向にあるような気がします。
こういった要素を忌避して、一方で昇給は諦めないのであれば、プレイヤーとしてより給与水準が高い会社に転職することになりますが、転職先も非管理職と管理職が同一の給与テーブルであれば、問題を先送りしているだけになります。
ところで、最近は、(特に優秀なエンジニアの採用や引き留めのために)専門職や技能職向けに、非管理職のままでも昇給できる給与テーブルを採用する企業も増えてきました。
実は、私が現職に転職する際も「非管理職としては上限がある」という話を聞いていたのですが、入社直前に給与テーブルが変わり、非管理職も管理職と同様に職級が上がっていく(管理職にならなくても、管理職並に昇給する)仕組みができました。
であれば、管理職になりたくない人はそういう会社を選べば良いのではないか、という話になりそうなものですが、そこではまた別の問題が出てきます。
専門性とインハウス弁護士の意義
会社がマネジメントを行わない非管理職の専門職として、弁護士を「長期的にかつ好待遇で」雇用する場合、必然的に、外部の法律事務所の弁護士に依頼する場合と比較されることになります。
インハウスであっても、特定の法分野や事業領域に関する専門性を極めていくことは可能であると思いますし、幸い、私はこの3年弱、情報セキュリティとデータ保護(個人情報保護)の分野で集中的に経験を積むことができました。
しかし、ブティック型の法律事務所や大手渉外事務所の特定分野のプラクティスチームに所属する場合と比較した場合、特に純粋に法的知見の深さの観点から見たときは、インハウスの専門性が外部弁護士に優っているというシチュエーションは多くはありません。
これは個人の能力の問題ではなく、単純に、経験する内容のバリエーションが一社の範囲だけだと限定的になるということと、特定の法分野のみを担当するインハウスという存在は稀で、全ての稼働時間を特定分野に集中させることができないことに起因します。
翻って、会社がインハウスで弁護士を雇用する意義は何かといえば、事業側の「課題の提起を待つ」のではなく、事業側に「課題を提起できる」専門家がいるということに尽きると考えています。
インハウス弁護士の意義については多くの書籍等で議論されているので詳論は避けますが、従来型の外部弁護士の立場では、どうしても課題設定を待たざるを得ず、また、提示する法的評価を受けてのリスク選択について、その最終判断に責任を持つことができません。
逆に言えば、事業部の設定する課題に法的評価を加え、それに対する法的対応策「のみ」を提示しているインハウス弁護士の機能は、外部弁護士で代替が可能ということになります。
法務部門の日常的な業務は、事業部門のアドバイザーである。最終的な判断はあくまで「事業部門」であるという「他人事」意識が強かった担当者(中略)にとっては、リスクを洗い出して代替案を提案するという今までの日常は、所詮「他人事」であったとの誹りを免れない。「ビジネスのパートナー」を標榜していても、所詮は敷居が低いくらいのキャッチコピー程度のものであったのかもしれない。
明司雅宏「希望の法務 ー法的三段論法を超えて」(商事法務、2020年)7頁
もちろん、高度な法務機能の内製化によるコストダウンや法的知見の内部蓄積といったメリットは残りますが、前者は外注コストを超える給与を得られないことを意味しますし、知見の内部蓄積の受け皿が「弁護士」である必要はありません。
では、事業側に「課題提案をできる」ようにするためにはどうしたら良いのかというと、事業側や経営陣が何をして、これから何をしようとしているのかや、どのような目標や価値観で動いているのかを日常的に把握しなければなりません。
これを実行することで、単なる法的対応策を超える提案が可能となります。
私の担当するデータ保護(個人情報保護)の分野では、「プライバシー・バイ・デザイン」という考え方があります。
これは、製品やサービスが出来上がってしまってから、ユーザ同意や規約の文言などの法的手段で適法性を手当をするのではなく、その企画・設計段階でデータ保護を意識したデザインにしましょうという考え方です。
具体的な仕事の仕方は同僚のエントリに詳しく書かれているので、そちらをお読み頂きたいのですが、例えば、日常的に開発担当者からサービス構成を聞いていれば、レピュテーションリスクの高い法的手段ではなく、安全性の高い技術的手段で対応することが可能になります。
また、経営計画の企画段階で情報を入手できていれば、早めに経営判断の要素に法的な観点を上程し、プロセスとして経営判断上の過失を避けるなどを可能とするアプローチが可能となります。
このように、プル型からプッシュ型でコミュニケーションを進めることが「課題を提起できる」働き方と言えますが、これはまさに「管理職」に必要な仕事や能力に他なりません。
結局、組織で仕事をする以上、このような働き方からは逃げられないのであり、このようなコミュニケーションから逃げ続けていれば、いつか、インハウス弁護士としての居場所はなくなることになります。
そうであるならば、インハウス弁護士を続ける限り、管理職から逃げることに意味はないのかもしれません。
法務部門におけるKPIと個人のパフォーマンスの限界
私の弁護士としてのキャリアは、米国系の法律事務所のアソシエイトからスタートしました。
国内の大手渉外事務所でも同様かと思いますが、基本的に、アソシエイトにはバジェット(年間の売上げ目標)が設定されており、このバジェットの達成度が評価に繋がります。
そして、渉外事務所は基本的に時間制の報酬体系を採用しているため、事務所が売上を増やすためには、稼働時間を増やすか、人を増やすかの二択しかなく、ここが労働集約型のビジネスモデルの一つの限界といえます。
私自身、スケーラビリティ(伸び率)が高い事業会社へ転籍したのは、労働集約型の制約を超えた収益(収入)を期待していた部分が多分にあったのは事実です。
しかし、新株予約権等のエクイティ型のインセンティブの比重が高くない限り、勤務先のビジネスのスケーラビリティが高かったとしても、そのことがインハウス弁護士の待遇もスケーラブルであることに直結しないことは、今考えれば自明でした。
まず、インハウス弁護士の待遇は法務部門全体の予算の中での再配分に止まるため、法務部門自体に配分される予算が、事実上の待遇の上限を決定づけてしまいます。
さらに、管理部門は、その性質上、営業成績への寄与が定量化しづらい側面があり、ひとたび定量化のための事前に設定した目標の達成度という形で数値化しようとすれば、処理の速度や件数だけがKPIになってしまいかねません。
現職では360度評価を導入し、事業部などの法務部門外の評価が人事評価の基準として採用されているため、個人レベルでは、処理の速度や件数だけの評価を回避していますが、組織レベルの評価はなお難しい問題です。
あなたが一人法務であるとして、法務部門のパフォーマンスを上げようと考えると、処理の速度・件数や専門的な能力を上げようとすると、いつかは必ず個人としてパフォーマンスの限界が来ます。
結局、法務部門のパフォーマンスを向上させるためには、人を増やすしかなく、特に自分が楽をしたい=手戻りを少なくしたいのであれば、専門性が高い人を多く採用するに限ります。
私は、情報セキュリティ部門で一人目の弁護士でしたが、リファラル採用では、楽をしたい一心で、常に自分の上位互換の人材を紹介するように心がけてきました。
結果的に、私の現職での仕事はかなり楽になりましたし、今回の退職に伴う引継も滞りがなさそうで安心しています。
一方で、これは個人レベルでは悩ましい問題です。
自分のパフォーマンスの限界を超えて法務部門のパフォーマンスを上げるために自分よりも専門性が高い人を採用することは、「あれ、自分って実は要らないんじゃない?」という状況を生み出すことになります。
反対に、意識的に「自分が欠ければ会社が回らない」状況を作り出すと、黙っていれば解雇はされないかもしれませんが、法務部門のパフォーマンスが上がらないため、昇給する可能性が下がります。
自分よりも専門性は高い人を採用してもなお、会社において存在意義がある人材でありたいと言うことになれば、そのような強みは法的専門性「以外」の部分に見出していくしかないことになるでしょう。
それが、先述の「管理職」的な能力なのか、それ以外なのかは、私もまだ答えを出せていません。
インハウス弁護士のExit戦略
タイトル回収できる作品は良作といいますし、そろそろこの散文をまとめないといけません。
2017年にLAWASIAの東京大会で「アジア太平洋地域における企業内弁護士の現在と未来 」というセッションがあり、そこで、Freshfields Bruckhaus DeingerのEdward Cole氏が、大要、以下のようなことをお話しされていたことが記憶に残っています(もし、ご本人が「そんな趣旨の発言はしてないぞ」と思われるとすれば、その記憶違いの責任は偏に私にあります。)。
「従来は、プライベート・プラクティスからインハウスへの転換は片道切符だと言われてきたが、今では、インハウスの経験が顧客へのサービス提供で生きると考える事務所が増えてきた。現に、企業のGC(ジェネラル・カウンセル)から国際的な事務所のパートナーへ転向するケースも多い。」
特定の業種での専門性を買われてというケースもあるでしょうが、私は、「インハウスの経験が顧客へのサービス提供で生きる」という部分は、法的知識というよりは、顧客へのアプローチ手法が事業戦略上で有効になると考える事務所が増えてきたことを表しているのだと理解しています。
先ほどは、「事業側の『課題の提起を待つ』のではなく、事業側に『課題を提起できる』」ことがインハウス弁護士の強みのように書きましたが、外部弁護士でもプッシュ型のサービス提供は可能です。
現に、スタートアップ向けを標榜する事務所では、経営や開発へのコミットを高め、インハウス弁護士のような働き方をするケースもでてきています。
このような傾向が強まってくると、法的専門性を強化するという伝統的なキャリアを歩まなくとも、ビジネスとの伴走力に優れた弁護士として、プライベート・プラクティスに移ることは可能となる時代になってきているといえるでしょう。
反面、このような傾向が続くと、採用する企業側は、インハウス弁護士を採用してもどこかで離脱する可能性があり、定着しないと考えて、採用に躊躇するかもしれません。
これは、短期的にインハウス弁護士の市場を萎縮させる方向に作用するかもしれませんが、人材の流動化は法務部門に限らないトレンドであり、自社に居続けもらえないのは長期的なキャリアパスを示せていないことに原因があると考えた方が良い気がします。
法的専門性で誰にも負けないエスタブリッシュメントを目指すというのはヒロイックで、私自身も憧れは捨てきれない部分もありますが、現実問題として、すべてのインハウス弁護士が取り得る生存戦略でないのも事実です。
労務、知財、情報セキュリティ、機関法務、業法など、インハウス弁護士でも専門が分化している領域はいくつかあり、インハウス弁護士として外部弁護士に比肩する専門性を身につけられる場も存在しますが、一社に専門特化型で居続けることが難しいことは先述のとおりです。
それでもなお専門性を志向するのであれば、上記のような特定領域の重要性が高く、専門部署でインハウス弁護士の採用をしているような会社を選択すべきでしょう。
以上を踏まえてインハウス弁護士としてのExit戦略を考えると、以下のような選択肢が考えられそうです。
改めて並べてみると、普通のことしか書いていませんが……
1)管理職としてキャリアを進め、法務部長やジェネラル・カウンセルを目指す。その先には、ポスト・インハウスとしてプライベート・プラクティスに入ることも視野に入れる。
2)やりたい専門分野を決めて、専門部署でその分野を集中的に扱えそうな会社で、(非管理職で)専門特化型の技能職のキャリアを歩む。この場合は、従来型の専門特化型弁護士として、プライベート・プラクティスに入ることも視野に入る。
なお、選択肢を広く持っておきたい方へ
ここまでは割と、自己正当化のバイアス気味に自分の選択を整理してきた部分もあり、こんなに整然とキャリアパスを考えられることは稀だと思います。
そもそも、インハウス弁護士とプライベート・プラクティスで悩む要素は、働き方を含めて他にも沢山ありますし、どちらを選ぶにせよ、他の道を歩む余地は残しておきたいというのが人の常だと思います。
リスク・オンで一所懸命でないと信用ができないというのは、安全圏からの物言いか、生存者の正当化バイアスみたいなものだと個人的に思っています。
なので、悩むくらいなら両方を選択する、つまりインハウスとプライベート・プラクティスを並行して行う「兼副業」もアリだと思っています。
もちろん、インハウス弁護士としての仕事とプライベート・プラクティスとしての仕事のどちらかが疎かになるのであれば止めるべきですが、可処分時間は許すのであれば、是非、皆さんにも挑戦頂きたいと思います。
並行することで、経験が一社に限定されるリスクは希釈されますし、他方でインハウス的なアプローチの経験値を逐次プライベート・プラクティスに生かすこともできます。
幸いなことに、並行して自分の事務所を持っていたおかげで、退職後も、現在の職場から仕事を依頼したいというお話しを、現在の上長や事業部から頂くことができました。
これも一つのExit戦略かも知れません。
3)元の勤務先を、プライベート・プラクティスの顧客にスライドする。
おわりに
ツラツラと書き連ねてきましたが、誤解を招かないように付言すれば、現職での待遇、働き方、社風は現在の市場で高い水準のものであり、自信を持って他人にお勧めできる職場とポジションです。
特に、働き方の柔軟性や事業部や経営層に至るまでの風通しの良さは特筆すべきレベルであると思っています。
今回の退職は、単に、上位互換の同僚が増えたことで「今の職場でのプレイヤーとしての自分の役割の終わり」を自覚したこととと、「法務部門の構造的課題を自分なりに解決してみたい」という想いが沸く中で、新しい挑戦ができる場所に出会えたという偶然が重なったことに因ります。
そんなわけで、来年から、医療統計データサービスを提供する株式会社JMDCで、リスク管理室長 兼 最高データ保護責任者 として働くことになりました。
インハウスハブ東京法律事務所の代表は引き続き務めておりますので、兼副業にチャレンジしたい方はお声がけください。
17日目は にょんたか さんです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
