
そもそも品質工学 第117話 ペーパーホイールの制御因子
なんか、ライアさんの動きに怪しい部分がありそうですが、それはストーリーパートの話ですね。
本編は、制御因子の話です。
実際の研修では、受講者に自由に制御因子を考えてもらっています。
なので、ここで紹介するのはあくまで一例。
もし、受講者が制御因子で困っていたなら、講師側が「こういうのはどう?」と誘い水をする。
そのための、制御因子アイディア編だとおもってください!








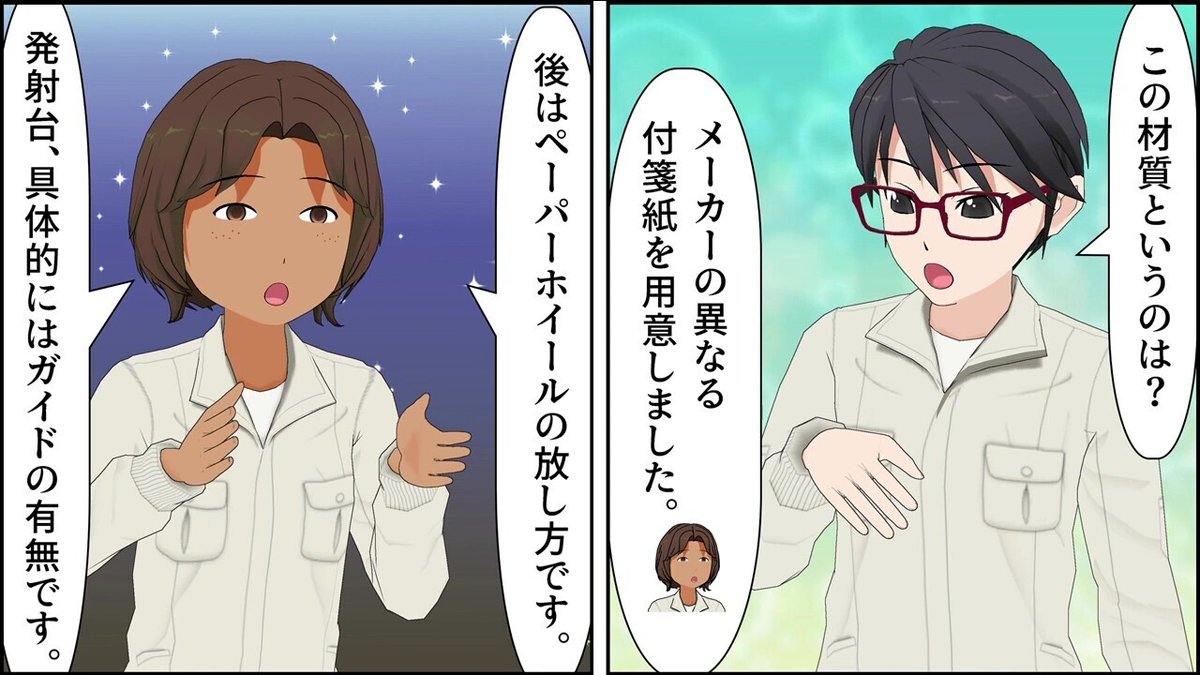














制御因子のアイディアを列挙するとこんな感じ?
・幅(付箋紙の種類、もしくは付箋紙を半分ずらして重ねる。)
・径(ペーパーホイールの直径)
・重さ(使用する付箋紙の枚数、もしくは基本形状に追加する付箋紙の枚数)
・丸め方(手で丸める、ペンに巻き付けて丸める)
・材質(色の違う付箋紙や、メーカーの違う付箋紙など)
・発射台(左右の位置調整ガイドの有無)
・放し方(手で放す、定規などでゲートを作る、ペンで押さえてそれを放す)
・発射台そのもの(角度や材質、これを変えると入力エネルギーが変わるので、あまりお勧めしませんが)
これ以外にももちろんあります。
受講者の突飛なアイディアも認めて、自由にやらせましょう。
過去には、付箋紙の外側を、セロハンテープで覆っていいですかみたいなものもありましたね。
それじゃ、ペーパーホイールじゃなく、テープホイールじゃないか!w
ちなみに、外周が補強されるので、良く転がります。(^^;
目的はすんなりと成功することではありません。
自分の実験のまずさに気が付く。
これが品質工学ですからね!
もちろん、後でちゃんとフォローする。
なぜ失敗したのか、どうすればうまくいったのか。
失敗したこの実験から、それでもいい条件を見つけるには?
そういったことをしないと、「品質工学ってつかえねー」って認識になってしまうので注意しましょう!
続きが気になる方はこちら!
↓ ↓
いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!
